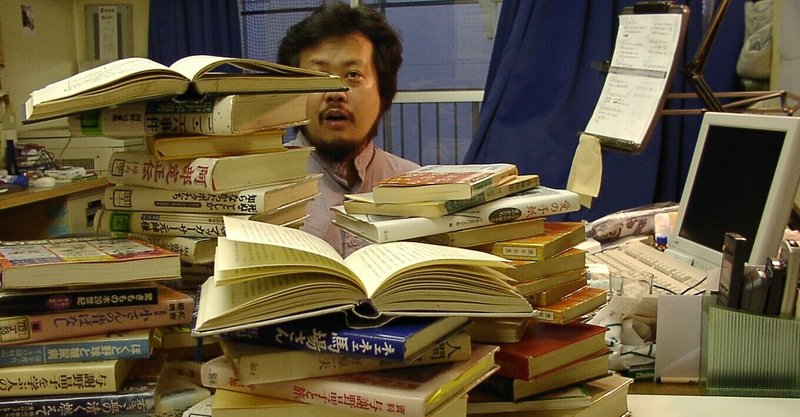
作家の収入/印税の夢と現実
1000円の書籍が1冊売れたとして著者の収入はいくらかご存じだろうか。
印税は10%だ。
つまり1000円の書籍が1冊売れて、私に入ってくる金額は100円だ。。
意外だろうか、妥当だと思うだろうか。
この印税10%の制度は、明治時代に決められてから令和の現代まで変わっていない。
社会の物価値が変わっても、変わることがなかった印税率の金額である。
再利用、中古、貸し出しでは印税は発生しない。
図書館の貸し出しで20人が読んだとしても、著者のもとには0円である。
いまから20年ほど前だったと思う。
当時のネットでは掲示板(BBS)が流行っていた。
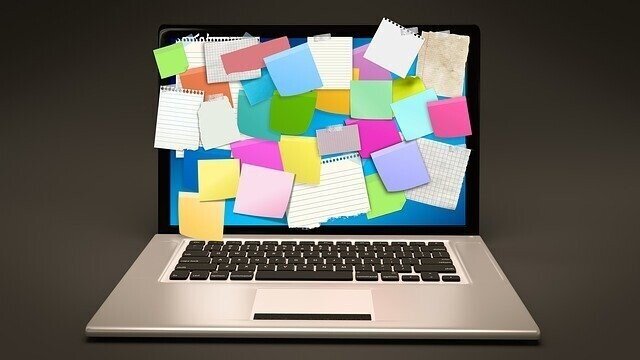
その掲示板で私は職業を尋ねられ、正直にも作家だと答えたら、掲示板のメンバーたちの書き込みが大騒ぎとなった。
「えっ、読みたい」
「どんな本を書いているんですか」
「本物の作家さんがこの掲示板に参加しているなんて驚きだ」
うっかりしたな、と思いつつ、私は出版してもらったばかりの小説『鬼が哭く』(祥伝社文庫)を掲示板に書き込んだ。
『東京百鬼/陰陽師・石田千尋の事件簿』シリーズの第2作めだ。
当時は本名で執筆していた。
美樹香月は2020年から名乗り始めたペンネームだ。
660円の文庫本だから、印税は66円である。
「さっそく読みました」
「面白かったです。感動しました」
「これは続編が楽しみになりました」
掲示板には、読んだ、読んだとの書き込みがまたも大騒ぎになった。
兼業主婦のK子さんは大興奮した様子で、感動して涙が流れたました……と、賞賛の書き込みをしてくれた。
「図書館で貸し出し待ちして、やっと読めました」
私としては、あらら……、0円も入ってこないのかと思いながら続きの書き込みを待った。
「貸し出しのハンコが23人分も押されていました。」
その後の書き込みが私の心をノックアウトした。
「この図書館の貸し出しの人数から察して、全国の図書館でもたくさん借りられているとしたら、みきみき先生のところには、ばく大なお金が入ってくるんでしょうね。いいなぁ、夢の印税生活」
そう……、読まれた数だけ、書籍の印税が発生するとK子さんは思っていたのであった。
「いや……それがですね……」
と私は掲示板に書きかけて、書きかけた文章を消した。
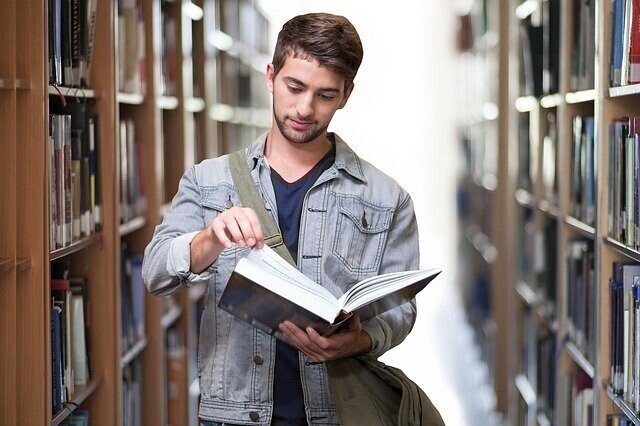
古書店で販売されている書籍からも、アマゾンで1円で再販されている書籍からも、著者のもとには0円すら入ってこない。
初動の売り上げがすべてなのだ。
いっぽう、音楽の二次使用となると事情が変わる。
作詞、作曲の印税はJASRACによって厳格に管理されている。
CDや音楽配信に限らず、たとえばカラオケで1曲でも歌われれば印税が発生し、作詞家、作曲家、ときには編曲家のところにまで、著作料が支払われる仕組みになっている。
出版は商売ではなく文化だ
書籍は、商品であると共に文化でもある、という考え方が印刷物の印税制度を著者にとっては歯がゆいものにしてしまった。
明治の頃は、高額な新刊書籍を買ってもらうことは、たとえば学生たちの生活を窮屈にする憂慮があった。
書籍は娯楽ではなく、文学というジャンル1つにしても、学んでもらうための社会的資産であった。
学んだ学生が、知識、知見、教養を身につけ、活かし、社会に還元するための文化という資産が書籍だと考えていたのだ。
だから、東京神田の神保町に古書店街ができあがり、新品の書籍を買うお金がない学生たちの、知識、教養の一大拠点であったわけだ。
古本は、出版社や著者の収入なんぞを度外視して、読んでもらうことこそ大切だと考えられていた。
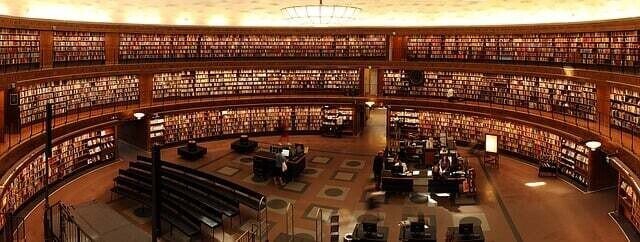
図書館にいたっては、読者は支払いなし、読了したら返却する。
返却された書籍は、また貸し出される。
文化の共有である。
学生に限らない。
経済的なゆとりがないが、向学心には燃えている人たちに、無料ででも書籍を読んでもらいたいという、出版社と著者との、情熱があったのだ。
この無料流通システムを維持してでも、書籍を通じて文化、教養、知識を多くの人に提供し、社会全体を良くするのだという気概が出版社にも、著者、作家、小説家にもあったのだ。
だから新品以外の書籍は、出版社にも著者にも、使用料(印税)は発生しない。
何だか、意地を張っているようにも感じる。
暴論を吐けば、もう書籍は文化でも教養でも知識でもなくなっている。
社会を支えるための文化、知識、教養ではないという暴論においてだが。
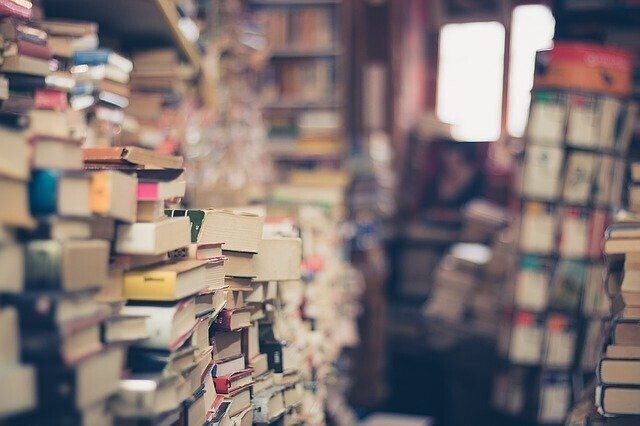
書籍には自社書籍・自社雑誌の広告は掲載されるが、他社の、たとえば家電や食品や自動車やお菓子などの広告は載らない。
これもまた、文化は中立であるべきという明治時代からの、出版社の意地とプライドなのだ。
昭和の半ば頃までは、この意地とプライドは通用していたのだが、平成、令和の時代には、もはや形骸なプライドにしか過ぎなくなったと思う。
20年前のネットの掲示板に、K子さんの昂奮したような書き込みに、
「いや……それがですね……」
と私は書きかけて、書きかけた文章を消した。
説明したところで理解してもらえないだろうというあきらめと同時に、私にも形骸化してしまったというのに、張り続ける意地と、貧乏を承知で文化を生み出してやるという、恥ずかしいばかりのプライドがあったからかもしれない。
1000円の書籍が新品で売れて100円の収入。
中古書籍が売れても0円の収入。
あなたにとっては、意外だろうか、それとも妥当だと思うだろうか。
サポートしていただけると、ありがたいです。 文章の力を磨き、大人のたしなみ力を磨くことで、互いが互いを尊重し合えるコミュニケーションが優良な社会を築きたいと考えて、noteを書き続けています。
