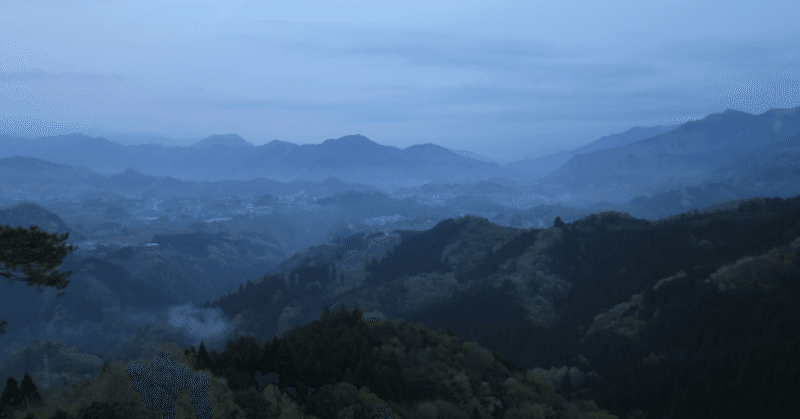2020年10月の記事一覧
額田の紫野は茜さしてこそ
子供の頃画用紙におひさまの絵を描く時、当たり前のように赤いクレヨンを使わなかっただろうか。
茜草という植物がある。表紙はその茜草の写真だ。薬草として、また染料として利用するのだが、その時に出る色はとても明るい赤だと言う。
『あかねさす』
和歌の世界において枕詞として有名なこのあかねは、茜草の色彩から太陽をイメージして昼間、日、照るの枕詞として使われる。子供の頃に描いた光るおひさまの色だ。
とて
みつせ川われより先に渡りなば
此岸と彼岸の間にあると言う三途。これは実際の川だとも、煩悩の例えだとも言う。
伝承から少し考えてみたい。
餓鬼道、畜生道、地獄道を意味する仏教由来説が有名で、そこに平安時代の終盤、徒歩では無く舟で渡り、その渡り賃が六文だとの言い伝えが乗ったらしい。
賽の河原伝説も加わり、また彼岸と言う言葉に対しては「彼岸」を「日願」とし、土着信仰の影響が乗ったとの説もある。
また、根の国を支配するスサノオ(
ねっとりよりホクホク
紅あずまなんですよ、好きなサツマイモは。
この季節、幼稚園の芋掘りも紅あずまは多いのでは?
次々に出てくるあれやこれやを芋づる式とは言い得て妙だと思います。
良く晴れた秋の一日に、蔓を引っ張りごろごろと顔を出すさつまいも。掘りたては味もしっかりしてほっくりです。
紅はるかやら安納芋やら、ねっとりしてるサツマイモより断然ほっくほくにわたしの軍配が、あがります。ただそれでも最近の紅あずまはやや甘す