
「都市の生死とは?」(後編)
本セッションは、生死の在り方をテーマに活動されている3人に登壇いただき「都市の生死」について語っていただいています。かつてミシェル・フーコーは都市国家の支配体系が「死政治」から「生政治」へと移り変わったことを指摘しました。また現在ではそれがバイオテクノロジーによって「細胞政治」へと拡張されつつあると言われています。新しい死生観が新しい都市のかたちをつくるとしたら、わたしたちはどう変わるべきなのでしょうか。
後編となる今回ではまず、テクノロジーの発展が人間の定義を更新しつづけてきた歴史を振り返ります。そして、死と寄り添う新しい都市を考える上で、日本的なアニミズムの感覚の重要性を議論します。最後に、バイオテクノロジー時代の倫理を切り開く存在としてのアーティスト像と、それを許容する「チバシティ構想」について語ります。(前編はこちらから)
本記事は、2019年1月に開催した『METACITY CONFERENCE 2019』の講演内容を記事化したものです。その他登壇者の講演内容はこちらから。
・TEXT BY / EDITED BY: Shin Aoyama (VOLOCITEE)
・PRESENTED BY: Makuhari Messe
*
新しいテクノロジーが登場するとき、それは僕ら自身、人間そのものをつくり替える
青木:ほんとに3人のお話からは、死と生、それをどのように社会に提示していくのかについていろいろ想像が広がります。まず最初に、みなさん生と死というのが根底のテーマとしてあると思うんですけど、パーソナルのところ、どうしてそれをやっていこうと思ったのかってところから話を広げていきたいなと思います。
高橋:僕は学部のときの研究テーマが、人間の歴史と技術の発展みたいな話だったんです。ざっとした見取図なんですけど、15世紀ぐらいから20世紀までのポートレートの歴史を、かなり恣意的にまとめたものです。
15世紀、ダ・ヴィンチのころは人間が神に取って代わって世界の中心に立つ、という意味で神と同じポーズをして人間が描かれます。でもゴッホとかマネの時代になると、写真によって写実的に描くことの意味がなくなってきた中で、デフォルメされた人体や光学的に分解された人間像ってのが出てきます。
そこから複製機械が社会に普及してくると、さまざまな情報に人間が触れることで人間の内面も分裂してきて、キュビズムみたいに多方向からものを描く、多視点的にものをつくる発想が出てくる。さらに機械工業が普及していくと、フォードが豚の解体場の工程から自動車の組み立てラインを思い付いたように、生命そのものを機械に見立てる視点が出てきて、デュシャンの機械化された身体、身体そのものを工学的に描く未来派とかレンピッカが出てくる。
マスメディアの登場、20世紀のデジタライズ技術とともに、情報的な人間、スクリーンに映る平たい人間像が出てきて、ものすごく記号化された人間が生まれる。このように、人間の描かれ方とテクノロジーの変遷はかなりリンクしていて、人間の捉え方や人間の定義そのものはどんどん変わっていくんだ、っていうのが僕の学部時代の研究テーマだったんです。新しいテクノロジーが登場するとき、それは僕ら自身、人間そのものや人間という概念をつくり替える。それによって人間の定義がどう変わるのか、それが芸術にいかに現れ、新しい美学がどう生まれてくるのかという問題意識が、今のバイオアートの実践にも通底しています。
青木:なるほど。アートと技術の共進化の中から次にどういったものが生まれてくるのかという視点で見てらっしゃると。
高橋:そうです。さらにそれが人間の変遷そのものにもリンクしていく。
青木:なるほど。ではそうした視点では、愛さんの作品とかはどのように捉えられるのでしょう。
高橋:愛さんはほんとに狂っていて、イルカを産みたいとか何言ってんだろこの人みたいな感じなんだけど、僕が面白いなって思うのは生物多様性の文脈なんですよね。よく多様性が大事だみたいなことを言うけど、そこには矛盾がある。だって、多様性を保護するのは人間に役立つものだけで、人間の役に立たない害虫とか害獣は絶滅させようとしてる。例えば、ハエは農業の邪魔だから根絶させろ、マラリアを媒介する蚊も絶滅させなくてはいけない、新しい種につくり替えてしまえみたいな。でもそういう人間中心じゃない多様性、人間が人間を産むのは当たり前じゃないっていう、他の生物のための倫理みたいなものが愛さんの作品にはあると思ってます。それが、これから人間中心的な社会から抜け出していこうという時に、ぶっ飛んではいるんだけど、ものすごい面白いし、価値のある視点だと思いますね。
青木:先ほどの基調講演での多自然主義の考え方に通じる点かもしれないですね。その辺って、愛さんってどう考えてらっしゃいますか。
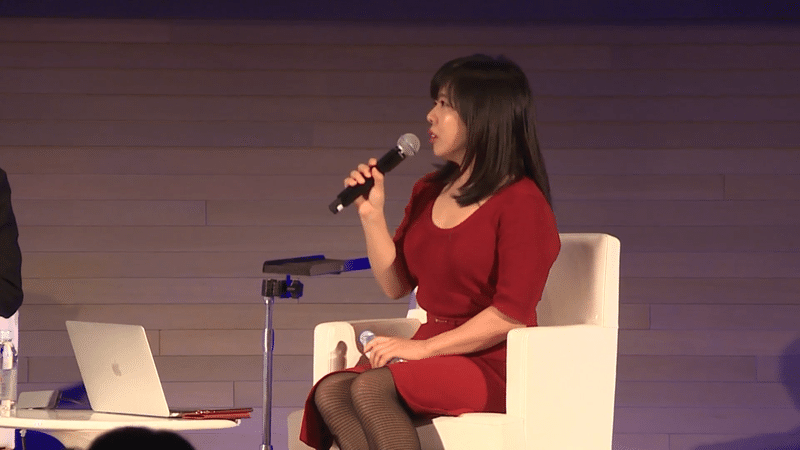
長谷川:ヨーロッパの方々って結構、イルカの作品を面白がってくれるんですね。なぜかって言うと、やっぱりヨーロッパって、どうしても人間中心主義なんですよね。だから人間以外のいろんなものに生命が宿ってて、それを尊重しようみたいなところがすごくアジア的だって評価をもらったりするんです。そういうふうに見るんだこの人たち、って面白かったですね。
青木:なるほど。愛さんから見て、らんさんの墓地はどう捉えてらっしゃいますか。テーマとしては対極にあるようにも感じられるのですが。
長谷川:個別性と連続性でしたっけ、ああいうふうにまとめられるんだと思って、すごい面白かったです。あと、環境とどうつながるかって話が面白くて。私も死んだ後の体をどうするか、どう体を無くしていくか、という作品で、人体を早く地に返すテクノロジーをリサーチしたことがあるんです。だから私がやってたのって、そういう墓地の意味と技術をつなぐところだったのかもしれないと思えて興味深かったです。
関野:ありがとうございます。愛さんはさっき、世界は分子でできてるなら実は境界がないんじゃないかって言ってたじゃないですか。生と死もそういうものだと思うんですね。だから境界をつくってるのは人間の概念で、実は自然界では全部連続してる。愛さんの作品も人間と他の種の境界をなくそうとしてるのかなと考えると、つながるとこがあると思いました。
青木:なるほど。死は普段、個人の死と捉えられますが、種として見ればそれは進化の過程であると捉え直せるとも思います。ちょっとここで個人から社会に広げてみましょう。DeathLABの活動は、コンセプトだけでなく切実な社会問題をどう解決していくか、というところから現れてきています。高橋さんは、DeathLABのような動きは日本においても展開されてくべきだとお考えですか。
死と生が寄り添いながら日常に溶け込んでいく
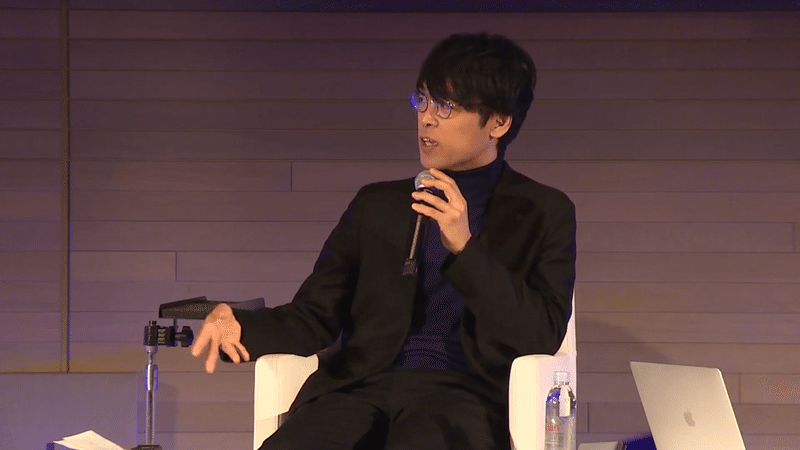
高橋:僕自身はそう思っています。2015年に『WIRED』のカンファレンスでカーラが登壇していて、アフターパーティーでいろいろ話してたときに、カーラの考えてることは日本のアニミズムとすごい親和性が高いなって思ったんですよね。
青木:そうなんですか。
高橋:彼女もいろんな古代宗教の墓地をリサーチしていて、ストーンサークルとか、金沢に来たときは木製の環状列柱を見に行ってました。縄文時代って広場の中心に墓地があったんですよ。それを囲むように家が建っていて、常に死が中心にあった。当然、今よりも死ぬ人は多い。けど、死者は深い森や海の向こうに還り、そこで神になって幸をもたらす存在へと変わる。それは忌避される死じゃなくて、祖先が自分たちを守ってくれるという意味があった。当然私たちは死んだものを食べて次の生を生きるわけだし、死者は常に生者と寄り添って生きていく。だから、お墓っていうのは円形つまり循環するような形につくられていて、太陽が回ると陰も一巡して、それが巨大な日時計の役割を持っていたりもする。魂の循環を表現するための文化的なシステムになってるんですよね。そういう、死と生が寄り添いながら日常に溶け込んでいくような形っていうのは、DeathLABとすごく似ている。しかもカーラのやってるのは、現代の死がもっている冷たいイメージを根幹からあたたかいものに変えることなんですよね。
青木:タブー視された死から。
高橋:そうそう。輝く温かい光に死んだ人たちが変わって、それが今を生きるわれわれを照らしてくれる。過去生きてきた全ての人たち、しかもそれは社会関係とか関係なく、富める人も貧しい人も、全ての人がお墓に入れば平等に社会を支え照らし出していく。未来をつくっていく光に変わるんだっていう、鮮烈なメッセージでもあると思うんです。いろんな都市の中で問題が起きていく中で、本当の意味で民主主義社会における死とは何かっていうのを考えた答えがあそこにあると思っています。でもアメリカだとあれはやっぱり結構過激な提案ですよね、神様信じてる人たちなわけですから。神によってつくられた身体を燃料にして電気をつくるなんて何事だ、みたいになってしまう。でもサイバーシティ千葉であれば......。
青木:許される。
高橋:そうそう。きっと許されるんじゃないかなと。そこに日本の可能性があるかもしれない。
青木:なるほど。どうでしょうその辺。結構タブー視された死って、日本のほうが強いって個人的に思ってたんだけど、宗教の話を含めるとちょっと違うのかなと。また実際につくる際に問題が出てくることもあると思うんですけど。
関野:そうですね。私もDeathLABの提案はなるほどなと思う半面、やっぱり衝撃的で。私としては個別性から全体性へ死が移ろっていく、人間が物質として環境に循環していくことは重要だと思うんです。だから、今つくられたお墓が、遺体が化学物質として環境にどう影響を及ぼすかはこれからの課題だと思っているので、その面では画期的だと思いました。でもやっぱりあの埋葬、お祈りする空間が心で受け入れられるかなっていうと難しい。頭で理解することと感覚のズレをどう空間としてつくっていくかは考えていきたいですね。
長谷川:質問なんですけど、光るバクテリアを付けて自分の家に持って帰る、っていう発想はなかったんですか。死というものは家の中に持っていきたくないのか、それとも実は昔は普通だったけどしなくなっただけなのか、どっちなんだろうと思って。臭いなんですかね。
青木:アメリカは土葬文化だからそもそも家にお墓って概念はないのかな
長谷川:映画とかでは骨つぼみたいに灰をポットに入れて、家に置いておく人も出てきますよね。
高橋:棺を家に持って帰って、自家発電できる設備にするみたいな。
長谷川:ネタバレですが邦画の『湯を沸かすほどの熱い愛』は、お風呂屋さんの奥さんが病気で死んでしまって、お湯を沸かすために死体を入れてしまうっていうオチでした。家族の肉体があったかいお湯になって、私たちをあっためてくれるって終わり方だったんですよね。彼らはお風呂屋さんだったからできたけど、他の人たちには難しい。やっぱり制度によって死が衛生的に切り離されてしまった感があって、死体を持ち帰ることとかがタブー視されてるのかなと思います。現在は人は病院でよく死にますし、病院で摘出した自分の一部は基本持って帰らせてくれないんですよね。病院や制度、社会衛生が私たちと死を切り離したのかなと思っていて。そこが変えられると一体どういう変化が起きるんでしょうかね。
高橋:なるほど。社会衛生の面で死を切り離すようになったのは確かにあるでしょうね。一方で、DeathLABの棺は1年で亡くなった人を土に還すんですけど、そこにいろんな人が繰り返し入り、常に橋のたもとが星座のように光り続けるってことに意味があるんです。亡くなった誰かを想う時間ってやっぱりすごく大事で、そのための期間をDeathLABは1年に定めている。その人が亡くなってから1年、だんだん発酵=発光して自然に帰っていく過程を目に見えるようにすることで、心の準備ができる。同時に、もちろん最初は亡くなった一人に対して祈ってるんだけど、それが星座のようなモニュメントとして機能することで、そこで亡くなった人類全てに対しての祈りに繋がっていく。いつか死んだ私のことを覚えてる人はいなくなってしまう。孫くらいまでは覚えてるかもしれないけど、いずれ誰からも顧みられない存在になる。それでもなお、そこで亡くなった人、これまで生きてきた人、全ての人たちに敬意を払いたいっていう思いが『星座の広場』にはあるんです。
長谷川:今のを聞くと、手の届かないところに置いておくことが重要な気がします。今のお墓も石の下に入れることで、封印されて手が届かなくなる。やっぱり、家族が溶けて分解していく様を毎日自分の枕元で見るとか、多分だいぶつらくって無理なんですよね、きっと。忘れていくためにはちゃんと封印をするというか、ここからは彼岸だって決めないといけないのかなと思いました。
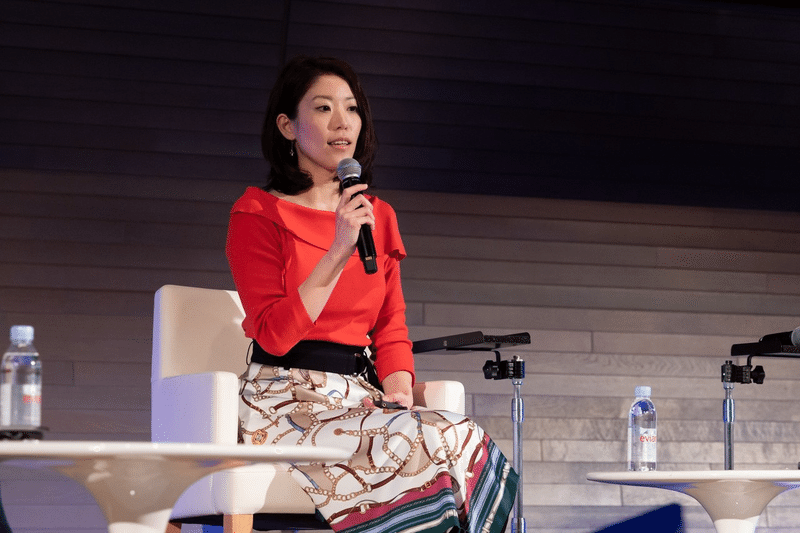
関野:私は個別性と全体性がいろんなレベルであると思ってます。昔の小さい集落には、亡くなった方の遺体を集落の人たちみんなで運んで洗うって儀式がありました。お墓に入れる前にも祈りをささげて、埋葬するのも1人じゃできないから、コミュニティーの全員でする。そこでは亡くなった方の埋葬は町全体が知って受け入れるための行為だったわけです。でももう隣の人が亡くなっても分からないじゃないですか。自分の身近な人の死は悼みたいけど隣の家で孤独死した人は受け入れられないみたいに、今は死が個別性に偏りすぎてると思うんですよね。だからそれを全体性の中にどうつなげていくか、っていうのが課題だと思っています。核家族化とかで身内が少なくなっている中で、血縁関係を超えた人のつながりをどうつくるかが私の一つの課題になんです。
私の設計したお墓では、買うのは1代なんですけれども、埋葬された後13〜33年たったら、骨つぼから出して合葬して土に還すんです。それで次の世代の人にそこを明け渡す。今までのお墓のように家で継いでいくわけではなくて、あの場所をいいなと思った次の世代の人が買ってくれて、血縁とは違うつながりで時間を継いでいってもらえたらなと思っているんですね。そしてそういう新たな人のつながりによって、個人の死が個別性でとどまらないようになることが重要なんじゃないかなと。
高橋:らんさんのお墓で言う全体性もいわば地球に還る、一体になるっていうことだし、アニミズムの感覚をすごく大事にされてるなと思って。やっぱりお墓って怖い、祟られそうみたいなイメージありますよね。DeathLABはそういう感覚をうまく使っていて、死者から作った土を使って植物とかを育てればその場所は開発しづらくなる。下手なことをしたら祟られるんじゃないかって思われることで、自然保護地域に変わっていく、みたいな考えを語っています。自然と死者を合体させていくことは、そういう観点でもエコロジカルになりうるんだなって。
青木:なるほど。個別性と全体性のバランスは時代と地域によって変わるし、友人や家族の死を受け入れるためのタイムスケールも違う。これらをどう調停するかが、一つ大きな共通点かなと思いますが、いかがでしょう。
関野:私の作品は、八王子という東京の郊外だからこそ成り立ったと思ってて、やっぱり都心部では難しいですよね。今都心部では、立体駐車場のように遺骨が回る形が増えていて、私は最初ちょっと抵抗がありました。でも自分でお墓の形式を整理してみると、やっぱり都市部は個別的、合理的、物質的なものにならざるをえないのかなとも思いました。ただ設計者としては、そこから全体性にまでつながる空間を提案できるようになりたいとは思ってます。
青木:なるほど。その視点ではDeathLABはまさに、都市のお墓にみんなが集える循環システムをどうつくっていくかを、ラディカルな形で表現してるのかもしれませんね。ところで、個別性と全体性の調停は死だけじゃなく生にも必要ですよね。まさに愛さんは、個別性と全体性の境界をズラしてやろうという感じがありますが、いかがでしょう。
長谷川:そもそも私の死生観が、YouTubeの画面みたいなものかもしれない思っているので。つまり、動画がいっぱいあって、一つ一つの動画は一人一人の一人称での人生だとします。見てる人は1人だけ。でも見終わらないうちに、他の動画も見たりする、見るのは同じ私ですよね。他の人間の肉体のうちに私と同じ鑑賞者が同時に存在するが故に、私は私だけど同時に他人も私でありえるっていう謎の死生観を昔から密かに持っていて。もし、個別性と全体性の境界をズラす感じがあるとしたらそこから来ているのかもしれません。
高橋:そもそもなぜイルカを産みたくなったんでしょう?
長谷川:あれは子供に対する選択肢の無さから始まってて。今は持つ、持たない、養子を取る、人間の代理母になる、っていう4つしかないですよね。そこで現実的に考えるのはいったんやめて、どうしたらうれしいかを考えてみたんです。そうしたら、絶滅危惧種の動物を産めたらうれしいなって。でも産んだあと食べてしまってもいいし、自分が死ぬときに海に帰してもいいと思ってます。なんで人間って食物連鎖の輪から逸脱しようとするのか、人間とそれ以外に線を引くのか、不思議過ぎるんですよね。やっぱり海に入っていると、自分は襲われる側だ、って感覚がすごく激しいんです。そこに若干の喜び、ああそういうものだよねみたいな感じも見出してしまう。
青木:なるほど。先ほどの講演で奥野さんがおっしゃってた、狩猟採集民の倫理観は、死ぬかもしれない緊迫感をベースに生まれるっていうのに近いですかね。愛さんの作品のアプローチは、倫理的な境界を超えたところにどういうことがあり得るのかを提示してくれてるとずっと思っていますが、高橋さんはキュレーターとして、こうした生や倫理の別の在り方を提示していく作品が新しく生み出す問題についてどうお考えですか。宗教問題とかが想像できますが。
アーティストが生命のフロンティアを切り拓いていく
高橋:歴史を振り返れば、新しい技術と倫理の対立は山のようにありましたよね。ラッダイト運動から、近年のDIYバイオがテロのリスクを高めるというような話まで。AIに関していえば、日本とヨーロッパだと若干様相は違うなとは思うけど、『マトリックス』であれ『ターミネーター』であれ、生が拡張されて機械が命を持ち始めるようになると、それが自分たちを疎外するんじゃないか、というオブセッションが常に生まれてきたましたよね。でもそういう倫理の境界を破っていくのは、常にアーティストたちだったわけです。ダ・ヴィンチだってあの時代、死体を解剖するのはある種のタブーだったけど、山のように解剖した結果、ああいう芸術として表現されて、評価されて、後世には残ってますよね。それにアーティストたちはある種「自分たちは神なんだ」って言ってのけたんです。デューラーがキリストと同じポーズの自画像を描くみたいに。当時の倫理からすれば逸脱したことをやってのけたにもかかわらず、それが次の社会の思想の基礎になって、新しい芸術や社会が生まれていく。そういうパラダイムシフトの歴史が連綿とあるんですよね。
そういう意味で愛さんは、生命が工学的に操作できるようになってきてる時代のアーティスト像をすごくきちんと示してると思います。これからはアーティストが生命のフロンティアを切り開いていく。愛さんは、人間の多様性があまりにも少な過ぎる、本当は生命にはもっともっと可能性があるんだから、人もいろんな生き方ができるはずなんだ、ってことを率先して提示していて、だからこそクレイジーだと言われるんだと思うんですよね。
いま西洋の個人主義が発達した結果、人間が神に成り代わって新しい生物種をデザインする、みたいな風潮が強くなってます。それこそルネサンスの「神としての芸術家」みたいなのが超個人主義の芸術家像になりかねない。それに対して愛さんは、「人間が神みたいな力を得たとしても、それを人間のためだけに使わない」という在り方を示してるのかなと。やっぱり、人間を含めた全ての生命を平等に見る、みたいな感性はすごく重要になってくるんじゃないかと思います。
生物多様性特区・チバシティ
青木:METACITYのコンセプト、新しい知覚・思考を生み出してバウンダリーを広げ、ありうる都市を考えよう、ともシンクロしますね。
高橋:今、都市や人間がぜんぜん多様じゃないってことはみなさん感じていると思います。だから千葉で是非やっていただきたいのは、生物多様性特区みたいな取り組みですね。愛さんの作品とかを受け入れて、千葉ならイルカもクジラも何でも産めるぞ、みたいな。
長谷川:確かに千葉は自然も多そうですしね。
高橋:そうそう。WIRED特区とかも出てきたし。しかも生き方だけじゃなく死に方の多様性もあるぞと。今、日本は火葬が99%らしいですが、そうじゃなくてらんさんのお墓とか、樹木葬とか、宇宙葬とか、DeathLABとかのオルタナティヴを何でも選べるみたいな。
青木:なるほど。素晴らしいまとめですね(笑)。千葉版WIRED特区でDeathLAB的な取り組みをしていくのも面白いかもしれませんね。
高橋:ニューロマンサーのチバシティのリバイバルとしてWIREDが世界中に発信したら、再び千葉がSFの代名詞になるんじゃないかと。
青木:先ほどの講演で語られたポストヴィレッジの在り方を探求していこう、というフレームの中でそういった活動ができたら面白いですね。
さて、都市の生死というテーマは壮大ですから、到底このセッションだけでまとめることは難しいですが、この先に繋がりそうなキーワードがいくつか紡ぎ出せたかなと思います。長い時間ありがとうございました。
*
NEXT:「ウェザードリブン・シティ」はこちらから
登壇者プロフィール
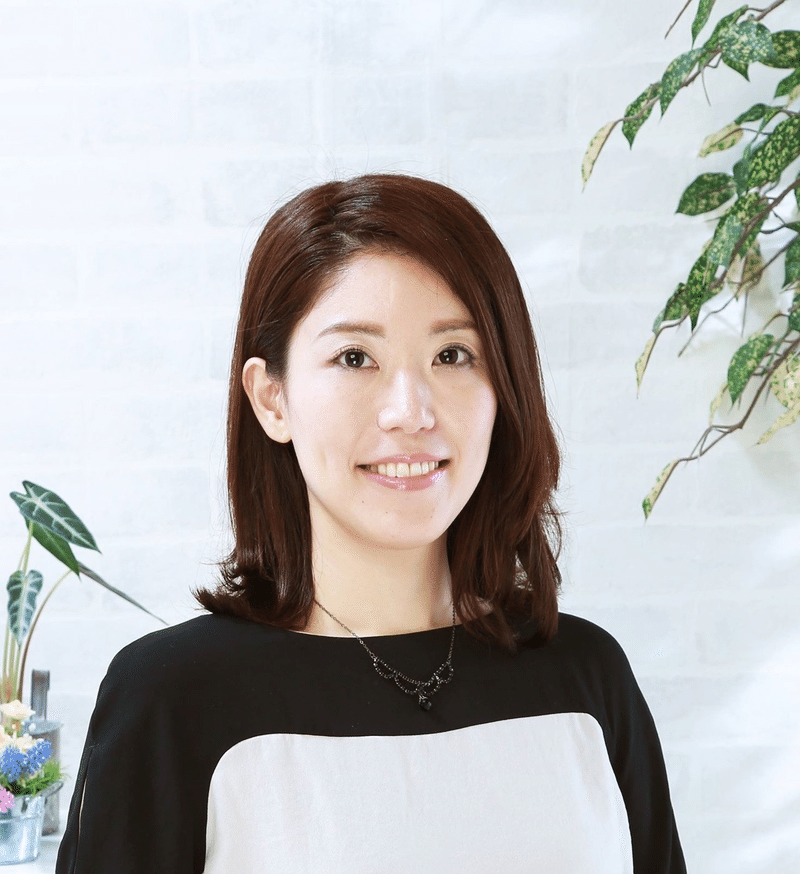
関野らん|RAN SEKINO
墓地デザイナー、建築家。
東京大学工学部社会基盤学科、同大学院修士課程にて、建築家 内藤廣に師事し土木と建築を学ぶ。川添善行・都市・建築設計研究所勤務を経て、2011年SRAN DESIGN設立。大学院在籍時より、従来の墓地の研究とともに、新しい埋葬形式を探求した墓地の設計に携わり、現在まで多様な墓地の設計を行う。主な作品「風の丘樹木葬墓地」(東京都八王子市)、「樹木葬墓地 桜の里」(東京都町田市)など。
人間の生と死について常に向き合い、分野を超えてランドスケープから建築、インテリアまで幅広くデザインし、100年後までつながる人の生きる場所を模索している。
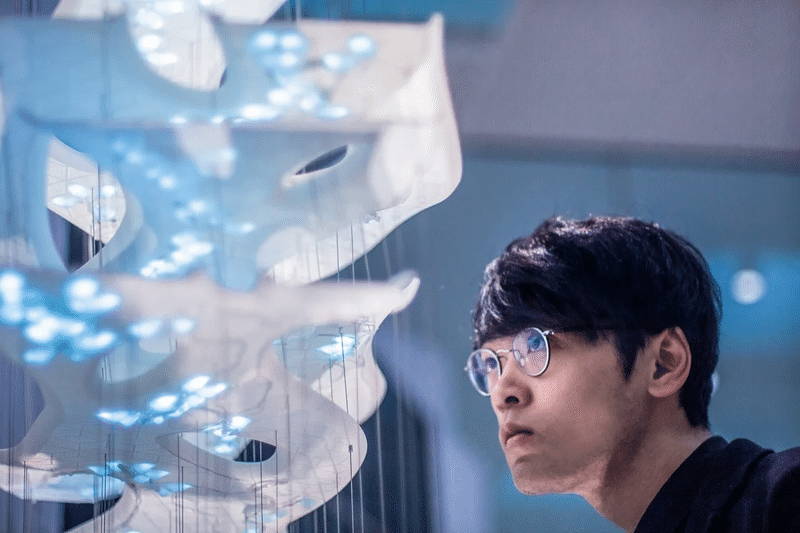
高橋洋介|YOSUKE TAKAHASHI
1985年東京都出身。金沢21世紀美術館キュレーター。東京藝術大学大学院美術研究科修了。専門はポストヒューマンの美学および超人間中心主義研究。
近年の主な企画に、「de-sport:芸術によるスポーツの解体と再構築」(2020、金沢21世紀美術館)、「ヒストポリス:絶滅と再生」(2020、GYRE)、「DeathLAB: 死を民主化せよ」(2018-2019、金沢21世紀美術館)、「2018年のフランケンシュタイン:バイオアートにみる芸術と社会と科学のいま」(2018、GYRE)など。
共著に「未来と芸術:AI、ロボット、都市、生命——人は明日どう生きるのか」(森美術館編、美術出版社、2019)、「SPECULATIONS 人間中心主義のデザインをこえて 」(川崎和也編著、BNN新社、2019)など。
主な講演に「超人間中心主義のルネサンス」(東京大学、2015)など。

長谷川愛|AI HASEGAWA
アーティスト。バイオアートやスペキュラティブ・デザイン、デザイン・フィクション等の手法によって、生物学的課題や科学技術の進歩をモチーフに、現代社会に潜む諸問題を掘り出す作品を発表している。 IAMAS卒業後渡英。2012年英国Royal College of ArtにてMA修士取得。2014年から2016年秋までMIT Media Labにて研究員、MS修士取得。2017年から2020年3月まで東京大学 特任研究員。2019年秋から早稲田大学非常勤講師。上海当代艺术馆、森美術館、イスラエルホロンデザインミュージアム、ミラノトリエンナーレ、アルスエレクトロニカ等、国内外で多数展示。著書に「20XX年の革命家になるには──スペキュラティヴ・デザインの授業 」(BNN新社)など。

青木 竜太|RYUTA AOKI
コンセプトデザイナー・社会彫刻家。ヴォロシティ株式会社 代表取締役社長、株式会社オルタナティヴ・マシン 共同創業者、株式会社無茶苦茶 共同創業者。その他「Art Hack Day」、「The TEA-ROOM」、「ALIFE Lab.」、「METACITY」などの共同設立者兼ディレクターも兼任。主にアートサイエンス分野でプロジェクトや展覧会のプロデュース、アート作品の制作を行う。価値創造を支える目に見えない構造の設計を得意とする。
Twitter | Instagram | Web
皆様の応援でMETACITYは支えられています。いただいたサポートは、記事制作に使わせていただきます。本当にありがとうございます!
