
#5 読書で世界一周 |エストニア語で書くからこそ、伝わるものがある 〜エストニア編〜
「読書で世界一周」は、様々な国の文学作品を読み繋いでいくことで、世界一周を成し遂げようという試みである。
5カ国目の今回から、北欧のバルト三国に入る。
初めはエストニアだ。メヒス・ヘインサーさんの『蝶男 エストニア短編小説集』を取り上げる。
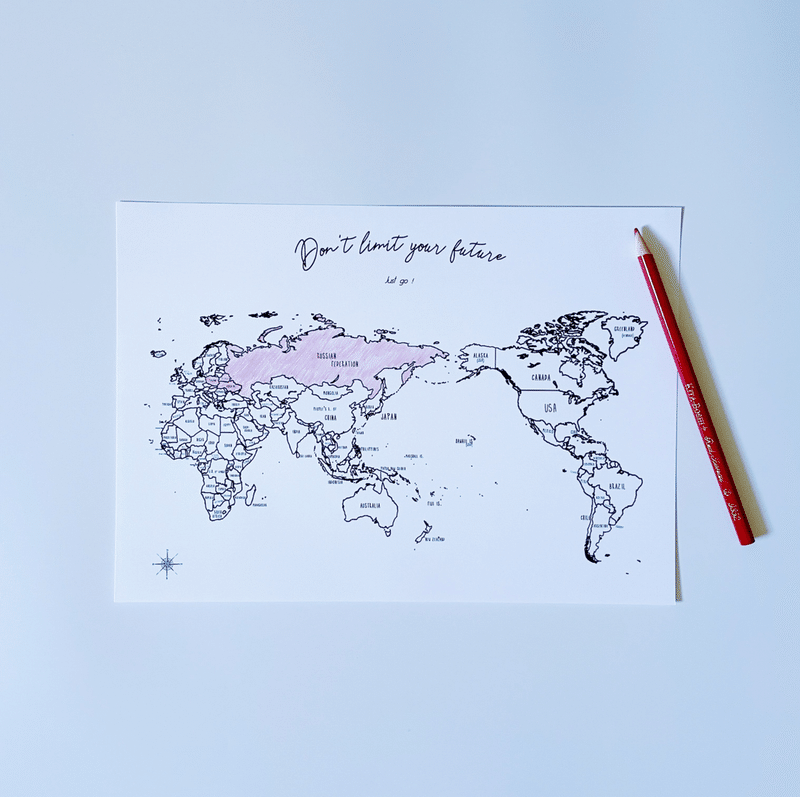
メヒス・ヘインサー|蝶男 エストニア短編小説集

エストニアの新世代作家による短編小説集です。
北欧(あるいは東欧)に位置する小さな国、エストニア。人口たった130万人の国ながら、優れた芸術家を何人も生んできました。たとえば作曲家のアルヴォ・ペルト、作家のアウグス・ガイリなど。この本の著者、メヒス・ヘインサーも、エストニアで最高の名誉とされるトゥグラス短編小説賞を2000年、2002年、2010年と3度にわたり受賞した、ヨーロッパ各国で注目を浴びる精鋭な作家です。
ヘインサーの作風は、マジックリアリズムと評されることがよくあり、日常の中で生まれた不思議な出来事や奇妙な現象に端を発し、主人公が普通の世界からどんどん逸脱していく様子がリアルに描かれるのが特徴です。エストニアの実在の地名を随所に織り交ぜながら、「幻想とリアル」二つの異なる世界を自由に、ちゃめっ気たっぷりに行き来して、スリリングに話を展開させていく独特のスタイルを持ちます。これが自分にとって唯一の世界を見る方法であり、リアルワールドに近づくやり方なのだ、というのがヘインサーの弁です。
フィンランド語、フランス語、ドイツ語など、英語以外にも数多くの言語に作品が翻訳されており、エストニア国外の読者からも大きな支持を得ています。ただ日本では、エストニア文学の翻訳は非常に数が少なく、本書はアンドルス・キヴィラフクの『蛇の言葉を話した男』(河出書房新社、2021年)につづく、新世代作家作品の貴重な翻訳書となると思われます。
どこか手作り感を感じさせるペーパーバックの本作は、「葉っぱの坑夫」という団体から発行されている。
葉っぱの坑夫は、2000年に発足した非営利のウェブパブリッシャーだ。様々な国籍・ジャンルの本を創作・翻訳し、国内外に発信している。
『蝶男 エストニア短編小説集』も、葉っぱの坑夫で活動されているだいこくかずえさんに魅力を見出され、一冊の本となった。日本語で読むことのできるエストニア文学作品は数えるほどしかなく、本作はそのうちの貴重な一冊である。

著者のメヒス・ヘインサーさんは、エストニア南部の学園都市タルトゥに生まれ、1994年から短編小説を発表し始めた。
「マジックリアリズム」と呼ばれる独自の作風・視点が読者を虜にし、エストニア国内で最高の短編小説賞を受賞している。
本作も、ヘインサーさんのマジックリアリズムの手法が遺憾なく発揮されている。リアルな日常生活の中に、幻想的なSF要素が織り交ぜられ、不思議な世界観が構築されている。
「幻想とリアル」の奇跡的な共存。思いもよらない方向へと話が展開していき、予測できないところがかえって楽しい。これは、ヘインサーさんにしか生み出せない物語である。
たとえば表題作の「蝶男」は、喜怒哀楽の感情が高まると、その感情の種類に応じて、何百種類もの蝶を身体から出現させる男が主人公だ。
その体質ゆえに様々な苦難を経験してきたが、類稀なる奇術師として才能を見出され、サーカスに入団する。その最初の公演で、色とりどりの蝶が男から生まれ羽ばたく光景は、非常に幻想的だ。しかしその先には、切ない結末が待ち受けている。
他にも、愛を身体に溜め込み体型が変化する男や、毎日死と蘇生を繰り返す男、椅子と一体化していく詩人など、不思議な短編が多数収録されている。
ひとつひとつの短編は短く、ちょっとした時間に読めるので嬉しい。星新一さんのショートショートが好きな方は、きっとハマると思う。
本作を読んでいると、エストニア文化の一面を知ることができる。
学園都市タルトゥやヒーウマー島など、実在するエストニアの地名が登場したり、エドアルト・ビリテやアルベルト・ウーフトゥルノーといった、エストニア人作家の名前が出てきたりする。
「ポルツァマー・ワイン」という、ブドウではなくリンゴやベリー類で作られた、ポルツァマーという町の名産ワインも登場する。こういう発見があるのも、本作の魅力である。
メヒス・ヘインサーさんは、エストニア語で書く作家である。
人口が少ないから、作家は自分がいちばん大事だと思うことに集中できる。もっと人口の多いところでは、多くの読書を喜ばせようとするから、ものを書くとき危険が生じる。
エストニア語の母語話者はそれほど多くなく、したがってエストニア語で読める読者も少ない。しかしだからこそ、本当に届けたい言葉をしっかり届けられるという考え方に、感銘を受けた。
エストニア語と文化が今も残っているのは奇跡に近い、これからも残っていくかどうかわからないという危機感がある。
私は大学で言語を学んでいたが、中には少数言語を扱う講義もあった。存在することが当たり前とみなされがちな言語も、時代とともに話者が減少するなどして、消滅してしまう危機にさらされている。
多和田葉子さんの『地球にちりばめられて』を読んだとき、自分の母語が地球上から消滅する恐ろしさを想像し、戦慄したことを思い出す。当たり前のように存在する言語や文化も、後の世代に継承していくために、大切に守っていかなければならない。
そういう意味で、新しい世代の作家がエストニア語で作品を発表するのは、とても素敵なことだ。これからも、エストニア語で素敵な小説を書き続けてほしい。
「読書で世界一周」、5カ国目のエストニアを踏破。次の国へ向かおう。
6カ国目は、お隣りのラトヴィアだ。デビュー作が世界10カ国以上で翻訳された、超新星の小説を取り上げる。
~読書で世界を巡る~
1. ロシア ドストエフスキー|カラマーゾフの兄弟
2. ウクライナ アンドレイ・クルコフ|ペンギンの憂鬱
3. ベラルーシ スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ|戦争は女の顔をしていない
4. ポーランド オルガ・トカルチュク|逃亡派
5. エストニア メヒス・ヘインサー|蝶男 エストニア短編小説集
←New
↓世界一周の続きはこちらから!
↓本に関するおすすめ記事をまとめています。
↓読書会のPodcast「本の海を泳ぐ」を配信しています。
↓マシュマロでご意見、ご質問を募集しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
