
今日も、読書。 |読書で世界を旅する
2022.2.20 Sun
破戒:384ページ
「ヤーガン語」という言語の、最後の話者が亡くなったというニュースを見た。ひとつの言語が、地球上からその姿を消したことになる。
研究とか、記録とか、そういう形でヤーガン語は残り続けると思うが、「生の言語」として、ヤーガン語が話されることはなくなったという。
このニュースを目にした時、私は多和田葉子さんの『地球に散りばめられて』を思い出した。日本が消滅し、数少ない日本語の母語話者として、世界に取り残された女性の物語。地球上で自分ひとりしか、その言語を話す人がいないという状況。自分が死んだら、その言語を話す人が、この世から消滅するという状況。彼女は一体、どんな想いだったろう。私には想像することしかできないが、胸が張り裂けそうになる。
2022.2.21 Mon
208日目。
破戒:384ページ
永井玲衣さんの『水中の哲学者たち』という本が、すごく良かった。毎日が同じことの繰り返しで、何のために生きているのか分からない。そう感じている人に、この本を読んでほしいと思う。
著者の永井さんは、哲学講師。「哲学対話」という、何とも面白い催しのファシリテーターを務めている。哲学対話については、ぜひ一度検索してみていただきたい。
彼女は、哲学は決して堅苦しい学問などではなく、実はどんな学問よりも、私たちに身近な存在であると説く。実際、彼女の文章を読むと、哲学への入口は日常生活の至る所にあって、いかにそれを見逃しているかに気付かされる。
普段は見落としている日常の何気ない物事に、「なぜだろう?」と疑問を持つこと。自分の無意識の選択に、「なぜだろう?」と問いかけること。その一瞬の思考から、哲学は始まる。いつもと異なる、新鮮な視点を得ることができるのだ。

本書を読むと分かるが、「仕事に追われ、人生が退屈だ」とは言っても、実は人生そのものが退屈なわけではない。人生それ自体は、あらゆる可能性に満ちていて、この上なく面白いのだ。それを退屈にしているものがあるとすれば、私たちの行動であり、選択だ。私たち自身が、数ある選択肢の中から、単調で退屈な生活を、選び取っているだけだ。そのことに気付き、はっとなった。
永井さんは、生活の中から哲学の扉を見つけ出すプロだ。様々なトピックが、ユーモラスかつ読みやすい文章で語られている。大部分が彼女の思考の話であるから、実際に何が起こるということでもないのだけれど、私はすごく、豊かだと感じた。それが、本書の魅力だと思った。
2022.2.22 Tue
209日目。
破戒:読了
カラ兄:上巻 0ページ
長らく読み進めてきた藤村の破戒を、とうとう読了した。
私は、丑松の勇気ある行動が、彼の道を切り拓いたと思う。あの勇気ある告白によって、彼がそれまで抱いてきた身分を隠すことへの後めたさから、解放されたのではないだろうか。彼は自身の行動によって、彼を救い出すことに成功したと思う。
確かに、穢多であるという理由で、たったそれだけのことで、蔑んだり、攻撃したりしてくる人はいる。新たな場所へと出立する丑松には、この先、更なる困難が待ち受けているかもしれない。
しかし、最後の場面で明らかになるように、銀之助やお志保、彼の教え子たちなど、身分という幻想の壁を超えて、彼を慕う人たちがいる。そして何より、彼自身がそれまで囚われてきた戒めから、解放された。この先丑松は、自分を隠すことなく、彼らしく生きていくことができるはずだ。
それにしても、銀之助、お前は本当に良いやつだ。今作のMVPは、間違いなく銀之助だった。

この「名作小説をじっくり読もう」シリーズ、非常に楽しかったので、この先も続けていこうと思う。
次の作品は、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』にすると決めていた。新潮文庫版で上中下巻に分かれる超大作だが、次はこの作品を、じっくり丁寧に読んでいくことにする。
2022.2.23 Wed
カラ兄:上巻 0ページ

さて、『カラマーゾフの兄弟』を読んでいこう。例によって、巻末の解説から読むことにする。
「ドストエフスキー 人と作品」。革命家として活動していた時期に逮捕されたドストエフスキーは、死刑の執行を直前で免れるという恐ろしい経験をする。このことが、彼の人生観、創作活動に、大きな影響を与えたという。
『カラマーゾフの兄弟』は彼の晩年に書かれた長編で、思想上・宗教上の問題の集大成的な作品とのこと。私はあえて、本作のあらすじや制作背景などに触れず、まっさらな状態で読み始めることにした。その方が余計な先入観なしに、ドストエフスキーの哲学に迫れる気がしたのだ。読了までどれくらいかかるか分からないが、とても楽しみである。
さて、この『カラマーゾフの兄弟』を読み始めるにあたって、もうひとつ始めたい挑戦がある。それは、読書で世界一周をする、というものだ。
新型コロナウイルスが流行し、気軽に海外へ行くことができなくなった。もともとインドア派の私にとって、海外は本当に、手の届かない場所になってしまったように感じられる。そんな状況下、せめて本の世界の中でも、海外を巡りたいという強い思いがあった。
ルールは至ってシンプルで、その国を代表する、あるいはその国らしさが感じられるような小説を読み、その国を訪れたことにして記録する、ただそれだけだ。選書の基準も特には設けず、その国らしい本であれば、基本的にはOKだ。ただ、できればその国出身の作家が書いた作品を読みたい。それが難しい場合は、その国が舞台だったり、その国の人物が活躍したりする作品でも良しとする。とにかく、読み終えた時に、その国を心ゆくまで堪能したと感じることができれば良い。
これを『世界読書巡り』として、生涯をかけて取り組んでいきたいと思っている。その第一歩として、私は『カラマーゾフの兄弟』、つまりロシアを読むことにする。

長い旅になる。いつか全ての国を読破し、世界地図を塗り潰せる日が来るだろうか。私の人生にまたひとつ、明かりが灯った気がした。生きることが、すごく楽しみだ。
2022.2.24 Thu
210日目。
カラ兄:上巻 37ページ
ボローニャに留学中に知り合った日本の友人と、久々の再会を果たす。西早稲田にあるイタリア料理店へ行き、数年ぶりにイタリア気分に浸る。
留学先で出会った友人たちと時間を過ごすと、あのボローニャでの、楽しかった日々が蘇ってくる。
都内のイタリア料理店を開拓する委員会、ボローニャ支部の発足を表明する。第1回は、イタリア人シェフが作るアブルッツォ料理店で、大満足のスタートを切った。都内の本場イタリアンを知り尽くす、プロフェッショナルへの道は続く。
表参道のポストカード専門店、<Tout le monde>へ。最近ポストカードの収集にハマっていて、ここはずっと気になっていたお店だった。フランスから直接買い付けたカードもあり、種類が豊富で、眺めているだけでも楽しかった。

その後、そう言えばコーヒー豆が無くなりかけていたことを思い出し、「表参道 コーヒー豆」で検索。ヒットした<KOFFEE MAMEYA>というお店へ。
到着して驚いたのだが、店の外に行列ができていた。入り口も、高級蕎麦屋のような佇まいで、これはパッと検索してふらっと来るような場所ではなかったか?と尻込みしつつ、店内へ。

浅煎りから深煎りまで、世界中の豆が20種類近く用意されていて、店員さんとお話やテイスティングをしながら、好みのコーヒー豆を見つけるスタイル。ひと組につき1人担当がつき、じっくりと好みをヒアリングしてくれる。これは、行列ができるのも頷ける。
浅煎りと深煎りの豆を1種類ずつ購入。豆の産地や挽き目のサンプル、淹れ方のコツまで細かく解説してくれて、特にコーヒーの淹れ方に悩んでいた私にとっては、目の前での実演がありがたかった。


近年稀に見る良い休日を過ごせたので、思わず長々と書いてしまった。普段家から出ることのない私にとっては、年に数回の、非常にアクティブな休みだった。
2022.2.25 Fri
211日目。
カラ兄:上巻 37ページ
大学時代、私は茶道部に所属していた。
表千家の茶道部で、週に1〜2回ほど和室に集まり、お点前の稽古や、お茶会の準備などをして活動していた。
部の雰囲気はゆるゆるで、そこに惹かれて入部したところもあるのだが、着物を着たり本格的な和菓子を用意したりはせず、私服でラフに稽古をしていた。お茶請けは、部員が海外旅行のお土産で買ってきた、世界各地のお菓子であることが多かった。月に1回お茶の先生がお見えになり、お点前の指導をしてくださるのだが、それが無ければ満足に薄茶点前も覚えられなかったのではないかと思うほど、とにかくゆるい部活だった。
私は、空きコマができると和室へ行き、無心でお茶を点てて心を落ち着けるのが好きだった。和室に行けば大抵誰かが稽古や談笑をしていて、すぐに茶室で練習することができた。お客としてお抹茶とお菓子をいただくのも良かったが、私はやはり、心を無にしてお茶を点てることが好きだった。何かうまくいかないことがあっても、ゆっくりとお茶を点てているうちに、心を入れ替えることができた。
森下典子さんの『日日是好日』を読み、あの茶道部での日々を思い出した。
お茶のお点前は、初めは意味のわからない型通りの動きを、とにかく覚えていくしかない。そして、それまでぎこちなかったお点前が、流れるように一本の線になる瞬間がやって来る。考えるよりも先に手が動くあの感覚のことを、森下さんが『日日是好日』の中で書かれていて、思わず「そうそう!」と頷いてしまった。無心でお茶が点てられるようになると、茶道は本当に楽しいのだ。

大学を卒業して以来、茶道とはすっかり疎遠になってしまったが、いつかまたお茶を点ててみたいと、そう思わせてくれる本だった。
2022.2.26 Sat
カラ兄:上巻 57ページ
スズキナオさんの『遅く起きた日曜日にいつもの自分じゃないほうを選ぶ』を読む。
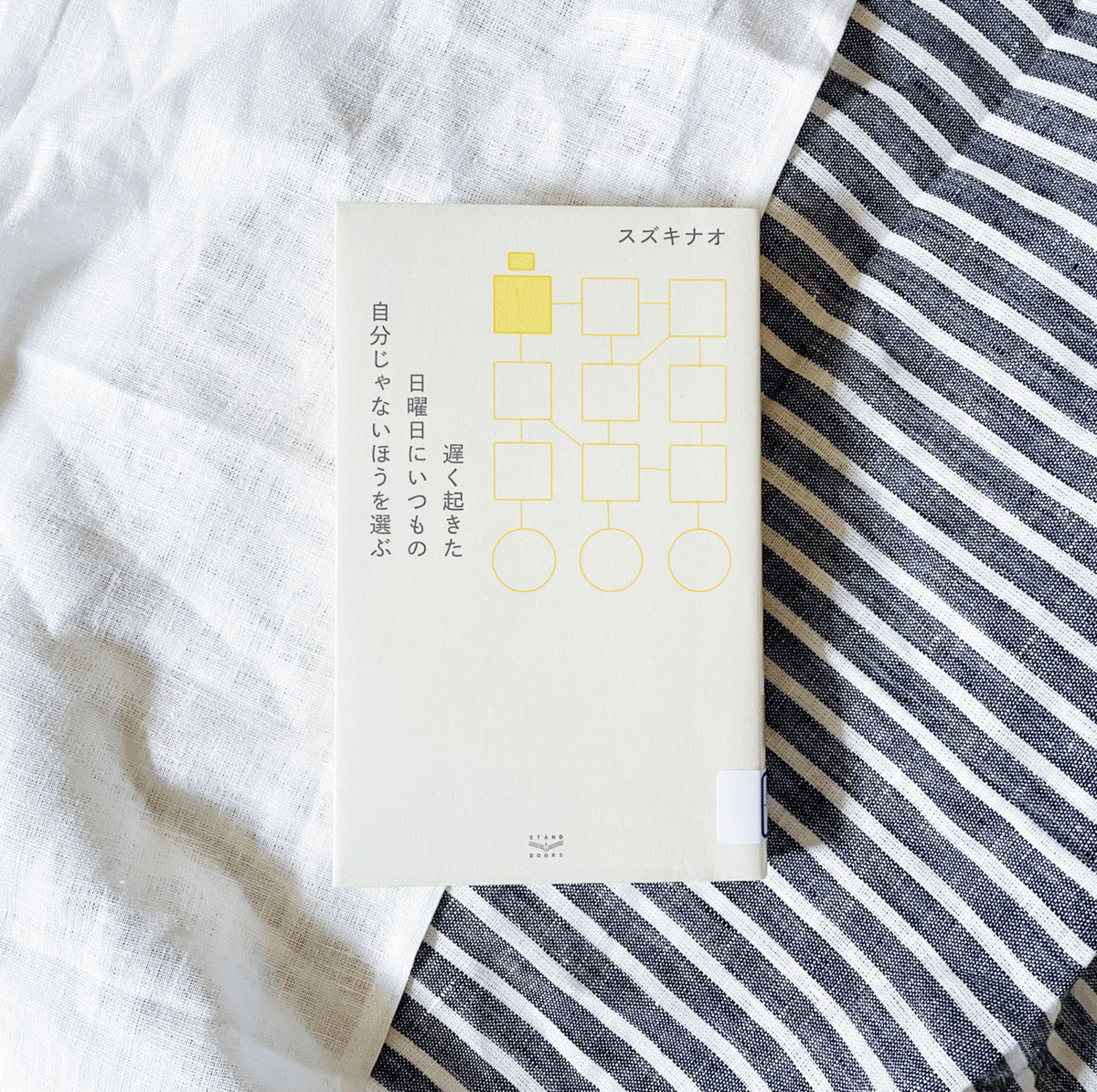
本書の中には、忘れかけていた細やかな幸せが詰まっている。スズキさんが休日にやったことを書いているだけなのだが、日常の小さな幸福の香りが、ほのかに立ち昇ってくるようだ。
例えば関東圏に住んでいて、朝イチ新幹線で京都へ行き、ぶらりと街を歩いて、夜には帰る。普段家でダラダラ過ごす休日とは雲泥の差だが、時間としては同じ1日だ。たった1日の休日で、ひとは東京-京都間を往復することができる、実はこんなにも行動できるのだということに気づいて、感動する。本書を読んでいると、あの感覚が蘇る。京都に行かなくても、自分の生活圏の中でだって、行動次第で濃い1日にすることができる。
特に良いなと思ったのは、タイトルにもなっている、「いつもの自分じゃないほうを選ぶ」1日だ。一言で言うと、いつもの自分ならこう選択するだろうなと思うことと、真逆の選択をし続けて1日を過ごすのだ。間違いなく、刺激的な休日を過ごすことができる。
また、「ガチャガチャマシーンからつまみが出てくる飲み会を開催してみた」も最高にアホらしくて良いし、「家の中のお気に入りポイント「俺んち絶景」を見せ合ってみる」なんて、今すぐ友人とやってみたい。
永井玲衣さんの『水中の哲学者たち』を読んだ時にも感じたことだが、日常を楽しむためのヒントは、既に私たちの周りにたくさん転がっているのだ。それをどのように拾い上げていくのか、そのヒントを、本は私たちに教えてくれる。そしていつか、自分だけの楽しみ方を見つけることができれば、人生に敵は無いはずだ。
↓「世界読書巡り」は、「読書で世界一周」としてシリーズ化し、記事を投稿しています。ぜひこちらもご覧ください!
↓「今日も、読書。」のイチオシ記事はこちら!
↓「今日も、読書。」の他の記事はこちらから!
↓本に関するおすすめ記事をまとめています。
↓読書会のPodcast「本の海を泳ぐ」を配信しています。
↓マシュマロでご意見、ご質問を募集しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
