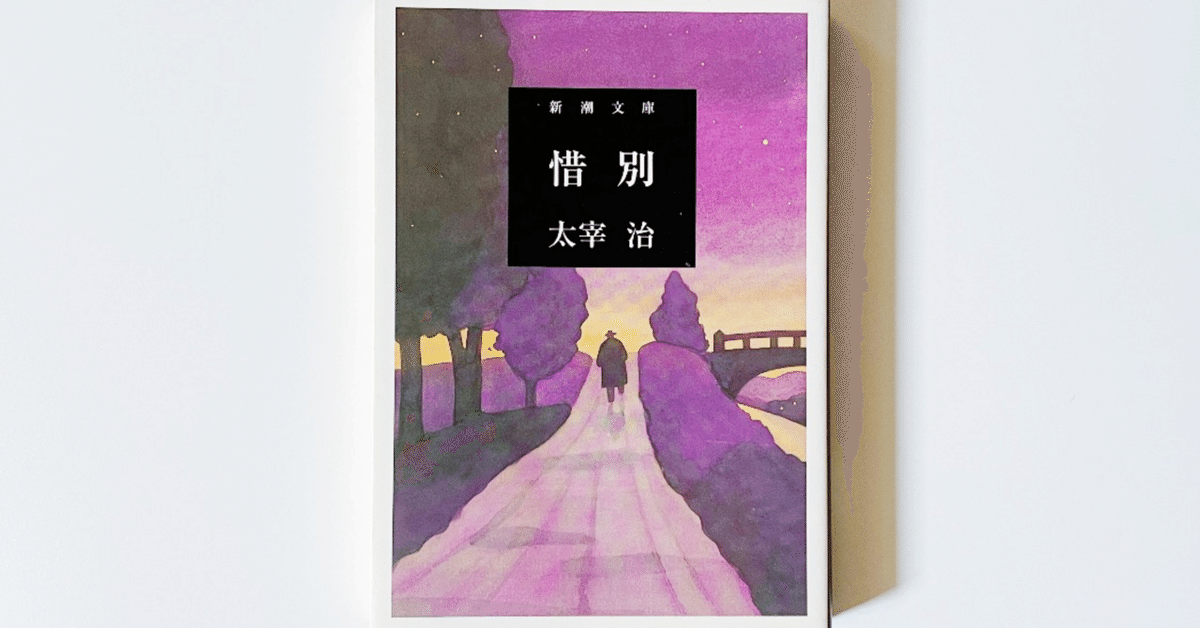
#10 太宰治全部読む |大戦が生み落とした名文
私は、太宰治の作品を全部読むことにした。
太宰治を全部読むと、人はどのような感情を抱くのか。身をもって確かめることにした。
前回は難敵『二十世紀旗手』に挑戦し、敢えなく敗退を喫した。太宰史上最も錯乱した作品たちは、何度読んでも、解読不能だった。
今回は、記念すべき第10回目となる。第二次世界大戦期に執筆された2編を収めた、『惜別』を取り上げる。
太宰治|惜別

仙台留学時代の若き日の魯迅と日本人学生とのこころ暖まる交遊の描写を通して、日中戦争という暗く不幸な時代に日中相互理解を訴えた表題作。"アカルサハ、ホロビノ姿デアロウカ。人モ家モ、暗イウチハマダ絶望セヌ"敗戦へとひた走る時代風潮に対する芸術家としての自己の魂を、若き頃からの理想像、源実朝に託して謳う『右大臣実朝』。太宰文学の中期を代表する2編を収める。
新潮文庫『惜別』には、戦争中に書かれた中編が2つ収められている。
戦争が泥沼化していき、周囲の作家が次々と執筆活動を中断する中、太宰は精力的に作品を発表し続けた。
戦時の日本文壇を支えたのは、太宰だったと言っても過言ではない。
「右大臣実朝」も「惜別」も、太宰作品の中でも特にしっかりと構成が練られた、美しさの光る小説だ。
軍部の検閲が厳しく、世間が戦争へと呑み込まれていく状況で、それでも小説を書き続けた太宰。それも、こんなにも生き生きとした、手の込んだ小説を。
当時の世相を考えながら読むと、太宰の作家人生に対する覚悟や、文章を書く喜びのようなものが、伝わってくるような気がする。そんな読書だった。
右大臣実朝
「右大臣実朝」は、太宰としては珍しく、嬉々として執筆に打ち込んだ作品だと言われている。源実朝を題材にした小説の執筆は、彼の幼少の頃からの念願だったという。
本作は、『お伽草紙』などのように、『吾妻鏡』という既存の文学作品を題材にして書かれたものだ。これは太宰が得意とする手法のひとつであり、既存作品を太宰調で読むことができて大変面白い。
ちなみに、『吾妻鏡』の原文が各所に挿入されているのだが、私は読み飛ばしてしまった。それでも充分に楽しめる作品である。
あらすじでも引用されているが、本作で特に鮮烈な印象を与えるのが、以下の文章である。
アカルサハ、ホロビノ姿デアロウカ。人モ家モ、暗イウチハマダ滅亡セヌ。
(明るさは、滅びの姿であろうか。人も家も、暗いうちはまだ滅亡せぬ。)
日本が戦争へと盲目的に猛進していく、狂気的な熱に当てられた社会。
その中にあって、太宰は「日本の滅亡」を垣間見たのではないだろうか。
これまで『ヴィヨンの妻』や『人間失格』などの作品を読んできた身からすると、これは本当に太宰が書いた小説なのかと、疑いたくなる気持ちもあった。
「右大臣実朝」には、軽口やユーモアはなく、かと言って陰鬱な雰囲気もなく、非常に完成度の高い「純粋な歴史小説」となっている。深く構想が練られていることが窺える。
大戦中にあって、平教経や源義経といった武将ではなく、源実朝のような風流人を描いたという点も興味深い。
日本を支配していた軍部への精神的抵抗として、源実朝の風流・芸術・貴族の生き方を描き出し、その素晴らしさを伝えようとしたのではないか、とも考えられる。
それにしても、物語終盤の実朝の意気消沈ぶりは、読んでいてとても辛かった。
わかるよ、当主なんてやりたくないよね……。実朝は、ただ純粋に、和歌を詠むことが好きだっただけなのに……。
惜別
「惜別」は、昭和18年に内閣情報局と文学報国会の依頼を受けて書き下ろした、太宰唯一の国策小説。依頼を受ける前から、構想自体は練られていたと言われる。
本作は、とある東北出身の日本人医学生が、仙台に留学していた時期の魯迅(周樹人)と交流する日々を描いた作品だ。
後に文学者として大成する魯迅だが、彼の青年期はどうなふうだったのか……と、想像が膨らんでいく小説である。
本作では、魯迅を通して、太宰本人の思想や告白が表れている。魯迅が、とにかくよく喋るのだ。
日中戦争の時代、中国人への差別が横行していた頃だが、太宰は本作で、真の日中親善を描き出そうとした。彼が注意深く筆を進めたであろうことが、文章からよく伝わってくる。
他の太宰作品と異なる点としては、やはり国策小説ということもあって、所々に日本賛美・天皇崇拝の趣が感じられる。
英語は一切出てこないが、同盟国であるドイツ語はバンバン出てくるところも面白い。
敗戦後、太宰は日本の現実に失望しきった作品をいくつも書く。そのような作品を、これまで「太宰治全部読む」で読んできた分、日本を賛美するような「惜別」の特異さが際立ち新鮮だった。
読んでいて「おっ」と思った文章がある。魯迅の台詞の一部だ。
「文芸はその国の反射鏡のようなものですからね。国が真剣に苦しんでいる時には、その国から、やはりいい文芸が出ているようです。」
これはまさに、「惜別」を書く太宰自身の境遇と重なる。国が戦争で苦しむ中、いくつもの名作を世に送り出した太宰。
きっと戦争中、日本文学の文脈が分断されてしまうことへの憂いが、太宰の心中にはあったのだろう。
彼はあくまで小説の執筆を続けることで、その憂いを払拭しようとした。
太宰が何を思い、何を願いながら小説を書いていたのか。その心境を推し量りながら読む読書だった。
↓「全部読む」シリーズの続きはこちらから!
↓本に関するおすすめ記事をまとめています。
↓読書会のPodcast「本の海を泳ぐ」を配信しています。
↓マシュマロでご意見、ご質問を募集しています。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
