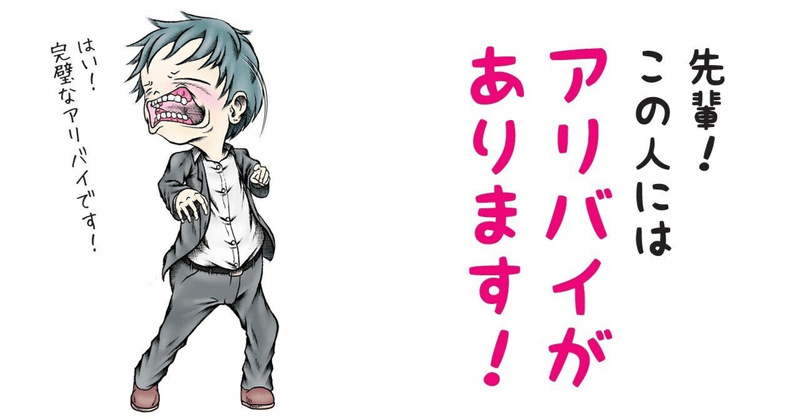
「アリバイづくり」のための「書類作成業務」が負担という話
人がいなくなる学校
学校現場の疲弊感については、すでに様々な媒体によって社会の知れ渡る点となった。その証左として、教員志願者数の減少というデータがある。
例えば、2020年の3月、関東圏における教員養成課程の雄である東京学芸大学の教員養成系学部の卒業生のうち、教員になった割合は55%にとどまったというデータがある(週刊東洋経済 2022年7月23日 「学校が崩れる」p42より)。
学校から人がいなくなっている。
先ほど引用した雑誌には、「都内の小学校に非常勤講師として勤務する女性は今年で82歳。」という衝撃的な文章もあった。
本誌が取材していると、女性の携帯電話が鳴った。相手は教頭で「また欠員がでてしまった。明日の午前中、授業に入ってもらえないだろうか」という相談だ。女性は二つ返事で応諾した。欠員の代替で入るのは今年3度目だという。
給与は週7時間の担当授業分を支払ってもらっているが、代替した授業時間分は無給だ。通常は毎日朝から夕方まで勤務し、給食の時間は特別支援学級の配膳も手伝う。「児童たちはひ孫に当たる年齢。子どもも授業も好き」だと笑顔で語る女性は、もし自分が代替を断れば学校運営がままならなくなることを、よく知っている。
学校現場は、僕も含めて「大量採用時代」に採用された「30代後半」が数多(あまた)いる。そして、彼ら彼女らは、今、まさに「産育休取得適齢」なのだ。本校にも、育休取得中の「男性教員」がいるし、「3歳未満の育児をしている」教員も複数名いる。後者の「3歳未満の育児をしている教員」については、「子どもが発熱した」などで、急な休みを取らないといけないことが多い。その場合は、校内の限られた教員でやりくりするしかない。本校でも、「一人で2クラスを同時に指導する」というのは常態化している。ちなみに、本校は「育休代替講師」は現在もいない。つまり、欠員も常態化している。
82歳で教壇に立つ自分を想像するのは辛い。現在、36歳の私でさえ、体力に不安を覚える事はよくある。子どもたちに授業をする喜びは否定しないが、この職務が「体力仕事」であることもまた否定できない。
アリバイづくりの書類作成
さて、そんな暗鬱となる話から、さらに辛い話を繋げていかないといけない事は心苦しいが、今回のテーマは「アリバイづくりの書類作成」である。
学校現場を疲弊させている要因は数多くあるだろう。しかし、我々を「本当に疲弊させる要因」というのは、他と区別がしやすい。その判定基準は、「その仕事の意味を見出せない」仕事である。
例えば、「教材研究」という業務がある。これは「授業準備」とは異なる意味で使っているのだが、それについては以下の記事をご覧いただきたい。
教材研究という業務は楽しい。そして、これは「授業改善」につながるので、その意味も見出しやすい。教材研究をすれば、授業の質は確実に上がる。だから、「教材研究をして疲れた」はあっても、「教材研究で疲弊する」ということを、我々はあまり感じない。それは、教材研究が有益であると実感できるからだ。
一方、「その仕事に意味を見出せない」仕事というのは、我々を疲弊させる。「疲弊」というのは、「疲れる」とは違う。疲弊は「疲れ、弱まらせる」のだ。つまり、生命力が奪われると言ってもいい。そして、そんな悪しき業務が、「アリバイづくりの書類作成」なのである。
いじめアンケート
今回は、その中でも「いじめアンケート」を取り上げたいと思う。
現在の学校現場において「いじめアンケート」を行なっていないという学校を見つけるのはかなり苦労するだろう。もしかしたら、田舎の超小規模だったらありえるかもしれないが、ほぼ全ての学校が「いじめアンケート」を行なっていると言っても過たないと思う。
この「いじめアンケート」には、かなりの「エネルギー」が奪われる。それは、アンケートを取ったら「はい、おしまい」という類のものではないからだ。
その手のアンケートもたくさんある。しかし、これらのアンケートは「取ったら、おしまい」というものなので、「授業時間が奪われる」ということはあっても「エネルギーが奪われる」という事はない(授業時間が奪われるのも大問題なのだが)。
いじめアンケートには「その後」がある。
いじめの定義
そもそも、いじめとは何か。
文部省による「いじめの定義の変遷」は以下のサイトより確認してほしい。
現在の文部省による「いじめの定義」は、「いじめ防止対策推進法」の施行に伴い、平成25年度からは以下のように定義されている。
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童児生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
この定義で大切な点としては、「一定の人間関係のある他の児童生徒が行う」、「影響を与える行為」に対して「児童生徒が心身の苦痛を感じているもの」という点であろう。
この定義について問題があることは、過去にも何度か論じているので、以下の記事をご参照いただきたい。
さて、いじめによる「心身の苦痛」は「見えにくい」。しかし、「いじめは放置できない」。そこでアンケートを取る。ここまでは、わかる。
しかし、繰り返すが、その定義が曖昧であるから、子どもたちも「何がいじめか」ということを考えることが難しい。そこで、「私が嫌なことは、すべていじめだ」ということになる。これは間違いではない。定義がそうなっているのだから、仕方がない。
例えば、僕が担任している二年生の学級には「指をしゃぶる」癖がある児童がいる。彼女はその癖を止めることができない。しかし、彼女はそのしゃぶった指で、いろいろなものを触る。というか、小学生が狭い教室にひしめき合っている以上、「触れる」を根絶することは難しい。しかし、彼女に触られたくない児童もいる。そんな児童が、彼女に触れられれば「心身の苦痛」を感じるだろう。
これは、果たして「いじめ」なのだろうか。
また、彼女に触られたくないと表明することは、彼女に対する「いじめ」にはならないのだろうか。それは、彼女が「苦痛を感じるか」で判断される。
さあ、話がこんがらがってきた。
しかし、そういう「ややこしい」ことを「アンケート」で聞こうとしていることをわかってもらいたいのだ。
つまり、アンケートの「その後」である。
いじめアンケートの「その後」
いじめアンケートにおける「その後」というのは「事情聴取」である。彼ら彼女らが、「何に苦痛を感じていじめと判断したか。それを聞き取り、解決まで導く」。このプロセスも含めて「いじめアンケート」なのである。以下に、いじめアンケートに寄せられる「いじめ」の内容を列挙しよう。
・ドッジボールで自分ばかりが狙われる
・鬼ごっこで自分ばかりが狙われる
・ジャンケンでいつも負ける(感じがする)
・給食の配膳が少ない(と感じる)
・授業中に意見を言ったら、笑われた(気がした)
他にも挙げ出したら枚挙にいとまがないが、二年生の「感じる」ような「心身の苦痛」はよくわかる。そして、これらを「いじめ」にしてもいいのだろうか。このやり取りにかなりのエネルギーが奪われる。
もちろん、この事情聴取を行うのは「休み時間」などである。授業と授業の合間のわずかな時間に、何人もの事情聴取を行うことになる。
さあ、問題はこれが「教育に資する業務なのか」である。資するのであれば、我々は喜んでこの業務をする。それは、「教材研究では疲弊しない」と同じである。しかし、私にはどうもこれらの「いじめアンケート」が「資する」とは判断できないのだ。
しかし、「いじめアンケート」は蔑ろにはできない。これは、法律(いじめ対策推進法)にも制定されている通り、「学校の内外を問わず、いじめが行われなくなるようにすること」なのだ。だから、慎重を期して行われなければならない。もしも「いじめを認知していたのに、何も対策を講じない」ことがメディアに報道されたら、教師人生の破滅である。
ここで、本記事の題名に戻ることになる。
つまり、「いじめアンケート」は「我々の命を繋ぐためのアリバイづくりの書類」なのだ。
もし、保護者から訴えられても、
「はい、我々は、その件については認知しており、また指導を致しておりました」
というための「証拠書類」なのだ。
仮に、「その件については、認知しておりませんでした」という、過去の教育委員会が連発したようなことを口走ってしまったのならば、それはメディアから集中砲火を受けることになるだろうことは、過去の事例を見れば一目瞭然だ。
そうならないためにも、我々は「これが、いじめなのだろうか」という本音をしまい込んで、「ドッジボールというのはね、相手にボールが当てられるから面白いんだよ。誰にも当てられないドッジボールほど、寂しいものはないよ」という話を、子どもたちに今日もすることになる。
