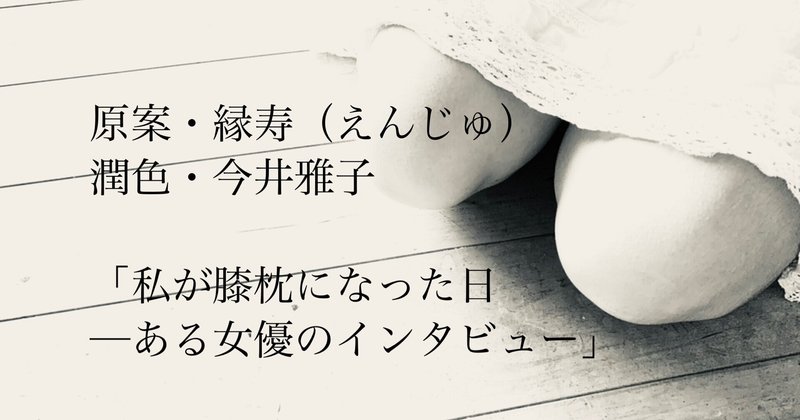
心の空腹を満たす膝─「私が膝枕になった日」
こちらで公開している「私が膝枕になった日─ある女優のインタビュー」(近道は目次から)は、2021年5月31日からClubhouseで朗読リレー( #膝枕リレー 経緯はこちら)が続いている短編小説「膝枕」(通称「正調膝枕」)の派生作品。
「人工知能膝枕」は登場せず、誕生の経緯は他の作品と異なりますが、詳しくはこの続きに。
二次創作noteまとめは短編小説「膝枕」と派生作品を、朗読リレーの経緯、膝番号、Hizapedia(膝語辞典)などの舞台裏noteまとめは「膝枕リレー」楽屋をどうぞ。
頭を預けることは自分を預けること
2021年5月31日にclubhouseで始まった膝枕リレー。このnoteを公開する7月31日で62日目。初日に次々と膝をつないだ膝枕三銃士(膝反射より食いつきが速い藤本幸利さん、「ミスター膝枕」徳田祐介さん、「膝蹴りの女王」下間都代子さん)が勢いをつけてくれたのが大きいが、面白がってくれる聴き手、二次創作を生み出す書き手を得て、思わぬ広がりを見せている。
「膝枕」が妄想をかき立てるだけでなく、思い出のスイッチを押すことを教えてくれたのは、若井尚子さんが書いた「おばあちゃんの膝枕」だ。
朗読を聞くと、心の中にいるおばあちゃんが呼び覚まされる。わたしはおばあちゃんっ子だったが、膝枕された記憶はない。けれど、おばあちゃんの膝に頭を預けている幼いわたしが思い浮かぶ。なんの心配もなく守られている心地よさに懐かしさを覚える。
世の中の怖さも将来の不安も知らない、小さな世界に生きていた頃の絶対的な安心感。「膝枕」はその象徴のようにも思える。
誰かに頭を預けることは、自分を預けること。
何も言わず、そのままの自分を受け止めてくれる相手がいる。それだけで、今ここにいる自分がまるごと肯定される。
短編小説「膝枕」に登場するのは、ヴァージンスノー膝が自慢の箱入り娘膝枕だが、「おばあちゃんの膝枕」は、無垢で、それゆえ弱くて傷つきやすくて、守られるべき存在だったヴァージンスノー時代の自分と向き合わせてくれる。
世界でいちばん好きな場所はママのひざ
2021年6月の終わり、膝枕リレー38膝目でご縁ができた活動弁士の縁寿(えんじゅ)さんが「膝枕」朗読ルームで二次創作が話題になっているのを耳にし、「私の忘れ得ぬ『膝枕』」とメッセージを寄越してくれた。
ベビーシッターをしていた頃に派遣された先で小学生の女の子に突然膝を求められた体験が縁寿さんの口調で綴られていた。
活動弁士の活写力もあるだろうが、何年も前の出来事なのに、つい先日のことのような生々しさを感じた。時を経ても忘れられないだけではなく、何度も思い返して煮詰められているような濃さがあった。
その少し前、わたしのパソコンが容量オーバーを訴え、フォルダに入っている写真を整理したら、娘が幼かったときのメモが出てきた。
「世界でいちばん好きな場所はママのひざ」
そんなことが書いてあった。膝枕リレーの影響で「ひざ」に反応した。娘の印象に残るほど膝枕してたっけと記憶をたどると、膝枕ではなく、娘を膝にのせて絵本を読んでいたのを思い出した。読み聞かせのときの指定席がわたしの膝だった。そこが世界でいちばん好きな場所になっていたとは。
自分を預けられる誰かの膝は、子どもにとってサンクチュアリなんだなと感じ、そんなに気に入ってくれていると知っていたら、もっと膝に甘えさせてあげれば良かったなと思っていたところに、「膝枕になったベビーシッター」の話が届いたのだった。
会ったばかりのベビーシッターに、どうしようもなく膝を求めた女の子。
その頭とさみしさを受け止めたベビーシッター。
子どもを置いて仕事に行かなくてはならない母親。
みんな懸命で、みんな切ない。
縁寿さんに語って欲しいと思った。縁寿さんが綴った体験を膨らませて、ある女優のインタビューという形のモノローグを書いた。
原案・縁寿 潤色・今井雅子「私が膝枕」になった日─ある女優のインタビュー」
もう一度会いたい人、ですか。
記者さんが聞きたい話とは違うかもしれませんが、時々、どうしてるかなって思い出す人がいるんです。
もう20年ほど前になりますが、シノギでベビーシッターをやっていたんです。ある日、単発で、ベビーではなく小学校高学年の女の子を見ることになりました。熱を出したので学校を休ませることになり、親が仕事に行っている間、自宅でつき添っていて欲しいという依頼でした。
産気づいた妊婦さんを病院に運んで出産に立ち会うことになったり、両親がテレビ局のディレクターでグレてしまった子になぜか気に入られてたびたび指名が入ったり、とんでもないお金持ちの豪邸でお嬢様のわがままに振り回されたり……。連続ドラマ「ベビーシッターは見た」が作れそうなほど、派手なネタには事欠かなかったのですが、いちばん印象に残っているのは、熱を出したその女の子と過ごした一日でした。
放課後はいつも一人で留守番しているので、親がいないことには慣れているという話でした。赤ちゃんのようにオムツを替えたりミルクをあげたりする手間がかからないし、絵本を読んだり歌を歌ってあげたりする必要もない。ただ見守っているだけでいいのです。出勤前の母親から申し送りを受けながら、今日はラクさせてもらえるなと思っていました。
ええ、手のかかる赤ちゃんでも、手のかからない小学生でも、ベビーシッターの時給は同じだったんです。
依頼人の一人っ子らしい女の子は、熱があっても礼儀正しく、大人しそうな子でした。横になったまま私を見て、よろしくお願いしますと言い、お辞儀をするように首を動かしました。普段から大人の言うことをよく聞く「いい子」なのが、すぐにわかりました。
二人きりになって30分くらい経った頃でしょうか。熱が下がっているか見ようとして女の子のおでこに手を当てたそのとき、横になっていた彼女が体を浮かせました。
次の瞬間には、小さな頭が私の膝の上にありました。何の前触れもなく、突然、彼女は私の膝を求めたのです。
「具合が悪いから、心細くなったのかな」
そう思って、彼女の髪を撫でながら、そのまま好きにさせていました。熱で汗をかいているせいか、顔に張りついた髪はじっとり湿っていました。
私の両腿にしがみつくように、彼女が手を伸ばしてきました。まるで、助けを求めてすがりついているような必死さを感じて、私は身動きが取れなくなりました。
その日に限って、私はGパンをはいていました。しかも、正座が苦手でした。太ももから脛にかけて圧迫された足が、しびれを訴えました。けれど、姿勢を変えるわけにはいきませんでした。
「ちょっといいかな」と声をかけるのも憚られました。
顔を私に見られないように顔を太もも側に向け、私の膝に吸いつくような格好で頭を預ける彼女の切羽詰まったさみしさが、膝を通して伝わってくるのです。
下手に動いたら、彼女を振り落としてしまう。そんな気がしました。もし、鼻の穴に虫が迷い込んでも、あのときの私はくしゃみを我慢したことでしょう。
会ったばかりの私に彼女はすべてを預けていました。私にできることは、ただ受け止めることでした。少しでも私が姿勢を崩したら、ぎりぎりのところで成り立っている彼女との信頼関係が壊れてしまうように思えました。
彼女も私も口をきかず、黙ったまま、時間だけが流れていきました。彼女が寝ついてしまったら、そっと膝を外すつもりでしたが、寝息は聞こえてきません。
そのまま2時間くらい経った頃でしょうか。足が鬱血してくるのを感じ、これ以上は無理だと私は音を上げました。
「ごめんね、トイレ行って来るね。すぐ戻るからね」
そっと膝を外させてもらい、しびれる足を踏ん張って立ち上がると、よろめきながらトイレに向かいました。便座に腰を下ろし、自由な両足を曲げ伸ばしし、束の間の休息を味わうと、ようやく感覚の戻った両足で床を踏み、彼女の元に戻りました。
もしかしたら彼女はもう気が済んだかもしれないという淡い期待は裏切られ、彼女はまた何も言わず、私の膝に頭を預けるのでした。
「お水飲む?」「なにか食べる?」と勧めましたが、彼女は水にも食事にも興味を示さず、私の膝だけを求めました。
あれほど、どうしようもなく、狂おしく、誰かに求められたことは、後にも先にもありませんでした。
彼女に膝を貸しながら、私は自分が子どもだった頃のことを思い出していました。小学一年生のときに両親が居酒屋を始めました。店は住まいから数キロ離れた場所にあり、夜はずっと妹と二人きりでした。妹とは気が合わなかったので、一人でいるよりさみしく、夜が長く感じられました。
けれど、母の前では、物分かりのいい子でした。さみしさを訴えたところで、母を困らせるだけなのはわかっていました。お姉さんなんだからしっかりしなくてはという気持ちもありました。家を出る母に「行かないで」と言えないかわりに、立ち去る背中に向かって念じていました。
妹が先に寝つき、時計が時を刻む音が大きく聞こえる部屋で母の帰りを待っていると、たまらなくなって家を飛び出し、母がいるはずのないバス停で母の姿を探したことがありました。母によく似た背中を見つけ、「お母さん!」と声をかけると、振り返ったのは、母には似つかない見知らぬ女の人でした。
そのとき、自分の思いがけない大きな声に驚くとともに、それほどまで母に飢えていたのかと思い知りました。
我慢を重ねると、そのことに慣れてしまい、自分に無理強いしていることを忘れてしまうのです。あるいは、大丈夫という強がりの暗示で自分を騙していたのでしょう。
私の膝を求めてきた女の子も、目の前の膝に衝動的に飛びついてから、それを求める心の飢えに気づいたかもしれません。
Gパン越しに伝わってくる彼女のさみしさは、かつて私が味わったさみしさでした。私は、大人として彼女をいたわるよりも、あの頃の自分への哀れみを感じていました。彼女に膝を貸しながら、あの頃の自分を甘えさせていました。
彼女は汗をかいたシャツを2度取り替え、水分を取り、トイレに1度だけ行きました。その間だけ、私の膝は自由になりました。
正座にいくぶん慣れた私は、彼女を観察する余裕ができていました。胸が膨らみかけ、体つきは大人になりつつあっても、心はまだまだ子どもで、母親の膝を求めるのだなとぼんやり思い、何を言ってるの、すっかり大人になった今だって、誰かの膝に甘えたい気持ちはあるじゃないのと自分をからかいました。
夜になって母親が帰宅しました。玄関のドアが開く音が聞こえると、彼女はすっと私の膝から離れました。先ほどまで頭を預けていた膝にも、私にも見向きせず、頭から布団をかぶりました。
熱が下がったことは、Gパン越しに伝わる温度で感じていました。その熱は病気のせいではなく、膝を求める切ない気持ちが熱を放っていたのではと思えました。
仕事に出かける前の支度の時間を縫って母親が用意してくれていた食事は、手つかずなままでした。彼女の分も、私の分も。ベビーシッターの日報には、ありのままを書きました。水分よりも食事よりも心の空腹を訴えた彼女のことを。それを読んだ母親は、一日中膝を求めた娘のさみしさに気づいたでしょうか。それとも、気づかないフリをしたでしょうか。
あれから20年あまり。あのときの女の子は今はもう30を過ぎ、もしかするとあのときの彼女と同じくらいの子どもがいたりするかもしれません。
私にとっては忘れられない、膝枕になった一日のことを彼女は覚えていないでしょう。それでいいのです。ただ、たった一日、むしゃぶりつくように膝を求めたあの日が、彼女の空洞をいくらかでも埋められたとしたら、私が子どもの頃に感じたさみしさも報われる気がするのです。
ねえ、記者さん。どうして泣いているの?
膝を求める理由
ところで、このnoteを書くにあたり、娘が書いた「一番好きな場所はママのひざ」のメモを探したが、見つからなかった。
かわりに掘り出されたのは、わたしの悪筆のメモだった。
「せかいじゅうどこにいてもままのひざがいちばん」
という走り書きの下に「これまでの人生で一番印象に残ったことは?」と書いてある。下にあるのが質問で、上が答えなのだろうか。
娘が書いたメモというのは思い違いで、わたしが見たのはこのメモだったのかもしれない。数か月前の記憶ですらあやふやで、それゆえ、縁寿さんの心に今もありありと描き出されるあの日の「膝枕」の生々しさに、あらためてうたれる。
「せかいじゅうどこにいてもままのひざがいちばん」と書き留めた記憶も残っていなかったが、メモの続きに、これもわたしの悪筆で
「ママ ねてるあいだにしんじゃわないよね にほんに帰れない」
とあり、その言葉を娘に言われたことは、よく覚えていた。
会社勤め時代の上司の結婚式に出席するため、初めて海外へ連れて行ったのだが、言葉の通じない国に母親と二人きりという状況が、「ここでママが死んだら日本に帰れない」と思い詰めさせてしまっていた。
「そんなこと考えてたんだ?」と驚くと同時に、子どもにとって親の存在は絶対で、とてつもなく大きいのだと思い知った。「膝枕」のもたらす安心感と対になる話だと思う。
今ここにいる自分を受け止めてもらうだけでなく、相手も今ここにいて、どこにも行かないことを確かめるために、子どもは膝を求めるのかもしれない。
膝開きは縁寿さん
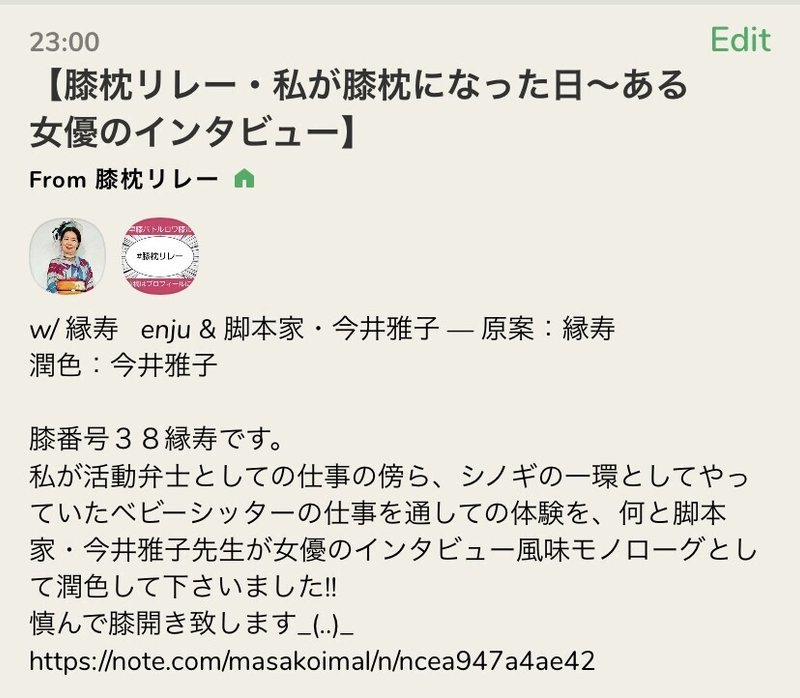
縁寿さんは途中でふと読むのをやめ、そこで気持ちが途切れ、続きは原稿ではなくご自身の体験を振り返りながら語る形になった。潤色のないむき出しの状態になったともいえ、ますます物語と現実の境目が消えて溶け合った。
その次の日、あつこさん(膝番号68)が続き、しばらく時間が空いて、10月になり、水野智苗さん(膝番号71)とFUJIKO ITOさん(膝番号25)が朗読。読み終えた後、それぞれが膝枕したりされたりの思い出を語ってくれる。
Clubhouse朗読をreplayで
2021.12.13 堀部由加里さん
2021.12.29 酒井孝祥さん
2022.1.1 水野智苗さん
2022.1.10 東千絵さん
2022.6.4 鈴木順子さん×縁寿さん作・演「膝枕の君に寄せて」(膝開き)2本立て
目に留めていただき、ありがとうございます。わたしが物書きでいられるのは、面白がってくださる方々のおかげです。
