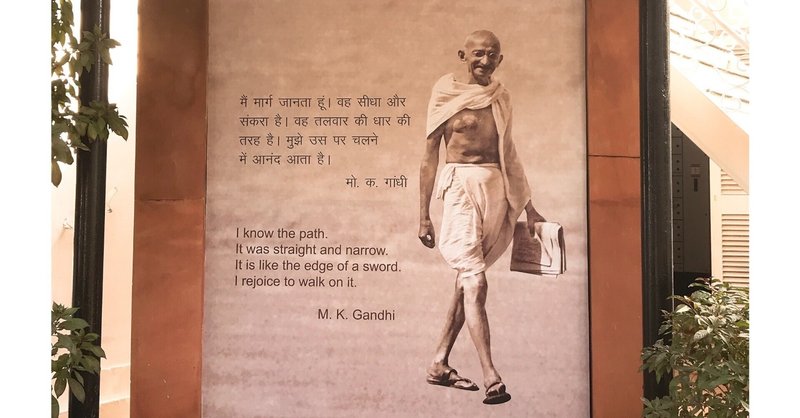
自分の道を思い描く
「学びは学習者が主体的に取り組んだときに、はじめて自分のものになる」
これは、私が常日頃思っていること。
私は教師になりたかったわけではない。
ただ、子供たちの可能性を広げたい。
その子供たちに触れ合えるのが「教育現場」と単純に思ったから、教師をやっているだけ。
大学卒業後すぐに教師にならなかったのも、教師になることが目的ではなかったから、寄り道をしていた。結局、卒業して5年後に初めて小学校に勤務した。
誰でもできることは、誰かに任せればいい。じゃぁ、私は何をするのか。誰もしないこと。そこを目指していた。
そこで、ある一つの解にたどり着いた。
「本気で学びたい人に、本気で教えたい。一緒に学びたいし、考えたい」
今でも自分の中の中心にある信念はこれのような気がする。
もともとあった自分の気持ちに経験が重なり、この思いが強くなったような気がする。インドでの経験、フィリピンでの経験、自分の過去の経験。そして、そこに加えて私の頑固な性格(笑)
さまざまなものが組み合わさって、出来た私の信念、価値。
「生きる力」「生きる力」と言われているが、生きる力をどう育むか…。私はそんなことよりも、まず「生きたいと思う気持ち」を先にもたせる必要があると思う。そして、大学院の入学の小論文にもこのことを書いた。
私は、やりたいことがたくさんあって、1日24時間では足りない。でも、長く生きたいとは思わない。なぜなら、世の中面白くないから。楽しいと言えば楽しいよ、その瞬間瞬間は。でも、私の中の真の楽しさには、残念ながら到達しない。
子供たちも一緒なんじゃないかな?その一瞬は、今は楽しいかも知れない。でも、将来のことを考えて親や教師、大人が不安になっていたら、子供たちにも伝染しちゃう。
最近子供たちからよく聞く言葉。
「つまらない」
「(心の中で)めっちゃ、わかるよ!」とつぶやく。
VUCA(ブーカ)の時代。「先行きが不透明で、将来の予測が困難な状態」とばかり言われているが、だから何?予測困難なのに、何に備えるの?この先、困難な状況が待ちわびているのなら、せめて今だけでも子供たちには楽しい時間をあげたら?そして、教師としての私ができる楽しい時間とはクリエイティブさを発揮させせる時間だと思う。
もちろん、誰もがこの考え方をしているなんて思わないし、不安だからこそ、もしもの場合に備えるっていう考え方も一理あると思う。もちろん何が正解で何が不正解かは分からないけど、自分自身にとっての「~したい」が行動力、思考力を一番生むのではないかと考える。
今、大学院に通っていて、英語に苦しんでます。
「IBを勉強したい」「大学院で研究したい」と思った中で、私の苦手な英語もなぜか一緒に飛び込んできた。
めちゃくちゃ苦しいです。学費をIBに払ったというより、英語学習に払っている感じです。でも、私の目標は英語習得ではないです。その先にあるので、どう英語に立ち向かうのか、どうやりきるのかの方法を考えなきゃいけないし、英語のせいでやりたいことを失うのも嫌だ。
やっぱり「~したい」が全てを支えているように感じる。
取りあえず、自分の未来を信じて今は頑張る!!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
