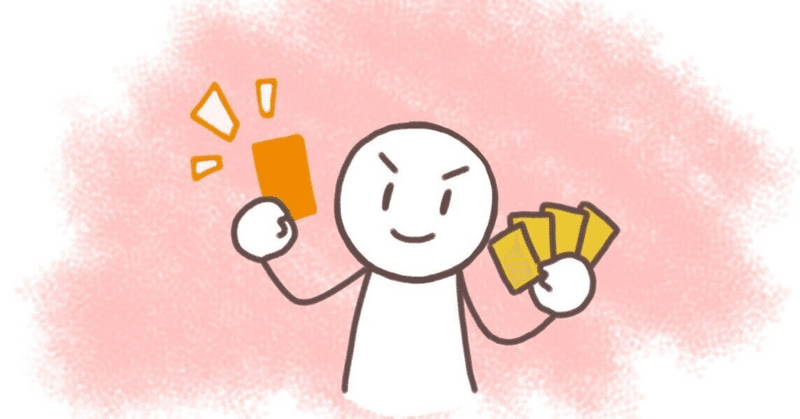
「決断と結果から,どう学ぶべきか」という本を読んだ
『How to Decide 誰もが学べる決断の技法』を読みました.本書はカーネマンやテトロックといった,合理性研究のスーパースターたちの協力のもと書かれています.そのため,ファクトチェックは十分だと思います.
個人的には,決断の本というより,上手にPDCAを回すための本として,とても参考になりました.参考になった点を以下にまとめます.
1.決断の良し悪しを,結果だけで判断しない
決断の良し悪しを,結果だけで判断しないこと.結果だけで判断すると,運の影響を過小評価する(実力とまぐれを混同する).また,「後知恵バイアス」により,事前に予測可能だったと思い込みやすい点も注意.
これらの対策として「反事実思考」が有効.「起こらなかったが,起きたかも知れない事実(反事実)」を書き出してみる.このとき,「自分でコントロール可能なこと」と「自分でコントロール不可能なこと」にわける.そうすることで,実力と運の影響を分析できる.
2.良い選択肢を発見するために,「外の視点」を活用する方法
現在の自分の視点だけでは,様々な認知バイアス(確証バイアス,自信過剰,直近効果など)により,選択肢が偏ってしまう.以下の視点で,選択肢を発見し評価することで,偏りを減らす.
・失敗した自分の視点
・成功した自分の視点
・未来の自分の視点
・統計
・他者の視点
3.他者やグループからフィードバックをもらうコツ
他者からフィードバックをもらうときには,「自分の意見」と「結果」を言わないこと.判断に必要な情報だけを伝える.これにより,偏りの少ないフィードバックをもらえる.
グループのときは,各人から偏りのない意見をもらうことはさらに難しくなる.なぜなら,「先に言った人」,「地位の高い人」,「実力者」などの意見に影響されるためである.そのため,あらかじめ判断に必要な情報を提供し,匿名で意見を連絡してもらうことが有効.
4.迅速に決断すべきこと
悩むより行動から学んだほうが良いことは結構多い.以下に,迅速に決断すべきことをまとめる.
・1年後の幸福に影響しないもの(どの映画観るかなど)
・得しかないもの(値切り,デートに誘う,仕事のオファーなど)
・同じレベルのもの(パリに行くか,ローマに行くかなど)
・取り返しのつくもの(始めるコストもやめるコストも低いものなど)
本書は,中学生の課題図書にしたいくらい,楽に読めて役に立つ内容でした.ワークブックのような形式で書かれています.そのため,理解が容易で実践的です.ぜひ読んでみてください.
おわりに
決断には,「判断基準」と「情報」の2つが必要だと思っています.本書では「判断基準」として「確率」を重視ししていたが,私は「確率」は大事ではないと思っています.なぜなら,人生は死んだら終わりだからです.死ぬリスクがなければ何度も挑戦できるため,人生においては「確率」より「損害」が大事だと思っています.この考えは『半脆弱性』という本から得たものです.この本は,不確実性に満ちた世の中での生き方について洞察に満ちた本なので,「判断基準」が欲しい人は読んでみてください.
以上です,最後まで読んでくれてありがとう.
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
