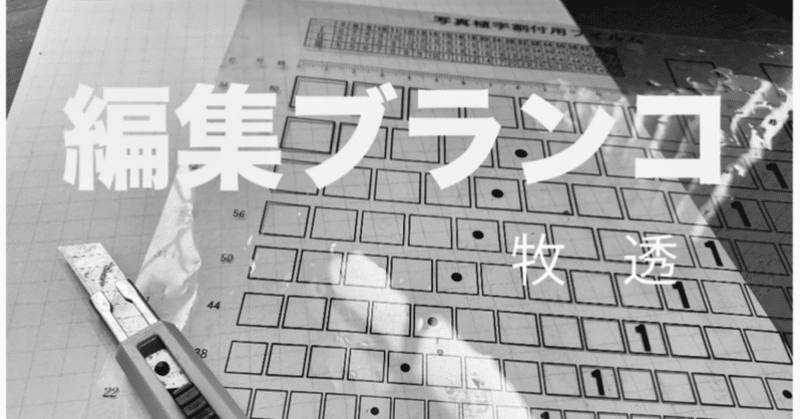
私の仕事人生(下)
大学浪人がジャズ喫茶のマスターに勧められて三流週刊誌のデーターマンをした。キャバレー、トルコ、ストリップ、バー、居酒屋などをまわってアンケート程度の取材をしてくるのだった。どこへ行って遊んでも仕事になった。不思議と怖い目に合わず、大したアルバイト料でなかったが面白いように稼いだ。そして恋をして、そんな世界から足を洗った。
今思えば、昔から型どることが得意だった。通信簿の図工はずっと5だった。何のことはない。喘息で寝込んでばかりいたから、寝床で絵ばかり描いていたのだ。そんなわずかな能力が編集のレイアウトや文章の組み立て方に生かされてきたのだろうと思う。もちろん仕事になるまでには成功ばかりではなかった。目の前で原稿を破られたこともある。しかしニ度目には不思議と仕事になった。
当時、編集の仕事はそれまでの机上の作業からコンピューターの画面上での作業に変わる大きな転換期にあった。取材もメールで送ればそのまま活字になってレイアウトに流し込むことができた。文字も写真もデジタル化され、原稿用紙も印画紙もなくなった。クライアントはデジタル利用を必須とし、できない者はたとえ才能があっても著名でない限り敬遠された。筆とフィルムにこだわる芸術肌を大いに苦しめ、フリーのクリエーターにとっては器材の準備にそれ相当の金も必要だった。
地方にいれば車は欠かせず、その維持費もあった。自分は夕方5時から夜10時までの専門学校の警備員をした。幸い新しい世界の仕事は生き甲斐を気づかせてくれた。警備の仕事が自分に合っていたわけではない。編集技術の大きな変化の狭間でその区切りをつけてくれたのだ。次へのステップになった。そんな気がした。
ステップに長い時間は必要なかった。警備員を3年程したところで思わぬ大きな仕事が入った。地元企業の記念誌で1年間を要する仕事だった。3分の1の経費が前もって支払われ、揃えたばかりのデジタル機器を大いに活用、先の短い未来をつかんだような自信へとつながった。その後もいくつかの仕事が入った。順当に稼ぎ、定期預金も初めて作った。
しかし、寄る年波には勝てずメニュエル病が襲った。病気ばかりではない。バブルはとうに過ぎコロナ禍となり、気づけば自分は後期高齢者となっていた。次第、あとは穏やかに生きたいという自分でも驚くほどの達観した気分が湧いた。わずかな仕事に励む孤独感は心地よかった。身辺整理と散歩を趣味に、本も新しいものより書棚の本を再読して処分することにし、散歩は市内の公園めぐりを楽しむことにした。
そして、冒頭のように残った仕事だけの自由業ということになり、書くこと・読むこと・歩くことを楽しむ余生と決めた。価値観が多様化し言語も美意識も変わって少々辟易気味の当世、無理なく自分をだいじに仕事もしながら生きていきたい。75歳、…ラストランだ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
