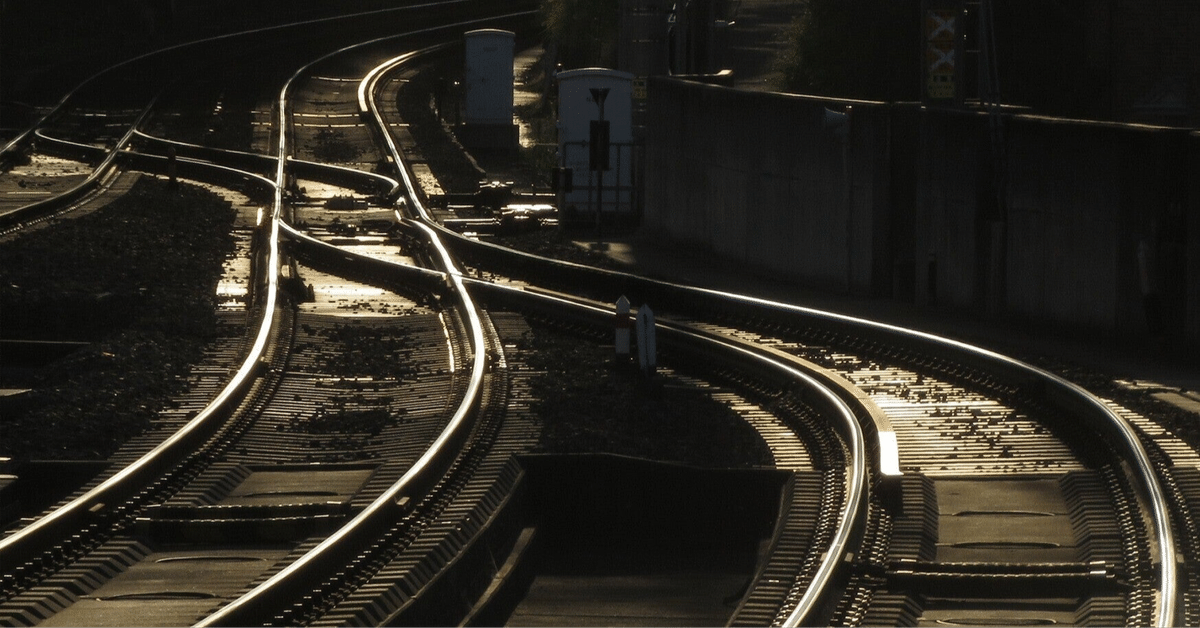
他の業者がよかったんだけど。。。
せっかく苦労したのに
意中のところにおちない
様々なプロセスを経てやっとのことでプロポーザルコンペまで辿り着き、更に民間事業者が企画提案書を提出してくれたのに、審査では意中の民間事業者が負けてしまった経験がある人も少なくないでしょう。
「他のグループの提案の方が良かったのに。。。」という思いを抱えながらスタートするプロジェクトが、本当に幸せなものになるのでしょうか。
パフォーマンスが悪い
あるいは、意気揚々と優先交渉権者と調整を経て契約に至ったのに、いざプロジェクトが始まってみると、企画提案で書かれていたことがただの絵空事でパフォーマンスが悪かったり、意思疎通がうまくできなかったりした経験はないでしょうか。
「十分な意思疎通ができない相手と進むこと」や公共資産・エリアのポテンシャルを活かせないプロジェクトがそのまちのためになるのでしょうか。
結局、うまく選定できていない
このような場面、自分自身も何度か経験してきましたが、やはり選定に向けたプロセス・要求水準書・審査委員会などの「つくりかた」「作り込み」が悪いからそうなってしまうのです。
残念ながら自業自得でしかありませんし、そのような経験知も蓄積することは決して無駄ではないですが、そこからキチンと学んでいくことが重要です。
更に言えば、先人がこのような痛い目に遭ってきたので、少なくとも確実に予見できるポイントについては共通項も多いので、押さえておくことで「初歩的なミス」を防ぐことができるはずです。
今回は、そのあたりについて考えていきたいと思います。
良いパートナーを選定するために
まずはビジョンとコンテンツ
やはり必要条件となるのはビジョンとコンテンツです。
そのプロジェクトにおけるビジョン、「何をしたいのか」「何のためにやるのか」を明確にしたうえで、それを実現するためのコンテンツ、「誰が・何を・どういう頻度で・どういう収支でやっていくのか」を整理し、要求水準書に落とし込むことです。それだけでなく、庁内でも共有すること、更にはサウンディング等を通じて応募しようとする民間事業者とも共通認識にしておくことが大切です。
拙著「PPP/PFIに取り組むときに最初に読む本」でも記載しているとおり、ビジョンは「みんな」「賑わい」といったマジックワードを使わず、抽象的・総花的な表現も排除して、人によって見解の違いが生じないようにしておくことが大前提となります。
優先順位
行政のハコモノ事業では、基本計画や公募の実施要領・要求水準書などで事業の目的が箇条書きで多数書かれていることが多くあります。
「ひとつのプロジェクトで行政の抱える経営課題を全て解決」できるようなことはありませんし、「あれもこれも」となっていることはビジョンが曖昧で定まっていない、軸がブレていて立ち戻る原点がないことを示しています。
民間から見ても、どこにターゲットを絞って提案して良いか見えにくくなってしまい、結果として「良いパートナーに巡り会えるチャンス」を逃してしまいます。
まちみらいで関わるプロジェクトでは、関係職員による徹底的なディスカッション、通称「地獄の缶詰作業」でビジョンの整理と合わせて叶えたいことを抽出し、優先順位の1、2、3位を決めていきます。
そして以降の要求水準書・採点表における配点などは必ずこの優先順位に基づくこととして、サウンディング等のプロセスで価値観が変わったときはここに立ち戻り、改めて優先順位の再設定及びビジョンの修正を行うこととしています。
民間事業者の思考回路
業務では民間事業者の企画提案書の作成支援を行うことも多いですが、民間事業者にとってプロポーザルでは「良い提案」をすることより「勝つ提案」をすることが求められますし、勝たなければ何も得られません。
そのために要求水準書を徹底的に読み解き「そのプロジェクトが求めていること」を導き出し、どのような提案すれば刺さるのか・自社のノウハウを活用できるのかなどを考えていきます。
更に誤解を恐れず言えば、要求水準書よりも重視するのは採点表です。配点の高い項目は1点たりとも落とすことがないようにコストをかけてでも提案をしていきますが、配点が低い項目や他社との差別化を図ることがほとんどない(≒点数差がつきにくい)項目は、極端に言えば「失格にならなければ良い」と割り切ります。そうしたところで割り切ってコストを落とすことで、価格点の獲得にもつながっていきますので、最後の最後まで「どうすれば1点でも点数を伸ばせるか」精査していきます。
同業他社がある程度見える場合は、相手の長所を消しながら自分たちのアピールにつながる提案なども考えていきます。
発注者としての行政は、このような民間事業者の思考回路もインプットしながら公募関連資料を整理していくことが求められます。
テクニカルな面での工夫
サウンディング
こちらのnoteでも書いたとおり、サウンディングを丁寧に積み重ねていくことも大切です。ビジョン・コンテンツ・与条件等を明確にしたうえで、きちんと自分たちから候補になりうる民間事業者へ営業し、本音で対話していきましょう。
「こちらのやりたいこと」と「民間のできること」を段階ごとに擦り合わせながらプロジェクトとして収斂させていくことが非常に大切です。久米島町のバーデハウス再生に向けたサウンディングでは、3期にわたって徐々に諸条件を絞り込んでいくこととしました。
包括施設管理業務では、「対象施設・対象業務(範囲)とやりたいこと」を示したうえで行う第1期と、それをベースに債務負担行為の設定額・要求水準書(案)などを示して行う「こういう条件で公募したいんですけど」の第2期で行うことが一般化していますが、少なくともこの程度はやっていきましょう。
要求水準書
サウンディングを積み重ねて、行政と応募を考える民間事業者の間である程度の共通認識が構築されてくれば、要求水準書で「わざわざ事細かに書かなくても良い」状況がでてきます。(サウンディングに参加しなかった民間事業者は本公募のときに行間のニュアンス等を類推しなければなりませんが、サウンディングに参加した事業者の「目に見えない・副次的なインセンティブ」としてあげて良いと思います。)
ビジョン・コンテンツ・与条件を明確にしたうえでサウンディングで市場性とマッチングさせていけば書くべき項目が明確になってくるので、そこだけ書けば良いのです。
「〇〇計画に基づき」「市では〇〇を推進しており」「〇〇という背景を」といった部分は冗長な情報であり、プロジェクトの質や民間事業者が企画提案書の作成には不要です。どうしても記したければ関連資料として添付すれば十分です。
特に前文・趣旨・頭書きの部分で明確に「何をしたいのか」「何を求めるのか」だけを書くことで、より民間事業者との共通認識が醸成されます。
コンサルタントにアドバイザリー業務等を委託すると、たいしたことないプロジェクトでも要求水準書が100ページを超えてきます。これは、サウンディングもなかった時代から脈々と過去事例を劣化コピーし続けてきたり、なんとなく厚い方が達成感があったり、室の面積や受付の人数まで記すような仕様発注になってしまっているからです。
「遵守すべき法律等」で地方自治法、建築基準法、都市計画法。。。と列挙し、最後に「関連するすべての法律等」といった表現をすることも多いですが、「関連する法律は遵守すること」だけで十分です。いくつかだけ特別に例示する意味はありません。
民間ノウハウをプロジェクトでクリエイティブに生かしていくためには、提案の自由度を高めることが大切です。そして民間と連携するうえでは契約もパフォーマンスに基づくSLA(Service Level Agreement)/KPI(Key Performance Indicator)が基本です。性能発注を徹底して、サービスレベルや最低限満たさなければならない項目、プロジェクトの成果指標だけ書くようにしましょう。
本公募に至るまでに自分たちのやりたいことが明確になっていて、民間事業者との信頼関係が醸成されていれば、要求水準書は非常に薄くできます。
ONOMICHI U2、津山市の糀ややGlobe Sports Dome、沼津市のINN THE PARKなどのイケてるプロジェクトはどれも要求水準書が非常に薄いのが共通項です。
企画提案書
民間事業者は、企画提案書の作成に膨大な時間とコストを投入します。どんなに労力をかけて提案をしても失注した場合には、そこに要したコストは返ってくることがありません(他のプロジェクト等のときに上乗せするなどしなければいけないので、結果的に不毛な戦いや不合理なプロポーザルを行政が繰り返していると、いつの日か自分たちも痛い目に遭います)。
要求水準書を薄くするのと同時に、企画提案書もシンプルにしていきましょう。
プロポーザルで大切なのは、自分たちのやりたいことと親和性が高くリアリティのある提案を提出した民間事業者を選定することです。
前述のようなプロセスを経ていれば、「何がプロジェクトのポイントなのか」が見えているはずです。ビジョン・コンテンツ・与条件から提案を求める項目を厳選して提案を求めていきましょう。
各社からの提案が集まったときに作成する提案比較表で、各社の特徴がきちんと色分けできることがポイントです。そこから逆算して考えていくことと、できるだけ項目も絞っていくことです。
同時に、審査員に各社の提案概要が正確に伝わるように企画提案書と合わせてA4用紙1枚の提案概要書を提出してもらうことも有効です。(これは要求水準書に明記しておくことが前提ですが、優先交渉権者の提案概要を公表する資料として使うことも可能で、様々な関係者にとってメリットが高いものとなります。)
採点表
「他の業者が良かったんだけど。。。」を防ぐための最大のポイントと言っても良いのが採点表です。もちろん、本noteに記載した様々な項目に注意するのは前提となりますが、前述のように民間事業者が最も気にするのが採点表です。
よくあるダメなパターンは、審査項目が膨大にあり各項目の配点がほぼ同一のものです。どこを意識して提案して良いのかわかりませんし、ちょっとしたことで順位が入れ替わりやすくなってしまいます。
実績や会社規模に配点の比重が多く割かれている場合も、大手にとっては好都合ですが、会社規模は小さくともクリエイティブな提案を考える民間事業者や地域に根ざしたプレーヤーなどは参加(や勝つこと)が難しくなってしまいます。
資本金を審査項目としている事例もありますが、近年では戦略的に減資する企業もあるため、短絡的に資本金の多寡で評価することも留意した方が良いでしょう。
まちみらいで支援させていただくプロジェクトでは、採点表の作成にあたって次の点を意識します。
1つめは優先順位の1、2、3位をビジョンで整理した「やりたいこと」の順に配点設定し、それ以外の項目と大きな点数差をつけていきます。こうすることによって、民間事業者と共通の角度からプロジェクトをみることができます。
2つめは採点基準の明確化です。「当該プロジェクトに対する認識」だけでは何を審査するのか分かりません。大項目がこれだとしたら、小項目や採点基準として具体的に例示することが有効です。
3つめに審査項目を絞ることです。1点目と相関関係がかなりありますが、項目が多ければ多いほど点数差をつけることが難しくなるので、可能であれば5項目程度、多くても10項目程度に絞るように考えます。
4つめに企画提案書の様式と審査項目を一致させることです。それぞれの採点項目はどの様式が対象になっているのか、1:1でわかるようにしていきます。こうした面からも「項目を絞ること≒企画提案書の枚数を減らすこと」に繋がっていきます。
これらが整理されていれば、複数の企画提案書を項目ごとに提案概要比較表にまとめやすくなります。提案概要比較表がうまく整理できないということは、これらの項目が十分に整理できていないこととほぼイコールと言って良いかもしれません。
(ただ、このあたりは「経験知」も必要なので、まずはやってみて徐々に意識しながらスキルを上げていけば良いと思います。)
価格点の割合
せっかく民間事業者と連携して行政だけでは難しいクリエイティブさを求めようとしても、審査における価格点の割合が高ければ一般競争入札とそれほど差が出なくなってしまいます。
過去の事例では価格点:提案=80:20みたいなものもありました。調達力を優先する電力の入札などでは、価格点の割合を高くしたうえで環境負荷や+デマンドデータの見える化など+αのサービスを提案項目として補足する」という考え方が合理的でしょう。自動販売機の貸付でも貸付料の割合を高くしたうえでWi-Fi・防犯カメラ・災害時の飲料供給などの+αのサービスを求める点で有効です。
ただし、これらは価格重視のプロジェクトに限定されたものになります。
一般的に民間ノウハウの活用を最大限に活用するプロジェクトでは、やはり提案:価格=80〜90:20:〜10程度にすることがポイントとなります。
更に包括施設管理業務など基準価格が各社によってほとんど差が生じない、(発生しうるコストを+αのサービスに転嫁した方が効果的なものは、)価格点の割合を更に低くすることも選択肢になるでしょう。実際に包括施設管理業務で支援させていただいた自治体では、(最終的には若干の配点をしましたが)価格点を採点項目から外すこともギリギリまで検討していました。
採点表をしっかりと作り込むことができれば、審査委員によらず似たような結果を得ることができるようになりますので、ここには特に力を入れましょう。
審査委員の選定
まちみらいで関わるプロジェクトでは、審査委員はできるだけ内部の職員で行うことを推奨しています。職員はそのプロジェクトに対する結果責任を負いますが、外部の審査委員はプロジェクトの結果責任は取りませんし、取る立場にはありません。良くも悪くも「その場限り」です。
そうはいっても、そのまちの文化・風土・状況やそのプロジェクトの質によっては外部の人材が求められる場合があります。そのような場合は、余計にプロフェッショナルな専門家を選任し、変な判断がなされないように留意する必要があります。
具体的には「現場のわかる人」を中心に選任することです。なぜなら行政は驚くほどに非合理的な組織だからです。理想論や学術の世界では通じないので、現場をやったことがない学識経験者、結果の数字だけを追う公認会計士、なぜか行政に入り込んでいる評論家(や自称地方自治の専門家)などは、それぞれクセが強く自分の想いを採点に直結させるので注意しましょう。
更にPFI法に基づくPFIなどでは要求水準書や採点表を案の段階で審査委員へ照会し、審査委員の声を言われるがままに反映していくことも慣例としてありました。
こうした意見を取り入れていくことで、ビジョン・コンテンツやプロジェクトとしての軸がブレたり、曖昧な点が出てくるリスクもあります。
しかし、ここまで述べてきたように(そのことが本当に合理的であれば別ですが、)基本的には結果責任を取る行政が自ら要求水準書・採点表等は確定し、外部審査委員には「なぜそうしたのか」の説明に留めた方が良いと思います。
時間をかけて共に試行錯誤していく
良いパートナーとは、そのプロジェクトを点としてではなく面として、そして時間軸で一緒に歩んでいける人たちです。提案の質はもちろん重要ですが、それよりも「その人たちと一緒にやっていきたい、お互いにフォローし合いたい」と思えるかどうかが求められます。
相手を間違って(変な提案を採用して)しまうと、そのプロジェクトが点として低質なものになり停滞、最悪の場合には頓挫してしまうだけでなく、エリアの価値を下げたりそのまちの財政に致命的なダメージを与えかねません。
様々な事象が激変する時代、企画提案書のとおりに10年を超えるようなプロジェクトが円滑に進むことはないでしょう。様々な場面で躓いたり軌道修正が求められたりするでしょうし、日々試行錯誤していかなければなりません。
プロジェクトとしても何度も何度も柔軟に時機に応じて契約変更していくことが必要です。
だからこそ、パートナー選定は慎重にかつ丁寧に行うことが必要なのです。
※↑2023.1現在4刷決定!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
