
雑感記録(59)
【小説が読めなくなった!?】
先週の土曜日から僕は4連休だった。厳密に言えば月曜日と火曜日の両日にお休みを貰ったのだ。土曜日は以前の記録で記した通り、友人の結婚式へ朝から晩まで参加。日曜日は1日休息。そして月曜日に相も変わらず神保町へ行ってきた訳です。いや~、愉しかったな…。
またまた本を入れた手提げ袋を両脇に抱え、東京の道をよたよたと怪しい感じで闊歩していた。しかし、いつ行っても神保町は愉しい。本を買う買わないは置いておくとしても、本が所狭しと並んでいるのは圧巻だし、見るだけでも愉しいのだ。これは本好きにしか分からない感情なのかも分からないが、本に興味がない人でも行けば愉しめるのではないだろうか。
神保町へ行って本を見て、「あ、この本良いな」「この本よさそうだな」と思って手に取ったものを僕は購入する。まあ、これは誰しもがそうなのだろう。自分が欲しい本を探すのも勿論だが、眼に付いた興味のある関係の本、また全く読まないようなジャンルを適当に購入してみるというのも1つの愉しみである。
そこで僕は手に取った本やら購入した本やらを眺めて気が付いた。
「あれ、おれ小説買ってないぞ…」
そうなのだ、ここ最近なのだろうか。僕は全く小説を読まなくなった。いや、小説を読めなくなったというのが正解なのだろうか。今回も神保町へ行って買ったものを改めて自宅に帰って眺めた時に小説がル・クレジオしかなかったのである。

これはこれでいいのかもしれないのだろうが、何だか寂しいような気もする。大学時代や社会人になりたてのころは小説が中心であったのだけれども、いつしかそれが変化してきて、哲学や批評が中心に据えられていったのだ。なんとも不思議な現象である。
別に小説が嫌いになったとか、読みたくなくなったとか決してそういう訳ではない。最近も何だかんだで保坂和志の『季節の記憶』を読み終えたばかりだし、古井由吉の『辻』を読み始めているところだし…。小説自体に対して僕は何も変わっていない。読みたいと思うこともあるし、実際に読んでいる訳だから小説を嫌いになっている訳ではない。
しかし、ここで1つ言えるのは、ここ最近は小説よりも批評や哲学の方に面白さを感じているということが大きいのだと思う。何と表現すればいいのか正直、自分自身でも分かっていないのだけれども、書き方という点に於いてそこらへんの小説読むぐらいなら批評や哲学を読んだ方がより文学性を感じるからなのかもしれない。
今、僕は安易に「文学性」という言葉を使ってしまったのだけれども、小説のぎっちぎちに詰め込まれたストーリーより批評や哲学のような断片の組み合わせが大きなものへと繋がっていく感じの方が自由度があって愉しいと感じるのである。これも表現するのが難しくて、非常にもどかしいところではあるのだけれども…。
人の思考を辿ることに面白さを最近はよく感じる。そういう意味で言うと批評や哲学はそれが垣間見えるので僕は好きだ。小説となると人物を登場させ、その登場人物の遭遇する出来事や考えることについて語られる。それはそれで面白いのだけれども、リアリティが感じられない気がしてならない。(ここではリアリティがなんであるかは不問とする。詳細は保坂和志『世界を肯定する哲学』を参考にするとよいかもしれない。)
僕自身、小説の人物が何か作者の意図を背負ってその小説という世界に存在しているとは考えていない。そこで語られることはあくまで小説の人物の思考性であり、作者の思考性とは似て非なるものであると僕は想定している。勿論、作者によってその考え方は異なるだろうけれども、少なくとも小説という世界の中に作者は存在しないのであるから。
批評や哲学というのは作者自身の語りである。ある意味で独自のディスクールが存在していると思う。何というか直接的に読者に語られているような気がして僕はその直接性が好きなのかもしれない。勿論、小説みたいに登場人物などのまどろっこしい関係性の中で見えてくるものも面白いとは思うのだけれども、どこか説得力に乏しく感じてしまうのである。物足りなさとでも表現しておけばよいのだろうか。
小説に求めるものは僕にとって言葉の美しさというか、表現不可能なことを言語に落とし込もうとしているその言葉の連なりに感動することが多い。あとは単純に小説という枠組みから外れたような作品が結構好きだったりもする。
先に僕は保坂和志『季節の記憶』と古井由吉『辻』を読んだ読まないだというような話をした。この2人に少なくとも共通していることは、まあこれは僕の肌感覚だからあまり真に受けないで欲しいのだが、「小説」というものではなく純粋な言葉の連なりとでも言えばいいのか…それを感じることが多い。
読んでいていつも不思議な世界線に入るような、得も言われぬ言語体験ができる。特に古井由吉なんかはその最たるもので、言語による美しさを体感できる。なんだろう、ここもうまく言葉に出来ないんだけれども、読んだときに何かこう「グッと」くるものがある。知的好奇心が掻き立てられる何かがある。保坂和志も僕にとっては同様である。
言語と自身の距離感?とでも言えばいいのかな。うん、よく分からないけどそこが妙に気持ちがいい。作中人物が語っていてもどこかそこに僕は作者を感じざるを得ない。そこが面白いところであり、愉しいと感じる所以なのかもしれない。要は「これはあんたにしか書けないし、もはやあんただよ。」っていう感覚なのだろうか。
そうだ、「言語に純粋に酔える」という点が僕には大きなポイントなのかもしれない。批評や哲学やなんかは本当に書いている人の思考の言語はその人独自の語り口であって、その言語に僕は酔いしれるのが好きなのだ。加えてそこに流れる思考の渦に巻き込まれたいと僕は思うのだ。
昔、大学の授業でとある先生がこんなことを言っていた。「マゾヒストは良き読み手になれる」と。今、それが思い起こされた。小説の世界観に身をゆだねるにはそこに至る言語潮流というものにうまく乗れるか乗れないかということが重要になってくると思う。さらに言えば、その言語潮流が心地よく、そして時には荒れ狂うような流れで襲ってくるということも1つの重要な要素になると思う。
その言語潮流を小説の中で巧みに生み出しているのが僕にとっては保坂和志と古井由吉なのではないかと思う。静謐な言葉の中に現れる荒れ狂った言葉の波が押し寄せるのが古井由吉であり、常に荒れ狂っているのに所々に落ち着けるゆったり流れる言葉があるのが保坂和志ではないかと今、ここまで書いていて感じた。
さて、少し遠ざかった気がする。話を戻そう。
批評や哲学は常に荒れ狂っている言語潮流にある。というよりも、自分自身が分かればいいんだというような姿勢が僕は好きなのかもしれない。というか好きだ。僕らを置き去りにしても「そんなこと知ったこっちゃねえよ。勝手についてこいや。」っていうスタンスが僕は堪らなくそそられる。
何と言うか「分かる人には分かればいい」という姿勢が面白さの1つにあり、その言語潮流に巻き込まれて引き込まれていくその感覚が僕は好きなのかもしれない。
今、小説よりも批評や哲学に惹かれているのはその言語潮流にやられたいという願望が僕の中に存在するからなのかもしれない。コテンパンにやられたい。そんな願望が僕には存在しており、改めて僕は本に関しては極度なマゾヒズムに向かおうとしているのかもしれない。それはそれで喜ばしいことだ。読書冥利に尽きるというもんだ。
纏まりがつかなくなってきたのでそろそろ終いにしよう。何かいい小説があればぜひご教授頂ければというお願いをして締める。
よしなに。

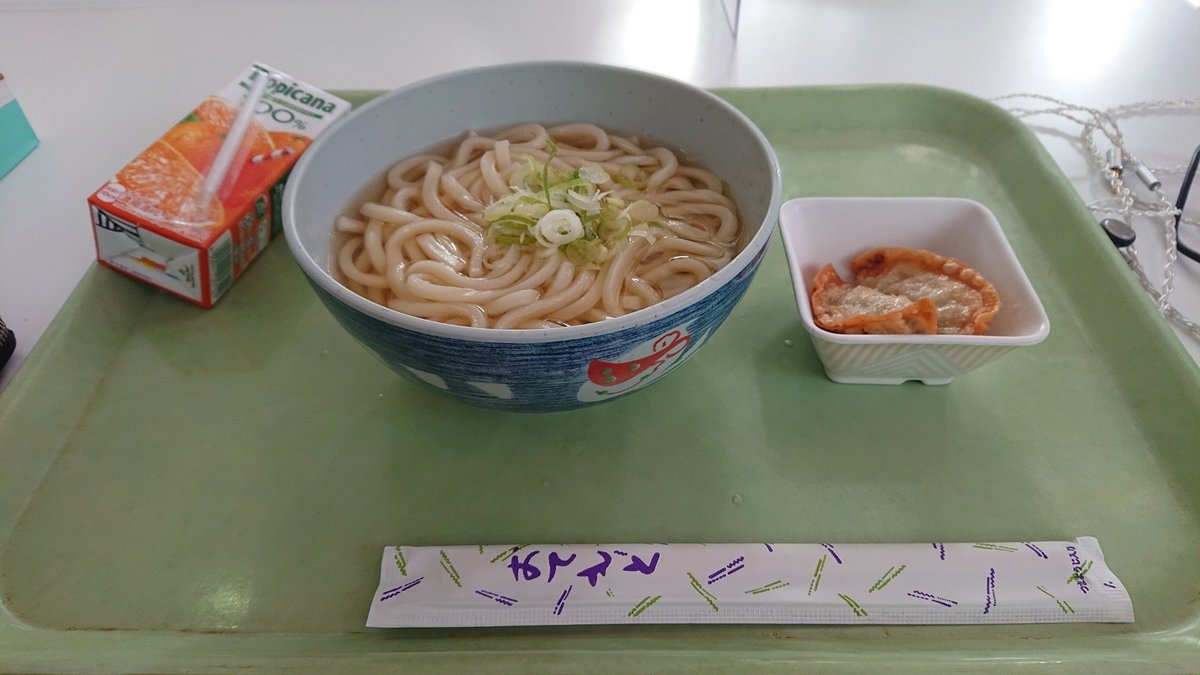
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
