
日本浪漫派、折口信夫『死者の書』と『浪漫者たち』『かぞくわり』
1932年(昭和7年)、東京帝国大学文学部美学美術史学科の21歳の保田與重郎(やすだ・よじゅうろう、1910年4月15日~1981年10月4日)が大阪高等学校同窓生と文芸同人誌『コギト』を3月号で創刊した。
1938年(昭和13年)2月発売の文芸同人誌『文學界』(文藝春秋社)3月号に、27歳の保田與重郎著「ヱルテルは何故死んだか」が掲載された。
グーテ(Johann Wolfgang Goethe、1749年8月28日~1832年3月22日)の書簡体長篇小説『青年ヴェアターの受苦』Die Leiden des jungen Wertherを論じた評論だ。
1938年(昭和13年)3月発売の『コギト』4月号に、27歳の保田與重郎著「ロッテの辨明」が掲載された。
1938年(昭和13年)12月発売の高級大衆総合雑誌『日本評論』(日本評論社)1939年(昭和14年)1月号から、1939年(昭和14年)2月発売の3月号まで、51歳の釈迢空(しゃく・ちょうくう、1887年2月11日~1953年9月3日)の小説『死者の書』が連載された。
ヤマトの権力者、藤原鎌足(ふじわらの かまたり、614年~669年11月14日)の孫にあたる豊成(とよなり、704年~766年1月12日)の娘で、奈良県葛城市にある當麻寺に祀られている中将姫(ちゅうじょうひめ、747年9月30日~775年4月22日)、天武(てんむ)天皇(?~686年10月1日)の皇子で、二上山(ふたかみやま、にじょうさん)に眠る、非業の死を遂げた、大津皇子(おおつのみこ、663年~686年10月25日)の恋を描く。
1939年(昭和14年)10月2日、「新ぐろりあ叢書」、保田與重郎著『ヱルテルは何故死んだか』(ぐろりあ・そさえて、1円20銭)が刊行された。
「ヱルテルは何故死んだか」と「ロッテの辨明」を収めた。
1943年(昭和18年)9月30日、56歳の折口信夫(おりくち・しのぶ)著『死者の書』(青磁社、3円、特別行為税10銭 売価合計3円10銭)3,000部が刊行された。
雑誌掲載分の各章を入れ替え・増補校訂した。
1944年(昭和19年)9月、『コギト』が終刊した。

1951年(昭和26年)2月20日、「學生文庫」、保田與重郎著『ヱルテルは何故死んだか』(酣灯社、90円)が刊行された。
1957年(昭和32年)3月15日発行、同人雑誌『同時代』第四号から1959年(昭和34年)6月5日発行『同時代』第九号まで、橋川文三(1922年1月1日~1983年12月17日)「日本浪曼派批判序説:耽美的パトリオティズムの系譜」が、最終章を除き連載された。
1960年(昭和35年)2月29日、38歳の橋川文三著『日本浪曼派批判序説』(未来社、300円)が刊行された。

1965年(昭和40年)4月15日、橋川文三著『増補・日本浪曼派批判序説』(未来社、680円)が刊行された。

1973年(昭和48年)6月10日、中央公論社が「中公文庫」を創刊した。

1974年(昭和49年)5月10日、「中公文庫」、折口信夫著『死者の書』(中央公論社、240円)が刊行された。
『死者の書』、「山越しの阿弥陀像の画因」を収めた。
解説は46歳の川村二郎(1928年1月28日~2008年2月7日)だ。
1989年(平成元年)10月発行の『季刊思潮』(思潮社)第6号が刊行された。
48歳の柄谷行人(からたに・こうじん、1941年8月6日~)「近代日本の批評・昭和前期Ⅱ」が掲載された。

1991年(平成3年)3月15日、49歳の柄谷行人編『近代日本の批評:昭和篇[下]』(福武書店、税込み1,400円)が刊行された。
「近代日本の批評・昭和前期Ⅱ」が再録された。
1994年(平成6年)12月発売の『文學界』1995年(平成7年)1月号から5月号まで、34歳の福田和也(1960年10月9日~)の評論『保田與重郎と昭和の御代:解体と超越についての試論』が3回に分けて掲載された。

1995年(平成7年)6月1日、35歳の守中高明(もりなか・たかあき、1960年3月1日~)著『反=詩的文法』(思潮社、税込み2,800円)が刊行された。

1996年(平成8年)6月10日、35歳の福田和也著『保田與十郎と昭和の御代』(文藝春秋、税込み1,700円)が刊行された。
1997年(平成9年)9月10日、「講談社文芸文庫」、柄谷行人編『近代日本の批評:昭和篇[下]』(講談社、本体1,050円)が刊行された。
「近代日本の批評 昭和前期2」、4「美的なもの」より引用する(165~168頁)。
岡倉天心が『東洋の理想』において芸術的な観点をとったのは、彼が美学者だったからである。しかし、そこにはかえって審美主義的な姿勢はない。審美主義的姿勢が明瞭に出て来るのは、大正期であり且つ「文芸復興期」である。日本回帰を特徴づけるのは、いわゆる日本主義などではない。それは、知(真理)と意(善)に対して、情(美)をもってくることである。日本回帰とは、実は、こうした「情」(もののあはれ)を優位におくことである。
いうまでもなく、それは、儒教(意)と仏教(知)を綜合した朱子学に対決した江戸時代の国学者、本居宣長において典型的にみられる。昭和初年代に、マルクス主義は知的で道徳的なものの極端な形態としてあらわれた。それに対する批判は、宣長が「漢意」と呼んだものへの批判と共通してくる。外来的な理論や宗教に圧倒された後に、日本人が自らの根拠や原理を見いだそうとすると、結局無原理=無根拠そのものを原理として見いだすことになる。それは、決まって「情」であり「美」なのである。また、それは対外的な関係に背を向けた「鎖国的」な状態において生じる。小林秀雄においては、さらに宣長がもっていたようなプラグマティズムが重視される。理論的な体系や道徳的な規範に対して、「もののあはれ」の直観と生活者の実践的な知恵が対置されるのである。
しかし、宣長においても大切だったのは、「もののあはれ」そのものではなくて、「もののあはれを知る」ことである。いいかえれば、情=美は、もう一つの「知」としてとらえられる。いわば、それが批評である。竹内好は、保田與重郎が知的カテゴリーを解体したというが、それはしかし、保田がそのような「知」をもってきたからである。岡倉天心の美學にはそれはない。それは、彼には宣長のような内閉的な排他性がなかったというのと同義である。
岡倉はアジアの世界交通を強調した。しかし、それと似ているようでいて、保田より国学的である。岡倉にあって、保田に欠けているのは、いうまでもなく外部=他者である。福本のマルクス主義は、すでにいったように、そのような外部=他者を強引にもたらした。だが、そこからの転向において、保田はいわば「原理」のない、あるいは「理想」のないという空無の自己意識を絶対化したのである。それがロマン的イロニーである。それはたんにロマン的なものではないし、もはや国学的なものでもない。
ロマン派的イロニー。それは、一切の有限的なもの、経験的なものを軽蔑することによって、そのようにみなす超越論的自己の優位を確認することである。それは一切の目的、したがってヘーゲル的な弁証法を斥ける。何かをなすとしても、意味や根拠によってなすのではない。しかも、それはニヒリズムでもない。逆に、無意味なことをそれと知りつつあえて真剣に戯れるという自己意識に意味を見いだすのである。ここに敗北はありえない。はじめから敗北を前提しているからである。イロニーとは、いわば、絶対的無力を認めることによる絶対的勝利である。これを政治的レベルでいえば、「哀れでかなしい日本」の不滅というようなものである。
カール・シュミットが指摘したように、ドイツ・ロマン派は、一切の決定論的な原因に反対し、マールブランシュのいう「機会因」をもってくる。マルクス主義が、デカルト的な機会的決定論でないとしても、スピノザ的な決定論であることはいうまでもない。保田は、文学を歴史的な原因から見るマルクス主義への批判において、それを逆転する。歴史は、文学の「機会因」にすぎない、と。こうして、彼の独特の日本文学史ができあがる。『戴冠詩人の御一人者』では、後鳥羽院が政治的敗北者・無能力者ゆえに、帝王振りの大詩人になったという。政治は、たんに後鳥羽院の詩の「機会因」にすぎないのである。詩あるいは詩人の優位は、このような論理によって見いだされる。

1998年(平成10年)6月10日、「講談社文芸文庫」、橋川文三著『日本浪曼派批判序説』(講談社、本体1,300円)が刊行された。
解説は45歳の井口時男(1953年2月3日~)だ。

1999年(平成11年)6月18日、「中公文庫」、折口信夫著『死者の書 身毒丸 』(中央公論新社、本体 590円)が刊行された。
『死者の書』、「山越しの阿弥陀像の画因」、「身毒丸」(『みづほ』第八号」、1917年(大正6年)6月)を収めた。
解説は川村二郎だ。
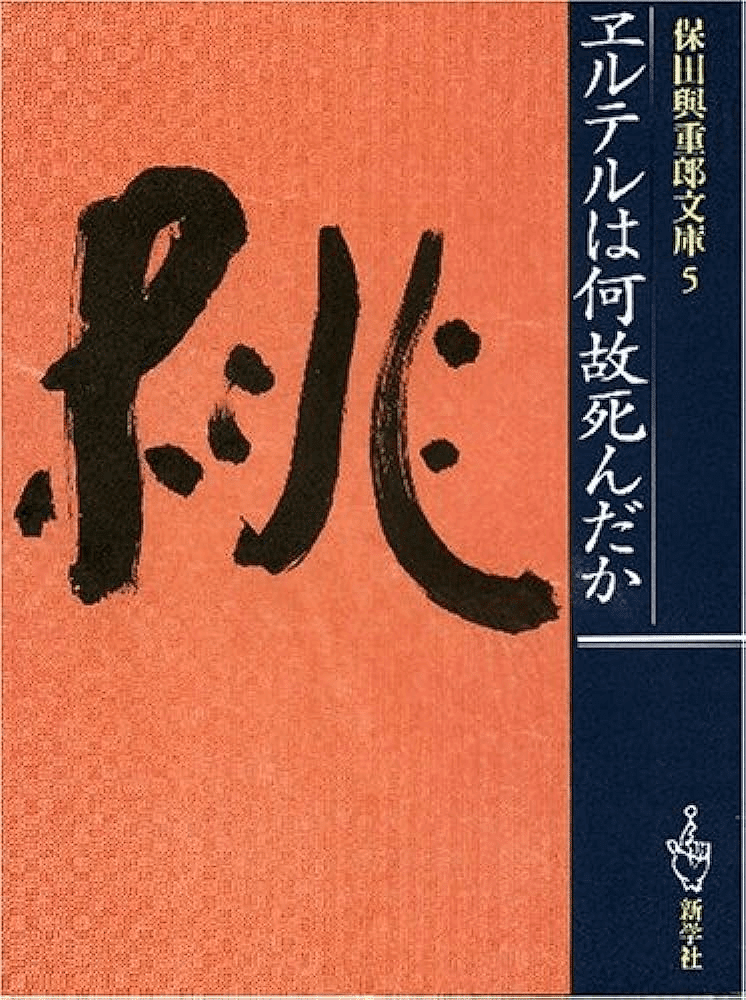
2001年(平成13年)1月8日、「保田與重郎文庫」5、保田與重郎著『ヱルテルは何故死んだか』(新学社、本体720円)が刊行された。
解説は40歳の山城むつみ(1960年9月24日~)だ。
2002年(平成14年)5月発売の文芸誌『群像』(講談社)6月号に、「第45回群像新人文学賞評論部門優秀作受賞」、34歳の安藤礼二(1967年6月15日~)著「神々の闘争―-折口信夫論」が掲載された。

2004年(平成16年)6月1日、44歳の守中高明著『存在と灰:ツェラン、そしてデリダ以後』(人文書院、本体2,400円)が刊行された。

2004年(平成16年)6月14日、折口信夫著、36歳の安藤礼二編『初稿・死者の書』(国書刊行会、本体3,400円)が刊行された。
「死者の書・初稿」、「死者の書・続篇」、「口ぶえ」、大嘗祭をめぐる『国学院雑誌』掲載論文「貴種誕生と産湯の信仰と」、「巻頭言(民族精神の主題)」、「高御座」、「大嘗祭の風俗歌」「大嘗祭の本義ならびに風俗歌と真床襲衾」を収めた。

2004年(平成16年)12月20日、安藤礼二著『神々の闘争: 折口信夫論』(講談社、本体1,800円)が刊行された。

2006年(平成18年)2月11日、東京・神保町の岩波ホールで、折口信夫原作、81歳の川本喜八郎(1925年1月11日~2010年8月23日)人形・脚本・監督の人形アニメ劇『死者の書』(70分)が公開された。

藤原南家の郎女の声を32歳の宮沢りえ(1973年4月6日~)が演じた。
語りは75歳の岸田今日子(1930年4月29日~ 2006年12月17日)だった。
2006年(平成18年)4月、立教大学が埼玉県新座市のキャンパスに現代心理学部(心理学科、映像身体学科)を設置し、東京・池袋にある文学部をキリスト教学科、文学科、教育学科、史学科に改組した。
2008年(平成20年)6月5日~9日、東京、白金台の明治学院大学白金キャンパスのアートホール、奈良県桜井市三輪の三輪明神で知られる大神神社や山の辺の道などで、牧野圭祐(まきの・けいすけ、1980年~)、金允洙(キム・ユンス、1986年2月20日~)、田中千世子(たなか・ちせこ、1949年~)脚本、田中千世子監督、劇団燐光群の27歳の伊勢谷能宣(いせや・ひさのぶ、1981年2月25日~)主演の映画劇『浪漫者たち』の撮影がおこなわれた。
古いヤマトの文化権威に興味をもつ舞台俳優の伊勢谷は、パリを舞台にしたキム・ユンス作『前夜』の青年彫刻家に扮し、通し稽古を進めていた。
稽古初日に観世流梅若会(かんぜりゅう・うめわかかい)の51歳の能楽師・梅若靖記(うめわか・やすのり、1956年7月8日~)先生は仕舞の「三輪」を舞う。
その後、伊勢崎は、奈良県の桜井駅の駅前で黄色いマウンテンバイクに乗った48歳の石川真希(1959年12月25日~)の姿を目にする。
伊勢谷が大神神社で出会った石川は「日本浪曼派」の保田與重郎の研究者で、記念に「日本浪曼派」の雑誌を伊勢谷に贈る。
その後、伊勢谷は狭井神社へと向かう。ここには三輪の神さまの御神体のお山に登る入り口があるが、お山に登る決心ができていない彼は狭井神社を出て、入口付近の市杵島姫神社脇にある池のほとりで1966年(昭和41年)6月24日に、41歳の三島由紀夫(1925年1月14日~1970年11月25日)が色紙にしたためた書「清明」が刻まれた記念碑を見つける。
しばらく歩いて檜原神社に着いた伊勢谷は、着物と袴に着替え、扇を構える。するとギターを抱えた、石川真希の夫、53歳の佐野史郎(1955年3月4日~)が現れ、伊勢谷をからかう。
東京に戻った伊勢谷は、茶道の中村洋子先生の娘・純子からピアノのミニ・コンサートと一緒に読書会もしたいので協力してほしいと頼まれる。
伊勢谷は読書会のテキストをゲーテの「若きウェルテルの悩み」に決め、保田與重郎の「ヱルテルは何故死んだか」を参考資料にする。
伊勢谷が司会を務めた読書会は思ったようには行かないが、参加者のキム・ユンスが浪漫主義に興味を示してくれた。
数週間後、キムと会った伊勢谷は、キムが書いた戯曲『前夜』に主演し、結末で、決して挫けない浪漫者の魂を告白する。
その後、久しぶりにヤマトを訪れた伊勢谷はお山に登る。
伊勢谷の友人役で明治学院大学の学生たちが出演した。

2009年(平成21年)3月31日、「おおさかシネマフェスティバル2009」で、映画劇『浪漫者たち』(75分)が公開された。

2009年(平成21年)5月30日、東京・渋谷のシアター・イメージフォーラムで、映画劇『浪漫者たち』が公開された。

2010年(平成22年)5月14日、「岩波文庫」、折口信夫著『死者の書・口ぶえ』(岩波書店、本体660円) が刊行された。
注・解説は42歳の安藤礼二だ。

2010年(平成22年)11月26日、59歳の前田英樹(1951年9月4日~)著『保田與重郎を知る』(新学社、本体2,800円)が刊行された。
DVD附録は、1年半をかけ、保田の故郷でありその文学を育んだ母胎・奈良県の桜井市や明日香村を中心に、折々の米作りの風景やそれに伴う祭事、そして保田文学ゆかりの史跡などを撮影した、保田與重郎生誕百年記念映像、前田英樹監修、佐藤一彦演出『自然(かみながら)に生きる――保田與重郎の「日本」』(本編70分、特典20分)だ。
語りは檀ふみ(1954年6月5日~)、朗読は草柳隆三(1937年4月9日~)、特別出演は菅原文太(1933年8月16日~2014年11月28日)だ。
インタビュー出演は、谷崎昭男(1944年2月28日~2019年10月26日)、前田英樹だ。
2012年(平成24年)4月発売の『群像』5月号の「折口信夫の起源」から2014年(平成26年)1月発売の『群像』2月号の「折口信夫の宇宙」まで、安藤礼二の折口信夫論が8回に分けて掲載された。

2014年(平成26年)11月26日、47歳の安藤礼二著『折口信夫』(講談社、本体3,700円)が刊行された。

2014年(平成26年)12月12日発売の『月刊コミックビーム』(エンターブレイン)2015年(平成27年)1月号(570円)から、折口信夫原作、57歳の近藤ようこ(1957年5月11日~)の漫画『死者の書』の連載が第一話「彼(カ)の人の眠りは徐(シズ)かに覚めていった」で始まった。

2015年(平成27年)8月24日、9月4日発行「BEAM COMICS(ビームコミックス)」、折口信夫原作、近藤ようこ著『死者の書』上(KADOKAWA、本体740円)が刊行された。

2016年(平成28年)3月12日発売の『月刊コミックビーム』4月号(570円)で、折口信夫原作、58歳の近藤ようこの漫画『死者の書』の連載が第十六話「姫の輝くやうな頬のうへに」で終わった。

2016年(平成28年)4月25日、5月6日発行、「BEAM COMICS」、折口信夫原作、近藤ようこ著『死者の書』下(KADOKAWA、本体740円)が刊行された。

2016年(平成28年)9月3日~10月10日、國学院大学博物館校史展示室・ホールで、生誕130年記念特集展示「折口信夫と『死者の書』」が催された。
2017年(平成29年)7月3日~26日、奈良県桜井市にある三輪山、葛城市にある當麻寺、大和高田市、香芝市で、折口信夫『死者の書』をヒントに日本の家族のあり方を描く、38歳の塩崎祥平(1979年1月18日~)脚本・監督、36歳の陽月華(ひづき・はな、1980年9月2日 ~)主演の映画劇『かぞくわり』の撮影がおこなわれた。
風景撮影は2016年(平成28年)5月、10月に既におこなわれていた。
當麻寺には本尊である當麻曼陀羅を蓮糸で一夜にして織り上げたという中将姫が祀られている。
奈良県のニュータウンの平凡な家庭で育った香奈はこの姫の生まれ変わりだったが、画家になるという夢を親に拒絶され、38歳になっても定職にも就かずに両親と同居しけていた。
ある日、妹の暁美が夫の不倫が原因で思春期の娘、樹月(きずき)を連れて突然帰ってくる。姉妹のけんかは絶えず、次第に家族が崩壊していく。
香奈は、鬱を患っていた若い頃に壁画を描いていた、旧日本陸軍が本土決戦に備えて作った地下壕、屯鶴峯に行き、建築家、清治と出会う。
清治は、自給自足しながら、これまでにないアートイベントを仲間たちと計画する不思議な人物だった。
父親役を63歳の小日向文世(こひなた・ふみよ、1954年1月23日~)、母親役を63歳の竹下景子(1953年9月15日~)、樹月役を17歳の木下彩音(2000年2月21日~)、暁美役を29歳の佃井皆実(つくい・みなみ、1987年12月18日~)、清治役を31歳の石井由多加(1985年8月12日~)が演じた。
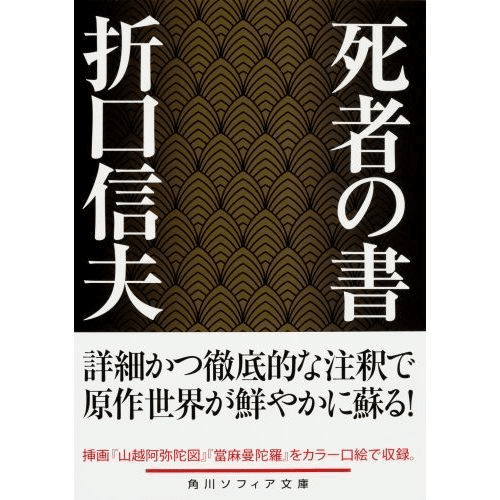
2017年(平成29年)7月25日、「角川ソフィア文庫」、折口信夫著『死者の書』(KADOKAWA、本体920円)が刊行された。
補注は池田弥三郎(いけだ・やさぶろう、1914年12月21日~1982年7月5日)、関場武、解説は持田叙子(もちだ・のぶこ、1959年~)だ。

2017年(平成29年)7月31日、前田雅之(1954年~)著『保田與重郎:近代・古典・日本』 (勉誠出版、本体3,800円)が刊行された。

2019年(平成31年)1月19日、東京の有楽町スバル座と奈良県橿原市、イオンモール橿原内「TOHOシネマズ橿原」で、映画劇『かぞくわり』(129分)が公開された。
2019年(令和元年)10月20日、有楽町スバル座が閉館した。

2022年(令和4年)4月27日、47歳の杉田俊介(1975年1月17日~)著『橋川文三とその浪曼』(河出書房新社、本体3,900円)が刊行された。
2022年(令和4年)7月29日、岩波ホールが閉館した。

2023年(令和5年)4月26日、71歳の前田英樹著『保田與重郎の文学』(新潮社、税込み14,300円)が刊行された。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
