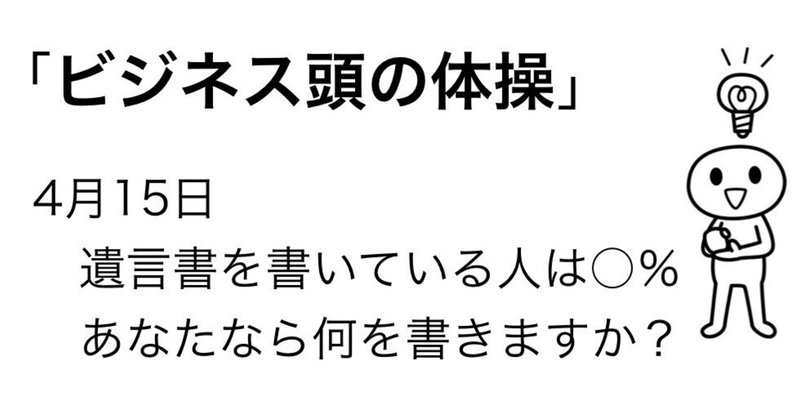
4月15日 遺言を書いている人は○%!?
はたらくおとな向け。普段の仕事と無関係なケーススタティで頭の体操。
普段の仕事を超えて、視野を広げ、ビジネスの頭の体操をするのにぴったり。
考えるための質問例はこちら。
→遺言書。今、書くとしたら、どのようなものになるだろうか?
近畿弁護士会連合会が制定。2007年からは日本弁護士連合会(日弁連)が主催するようになった、「遺言の日」です。
四(よい)一(い)五(ご)で「よいいごん」(よい遺言)の語呂合せ。
遺言。
お金持ちが書くイメージがあります。
私は以前、仕事で遺言書の作成や、相続手続きに携わったことがあるのですが、実は相続人が妻と子が1人だけというケースでも、子が未成年ですと相続手続きは結構面倒です。
通常、未成年の代理人は親権者である親ができますが、相続手続きにおいては、親はいわば利益相反の立場にあたるので代理人になれないのです。となると、別途代理人を立てる手続きなどが発生するのです。
とはいえ、じゃあ遺言書こうか、というほど身近ではないですよね。
日本財団が昨年の1月5日に公表した遺言に関する調査によると(日本財団は1月5日を「遺言の日」にしているそうです…)
☑️ 既に公正証書遺言を作成している : 1.3%
☑️ 既に自筆証書遺言を作成している : 2.1%
ということで、遺言書を作成済みの人は全体のわずか3.4%です。近いうちに作成しようと思っている人は13.9%いますが、それを合わせても2割にもなりません。
逆に「今後も作成しない」が42.7%、「しばらく作成するつもりはない」が35.4%と、8割近くは作成する考えもないことが分かります(下図)。

やはり多くの方に縁のなさそうな遺言ですが、作成した人に良かったと思うことを聞いた結果が以下の通りです。

最も多いのが「気持ちの整理になった」(44.8%)
また、「自分の財産の使い道を自分の意思で決められた」(32.8%)が2番目に多くなっています。
特に2番目は、お子様がいないなどの理由で残す相手がいない方が、どんな団体に寄付したいか、というのを遺言で指定することができるニーズもあります。
ちょっと脱線しますと、実は遺言がなく相続が発生して兄弟間で揉めたりすると、「親からもらった」という感じより「兄弟との争いから自分が勝ち取った」という感じになってしまう、というケースが実際あります。あれは切ないです…
さらに脱線すると、相続で揉めるのは残された財産が多くなくとも、というか、少ないほど揉めます。ですから、遺言は資産家のもの、という認識は改めた方がいい、と経験から思います。
なんか、頭の体操ではなく、私の経験談になってしまいました。すいません…
気を取り直して最後に、公正証書遺言の推移データをご紹介します(下図:出典 日本公証人連合会)。

令和3年で約10.6万件の公正証書遺言があることが分かります。
参考までに日本の65歳以上人口3,640万人(2021年9月推計)を分母とすると約10.6万件は約0.3%となります。多いのか、少ないのか…
→遺言書。今、書くとしたら、どのようなものになるだろうか?
最後までお読みいただきありがとうございました。
一昨年7月から続けております。
以下のマガジンにまとめてありますのでよろしければ。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
