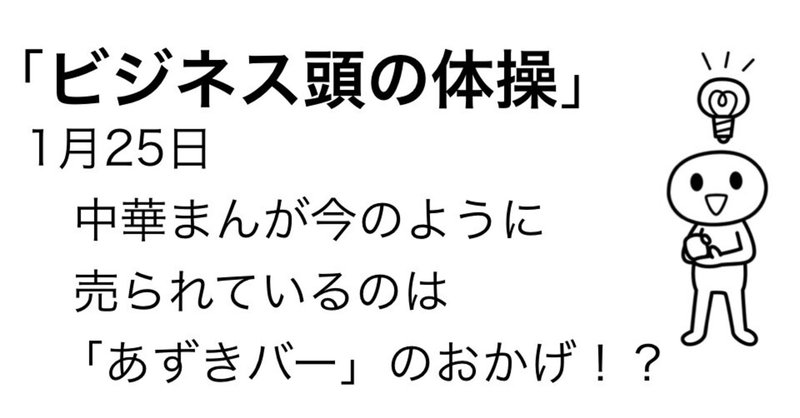
1月25日 中華まんが今のように売られているのは「あずきバー」のおかげ!?
今日は何の日?をビジネス視点で掘り下げ「頭の体操ネタ」にしています。 今日の「頭の体操」用質問例はこちら。
→中華まんが売れるようになるまでの経緯には、他の商品やサービスで応用することができそうなものがある。応用するとすれば何が考えられるだろうか?
1902(明治35)年のこの日、北海道旭川市でマイナス41度という日本の気象観測史上最低の気温が記録された、「日本最低気温の日」です。
さて、最低気温。寒いと食べたくなるもの、ということで「中華まんの日」でもあります。
そこで、中華まんについて調べてみました。
実は、中華まん、元々は一部の中華料理店でしか食べれないものでした。それを今のように店頭ですぐ食べられる状態で売るようにしたのは1964(昭和39)年に井村屋さんが始めたことがルーツになっています。
今では当たり前の光景ですが、この背景には非常に面白い「マーケティングの頭の体操ネタ」がありました。
なぜ井村屋さんは中華まんをスチーマーですぐ食べれる状態で売ろうと思ったのでしょうか?
ヒントは、当時の井村屋さんのメイン商品は「あずきバー」を始めとしたアイスバー(アイスクリーム)だった、ということです。
いかがでしょう?何か思いつきますか?
今と違って、アイスクリームは夏にしか売れない商品でした。 となると、アイスクリームの冷凍ケースは冬場には邪魔になります。アイスクリーム用の流通経路も稼働しません。 これらを活用するために考えたのが、肉まん・あんまんを作って店頭の冷凍ケースで販売する、というものです。
つまり、夏には邪魔にしかならない冷凍ケースと流通経路の活用から発想したものだった、というわけです。
あぁ、なるほど、と思ったかもしれませんが、実はこれは失敗します。
なぜなら、当時、1964年の冷蔵庫の普及率は38.2%です。ということは、買っても家で冷たいまま保管することはできません。
さぁ、困りました。どうしましょう?
井村屋さんが次に考えたのが、「店頭で温めた状態で売ればいい」ということです。そこで、スチーマーも店頭に置かせてもらい、必要な分だけ冷凍ケースから出してスチーマーで温めて販売する、出来立てのホカホカを食べられる、ということでヒットにつながったのです。
ここまで読んでいて、なんとなく、コンビニの店頭を頭に浮かべていた方も多いかもしれませんが、この時点ではコンビニエンスストアはありませんでした。
が、コンビニが登場すると、ご想像の通り、親和性が高く、現在では中華まんの流通シェアで7割をコンビニが占めるようになった、ということです。
中華まん市場の規模は、2014年に580億円だったものが、2017年に670億円、2018年は680億円と成長していましたが、2019年は626億円と減少しました。
これは暖冬の影響と家庭での軽食が冷凍食品のピザなどに流れたと考えられています。
なお、2020年は感染症の影響でコンビニでは販売は減少する一方、巣篭もり消費で冷凍中華まんは増加、となっています。
そんな中華まん、コンビニ各社で競争が激しい分野です。最近では「手包み製法」と謳う製品があるが、それって本当に手で包んでいるのでしょうか?そして、そもそもそれ以前はどのような製法で量産されていたのでしょうか?
個人的には、「へぇ〜」だったのでご紹介を。

左が従来、右が手包み製法、です。
(セブンイレブンプレスリリースより)
今までの製法が分かるようでまだ完全には分かっていないのですが…
→井村屋さんの中華まんが売れるようになるまでの経緯、他の商品やサービスで応用するとしたらどのようなことが考えられるだろうか?
最後までお読みいただきありがとうございます。
過去の投稿は以下にまとめていますので頭の体操ネタに覗いていただければ幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
