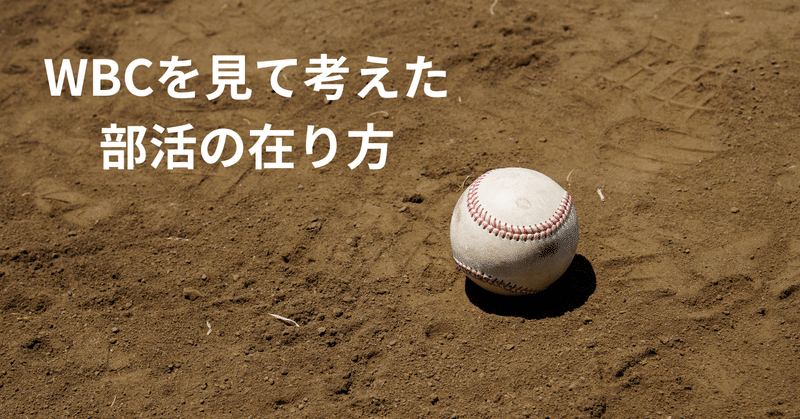
WBCを見て考えた部活の在り方
日本中を熱狂させたWBCは、日本が優勝という結果で幕を閉じました。
熊本県出身の村上宗隆選手の活躍もあってか、私のクラスの生徒も関心が高く、
決勝のあった日はソワソワして廊下を行き来しており、
世界一になった瞬間、クラスが大騒ぎでした(笑)
子どもたちまで巻き込む野球の面白さに、テニス部顧問として考えさせられたことがありました。
その内容をお伝えできればと思います。
1)世界一強い選手が、楽しむことを大切にしているという事実。
様々なメディアで言われていますが、私も今大会は選手が生き生きと楽しんでいる姿が印象的だと思いました。
国際大会だとどうしても「勝たなくてはいけない」という切迫感が少なからずあります。
しかし、ダルビッシュ有投手が率先して「楽しむ」チームづくりを心がけており、非常に良い雰囲気で試合に臨んでいました。
楽しむといっても結局、自分たちより強い選手は真剣に勝利だけを求めてやっていると思い、
その考え方は甘いだろうという考えが頭のどこかにありました。
ただ、侍ジャパンは結果を持って「楽しむことの大切さ」を証明してくれたような気がします。
最高に楽しんだものが勝つ。
その最高の楽しみを得るために、技術や心を磨く。
そのために日々の練習で一生懸命努力をする。
こういう思考回路でどんどん強くなっていくのかなと考えました。
2)テニスの楽しさって何だろう。
では、テニスの楽しさとは何か。
・きちんと真ん中に当たった時。
・サービスエースをとった時。
・コーナーに打ったボールがいって、決まった時。
・長いラリーを制した時。
振り返れば、勝ち以外でも気持ちよさを感じる瞬間がたくさんあるなと思いました。
私がテニスをしていて人生で一番楽しかったのは、
自分の思い通りにボールをコートへ運べた時です。
「こういうテニスをしたい」が形になった時に、喜びがありました。
ずっと公式戦で初戦敗退や2回戦敗退が多かった中で、
初めて自分に自信が持てて、「テニスって楽しい!!」と感じました。
そして自然と勝利が後からついてきました。
もちろん勝つことは嬉しいですし、達成感もあります。
ただ、勝利を目標におきつつも、そのプロセスや日々の積み重ね、
そして「楽しさ」という要素にもっと焦点を当てるべきなのかもしれないなと思いました。
「勝利は与えられるもの」という感覚が必要かもしれません。

3)生徒たちへの接し方を考える。
栗山監督の「信じて待つ」という信念は何か教育者として通じるものがあるなと感じます。
専門の競技を持っていればいるほど、口を出したくなります。
でも、言えば言うほど生徒は自信を無くしていくような気がします。
逆に生徒が求めるまで待つ。
最近はその姿勢で接していく中で、
公式戦で負けたあとに「どうしたら勝てますか?」と
尋ねてくる生徒が出てきました。
選手の「もっと強くなりたい」「もっと上手くなりたい」という気持ちを見逃さない。
授業も学級経営も一緒です。
「もっと知りたい」
「大学にどうしても合格したい」
「クラスでいい雰囲気をつくっていきたい」
そんな時に耳を傾け、適切なアドバイスをする。
そして求める姿勢が出てくるまで、きっかけを与え続けていく。
そういう教育者でありたいです。

教育のこと、授業をしている倫理や政治経済のこと、熊本の良いところ…。 記事の幅が多岐に渡りますが、それはシンプルに「多くの人の人生を豊かにしたい!」という想いから!。参考となる記事になるようコツコツ書いていきます(^^)/
