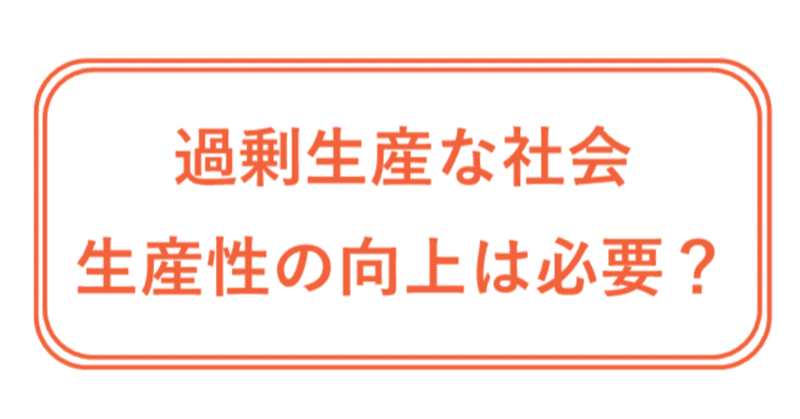
過剰生産な時代において「生産性の向上」は本当に必要なのか?
■生産性の向上を目指す社会
昨今はビジネスの世界で「生産性の向上」というワードを耳にする機会が増えた。これは私が身を置く介護業界においても同様であり、人手不足が続く
状況でも高齢者介護サービスを継続するために国も提言している。
ここで個人的な意見を言わせていただくと、この「生産性の向上」というワードはICTとかDXなどと大して違いのない、その時代ごとの流行語のようなものだと思っている。
そもそも、何をもって「生産性」としているのか曖昧である。生産性は業界や職種によって異なるし、社会的ニーズも流通範囲だって違う。
また、少し前まで提唱されていた「業務効率化」とは何が違うのか?
何となくだが、単に業務改善の類として「業務効率化」が「生産性の向上」というワードに変わっただけに見える。
もちろん、「業務効率化」と「生産性の向上」の定義やプロセスは異なることくらいは分かる。しかし、結局のところ目指すところは同じではないか?
■生産性を向上する必要はあるのか?
別に嫌味を言いたいわけではない。単純にいまさら「生産性の向上」というワードを喧伝するような社会に疑問を抱いているだけである。
確かに日本のGDPが良好とは決して言えないし、諸外国と比べても競争力が低下しているのは肌感覚でも分かる。
しかし、何だかやみくもに「生産性を向上しよう!!」と言っているように思える。そうして新しいビジネス用語もどんどん飛び回り、怪しいビジネスモデルやセミナーも活発になっている様子も伺える。
ここで根本的なことを問いたい。
――― 生産性を向上する必要はあるのか?
――― 生産性を向上した先に何があるのか?
例えば、最近あるいは今日でもいいので、自分が店舗やネットで購入した商品を1つだけ思い浮かべていただきたい。
もしも、その商品を作っている企業が生産性を向上することに成功したとして、その商品を大量に生産し、日本中あるいは世界中に流通したとして、それはちゃんと購入されるのだろうか? 使用(消費)されるのだろうか?
これはあくまで、1つの商品において文字通り「生産性の向上」として大量生産・一斉流通したという極端な仮定(妄想)だ。しかし、思い浮かべた商品が何であれ、おそらく「う~ん、そこまでのモノでないかも・・・」となると思う。
何が言いたいのかと言うと、本当に考えるべきは「生産性の向上」そのものよりも、社会における商品やサービスの「価値」に着目することではないか? ということだ。
■ 過剰生産なのに生産性を向上する?
このようなことを考えるのは、おそらく私が介護サービス事業を営んでいるからだろう。
冒頭でお伝えしたとおり、介護業界は人手不足である。一方で介護を要する高齢者は多い。つまり、社会において「価値」がある。
しかし、現状は「介護を要する高齢者数 > 介護従事者数」である。いや、現状どころか過去から現在まで変わってないと言ったほうが正しい。
そこで、この人手不足な状況をカバーしようと介護業界は四苦八苦しており、国もICT推進やら生産性の向上を提言している。
これは介護だけでなく、医療福祉、建築、運送、情報システムなどの業界にも同様のことが言える。いわゆる需要が供給を上回っている状態である。
(でも賃金や単価が上がらない、という手合いの話は本記事では割愛する)
一方、その他の商品(生産)やサービスはどうだろうか?
こちらもまた人手不足は同じく、さらに物価高騰や原材料の確保などが追い付いてない。しかし、本当に必要なのかどうか分からない物を、どんどん生産しているようにも見える。
例えば、コロナ禍のマスクは必須であり、一時期は高騰しても誰もが欲しがった。そして「マスクが売れる!」となったら、マスクなんて関係ない企業までも参入するような事態となった。
これはマスクに限らす時々ある話だが、本当に必要かどうか分からない商品や一時の流行で大量生産が広まった結果、供給が需要を超えてディスカウント扱いされたり、ときには廃棄することも珍しくない。
これはいわゆる「過剰生産」である。
そして、周囲を見渡すと過剰生産された商品はたくさん伺える。
もしも意図なく過剰生産していることが常態化しているならば、むしろ「生産性の向上」なんて目指さないほうが良いのではないだろうか? と思ってしまう。
――― と、誤解のないようにお伝えすると、色々な業界の事情に詳しいわけでもないが、各社がマーケティングなどを根拠に生産していることくらいは理解している。また、低コストで商品を提供するため、血と汗を流しながら効率化や生産性の向上という企業努力もあると思う。
また、本記事は「生産性の向上」をあくまで物量として見たものであるため、本質から逸れていることも否めない。
しかし、過剰生産ぎみであるのは事実であると思う。
ちなみ、過剰性は何も商品に限った話ではない。上記で介護を含めた人手不足の業界は生産性の向上が適合しているみたいにお伝えしたが、実はこれらの業界も過剰生産というか過剰サービスになっている部分は探せば色々と出てくると思う。
実際、介護サービスの中には料金や制度の範囲を超えた過剰サービス・過剰対応は慢性化している。その求めに応じすぎるがあまり、本来の介護に従事できないうえに、度を越えた部分で過重労働になっていることもある。
では、どうすれば良いのか? という話になるが、ただでさえダラダラ長いのに、続きも書いたら文章にしたらもっと長くなってしまったので、本記事はここまでとする。
ここまで読んでいただき、感謝。
途中で読むのをやめた方へも、感謝。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
