
映画研究者/批評家 北村匡平さんが出逢った高山宏 『表象の芸術工学』──わたしの仕事と工作舎の本#2
工作舎の本って、どんな人に読まれているんだろう。
どんな役に立っているんだろう。
「わたしの仕事と工作舎の本」第2回に寄稿していただくのは
映画研究者/批評家の北村匡平さんです。
映像表現の技法をつぶさに分析し、京マチ子から椎名林檎まで
時代の欲望と価値観を映し出す文化現象を論じる北村さんが
大学時代に出逢い「感染」してしまった一冊の本。
それが『表象の芸術工学』(2002年 工作舎刊)。
博覧狂気の学魔と呼ばれる高山宏さんの講義録です。

高山宏『表象の芸術工学』
北村匡平
ミッキーマウスを議論できない美術評論家
学部生の早い時期にこの本に出会ったと記憶する。すでに研究者になりたいという目的をもって大学に進学した僕にとって、読書は特別なものではなく、ごく日常的な営みだった。本を1日1冊読むという過酷なルールを課し、ブックオフで売られている100円の本や図書館で借りた本をほとんど消費するように貪り読んでいた。どうやって手に取ったのかはまったく覚えていない。おそらく最初は図書館で借りたのではないかと思う。後々まで影響を受けるほどの本には、そう簡単にめぐり会えるものではない。だが、高山宏の『表象の芸術工学』を手に取ったとき、絶対に手元に置いておきたいと思ってすぐに購入したのだった。
僕の専門は映画だが、そもそも当初、美術史の研究者になりたくてドイツ語とフランス語を学びながら、絵画に関する研究書や論文を読み漁っていた。大学に進学する前には映画学校で映画製作や舞台について学んでいたので、映画学を専門にすることも考えていて、途中までずっと迷っていた。だから学部2年でアメリカの大学に留学したときは、フィルム・スタディーズとアートヒストリーを中心に学んだ。
結局、西洋美術はお金がかかるということもあって、学部4年で映画学を自分の専門とすることに決め、いまはいちおう「映画研究者/批評家」という肩書きで本や論文を書いている。しかし、上述したように学部時代は美術史と映画学を中心に学んでいて、僕の中で明確に映画学は映画学であり、美術史は美術史だった。多くの人にとってもそうだろうと思う。これらが学問上で交差することはないと思っていた。だが、この神戸芸術工科大学のレクチャーをもとにした高山宏の講義本に出会い、そういった固定観念は完膚なきまでに打ち壊されることになった。
レクチャーⅠは江戸時代から始まるや、いきなり学問についてのあり方が語られる——「美術史の中でミケランジェロの絵を議論することはあるのに、なぜミッキーマウスが白い手袋をしていて、あるときそれを脱ぐのか、という議論がないのか」。続けて「ミッキーマウスが妙にふんぞりかえっている、あのアングルは何かを議論できる美術評論家がいない」と、こうくる(ちなみに僕はこの「煽動」を自らの表象文化論の講義で借用している)。つまりハイカルチャーのみが学問の対象とされ、ミッキーマウスのような「低俗」な文化現象には無関心なアカデミアの射程の狭さが痛烈に批判されているのだった。
いまでは表象文化論や視覚文化論の拡がりによって、それほど状況は悪くないように思うが、文学は文学を研究する学問であり、歴史学は歴史を研究する学問であると思い込んでいた当時、目で見るすべてを対象とした視覚文化のアプローチの重要性をずっと言い続けてきたという高山宏の煽動的な問題意識に、妙に感銘を受けたのだった。

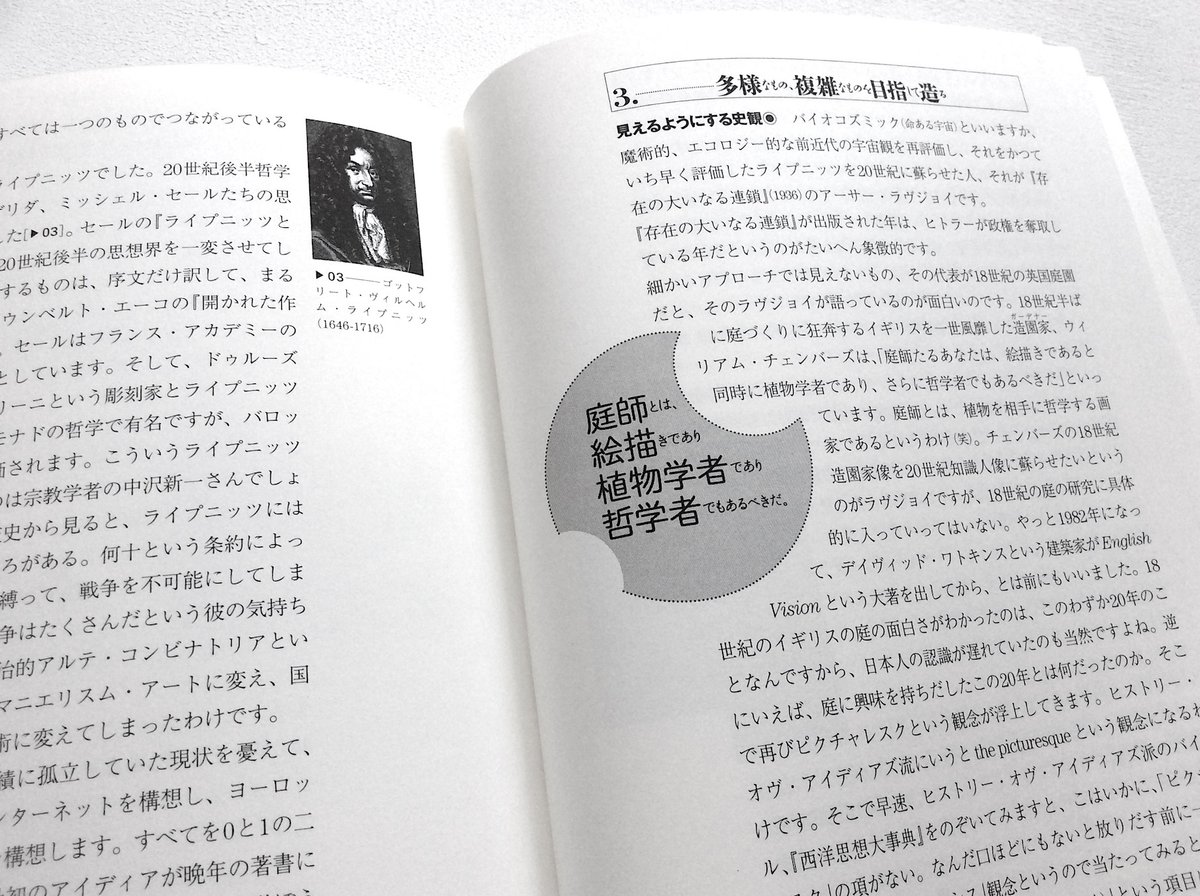
繋ぐ快楽、見て愉しむ本
ページをめくっていくと、得体の知れない猿と魚が合体したキメラや、グロテスクな怪物人魚など悪趣味な図版が次々と並べられている。そして江戸の黄表紙やオランダ人が外科手術をしている様子が描かれた絵が続く。江戸の話かと思えば、17世紀オランダのフェルメールの話になり、次に18世紀スコットランドの百科事典『サイクロペディア』の話になると、続いてリンネの分類学の話題に突入し、再び江戸に戻って蘭学と刃物の話になる。
レクチャーⅡも観相学の話題からエドガー・アラン・ポーの『黄金虫』、コナン・ドイルの『緋色の研究』、江戸川乱歩の『二銭銅貨』と時代も国も違う小説が取り上げられる。すると「驚異」というキーワードから、今度はマニエリスムやヴンダーカンマー(驚異の部屋)へと移行、レクチャーⅢはミシェル・フーコーのパノプティコンに始まり、べラスケスの「ラス・メニーナス」や18世紀イギリスの「ピクチャレスク」の話題になって、メタフィクションやミザ・ナビーム(紋中紋)へと行き着く。レクチャーⅣは、先のイギリスのピクチャレスクという概念がマニエリスムとアメリカ人作家であるポーの『アッシャー家の崩壊』と結びつき、グランド・ツアーと崇高論、江戸川乱歩と谷崎潤一郎が話題にのぼる。レクチャーⅤは英国式庭園からピーター・グリーナウェイの作品が……と続けていくと読者も(僕も)脳みそがパンクしてしまいそうなので、この辺でやめておこう。


各ページにも図版はふんだんに使用されているが、真ん中に厖大な「ヴィジュアル・ページ」が付されている。それらはどれも、いわゆる美術史の教科書や研究書にはめったに出てこないような奇妙なものばかり——本は見て楽しむものという面白さも味わった(アートディレクションは、あの杉浦康平だ!)。講義内容も上のような調子なので、論文やら専門書やら整理された文章を中心に読んでいた僕は、この講義本を初めて読んだとき「お前さんはいったい何の話をしているんだ」と幾度となく激しいツッコミを心の中で入れざるを得なかったのだが、不思議とこれがどんどん読めてしまう。いつの間にか、クセのある高山節と、意想外なものが次々と結びついてゆく知的なダイナミズムの虜になっているのだ。実際、知らないことだらけだったのだが、これらをすべて知り尽くしてやりたい、そう思わせる感染力の高い書物といえる。


実際、この本を読んでからすぐに、スヴェトラーナ・アルパース、ノーマン・ブライソン、マイケル・バクサンドール、アビ・ヴァールブルグなどを読むことになったり(その流れでジョナサン・クレーリーの書物にたどり着いたのは「僥倖」としかいいようがない)、マニエリスムや崇高美、英国式庭園といった言葉から無数の書物へと誘われていったり、とにかく、どの本を読むよりも、僕にとっては「教育効果」がきわめて高かった(事実、巻末に付けられた「リーディング・ガイド」を片っぱしから読んでいった)。視覚文化論や表象文化論といった領域横断的でスリリングな書物に出会い、強烈に影響を受けた僕が、初めて学部生のときに雑誌に寄稿した論考は「眼差しの系譜学——ベラスケス、マネ、ベケット」、「視線」を軸に時代を超え、絵画/映画を越境してゆく脱領域的なアプローチのテクストだった。
古今東西、縦横無尽に視覚的な文化現象が「類似」によって結びついてゆく。この大胆不敵な文化史の捉え直しが、どれほど学問を志そうとする浅学者の知的好奇心を触発したかはいうまでもない。高山宏の脱領域的な語りと出会っていなかったら、いわゆるスタンダードな映画学をプロパーとする「まとも」な研究の道を歩んでいただろうし、映像を他のメディアや文化表象との関係性のもとで捉えることも意識してこなかっただろう。この書物を通過しなければ、実写における映画スターの身体表象、アニメキャラの運動性、アイドルのパフォーマンス、バーチャルYouTuberを同時に思考するような作法は身につけていなかったかもしれない(1.)。そういう意味で、僕の研究の道における礎となっただけでなく、複眼的なパースペクティヴをもたらしてくれた大切な書物だ。
以下の論考では、バーチャルYouTuberを論じるために映画館の映画スター、テレビのアイドル、アニメーション、インターネットのセレブリティ(YouTuber/Vtuber)を比較している。北村匡平「デジタルメディア時代の有名性──〈アニメーション〉としてのバーチャルYouTuber」、伊藤守編著『ポストメディア・セオリーズ──メディア研究の新展開』ミネルヴァ書房、2021年、233-258頁。
教育論/教師論の本として出逢い直す
大学で教鞭を執るようになって最近、教育とは何かを考えることがしばしばある。あるいは「よい教師」とはどんな人間なのかを考えることも増えた。いまこの講義と同じような授業をやっても(同じような授業ができるはずはないのだが)、おそらく授業自体が成り立たない。2010年代という時代はそれほど教育に関わる重大な何かが決定的に変質したと思う。高山宏の『超人 高山宏のつくりかた』(NTT出版)や四方田犬彦の『先生とわたし』(新潮文庫)で描かれているような「ゆとり」のある大学教員の世界は皆無だし、学生とひたすら最近読んだ本や観た映画について語り合う余裕もない。
教員は厳しい業績評価の導入によって目先の成果に縛られ、授業準備と教務・雑務に追われてあくせくしている。専門分野は細分化され、実証主義が跋扈して、エビデンスやデータ、数字が重んじられる(もちろんデータや根拠が重要でないわけではない)。とてもではないが、僕たちに本書のような講義はできない——「もっとわかりやすく説明してください」「意味がわかりませんでした」「エビデンスはありますか?」というコメントが授業後に殺到するだろう。個人的には100人いたら5人が感化され、彼ら彼女らの人生を変えてしまうような体験の授業になったら素晴らしいと思うが、実際は100人いたら、なるべく全員がわかるように丁寧な解説の授業を心がけなければならない(そうしなければ授業評価アンケートに直結する……!)。この本で描出されている、こんな魅惑的で優雅な空間は、2020年代の日本のどこを探しても、もうほとんど残ってはいない。
改めて考えてみれば、僕が本書から受け取ったものは余りにも大きいと思う。本は「読む」ものという固定観念が崩れ、本を「見る」ことの愉悦を覚えただけではない。自由自在に文化現象を縦断/横断して繋げてゆく快楽を味得し、歴史をダイナミックに捉えるアクロバティックな作法を体感させてくれた。さらにいま、この本の高度で知的なライブ空間から、本当の教育とはどういうものかを深く考えさせられている。こうして教える立場になったいま、僕は図らずもこの本と出逢い直すことになった。かつてほど難解で珍紛漢紛ではなく、むしろわかりやすく、その繋がりの必然性も理解できるが、それ以上に感銘を受けるのは、この講義の知的空間と教師のありようである。研究・教育両面において、これまでも強力に人生に影響を及ぼし、これからも影響を受けるに違いない。そして何度も立ち返ってゆく本にもなるだろう。
北村匡平(きたむら・きょうへい)
1982年生まれ。映画研究者/批評家。専門は映像文化論、メディア論、表象文化論。東京大学大学院学際情報学府修士課程修了、同大学博士課程単位取得満期退学。現在、東京工業大学 科学技術創成研究院 未来の人類研究センター/環境・社会理工学院 社会・人間科学コース 准教授。
単著に『美と破壊の女優 京マチ子』(筑摩選書)、『スター女優の文化社会学 -戦後日本が欲望した聖女と魔女』(作品社)、『24フレームの映画学』(晃洋書房)、『アクター・ジェンダー・イメージズ』(青土社)など。『椎名林檎論──乱調の音楽』(文藝春秋)が2022年10月に刊行予定。

『表象の芸術工学』について──工作舎より
本書は工作舎刊行の「神戸芸術工科大学レクチャーシリーズ」の一冊として、英文学者・視覚文化研究者の高山宏さんが2000年から2001年にかけて行なった一年間の講義を書籍化したものです。
英文学を本領としながらも古今東西の視覚文化やデザインに通暁した高山さんを特別講義に誘ったのは、当時、同大学の視覚情報デザイン学科教授を務めていた杉浦康平さん。本書をはじめ、レクチャーシリーズの書籍のアート・ディレクションも手がけてくださいました。
著者・高山宏あとがき(本書298頁)より
教場が祝祭的というか、わくわくするようなパフォーマティヴな場でありうるなど、今の日本の不安と不信、疑心暗鬼と事なかれの教育の現場では、いかにもそらぞらしく響くのが残念でならないが、とにかくひょっとしたらそういう教室もあったという記憶なり、願わくば伝説が、その年、神戸芸術工科大学の大学院に出入りした学生と市民の方々のあいだに残ればいい。そのような気持ちで、憧れの杉浦康平先生のお誘いを受けたのだった。
こうして始まった特別講義の縦横無尽ぶりには、聴講生ばかりでなく、本書を担当した編集者も何度となく「脳みそパンク」させられたそうです。当時の編集裏話をここにご紹介します。
担当編集者・田辺の制作エピソード
まずは、カセットテープ10数本と、A3判レジュメ(高山先生によるコラージュ)全講義分の束を受け取りました。講義はパフォーマンスであると言わんばかりの高山先生の声が、テープから伝わってきました。「メラヴィリア!」とかの叫びがすごくて、思わず真似てみました。
講義は毎回、活気に満ち溢れていましたが、しばしば「えっ、何の話?」ととまどうことも。それでもとにかくできるだけレクチャーのかたちに近づけよう、不明確な点は高山先生に訂正・加筆願えばいいのだから、と努めました。
その後、高山先生は、私たちのテープ起こしからのまとめ原稿をベースに、訂正加筆というより、ほぼ書き下ろしをされました。今もその丁寧な手書き文字が目に浮かびます。つまりここで、大いなる洗練が起きたのです。
それなら最初から書いてくださればいいのに……いや、そうではありません。『表象の芸術工学』誕生には、ここまでの全プロセスが不可欠だったのだと思っています。後に「高山宏の世界の良き入門書」と評されもしましたが、本が出来るまでの、ほとんど表には出てこない、厳しくも楽しかった経過に思いを馳せています。
カセットテープ10数本というところが2000年代初頭のアナログ感を感じさせますね。そしてほぼ書き下ろしの手書き原稿。
現在なら、講義をそのまま動画としてYouTubeにアップしたり、講義そのものをオンラインで行うことが当たり前になっています。また音声データを自動で文字起こししてくれるAIもあります。
しかし編集者が脳みそパンクさせながらカセットの音源にかじりついて形にしたテキストと、機械的に文字起こしされたテキストが同価であるはずはありません(AIは「メラヴィリア!」なんて口真似しないし)。そして、聴講生を前にしての講義録をより多くの未知の読者に届けるために、高山さんが言葉を吟味し、文脈を組み立て直しながら変換し、セルフリメイクともいうべき『表象の芸術工学』という書物が誕生したのでした。
大学生だった北村匡平さんは、本書を通して高山ワールドに足を踏み入れ、その後、視覚文化を中心に領域を自在に横断する学徒となられました。
一度目は知の迷宮への先導役として出逢い、教育者となった今、あらためてこの本に出逢い直した北村さん。わかりやすさと効率性が優先される今日の教育現場の息苦しさを笑い飛ばし、学生たちの人生を深く迷わせてしまうような特別講義をいつの日にか実現していただき、願わくばその講義録を工作舎で刊行させていただきたいなあと願っています。(文責・李)

『表象の芸術工学』はまだ新品在庫がございます。工作舎へ直接注文のほか、全国の書店やネット書店でもご注文いただけます。Amazonは在庫数が少なく一時品切れになりがちでスミマセン。楽天ブックス、honto、7net、e-hon、紀伊國屋書店Book Webなどもご利用下さい。

(鈴木成文=監修、杉浦康平=アートディレクション)
A5判並製308頁 定価 本体2,800円+税 2002年 工作舎
北村匡平さんの単著はこちら↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
