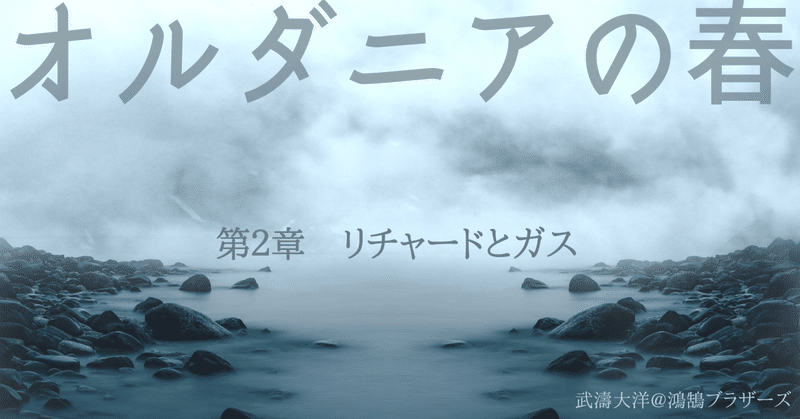
『オルダニアの春』16・創作ファンタジー小説(約2000字)
第3話 ままごとの続き
それは子供の時分に、遊びでつけたあだ名だった。小枝を剣に見立て、片膝をついたガスの肩にそれを置いた。
「ガス、汝は我が騎士として、生涯忠誠を誓いなさい」
「我が君、リチャード」
そうして王様と騎士ごっこを楽しんだ。
今、ままごとが現実になろうとしている。
「このままリシェルとして一生を過ごすのですか? 結婚し、子供を産み、育て、家を切り盛りする……」
「それは構わない」と、リシェルはガスを遮った。「私は父を愛している。父ために嫁ぐことも、子をなすことも、承知している……。していたはずだった」
さっきは苛立ちに任せて悪態をついたが、これがリシェルの本心だった。
「だが、私は女ではない」
「それを訴えて、証明できますか? エセルバート様に。ご家族に。ギャラン様に、エドワード様にも」
リチャードは、ついに覚悟を決めた。
「ガス。ここにはいられない。どうしたらいい?」
ガスは素早くリチャードの背後に回り込んだ。
「どうか私を信じてください」
どこに隠し持っていたのか、彼は短刀を抜くと、ひと思いにリチャードの髪を切った。肩の上まで、ばっさりと。
そしてろうそくを取って暖炉にくべ、髪も放り込む。
「着替えてください。例の服に」
肩越しに指示を飛ばしながら、ガスは布団にふくらみを作り、寝間着を隠している。
リチャードが着たのは、いつかガスがくれた、お下がりだった。
服が欲しいと言ったとき、彼は少しも驚かなかった。今にして思えば、あの頃から気づいていたのだろう。
一転してキビキビと行動する彼は、掬い上げるようにリチャードの手を取った。あの日、リチャードが彼にしたように。
「行きます。静かに。立ち止まらないで」
今までどのくらい計画を練ってきたのだろうか。ガスの動きは滑らかだった。
石造りのほの暗い廊下を、素早く、堂々と、しかし角かどでは人の気配に気を配って歩き、階段を降りて居城の隅へ、下へ。まずは半地下の使用人部屋へ連れて行かれた。
そっと様子を伺い、誰もいないことを確認する。
他の厩番と共に寝起きしていると聞いていたが、リチャードは初めてその中に入った。部屋そのものは城と地続きだが、妙に冷たく、埃っぽい。暖炉がないのだと気がついたが、他を観察する間はなく、ガスは自分のテリトリーにまとめておいた簡素な毛皮の外套を掴み、藁の山から荷物を取り出した。
リチャードは思った。本当は、毎日のように空想していた。ここから逃げ出すことを。けれども、それは窓から飛び降りるとか、暖炉の中をよじ登って煙突からとか、およそ叶うはずのない、単なる妄想だった。逃亡が実現しようとしている今、その方法はとても確実で、用意周到で、大胆なものだった。
二、三度使用人たちとすれ違ったが、まったく気づかれなかった。
誰が思うだろうか。エセルバートの娘リシェルが、婚約を控えた夜に髪を切り、下男の格好をして、こんなところを歩いているなんて。
ガスは勝手口から、いとも簡単にリチャードと城の外へ出た。
『東の鉄壁城』は、その名の通りの城である。四方十六の物見棟と城壁がぐるりと城を囲み、平野の真ん中に建っているとは思えないほど堅牢な作りだった。
オルダニア大陸のやや東にあって、国の基幹を成す『王の道』の交差する場所にある。これより北には『金の鉱山』があり、東にはエドマンド領。少し逸れるが『崖の町』もある。南には『王都』があり、西は『滅びの山脈』方向へ続いている、要の城なのだ。
城壁の周りには町が整備されていて、さらにそれらを取り囲む『古代の壁』が二重に城を守っている。大胆に行われた治水工事で、大河の支流が町のすぐ外を通って潤していた。
リチャードとガスは、まず一つ目の壁である城壁を越えなければならない。しかし、それも彼の手にかかれば、単に右から左へ物を動かす程度のことだった。
早口に、「ひとことも話してはいけません」と念を押すや、裏戸の門番に「冷えますね」と、抜け抜けと声をかけたのだ。
これにはリチャードも肝を冷やし、外套の胸元に首を縮めた。
若い門番二人はガスの顔を確認するや、「なんだ、またお前か」と、にやにやしている。「間抜けが来たぞ」と額に書いてあった。
ガスは白い息を手に吐きつけた。
「今夜も女のトコに、あったまりに行きたいんですが」
途端に二人は腹を捩った。
「お前も好きだな。リシェル様が人のモンになるからって、やけを起こしてるんだろ。それをな、嫉妬って言うんだぜ。わかるか?」
番兵の舐めきった態度に、リチャードは怒りが込み上げてきた。だが、口を利かないと約束させられている。唇を噛んで堪えるしかない。
ガスはその二の腕を引き寄せた。
「今夜は、新人教育もありまして」
「いい気なもんだな」
と、鼻を鳴らしながらも、番兵は門を開けた。
ガスから小銭を受け取るのに夢中で、リチャードの顔を確かめることもない。「朝んなる前に帰ってくるんだぞ」と、背中に投げて寄越しただけだった。
-----マガジン
----- 作者プロフィール
----- Twitter
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
