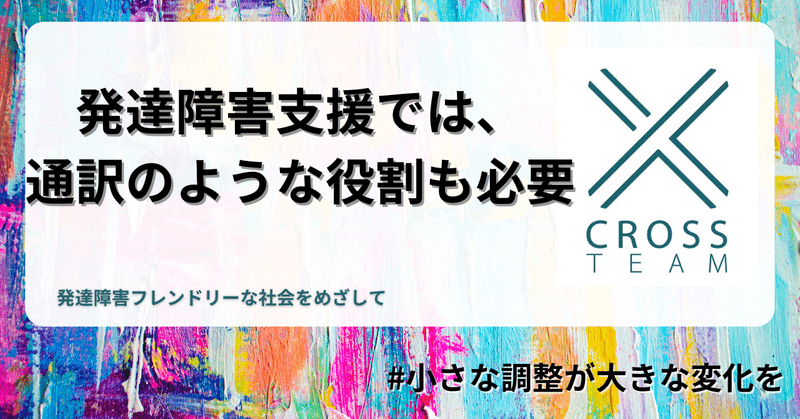
ASD支援では、通訳のような役割も必要
この記事は1,471文字あります。個人差はありますが、3分〜4分でお読みいただけます。
このnoteではVoicy(音声配信)で配信した内容のテキスト版(要約版)です。詳しくはVoicyで聴いて頂ければと思います。
ちなみに、Voicyは下記チャンネルで毎日更新しています!
今回のテーマは、「発達障害支援では、通訳のような役割も必要なのではないか」です。どうぞお付き合いください。
受け取り方の違いを理解しようとする
自閉症スペクトラム(ASD)の方々は、ものごとの捉え方や感じ方に違いがあると言われています(専門用語で言うと「認知特性が違う」)。
例えば、感覚の偏りが典型的な例かもしれません。多くの人が何気なく過ごしている空間でも、匂いや音が辛いということがあります。電車の人混みがどうしてもダメで、電車に乗れないという場合もあります。
一生懸命話を聞こうとしても、部分的にしか話をキャッチできないということがあります。例えば、「手を洗ってからおやつを食べよう」と言われた時に、「手を洗う」という部分がうまく聞き取れず、おやつを食べに行こうとしたところを止められて、(本人にとっては"止められた"という想定外のことが起きてしまい)混乱することがあります。
全体像よりも細かいところが気になってしまって確認し、周囲から「細かい」「そんなこと気にしないで欲しい」と言われてしまうこともあります。合理的に考えるタイプの方にとっては、自分にとって納得できる理由がないと質問を繰り返すことがありますが、それを嫌がられたりすることもあります。
これらはほんの一部ですが、ここまで書いたように、ご本人にはご本人なりの言い分や考え方があります。
行動の背景には、どう情報をキャッチしているかが関係する
僕らは何らかの情報をキャッチして、その結果として行動をします。例えば、水を飲むのは「喉が渇いた」と感じるからです。僕自身は納豆が食べられませんが、それはアレルギーとかではなく、単に納豆のにおいや味がダメだからです。それを無視して、「体にいいから食べな」と行動だけを変えようとされると、まぁまぁ苦痛です。
ASDの方々の行動の理由は外から見ただけではわからないことが多いのですが(まぁ、ASDに限らずに、人の行動の意図を100%わかるなんてことは、少なくとも僕はできないと思っている)、それを自分でもうまく説明できないこともあります。
僕が納豆がいかに苦手かを人に理解してもらえるために行動できるのは、言語という手段があり、またそれを自分で説明できるからです。
でも、それが難しいとしたら?
言葉によるコミュニケーションが難しい方は特にそうですし、言葉で伝えられる方でも、説明がうまくできずに誤解されることがあります。
まとめ
支援者をはじめとする周囲の人たちに求められるのは、ご本人の行動の背景にある情報を推測し、理解しようとすることです。「何度言っても聞いてくれない」と思われる場合も、背景には理由があります。そして、それを伝えていくことが、周囲の理解や支援につながります。
それが、通訳のような役割があるということです。
そのためには、発達障害についての正しい知識を持つことも重要です。ASDやADHD、学習障害、知的障害などについて理解し、説明できるようにすることがそのための一歩でしょう。
とはいえ、偉そうに書いてきましたが、僕自身もまだまだわからないことも多いですし、これからもアップデートしていけるようにと思っています。
より詳しくはVoicyを聴いてもらえればと思います。
では。
佐々木康栄
災害時に役立つさまざまな情報
これまでnoteにまとめていましたが、TEACCHプログラム研究会東北支部のホームページに集約しました。宜しければご活用ください。
その他お知らせ
オンラインサロン「みんなで考える発達障害支援」
SNS
▼Voicy
▼stand.fm
▼X
https://twitter.com/KoeiSasaki
https://www.instagram.com/koei.sasaki/
https://www.facebook.com/koei.sasaki.5
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
