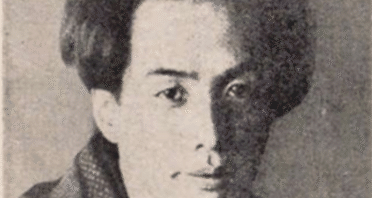2024年3月の記事一覧
まずちゃんと読もうよ 本当の文学の話をしようじゃないか⑬
結局人文学系の学者というのは自分の「専門分野」においてさえ、事実確認する義務を免除されている、という状況があることが問題の根本ではないかと思う。「会社法」を専門としながら会社法の運営を知らず、株主総会に参加してもいない。何なら自分が問題視した株主提案を読んでさえいない。ネット記事の拾い読みで批判することが許されている。そういういい加減なものが文学以外のアカデミックな領域に拡大しているのではないか
もっとみる罰するだけの如来様? 芥川龍之介の『尾形了斎覚え書』をどう読むか②
昨日は何故伴天連に助けを求めず医者の所に来たのかというあたりについて書いた。『邪宗門』の摩利信之法師のような念力は伴天連にはないのかあるのか。そもそもこの切支丹はどういう種類のものなのか。そのあたりが解らないから引っかかるという意味だ。
この引っかかるということをこれまでずーっと何千回か書いてきた。それはつまり「流さない」ということだ。Audibleで『黄色い家』を聴いた人の感想を読んだら「
その一人があらわれる日の為に 本当の文学の話をしようじゃないか⑫
芥川はともかく三島由紀夫もインターネットを知らずに死んだ。それはとても想像できない世界だったのだ。例えば『AKIRA』にもスマホは出てこない。インターネットのない時代に、何故か中国の脅威とテレパシー連携による集合知の可能性について書いたSF作家がいた。
ここには確かにうっすらとだがネットワークの発想がある。そして数年前に現実となった中国の脅威をいち早く言い当てていたことにも驚く。
あるい
切支丹の奇蹟はどうした? 芥川龍之介の『尾形了斎覚え書』をどう読むか①
散々芥川作品を読んできて、なおこれらの問題には明確な答えが見つからないように思う。
①何故芥川は切支丹ものを書き続けたのか。
②最後にイエス・キリスト個人について批判したのは何故か。
この二つ目の問いは「イエス・キリスト個人に対する批判と切支丹ものにはどのような関係があるのか」という第三の問いへ還元されうる。
よくよく読めば芥川の切支丹ものにおける信仰の対象はさまざまで、それはさまざ
芥川龍之介の『貴族』をどう読むか①
※大恭……中国語で💩
これはあくまで貴族という題名だが、「何処の国でも、先祖は神々のやうな顔をするかも知れず」とは天子様に対する大変な皮肉である。そしてさらには「徳川時代の大諸侯は、参覲交代の途次旅宿へとまると、必ず大恭は砂づめの樽へ入れて、後へ残さぬやうに心がけた由」とは皇族にも同じような努力をせいという追い打ちである。最後に「何故人は神だと思はないかと云ふと、云々」は大恭をする以上付け
誰が猿なのか 芥川龍之介の『猿』をどう読むか⑧
昨日は無意識と意識のずれが意識されていて、「私」が分裂していて、奈良島の言葉が少しおかしいというところまで書いた。勿論語りながら聞き手に回る時点で芥川としては分裂する気満々である。猿股とオオストラリアの猿を出したところで「ないことないこと」を書く気満々である。
どんな文章を読んでもたちまち意味を理解してしまう素晴らしい読解力をお持ちの皆さんならば、「私たちより大きい、何物か」がなんなのか
そういう言い方はないだろう 芥川龍之介の『猿』をどう読むか⑦
昨日は帆船は古いと書いた。
スライダーのようなとぼけた比喩、特殊過ぎて解りにくい比喩を使い、素人の語り手であることを強調しながら、「小説家」に向かってとても想像の出来ない恐ろしい顔をについて語って聞かせる「私」はついさっきまで優越感に充ちたハンター、恐るべき若者たちであったはずなのに、その恐ろしい顔の前になにかもう砕かれそうになっている。
これはもう何が何でもこの先を読まなくては気が済む
帆船はもう古い 芥川龍之介の『猿』をどう読むか⑥
昨日は『猿』が直接読者に向けた語りかけではなく、軍艦に乗ったことがある聞き手が存在し、その相手に向けられた語りであるということを書いた。
最初から分かっていたという人がいれば退屈な記事だったかもしれないが、おそらくそんな人はいないだろう。何故なら昨日の記事も誰一人読めていないからだ。『猿』が直接読者に向けた語りかけではなく、軍艦に乗ったことがある聞き手が存在し、その相手に向けられた語りである
天皇は乳房か 本当の文学の話をしようじゃないか⑨
谷崎潤一郎が大谷崎であり、本物の文学者であったことを疑うものはあるまい。しかしおそらく多くの人はこの二つのことを知らなかったはずだ。それは谷崎潤一郎がこんな悲壮な覚悟で書いていたこと。
そして谷崎の原点に小波、巖谷漣山人の「新八犬傳」があるということ。
つまりその原点には間接的に馬琴が隠れていることにもなるが、そこは話を飛ばさず、しばし巖谷小波について考えてみよう。
巖谷小波はさまざ
聞き役がいた 芥川龍之介の『猿』をどう読むか⑤
昨日はオオストラリアには猿はいないと書いた。もう繰り返すまでもないことながら「そんなのたまたまだよ」と意味を拒絶することには何の意味もない。素朴な書き誤りや誤解を確認することも繰り返しやってきた。
そのうえで書き誤りや誤解に還元できないところを指摘して来た。
俳句の植物に関する知識からして、芥川の博物に関する知識はかなりのものだ。同様に地理、歴史の知識も豊富だ。何しろ帝国大卒の知的エリー
二度あることは三度あるっていうじゃない 本当の文学の話をしようじゃないか⑧
読書好きとか、本が好きという人の大半は信用できない。彼らの大半は本来読めるはずのないものを読んだことにしているからである。そうでなければ「ハイポーが抜ける」で検索して私の記事が最初に出てくることはなかろう。「矢の根を伏せる」とはどんな作法なのか書かれている記事がない。言葉には意味があるのに、みな言葉に意味があることなど忘れて、ただ文字を追いながら自分の考えに耽っていたに過ぎない。
この引用に
オオストラリアの猿? 芥川龍之介の『猿』をどう読むか④
昨日は語り手が危険な優越感に充ちていて、奈良島を「猿」と呼び、狩ろうとしているというあたりの感覚の斬新さと気味悪さについて書いた。なんだかとても気持ちが悪い。それは自分の中にもそういう恐ろしいものが潜んでいるのではないかという不安があるからであろう。その不安は間違いなくこの若い書き手が操っているものだ。そしてそのような意匠は何度考えても芥川以前には見いだせない……。
いや、そこまでは言い過ぎ
サリンジャーの焼きそば 本当の文学の話をしようじゃないか⑦
結局文学の胆の部分というと微妙なものの微妙さを捉えることで、それは「サリンジャーの焼きそば」や「黒板の前に立っている恰好」なのではなかろうか。何か逆張りのような皮肉なような言い方ながら、これは本当のことだと思う。
これが太宰治であれば「黄村先生の玉子どんぶり」であることは既にどこかに書いた。初期村上春樹の魅力の一つ、オールドファンを捉えた重要な要素は『グレープ・ドロップス』に見られた言語感覚
狩る快感 芥川龍之介の『猿』をどう読むか③
昨日はこの『猿』の語り手が全く信用できない冷酷な二重人格者に見えるという話を書いた。「私」「僕」「私たち」と自称する語り手は仲間が自殺したかもしれないのに平然としている。しかし解らないのはこの語り手が語っている現在の位置だ。そろそろこの人は何を語ろうとしているのかと疑問が湧いてくる。これは何のための語りなのだろうかと。
海軍士官候補生の優越、ここにはそんなところには収まらない危険なものがあふ