
聞き役がいた 芥川龍之介の『猿』をどう読むか⑤

昨日はオオストラリアには猿はいないと書いた。もう繰り返すまでもないことながら「そんなのたまたまだよ」と意味を拒絶することには何の意味もない。素朴な書き誤りや誤解を確認することも繰り返しやってきた。
そのうえで書き誤りや誤解に還元できないところを指摘して来た。
俳句の植物に関する知識からして、芥川の博物に関する知識はかなりのものだ。同様に地理、歴史の知識も豊富だ。何しろ帝国大卒の知的エリートなのだ。教科書が間違っていたら間違いも覚えるだろうが、オオストラリアの猿が「そんなのたまたまだよ」ということはあり得ないのだ。
恐るべき若者たちによって読者を不安にさせること、オオストラリアの猿によって恐るべき若者たちの驕りを感じさせるところまでは明確な作者の意図であるが、作者の意図を前提にしないという頑ななテクスト論的読みにおいてこそオオストラリアには猿はいないという事実は重要な意味を持ってくるだろう。作者の意図に関わらず、恐るべき若者たちの成功体験はあり得ないことであり、その優越感はもろくも崩れ去る驕りであるはずなのだ、という理屈になる。「そんなのたまたまだよ」と言いたいのは、たん自分が見逃していたことを胡麻化したいというプライドゆえのことであり、それはオオストラリアの猿による自己肯定と同じ事で屁のツッパリにもならない。次の燃せるゴミの日に捨ててしまうといい。
※関東大震災の震源地に近いある場所では燃えるゴミの日ではなく燃せるゴミの日と掲示してある。

この辺りは津波で大変な被害を受けた。
これはたまたまではない。海軍機関学校に勤務したままその日を迎えていたら、芥川も津波に流されていたかもしれない。
また日本から輸入したニホンザルを貰ったのかもしれないと粘る人は重傷だ。オオストラリア人が日本に立ち寄ったらカンガルーやコアラをプレゼントするかね? そういう感覚?
その粘りは別の方向に向けた方がいい。
私は、その時、一番先に、下甲板へ下りました。御承知でせうが、下甲板は、何時もいやにうす暗いものです。その中で、磨いた金具や、ペンキを塗つた鉄板が、あちらこちらに、ぼんやりと、光つてゐる。――何だか妙に息がつまるやうな気がして、仕方がありません。そのうす暗い中を、石炭庫の方へ二足三足、歩いたと思ふと、私は、もう少しで、声を出して、叫びさうになりました。――石炭庫の積入口に、人間の上半身が出てゐたからです。今、その狭い口から、石炭庫の中へ、はいらうと云ふので、足を先へ、入れて見た所なのでせう。こつちからは、紺の水兵服の肩と、帽子とに遮られて、顔は誰ともわかりません、それに、光が足りないので、唯その上半身の黒くうき出してゐるのが、見えるだけです。が、直覚的に、私は、それを、奈良島だと思ひました。さうだとすれば、勿論、自殺をするつもりで、石炭庫へはいらうと云ふのです。
さてここで私が何と書くか解ったよって方、ちょっと挙手してもらえますか?
恥ずかしがらないで。
います?
いません?
どっちですか?
あらない?
ええと「御承知でせうが、」って何ですかね。みんながみんな軍艦の下甲板へ下りたりはしませんよね。軍艦は女人禁制かと思っていたら三島由紀夫が軍艦に慰安婦かなんかを載せていたので、これは「女性を排除した語り」ではないですよね。そういうこともちらっと考えましたが、そういうことではなくて、ここで一つの人格を持った聞き役が登場したことになりますよね。
つまりこの話は単に読者に直接向けた語りではなく、この軍艦でなくてもいいんですが、ともかく何かの軍艦の下甲板へ下りた経験があるという特定の聞き役に対する語りだったわけです。
しかしこれまでに、
①やつと半玉(軍艦では、候補生の事をかう云ふのです)
②勢よく例の上陸員整列の喇叭が鳴つたのです
③身体検査ですから、勿論、皆、裸にさせられるのですが
……などといった説明があることから、この聞き役は少なくとも軍艦のしきたりには不案内でありながら喇叭の合図は知っていて、なおかつ軍艦の下甲板へ下りた経験があるという……例えばまもなく海軍機関学校に教員として採用され研修の為軍艦を見学する芥川龍之介のような、そういう特殊な人物が想定されていると考えるべきであろうか。
そんなうまい話はなかろう?
そんなうまい話はないと思う。
どうも芥川龍之介自身はその前に軍艦には乗っていたようだ。その経験が『猿』に繋がっているとはまず考えてよかろう。どうしてここで聞き役を出してきたのか、その意図はまだ分からない。ただまた「私」に戻った語り手が奈良島らしき男を石炭庫の積入口に見つけたと誰かに語っている。ここで読者はこれまで直接語り手から聞かされていたという話が、実は語り手と聞き役の間の話の盗み聞きであったことを知らされる。そういえば「例の」とは「私って〇〇な人じゃないですか」というくらい押しつけがましいなと、今になって恨めしく思いだす。
そしてほんの少しは聞き役の気持ちについて、同じ軍艦に乗り合わせた仲間を猿呼ばわりして狩ろうとする恐るべき若者の話を聞かされる軍人ではない聞き役の気持ちについて、彼は今どんな気持ちでこの話を聞いているのだろうと考えてみる。
母、私がADHDの検査でIQ出したら国語系が100超えたと報告しただけなのに、以降母の前で鏡花全集とか読んでいたら、何度も「そりゃあんたは頭いいでしょうね」とつっかかってきて厄介すぎた。
— 🐉和田塚のねこ@本所両国🐉 (@R_Akutagawa0301) March 24, 2024
母、学生時代に鏡花作品、芥川作品を読もうとしてどうやら挫折したらしい。
だからって読書の邪魔しないでと https://t.co/e9aTrETZ7O
いや、そんなこと全然考えてもみなかった?
聞き役なんか本当にいるのかって?
ごく普通に読めばいるとしか言えない。
ごく普通に読めば。
これ村上春樹さんの『クリーム』でもそうだったよね。あれは誰か解らないけれど年下の青年らしき聞き手を挟んだ話だった。

そういう作品の構造というものを見つけられないと、芥川には構成力がないとか、そんな低次元の話が出てきたりするわけだ。『奇怪な再会』なんかも「私」が話を複雑にしている。
こういうところをしっかりと捉えないととんちんかんな読み方になってしまう。
しかし実際教育者の立場にありながら『こころ』の先生は明治天皇の崩御の報を聞いて自殺すると書いてしまう人がいるくらいなので、普通に読むという事が出来ない人が教育者になれるという現実に鑑み、普通に読むということはかなり難しいことなのかもしれない。
いや、これまでみてきたように、それは迂闊な人々とつてはかなり困難なことであろう。
迂闊な人に共通してみられる特徴は私の本を買わないことだ。
まだ分からないかね?
おそらく芥川は『芋粥』で持ち出した善良な読者の代わりに聞き役を置いている。本当の読者には何も期待できないから。
つまりこの聞き手は恐るべき若者の話を冷静に聞いている。賛同はしていない。オオストラリアの猿でニヤリともしなかった。泳がしている。「私」はいい気だ。
そのいい気というのがどのくらいいい気なのか書きたいところだが、ちょっと用事があるので今日はここまで。
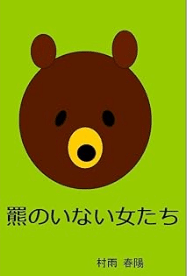
[余談]
吉野家を出てくる小学生とお母さん。
店員が「ありがとうございました」と声をかけると、くるりと振り向いて「ありがとうございました」とお辞儀をする小学生。
誇らしげなお母さん。
美しき日本。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
