代表コラム7.学びの姿勢は表面化する
今日は学びの姿勢について。
子どもの時は幼稚園、小学校、中学校、高校、大学と学ぶ環境が自然に用意されているので必然的に学び成長していく傾向にある。
ところが大人になってからはどうだろうか?
目の前に与えられている業務やタスクをこなすだけで自己成長ができている人といない人で分かれる。
これは特定のスキルなどの領域に限らず、対人のコミュニケーションなどからも読み取れる。
人は事象と解釈の二つを物事に対して考える。例えば、
事象:◯◯さんが殺された。(事実)
解釈:◯◯さんが可哀想。(感情)
といった具合に、解釈にはその人のこれまでの人生観などが描写され、感情が入る。
例えばこの時、◯◯さんが殺された人の家族を殺していて、その人の復讐だとしたら、同じ感情が湧くだろうか。
例えば、◯◯さんが飲酒をした後に横断歩道を渡っていて、明らかな信号無視をしていて引かれたとしたら。
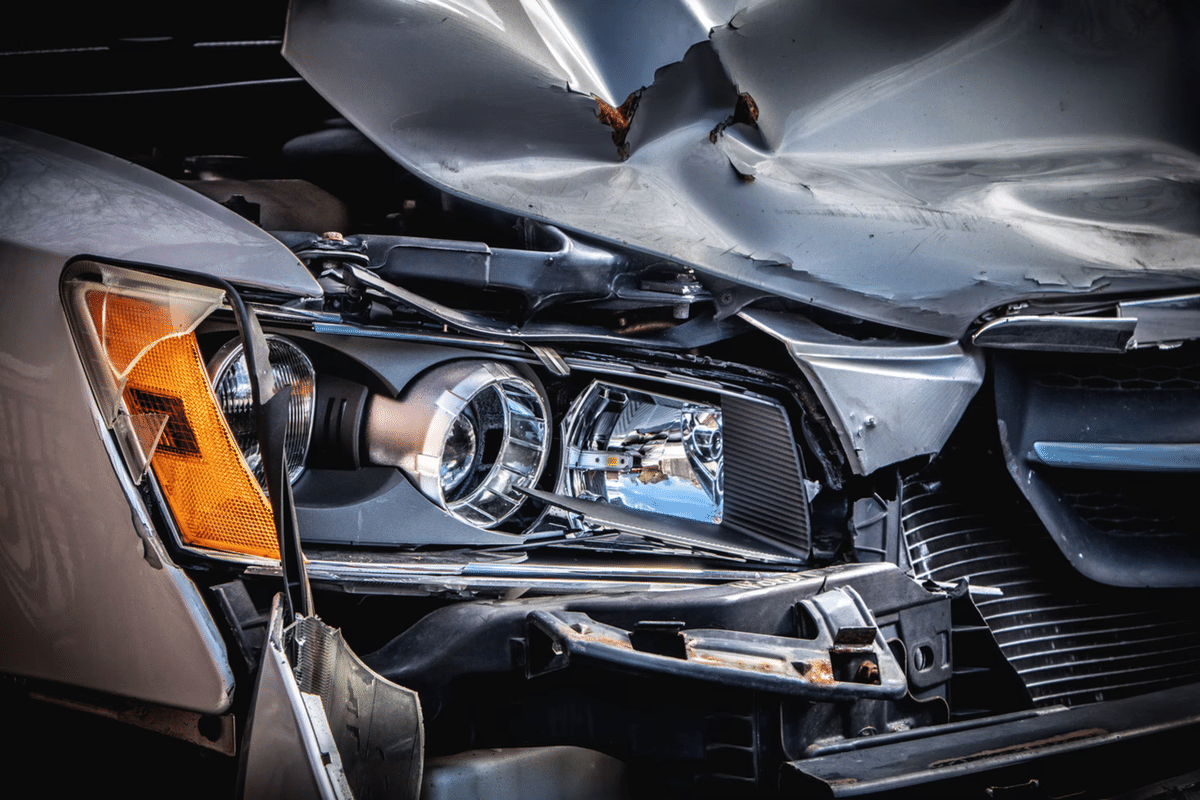
こういった起こりうる可能性というのは、情報量によっていくつも発生する。従って、起こった情報をかき集めながら起こりうる事象を可能性ごとに検討した結果、
A,B,C,D,E,Fがあるんだけどももっとも起きているであろう仮説はCなんだよね。Cが起きているとしたら。。。
といった具合に、想定をした上で結論を出すのと、Cしか考えないのとではその後の行動や選択肢が異なる。
これはどの仕事をする上でも必須である。例えば経営者は起きうる将来のリスクに対して想定をし、第一優先事項として何がなんでも会社が存続するための選択肢を取り続けなければならない。
となると、常日頃情報の変化に対するアンテナを張り巡らせるのと同時に、錯綜する情報を"必要な情報(データ)"として検知して自ら学び適応していくことが大切であると考える。
サラリーマンにおいても、大きな企業になればなるほど作業は細分化されており、全体像にはなかなか触れにくい。そうすると物事の原理だけ目の前の相手から要求されていること(もしくは2,3手先)までは思考、遂行をしてもその先については考えないことが多いです。(考えない仕組みにしているので被雇用者として限界がある)

つまり、自分が身を置かれている場所自体にも学びはいくつもあり、また学び続けていかない限りは外部要因によって淘汰される可能性がある、ということです。
そして学べば学んでいる人ほど、自分が無知であることを知り、より謙虚な傾向にあると言えます。ソクラテスの「無知の知」とはよくいったもので、知らないことが何かを知ることが大切ですね。
人生、学びの姿勢。これこそが次の一手を生む根幹なのかもしれません。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
