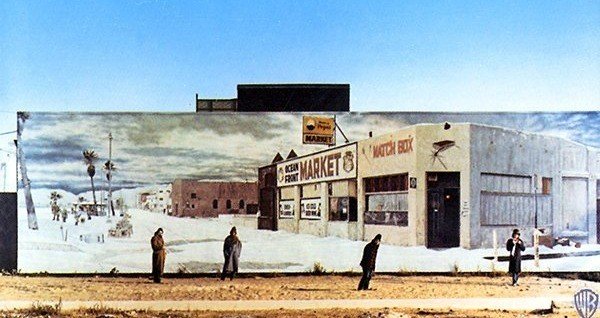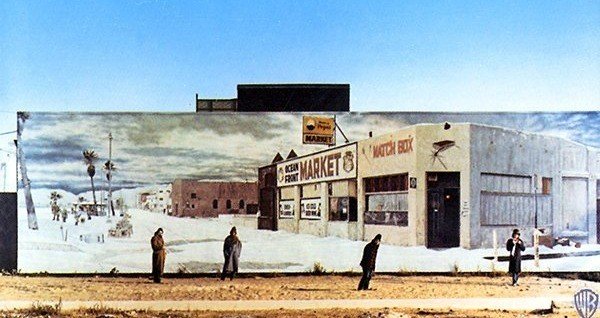小田嶋隆の本を三冊読んで「中二病」について考えた
日経ビジネスオンラインで連載している「小田嶋隆のア・ピース・オブ・警句」を楽しみにしている。コラムニストの小田嶋氏が「引きこもり系」で「上から目線」という独特なポジショニングと炎上覚悟の批評的な切り口で時には強引な自らの意見を披露してくれる。
今回小田嶋氏関連の本「もっと地雷を踏む勇気」、「超・反知性主義入門」・「いつだって僕たちは途上にいる」を三冊まとめて読んだ。
最初の二冊は「小田嶋隆のア・ピース・オブ・警句」を書籍化したものなので、一部は過去オンライン掲載時に読んだ