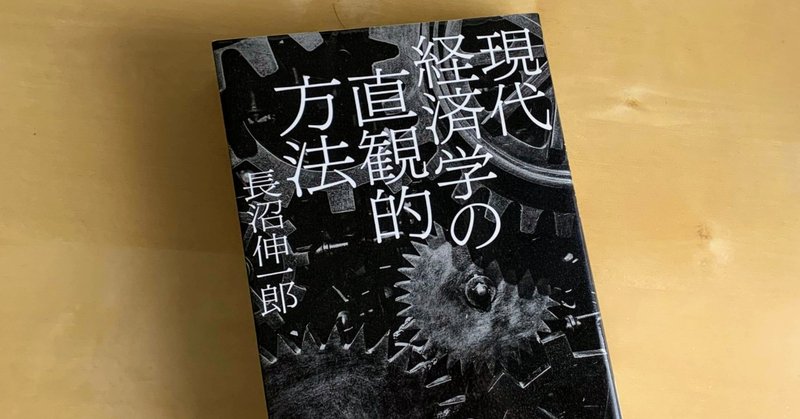
長沼伸一郎「現代経済学の直観的方法」
私は一応経済学部を卒業しているが、大学時代はスキーが主な活動だったし、日本経済史のゼミも単位を頂けるという理由だけで参加させてもらっていた不甲斐ない学生だったので、経済学について人に語ることができるほどの知識も素養も無い。
今回ご紹介する本書「現代経済学の直観的方法」は応用物理学の専門家である長沼氏が次のスペックで書いたものである。
”経済というものが全くわからず予備知識もない(ただし読書レベルは高い)読者が、それ一冊を持っていれば、通勤通学などの間に1日あたり数十ページ分の読書をしていくだけで、1週間から10日程度で経済学の大筋をマスターできる”
おお、これなら流石の私でも十分読む資格があると思って本書を手にとってみた訳だ。
とは言え、実は私のような読者は著者の本命の読者では無くて、理系である著者からいうと同じ理系で経済学を避けて来た人に経済学を一冊で教えようという狙いがあるようだ。また著者によると本書は意識的に入門書と専門書の中間的なポジションに位置づけたものだとのことである。
「直観的方法」とあるのは、著者には1987年に「物理数学の直観的方法」というベストセラーがあって、今回もそのシリーズの一つとして「直観的方法」という書名を冠している。とはいえ著者にとってもこの分野外での挑戦は大変苦労の多いものだったようで本書の企画から出版まで足かけ20年かかったという。
そういう背景を理解した上で読んでみると、これまで伝統的な経済学の教科書しか見たことが無い私にとって、理系ならではの新しい視点での経済学の解説は興味深い。特に第8章「仮想通貨とブロックチェーン」での説明はこれまで読んだ中では一番わかりやすかった。
全体を読み終えると、この本のクライマックスが最終第9章「資本主義の将来はどこへ向かうのか」にあることがわかる。以下この章を中心に著者の主張を紹介してみよう。
著者は現在の「経済が(巨大企業に)縮退している」と言う。「縮退」は元々は量子力学の用語だそうだ。
「中心部が栄えて全体としては量的に大きくなったとしても、生態系としては劣化している」...「一旦縮退状態に陥ってしまったものは、そこからゆっくり回復するより、むしろ全体が一種の大破局でリセットされて、更地から再出発していることが多い」
中心部は超巨大企業と巨大機関投資家と言い換えて良いだろう。一部の企業と投資家が成長しているが、全体でみると成長どころか劣化している姿を独特の語彙で表現している。GAFAの肥大化を欧米政府が懸念し、実態経済と乖離した形で投機マネーが株価を押し上げている現在はまさに「縮退」だ。
もう一つの本書のキーワードが「コラプサー」で、こちらもブラックホール関連用語だそうだ。「コラプサー」とは次の状態だとする。
「短期的願望などが極大化した状態で、進むことも退くこともできなくなり、回復手段を失ったまま半永久的にそれが続くようになってしまっている状態」
その上でこの「縮退」と「コラプサー」という二つのキーワードが根源的な問題だと指摘する。
「縮退とコラプサー化の問題こそ、環境問題と格差問題の二つの背後にラスボス的に控える共通の源であり、これこそが人類が取り組むべき真の脅威」
環境問題や格差問題が大切であることは明白なのに、人類はいまのところその優先順位を変えることはできない。その原因は、環境問題や格差問題があくまでも現象面だからであり、その根源には「縮退」と「コラプサー」があるというのだ。
現在の状況を数字で見てみる。一日に投機のために移動する資金量が一兆ドルで、実際にモノが動く世界全体の貿易額の一日あたりはわずか130億ドルに過ぎない。
「本来ならば世界のマネーはその外側の領域全体をくまなく隅々まで広く回るべきものなのだが、現在の世界経済ではその流れ全体がどんどん縮退し、狭い金融市場の内側だけで投機のために回るようになっている」
それではこういう状態をどうして招いたのだろうか。それは「大勢の短期的願望(部分)を集めていけば、それは長期的願望(全体)に一致する」ことを教義とした米国のリベラル進歩主義が、単なる縮退を社会的進歩と勘違いしてしまったのであり、皮肉なことに近代以前の社会のほうが、短期的願望を人為的に抑え込む必要性をよく理解していた、のだと言う。それが今では糸の切れたタコのように歯止めが利かなくなりつつある。
そして著者はこういった状態を止めるのは難しいと言いつつ、逆のモメンタムがあれば止めることは不可能ではない、とする。
「縮退を止めるための力学として人間社会が縮退の少ない方向へ向かい、経済社会の金銭的な利益を求めるマネーが社会の縮退が大きい方向へ動こうとして、その両者の力が拮抗すれば縮退を止めることも不可能ではない」
それでは人間社会の縮退の少ない方向とはどういうものなのか。著者は「呼吸口」と表現する。
「人間の精神の呼吸口、精神が希望を感じて窒息しない状態を極大化すること」
物質社会でモノが溢れるにも関わらず幸福を実感しない現代人。幸福は「幸福な境遇」それ自体ではなく、「想像の中の幸福」を吸収することで幸福を感じるのだ、という。
著者は人間の内的想像力が発揮できる、すなわち呼吸できるためには、人間同士をつなぐジョイントが必要で、それを碁石に例えて表現する。それでは「呼吸口」やジョイントはどうすれば作ることができるのか。その答えは簡単では無いが、ジョイントにはある特性がある、とする。
「人間同士の相互依存が強い場合にはその間のジョイントが強固になり、そしてそれは上下では生じやすいが横方向には斥力が作用して発生しにくい」
その上で
「地域的な結びつきを強める試みや愛国心の復権などは、ある程度までは呼吸口を増やす役に立つと思われるが、巨大な金融の力に対抗するにはさすがにそれでは力不足である。」
とポスト資本主義としてローカル化を提唱したり、逆にナショナリズムを強調することでも巨大な金融の力は止められないとする。
そして筆者は過去の歴史の教訓から学ぶとすれば、モメンタムを止められるのは大きな思想の登場が必要だという。
「当時の最高レベルの知性を持つ人々に支えられた一種の大きな思想が存在していて、それが一般の人々に「これこそ宇宙や世界の唯一無二の真理である」という一種の畏敬の念をもって受け入れられていなければならない」
政治家が小手先の思い付きですることでは金融の力には対抗できず、大きな思想の登場で、所詮「政治家は仕上げの役割のみを担当することが多い」とする。
大きな思想の登場を待望しながらも、最後に著者は「縮退」を完全に無くすことが必要ではなく、また人類は伝統的には「縮退」を弱める「資源」があったもので、これを大切にすることで「縮退」を弱められる、と締めくくる。
「完全に縮退しない社会などは作れない」...「ある程度の幅で縮退や自由を許容する社会の方がむしろ望ましい」...「縮退の少ないように功名に作られた伝統的な制度というものは、実はそれ自体が一種の「資源」なのである」
なにやら宗教的・保守的な匂いもしてくる締めくくりだが、果たして環境問題や格差問題などを解決するための大きな思想とはどういうものなのか。そこまでは本書では明らかにしていない。
この著者の本書での結論を光明と見るのか、コラプサーを宿命と見るのか。それは短期的願望だけに終始しない人類の力を信じるのかどうか、の違いなのだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
