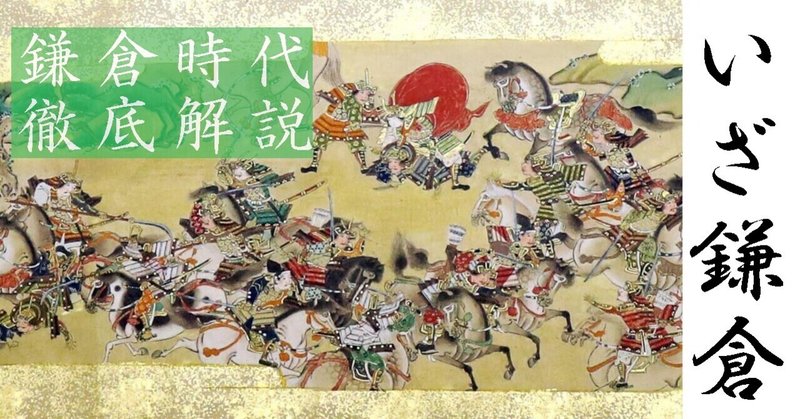
【いざ鎌倉(47)】北条義時の勝利宣言
前回の振り返り。
京へ侵攻する幕府軍とそれを防ごうとする官軍は宇治・瀬田で激突します。
官軍は武士だけでなく貴族まで前線に送る総力戦を展開し、長雨による河川の増水にも助けられ幕府軍を大いに苦しめました。
しかし、幕府軍が渡河を強行し、成功させると万事休す。戦いは幕府軍の勝利と終わり、最早京への侵攻を防ぐ戦力は官軍に残されていませんでした。
すれ違う後鳥羽院と武士
宇治・瀬田で敗れた武士たちが院御所に敗北を奏聞に訪れたのは6月14日夜半から15日早朝にかけてのことでした。
三浦胤義・山田重忠・渡辺翔らは院御所門前にて、「戦いは敗北に終わりました。開門して下さい。院御所にて敵を迎え撃ち、力の限り戦う様をお見せして討死したいと思います」と奏聞しました。
これに対し後鳥羽院は「お前たちが御所に立て籠もったら私が攻撃されることになるではないか。早々に立ち去れ」と返答し、院御所の門が開くことはありませんでした。
三浦胤義は落胆し、後鳥羽院の計画に加担したことを後悔しました。
見捨てられたと感じた胤義らの落胆は理解できますが、彼らの思考は武士の論理です。
後鳥羽院の頭には武士が求める「美しい死に様」なんて考えは微塵もなかったことでしょう。皇室の家長である後鳥羽院にとって最も重要なことは「敗戦が確定した中でいかにして皇室を存続させるか」なのです。
この時の院御所には自分だけでなく、仲恭天皇、土御門院、順徳院、冷泉宮、六条宮が集まっていましたから、ここを戦場とするなんて後鳥羽院にはありえないことです。敗北が確定した後の死が確実の戦いなんてものは無意味かつ迷惑でしかありません。
皇室存続のために戦後を見据えて動かねばならない立場の後鳥羽院と、生きることを諦めて美しく散る事を求める武士たちがすれ違うのは必然でした。
最後の抵抗
後鳥羽院に門前払いされた胤義らは東寺に立て籠もり、幕府軍を迎え撃つことにしました。
その数わずか30騎。
勇者たちの最後の戦いとなりました。
尾張・美濃の戦いでは最後まで幕府軍と戦い続けた山田重忠はこの日も幕府軍を相手に奮戦し、15騎を討ち取りましたが配下の武士にも多数の損害がでたことで嵯峨へと落ちていき、自害しました。

山田重忠
重忠同様、美濃でも奮戦した渡辺翔は「西面衆愛王左衛門翔とは我がことなり」とこの日も声高々と名乗りを上げて幕府軍を相手によく戦いましたが、最後は大江山へと敗走しました。その地で自害したと考えられています。
自身の最期に選んだ地は先祖である渡辺綱が酒呑童子を退治した伝説のある大江山となりました。
三浦胤義は、敵軍の中に兄の三浦義村を見つけると攻めかかりました。
そして兄に対し、「味方になってくれると思って手紙を差し上げたのに、叔父・和田義盛も裏切った兄上を頼りにしたのは間違いであった」と語りかけました。
兄・義村は「愚か者の相手をするのは無意味だ」と語り、退きました。
胤義は残された兄の軍勢を相手に戦った後、洛西の木島へと落ち、15日辰の刻(午前8時頃)、子の重連とともに自害しました。
京の人々は立派な武士であったと三浦胤義の死を惜しんだといいます。

三浦義村軍vs三浦胤義軍(『承久記絵巻』)
なお、後鳥羽院の信頼篤く、実質的な総大将の役を任された藤原秀康は潔く死ぬのではなく逃亡生活を選びました。しばらくの間、奈良に潜伏することになります。
幕府軍の入京
敗走する官軍を追撃する形で幕府軍は遂に入京を果たします。
これにより京の市中各所で火災が発生し、略奪が横行しました。

官軍を追撃する幕府軍(『承久記絵巻』)
15日辰の刻(午前8時頃)、後鳥羽院によって勅使が幕府軍に遣わされ、北条泰時、三浦義村と対面しました。
勅使により幕府方に、今回の大乱は後鳥羽院の叡慮によるものではなく謀叛を企む謀臣によるものであったことが述べられ、その上で北条義時追討の宣旨の撤回、帝都での略奪禁止、全て幕府の申請通りに聖断を下すことが伝えられました。
事実上の敗北宣言でした。
後鳥羽院は、京の治安維持を求めることが精一杯でした。
この日のことについて、幕府の史書『吾妻鑑』は下記のように記します。
武勇を好む西面・北面忽ち亡び、辺功を立つ近寵臣悉く虜えらる。悲しむべし、八十五代の澆季に当たり、皇家絶えんと欲す。
皇家絶えんと欲す。(皇室が絶えようとしている)
最期まで幕府を相手に戦った武士たちを突き放し、自身の責任を回避することで皇室の存続を願った後鳥羽院ですが、このときの皇室は幕府の意向次第で滅亡しかねない大変な危機でした。
勝てば官軍
6月15日巳の刻(午前10時頃)、北条泰時・時房らは六波羅に入りました。同所は平家が拠点として以来、京における武士の拠点でした。泰時・時房は共に新たに創設される六波羅探題としてこの地で「占領統治」を進めることになります。
6月17日、名越朝時率いる北陸道軍も入京しました。これにより5月22~25日に鎌倉を出陣した軍勢のほとんどが京に入りました。
6月19日、朝廷は戦場から逃亡した藤原秀康らの追討を命じる宣旨を畿内諸国に下しました。
「勝てば官軍」。
北条泰時追討令は撤回され、官軍の事実上の総大将であった藤原秀康の追討令が発せられました。官軍と幕府軍の立場はここに入れ替わり、幕府軍こそが官軍として朝廷の命令により藤原秀康らを賊として追討する立場になりました。
北条義時の勝利宣言
絶対の帝王・後鳥羽院を敵に回し、朝敵となった北条義時は不安であったに違いありません。
神話に連なる歴史を持つ皇家を敵とすることは当時の人間としては考えられないことであり、幕府の権力抗争を勝ち抜いた義時にとってもそれは例外ではなかったことでしょう。
6月23日、鎌倉に戦勝の報告が届けられ、義時は次のように語ったと伝えられます。
「今ハ義時思フ事ナシ。義時ハ果報ハ王ノ果報ニハ猶マサリマイラセタリケレ。義時ガ昔報行、今一足ラズシテ、下臈ノ報ト生レタリケル」
(=今は自分に思うことは何もない。義時の果報は帝王の果報に勝っていたのだ。前世での善行が1つ足りなかったがために、武士という低い身分に生まれたにすぎなかったのだ)
安堵ともに義時は幕府の勝利を喜び、自身が現世において受ける報い(成果、幸運)は後鳥羽院に勝っていたことを宣言しました。
北条義時による勝利宣言でした。
こうして後鳥羽院による北条義時追討の計画は失敗に終わり、幕府軍の完勝で戦いの幕が下ろされました。
次回予告

戦いに勝利した鎌倉幕府による戦後処理が始まった。
幕府に拘束される三上皇と退位を余儀なくされる天皇。
幕府は皇位継承に干渉し、後鳥羽院の皇統は否定される。
異例の不登極帝の登場が武家政権と皇室の新たな歴史の扉を開くのであった。
そして、後鳥羽院の命で前線に出陣した貴族たちには過酷な運命が待ち受けていた。
次回「鎌倉幕府の戦後処理」。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
