
<第3章>活動による言語育成の手引き(Handbuch Sprachförderung durch Bewegung)
「要約」
<音について>
・3歳までの子ども達は、音の単純化をよく行う。
・6歳頃の子ども達は、全ての音を理解できるようになる。
<語彙力について>
・単語の持つ意味を理解するには、実体験や興味関心が大きな役割を持つ
・1歳の時に子どもは言葉をしゃべる。
・2歳半ぐらいで、語彙力は約50~100単語。
・大人による「読み聞かせ」、「絵本を一緒に見る」、「コミュニケーションを取る」といった行動が、子ども達が言葉を習得する上での大きな刺激となる。
・子どもが間違えたこと(例えば、Ich bin gelauft)を言った際は、直接的に間違いを訂正する(gelauftではなく、gelaufenでしょ!)のではなく、フィードバックの中に正解を入れるようにする(「Ja, du bist ganz schön schnell gelaufen(そう、とても早く走ったんだね)」)。
<文作成能力について>
・最初:1つの単語をしゃべる
・2歳頃から:2つか3つの単語を組み合わせる
・2歳頃から3歳頃にかけて:簡単な完全文を作る
・3歳頃から4歳頃:主文と副文、受け身、因果関係文を作れる
・6歳頃:基本的に完全文を作れる
・ドイツ語の動詞の変化は3歳頃から習得していく
私たちは独特のリズムや、特別な会話メロディー、(状況に適した)特定の音量を用いて話し、会話の間を取り、単語を強調し、それらによって自分の発言に意味をもたらしている。トーンの高さとそれらの流暢さによって例えば人は、その発言がただの独り言なのか、それとも質問なのか、あるいは命令なのか、はたまたお願いなのかどうかを見分けることが出来る。

まだ取得していない音を省略したり、取り替えたり出来るように(例として、Bananeの代わりにnaneと言ったり、Kofferの代わりにtofferと言ったり)、3歳までの子ども達は言語においてよく単純化を行う。しかし、その後は音の生成がだんだんと上手くなっていく。幼稚園を卒業する年齢になれば、ほとんどの子ども達は全ての音の発音を習得し、意味の差別化において、発言を理解したり、自ら生成したりすることが機械的に出来るようになる。

幼稚園の年齢の子ども達は、韻を踏んだり、単語の綴りを分解したり、他の言葉遊びに大きな楽しみを感じる。綴りに合わせて拍手したり、足踏みしたり、叩いたり、綴りを数えたり、綴りを強調したりすることができるようになり、そのことは、子ども達が話されている言語の音構造の理解に役立つ。

「So-fi-a」名前のどの音を伸ばすか、ゆっくり発音するか?動きで名前を表してもいい。どの音を大文字にするか(母音を伸ばす)?自分の名前はどんな感じ?他人の名前はどんな感じで、自分の名前との違いを説明できる?この遊びによって、子ども達は音韻論的動きを色々な感覚を通じて練習できる。単語から音を聞き出すというのはより難しいが、そうすることが一般的には、学校における書き言葉の習得の練習にもなる。・・・。百科事典が記載されている語彙が示すところは、意味論は単語の意味を内包するという事である。語彙は、ある面では単語の理解(受け身的語彙)、もう一方では単語の積極的使用(能動的語彙)を含んでいる。・・・。言葉の理解と生成は同時には発達せず、言葉の理解はしばしば言葉の生成を前提としている。時々は、子ども達が大人達が使う言葉を小耳にはさんで、その言葉の意味を理解せずにそれを使うことがある。

単語にどんな意味を子ども達が結びつけるかは、子ども達がしてきた経験に因る。子ども達は既に知っていて、自分の主観を成していることを言う。なので、都市部の子どもが「木」という単語を田舎に住む子どもとは別の感じで示すことがある。田舎の子どもが「木」をリンゴの木やスモモの木、オークの木、梨の木といった特定なモノとして指すことが出来るであろうことに対して、都市部の子どもはもしかしたら、ただ単純にある木として示すことしか出来ないかもしれない。言葉の意味の構築は経験内容と子どもの興味関心にかかっている。幼稚園児は例えば、ポケモンに関して豊富な知識を持っているし、40種類の異なる型が分かる。 大人はポケモンという言葉だけで拒絶反応を示し、「そんなの聞いたことない。何も知らない。」と言う。
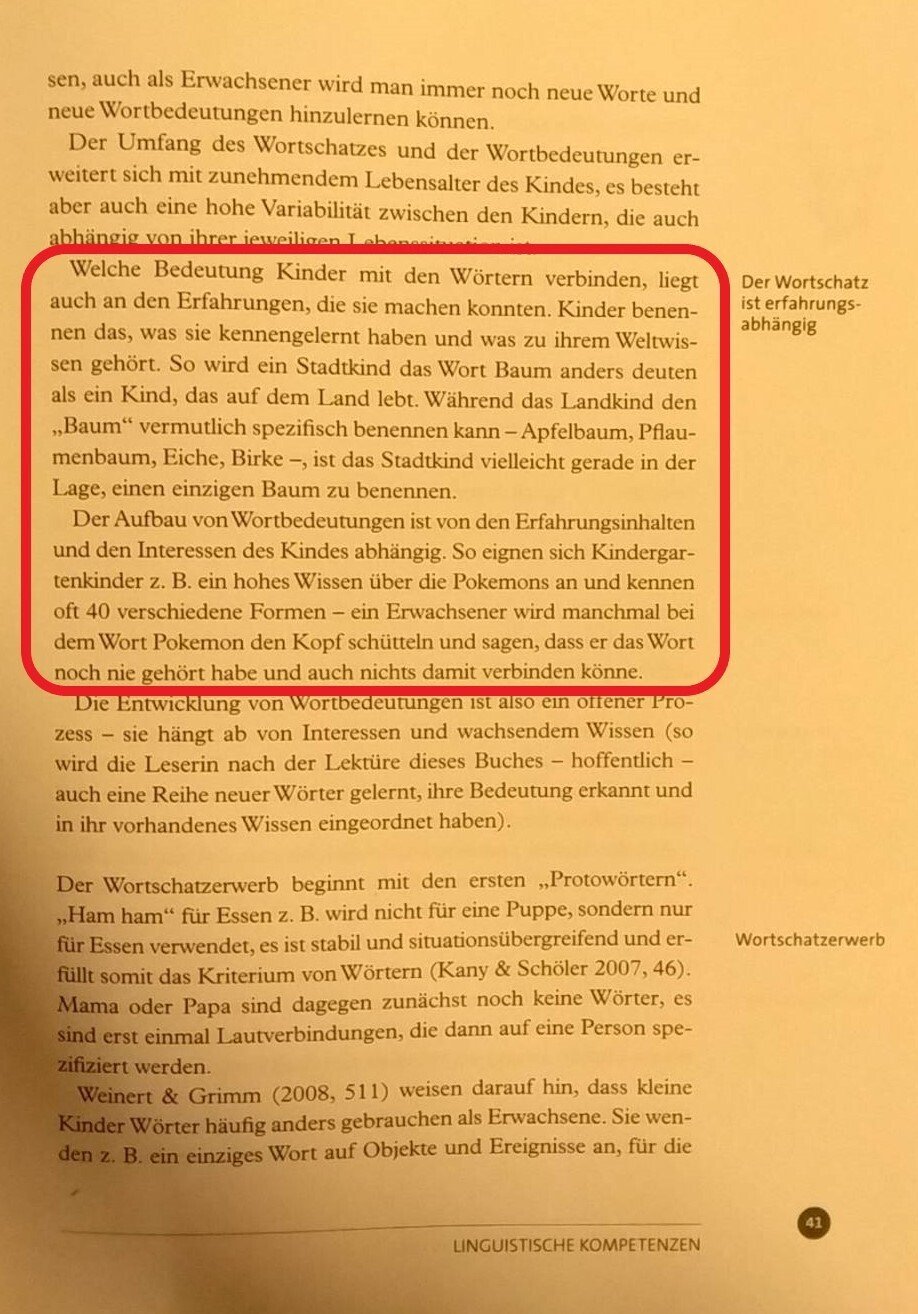
子ども達が、全ての物には名前があることを発見するや否や、子ども達の語彙力は日々増えていく。一般的には、子どもは1歳の時に初めて言葉を作り出し、そこからゆっくりと新たな言葉を足していく。2歳半になって語彙力が約50~100単語になった時に、ほとんどの子ども達の語彙力は大きな飛躍を遂げる。毎日新しい言葉を加えていく。ただその年齢は、発達障害の有無にかかわらずバラバラである。語彙力の向上の為に、ある面では学んだり、記憶したりするプロセスが大事ではあるが、・・・

・・・子ども達の周りにある社会的な環境による刺激も必要不可欠である。その刺激というのは、単語の理解にも、そして、言葉の生成においても大切なことである。刺激というのは例えば、読み聞かせしたり、絵本を一緒に見たりすることが含まれるが、子ども達と大人が密になって互いにコミュニケーションしあっている遊びの状況もそれに含まれる。

子ども達自身から、「Ich bin gelauft」や「viele Eimers」のようにどんどん間違ったことを言うのは、文法の成長過程において大切なことである(正しくは、「Ich bin gelaufen」「viele Eimer」)。大人はその間違いを訂正するというよりかは、訂正のフィードバックを与えるべきである(「Ja, du bist ganz schön schnell gelaufen(そう、とても早く走ったんだね)」のように)。

まず初めに子どもというのは、一つの単語を発するようになる。「道、ボール、あそこ、ママ…」。2歳頃から、2つか3つの文を組み合わせるようになる。例えば、名詞と動詞を不定詞の形(人形 食べる)や動詞の一部(ドア 閉じる)を用いて結び付ける。空間的な動きも表現する(車 入る)(猫 逃げる)(リサ 腕(腕の上に乗りたい))。・・・。2006年のLeuckfeldの研究によると、2歳から3歳にかけて、子ども達は簡単な完全文を作り、言葉の位置は概ね正しく、動詞も主語に合わせて変化させてるし(犬 吠える)、動詞を2番目に置くし(パパ 働く)、最後に置くこともできる。3歳から4歳にかけては主文と副文を使うことができ、能動態や受け身を理解し、因果関係を示す文を作れる(リサは悲しい、なぜなら・・・)。幼稚園を終了する年齢になるまでには、基本的に子ども達は、完全な文を作る基本的能力を有している。

単語の形の変化には、主語や単数形、複数形に応じて動詞の末尾が変化することも含まれる。子ども達は最初に、動詞の根幹を使う。子ども達は言う、「Ich laufen(正しくは、Ich laufe):私は走る」、「Mama kaufen(正しくは、Mama kauft):ママは買い物をする」と。ただ段々と、動詞は活用されていく、「Baby schreit:赤ちゃんが叫ぶ」のように。この能力は3歳頃から比較的問題なく習得される。それに反して、より困難なのは動詞の過去形である。これに関して子ども達は初めたくさんの間違いをする(gegessen(食べた)の代わりにgeesst、hingefallen(転んだ)の代わりにhinfallt)が、この間違いというのは、いくつかの過去形に気付いており、機械的に使ってみようと試みていることを示している。・・・。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
