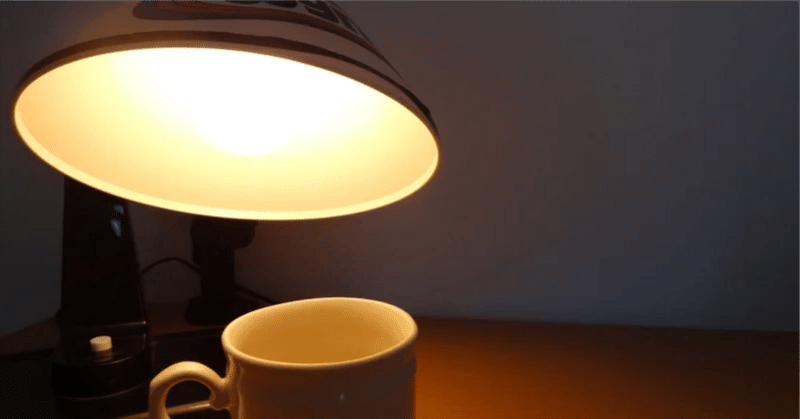
【部屋のあかり】都会的なもの・村上さん
自室の本棚には、そこまでたくさんの本は残っていない。高校のときに多読していた現代小説・エンタメ小説は、廊下の本棚に出してある。部屋に残っているのは、ほとんどが村上春樹さんの小説だ。
それこそ高校のころ、村上さんは僕にとって神様のような存在だった。『海辺のカフカ』を初めて読んだときには、「この本と出合うために、いままで多読をしてきたんだ」と衝撃を受けた。Book-offで『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』の上巻を中古で買ったときには、その日の午後じゅう読みとおし、次の日には新品の下巻を買いに行った。それ以外の作品は学校の図書館で借りて、中古で見かけたときには、きまって購入していた。だから、自室の本棚に置いてある村上シリーズは、じつはそれ自体は読んでいない本もあるかもしれない。
そのような訳もあり、上京するまで(いや、上京してもかなりの間は)、村上さんを世界で一番好いているのは自分だと思っていた。どの作品を読んでも「これは僕のために書かれた小説なのだ!」と感動していたから、仕方ないとは思う。
けれど、辺りをよく見まわせば、村上さんは人々にとても好かれていることが分かって来た。しかも、僕がいま書いたような理由を持っている人も多かった。あまつさえ、僕が授業を受けている大学の建物の隣に「村上春樹ライブラリー」が完成し、お洒落で知的な大人の女性が、併設されたカフェ「橙色猫」で談笑しているのを何度も見た。しばらくの間、僕は変な妬みのようなものを持っていたが、だんだんとそれにも慣れてきた。
これまでの東京と田舎の話(「【部屋のあかり】家郷」)に関連させると、どうも、村上さんの作品に出てくる人は、「家郷喪失者(ハイマートロス)」のような雰囲気を帯びている人が多い。彼らは一様に孤独であるけれど、その孤独というものは、第一の要因として「家郷」が失われていることが大きいように見える。そして、高校の後半から大学の前半にかけて、僕はこの形の孤独に身を浸そうとしていた。なにかこう、「それを体験することが、ぜひとも必要なのだ!」という気分で、大学の前半では、自らすすんで「家郷喪失者(ハイマートロス)」の孤独に耐えていた。
いま考えてみると、自室の本棚に並んだ村上シリーズは、僕が彼の小説を読むことで、「家郷喪失者(ハイマートロス)」の孤独に踏み入れるための前哨戦をしていたことの名残かもしれない。ならば、僕にとって村上さんは、文章作法やユーモアを見習う人である以上に、そういう孤独を「共にする」ことができる人間だったのだろう。孤独を「共にする」というのはヘンテコな言い方だけれど、僕がとても孤独で絶望していたころ、灯のようになっていたのは、村上シリーズの主人公たちの記憶だった。
今でも、村上さんは尊敬する人のひとりだ。神様ではなく、人間として。
【部屋のあかり】
・2024. 3. 8から3.11までの記録
・目次
1. 性格
2. 家郷
3. 都会的なもの・村上さん (3/13)
4. 街のあかりの数だけ、そこには人間がいるのに (3/14)
5. 部屋のあかり (3/15)
6. おわりに 港町の門 (3/16)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
