関西学院大学准教授 貴戸理恵さんインタビュー・4
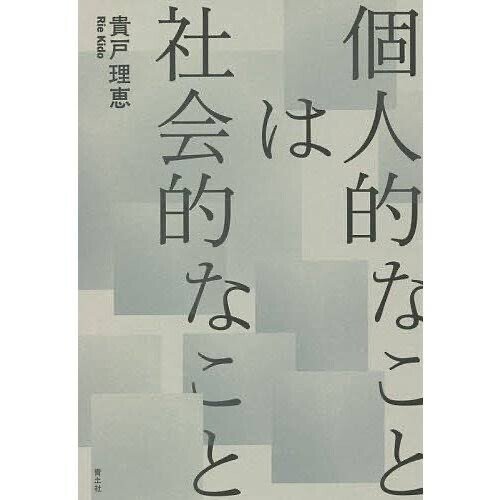
不登校の不思議さに立ち返りにくい時代
貴戸:不登校の不思議さは、「貧困や病気など合理的な理由がないにもかかわらず子どもが学校に行かない」というところにあります。子どもにとって学校というものが、生まれ落ちた家族のあとに初めて出会う「社会」だとすれば、学校に行かない子どもは「個人は理由なく社会とつながらなくなりうる」という現実を突き付けてくると思うんですよね。長期欠席・不就学の歴史は長いですが、そのほとんどが貧困や親の教育力の無さによるものです。それが戦後日本社会が近代化して豊かになるなかで目立たなくなり、「理由なく学校に行かない子ども」が1950年代末ごろから見いだされていきます。これは、都市部の中産階級で親の教育意識も高いのに、なぜか子どもが学校に行かない、という現象として、school phobia(学校恐怖症)やschool refusalといった欧米の精神医学の概念で理解されました。のちの「心の問題としての不登校」という理解の出発点となるものです。ところが、2020年代の現在では、これは貧困の問題を考慮していない中産階級モデルだと批判されています。「貧困による不登校」「貧困世帯のひきこもり」という問題が再発見されています。この視点は重要ですが、他方で、福祉的な救済モデルのみになってしまうと、学業達成や登校というゴールは疑われにくくなり、「個人が社会とつながるとはどういうことか」という、根源的な問題が問えなくなってしまう、とも感じます。
杉本:なるほど……。新刊を読ませていただいて、それは改めて思う点です。
貴戸:他方で、「不登校はオルタナティブな進路」としてキャリアの多様性へと回収する文脈もあります。中等教育は多様化しているので、義務教育段階で不登校でも高校で通信制やサポート校に行けばいいのではないか、「不登校特例校」もあるではないか、オルタナティブ教育を選んでもいいし・・・という語られ方が増幅しています。けれどもそこでは不登校は、個々の人生経歴の問題に切り詰められてしまいます。個人にフォーカスするとキャリアの多様性という話になり、社会にフォーカスすると貧困とか福祉とかという問題が立ち現れてくる。いまはそのどちらかにすごく引きずられている感じがありますね。
でも私は、80年代から自分の人生を通じて不登校の問題を見てきて、「不登校から社会を問う」ということの一番の重要性は、そのどちらでもなかったはずだと思っているんです。貧困が解決されてもスムーズに社会に繋がれない・つながらない存在はいる。そして、「不登校でもその後のよいキャリアを構築できる」という話でもない。そうではなくて、「漏れ落ちた者の視点から、この社会を問い直し、あらたな場を生み出していく」ということが重要。その視点を、不登校・ひきこもり研究の領域から失いたくないと強く思っていますね。
杉本:おっしゃる通りだろうというふうに私も認識してます。ぼくのように高度経済成長、安定成長時代を生き、バブル期に20代後半を過ごした人間から言えばいまはもう全く別の社会になっているでしょう。端的にいえばいま現にあるのは「格差社会」ですよね。その結果まさに生活困窮として教育の機会が奪われている。あるいは行く意味が見出せず、展望が感じられない。一方では経済的にも文化的にもある種の資本を持っている子どもが学校と折り合いがうまく行かなければ通信制高校とか、そちらの方で普通の通い方をするよりも自分の能力を活かせるかもしれない。もちろんそれだけではないと思いますけれども、今は通信制高校はかなりの高いレベルのところまで勉強ができる時代になりましたよね。そうすると80年代であれば学校に行けないのは何か病理性があるはずという医師の見立てに対して、親御さんが「いや、学校にも問題がある」と。裏返した形、というと怒られるかもしれませんが。そういう運動があったわけですよね。反対側から学校の管理教育を問うという形があったと思うんです。貴戸さんの親御さんも運動をされていて、自身はもっと自分の個人的な違和感、自分と社会のつながりのところに違和感のようなものを持っていらっしゃった。だから貴戸さんの問題意識の持ち方みたいなものこそ本当は重要なのだけど、今の日本社会の二極分裂状況みたいなもので、ちょっとそこが埋没させられつつある印象がある。
もはや不登校から「社会と個人の関係の複雑さ」は見れない
貴戸;そうですね。一方で、不登校から貧困でも選択肢の多様化でもない「社会と個人の関係の不思議さ」みたいなものを見ていくことが可能だったのは、ある時代的な文脈においてだっただろうという思いもあります。
杉本:それは何か勿体無いというか(笑)。その中から哲学とか、いろんなものの進歩、というのも単純すぎるのかもしれませんが。その蓄積の意味となる現象ではなかったかという風にも思えるし、現に貴戸さんの立ててきた議論というものは、ある程度ものを考える人への社会的オピニオンとして発信され、今も引き継がれていると思うんですよね。ただそれが、例えば貴戸さんの指摘してきた単一の教育機関フレームで学んだりすることに対する違和感みたいなこと、あるいは大学を出たら新卒一括採用の世界に入っていくことの不思議さ。そういうことが「何か変ではないか?」という違和感に対して、「それがそんなに不思議なこと?」という風になっていくとやはり不気味だなと思わざるを得ないんですよ。それはやはり社会の管理化、全体化のように思えて。そういう意味では私も一種の進歩主義で、世の中の次第に対して、疑問を持ちつついろんな人がそういう疑問はどういう意味があるんだろうか?ということを語り合える。それがやはり民主主義社会や自由主義社会のありようだと思うので。ただそれもミクロ的な疑問の立て方ではあるだろうなという意味では大文字の政治的・社会的な議論にはなりにくいだろうなというのもありつつ、そういう貴戸さん的な疑問の立て方は捨てられないですね。自分自身がそうだったという経験を踏まえて。
貴戸:結局、「不登校から社会を問う」ことを可能にしていたのは、戦後日本が作り上げた「学校と企業が成功しすぎた社会」(貴戸2019「教育」小熊英二編著『平成史 完全版』)だったという面があります。子ども若者への公的支出が少なくて、家庭と学校と企業がそれぞれ人的資源形成を担っていくシステムですね。でももう制度疲労を起こしている。新卒一括採用は若者の自由なキャリア探索を阻害しているし、現在の正社員的な雇用保障を得る代わりに来週にも転勤させられるかもしれないなかで長時間労働をするとか、その正社員の雇用を守るためたくさんの非正規社員が一人では自活できないような状態に捨て置かれているとか、個人の人権の面でも不当だし、構造的に見ても、産業が硬直化して国際社会で経済的なプレゼンスを失っているし、良いことはないのにやめられなくてもう何十年もきている。そういう日本型の生活保障と人的資源の構築システムが不登校を大きな社会問題として扱うことに帰結していた。それがひるがえって、「不登校から社会を問う」という固有の視点を裏から支えていたと思います。だから、そういう日本的なシステムが崩壊して別のものに置き換わっていけば、不登校という「窓」から見える固有のものはなくなっていくでしょう。でもそれはなくなった方がいいんですよ(微笑)。なくならざるを得ないんです。
杉本:不登校という窓から、不登校という枠組みから問うことはもうなくなった方がいいと?
不登校原因論の二項対立時代の終わり
貴戸:なくなっていくのは仕方のないことですね。精神科医の*滝川一廣さんは1998年に不登校の「一般化のいっそうの進行によってあまり社会問題視されなくなるか、ほかにもっと深刻な学校問題を抱えて長欠ぐらいはさして問題でなくなるか、その両方かで解消に向かおうか」と書いています。実際に、2021年度の不登校は小中で約24万人、中学では20人に一人が不登校、となっており、不登校は「それ自体が問題」というより、学習の遅れを何とかして、自分なりに進学できればいいというかたちで脱問題化されている面もあります。不登校で問題はないということを、親の会やフリースクールを生み出した不登校運動はずっと言ってきましたが、一方では大して問題化されない社会が、良くも悪くもいま実際に実現してしまっています。それを考え合わせると、「不登校から個人と社会の関係を問う」ことを可能にする文脈は、もう存在しないように思います。
杉本:むしろ先ほど言われたように貧困がメインで学習権が奪われているということ。その逆には、近代を達成するための一斉授業みたいな枠組み。これは国民国家を作るために必要なものとして無償教育のためカンヅメ教育みたいなことをやってきたことに対して、とうとう子供たちが耐えられなくなった。その前に校内暴力というものが子供たちが多い時代にありましたけど。その後は個別バラバラに櫛の歯が欠けるように公教育から離脱していくというか、事ここに至って因果を辿れば「そうだよね」という状況になってしまったという風に捉えた方が真っ当で生産的だという捉え方でしょうかね。何かすごい乱暴な言い方になってますが。
いま一度、社会権を保障する役割としての公教育は重要に
貴戸:むしろ子どもの権利として教育を見ていくことがますます重要になってきていると思います。
杉本:逆に今はそこなんですね。
貴戸:公教育の保障の重要性を改めて強調する必要があると思いますね。本当に学校が最後のセーフティネットみたいな子供たちがいて、ネグレクトと区別がつけ難い不登校もあるわけです。そこに対応していく。それと並行して、外国人学校、夜間中学、高等専修学校など、今まで学校教育の周辺にあって、必ずしもきちんと制度的な保障がされてこなかったような学校を、学校教育の中にきっちりと包摂していくという方向が必要だと思います。その領域の研究者はどんどん出てきていると思うし、すごく頼もしく思っています。その反面、自分自身を振り返ると、一足飛びにそちらに行けないという感じがあるんですよね。私はやっぱり、「経済の問題が解決されても学校に行かない人は行かなかった。そこに何があったんだろう?」ということを多分ずっと見続けていくと思います。
杉本:個別的な、というか。ある種実存的な問題と向き合ってしまうというか。
貴戸:そうですね。
杉本:そういう人はいつの時代も必ず出てくると思いますね。
貴戸:ええ。
滝川一廣- 1947年名古屋市生まれ。1975年名古屋市立大学医学部卒業後、同精神医学教室に入局。岐阜精神病院(現・岐阜病院)に赴任。1981年名古屋市立大学医学部精神科助手。1984年より名古屋市児童福祉センターに勤務。同センターの児童相談所部門の医師および情緒障害児短期治療施設部門の長を務める。1995年東京に移り、青木病院に勤務。1999年より愛知教育大学障害児教室および同治療センターの助教授。前学習院大学教授。あなはクリニック+オリブ山病院医師。(2018年8月現在ー日本評論社、ホームページより)
よろしければサポートお願いします。サポート費はクリエイターの活動費として活用させていただきます!
