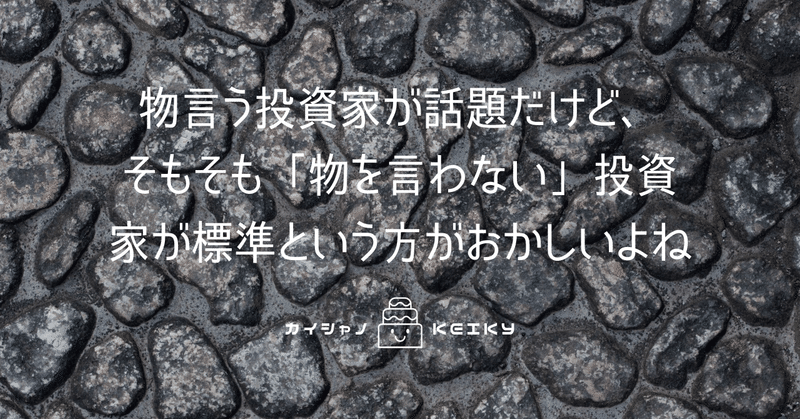
物言う株主が話題だけど、「物を言わない」方が標準な時点でちょっと違和感がある日本の上場システム
昨年は日本でもモノ言う投資家、いわゆるアクティビストが活発になった一年だった気がする。
ライブドア事件があった2004年ごろも一時的に活発だったが、リーマンショック以降あまり話題にはならなかったが、特に2019年は良く話題に上がっていたと感じる。
上場会社で働いていたり、株式投資をしていない人からしたら何のことかサッパリかもしれないが上場会社で働いていたり株式投資をしていたら昨年はそういったニュースが多かったと感じるかもしれない。
それもそのはずで2019年は重要提案を目的とする株式の新規・ 追加取得が過去最高の水準だったといわれているという事実がある。
■ なんで物言う投資家が活発に活動するようになってきたか
なぜ活発になってきたかというといくつか理由があって、海外のアクティビスとと言われる投資機関は日本の会社の株価の割安さ(実際によりも価値が低いような株価で推移している)ということがまず注目される理由の一つ目として挙げられる。
もう一つは企業側の変化がアクティビストの動きが活発になってきた理由となっている。
どういうことかというと今まではそいうったアクティビストはハゲタカと言われて企業側と敵対的な関係でしかなかったが、企業側がガバナンス改革ということを真剣に考え始めているということからアクティビストの話を聞く雰囲気が依然よりあるというのが理由だ。
割安というのはどういうことかというと、株価×株数が会社の価値(時価総額)とされているが、それがその会社がもっている資産(色々な土地や設備)よりも低いというということで説明できる。
たとえば土地の価値が1億なのに時価総額が8千万円だと会社を辞めて清算した方が高い価値となってしまう。ちょっと異常に思えるかもしれないが、多くの超一流の有名日本企業も資産価値(一般的には清算価値という)の方が高く出てしまっているので割安ということになる(細かくは説明しないがPBRという指標が使われていて1というのは資産価値と同じという意味を指す。日本は1倍台だがアメリカは3倍台なので日本企業は低く見られている)。
■物言う投資家は何を求めているか
物言う投資家というのは平たく言うと会社の株を安く買って、高く売ることで利益を設けることを目的とした投資家とざっくりいうことができる。
株価を上げるために色々な提案を行ったり、役員を派遣して改革を断行させるなど、とにかく会社の企業価値を上げるために実際に発言権を持てる一定の数の株を買って会社に対して変革を要求するような投資家のことをいう。
こういった投資家もかなりポリシーがあって資本主義をそのまま実行しようとしており、株主のために経営者が経営するように迫っているので、こういった投資家に狙われる企業というのは経営者がだらしがないということも言える場合が多い。
とはいえ、アクティビストも色々な種類がいて、とにかく株価さえ上がれば良くて事業のことは考えていない投資機関もあれば会社にじっくり関与して会社に伴走しながら会社を良くするサポート的な立場で進めるようなアクティビストもいるのでさまざまな会社があるといえる。
近年はこういったアクティビストの動くを歓迎する一般投資家や金融機関もいる。事実株価が上がったり、会社の新陳代謝が進むことで自分たちが持っている株価もあがるのであれば応援するような動きが出てきても不思議ではない。
■ なぜこういった物言う投資家にものを言われるか。
物言う投資家という言葉が語っているように、会社の上場機能というのはあまり機能していなくて、むしろ形骸化しているといえるのかもしれない。
どういうことかというと本来、取締役を株主が任命するので、社長は外部が決めるという外圧があるはず。しかしながら実際に株主側はそういったプレッシャーを株主はかけられていない。
多分これは株主は株の売買による経済的な利益、つまりは株価や上がり下がりだけにしか興味はなくて、会社の事業の中身に対する議決権の行使に関心がない面が強いと言える。そうすると株主総会が完全に形骸化してしまうからだ。
自分が買った株があがるか下がるかにしか興味がなくてその会社がどうなろうと利益だけあげていれば良いという考えを株主や株式市場がしていると会社の中のことにはまったく興味がない状態が生まれてしまう。そうすると経営者がやりたい放題になってしまい、結果的に企業の価値が毀損していく場合もある。
そうではなくて、本来の株主の機能をアクティビストというのは発揮をしようとしてちゃんと経営に対して「ものをいう」からアクティビストと言われていて、「株主=ものを言わない株価にしか興味がない人たち」というのがスタンダードになっているというのは本来の株式市場が果たす役割を担えていないのは企業の価値が上がらないということにもリンクしているといえる。
社員からすると外部から入られて変革させられるのは良し悪しがある。ぬくぬくと良い環境にいたならいきなりシビアな変革をさせられて居心地が悪くなるかもしれない。一方で経営人に嫌気がさしていて変化させたかったらまさに渡りに船かもしれないし、一概にどっちがいいとはいえない。
■ アクティビストのタイプと活動例
最近の日本でのアクティビストとしてエリオット社によるアルプスアルパインの統合、バリューアクト社によるオリンパスへの取締役派遣、サードポイント社によるSONYに半導体事業の分離要求、オアシス社によるジャパンディスプレイ、エフィッシモ社による川崎汽船への取締役派遣などが記憶に新しい。
こういったアクティビストの動きというのは大きく二つのタイプ分かれる。ニュースを見るときにどちらのタイプのアクティビストなのか考えながらニュースを見ると勉強になったりする。
1.強行型アクティビズム
⇒株を多く持って経営者に提案を突き付けるタイプ。会社の大きさとしては中小型の会社が多い。主な提案内容は株主還元などアクティビストの利益を全面に出した提案が多く、 ファイナンスやガバナンス改革がメインである場合が多い。逆にいえば事業内容の改革よりも財務体質の改善などが多い。
たとえば村上ファンドの黒田電気やアコーディアゴルフへの提案や、エフィッシモによる川崎汽船、ダイワボウ情報などがこのタイプにざっくりとあてはまるといわれている。
2.扇動型アクティビズム
⇒もう一つが機関投資家からも賛同を得ながら改革を扇動していくスタイル。
一般株主や投資家や世論を味方につけて会社に経営の変化を促すようなやり方。狙う会社の大きさとしては大型株が多くて、株数自体も少数株を保有して元手は少なくしてア プローチする特徴がある。サードポイント社によるSONY、オアシス社によるパナホーム・パナソニック、エリオット社による日立国際電気、日立製作所への提案などが例として挙げられる。
こういったアクティビストに狙われやすい会社というのは条件がいくつかあるのでまた何か機会があれば具体的にご紹介したいが、時価総額が200億円以上あって、先ほどのPBRが1.3以下、 株主構成で外国人が20%以上いて、一般企業などがもっている株数が25% 以下といった会社が狙われやすいとされている。
本来会社の経営者というのは株主や債権者のために会社の企業価値を上げていかなければならない使命をもっているが、既に説明した通り日本の株式市場自体が形骸化していて会社に変わる様に外圧を与えらえるような存在になりえていない。
業績が悪かったり怠慢な経営をする経営者を嘆く一方で、そういった経営者に永遠と会社を運営させる株式市場についても嘆くべきシステムの欠陥があると言わざるを得ない。上場している以上は経営者も株主も事業活動を通じて社会・社員・顧客に価値を提供出来る様な会社を目指すことを第一に考えてもらいたいものだ。
利益は大事だが利益がすべてではない。会社は社会のインフラとして重要な箱としての役割があることを意識した経営者にぼくはなりたいと常々思っている。アクティビストに狙われる前に、自ら変われる会社。そんな会社を目指せたらうれしいが今の会社では難しそうだ。
こういうことを考えていると大企業で働くというのはモヤモヤを感じるものだ。同じ志を持てそうなメンバーとベンチャーを作ったり、もう少し規模の小さな会社で全面的に組織をリードするような仕事をしたくなってしまう。
そういう出会いがあればチャレンジもまた一つの人生だなあ。
keiky.
いただいたサポートは、今後のnoteの記事作成に活かさせていただきます。ますます良い記事を書いて、いただいた暖かいお気持ちにお返ししていきたいと思います☆
