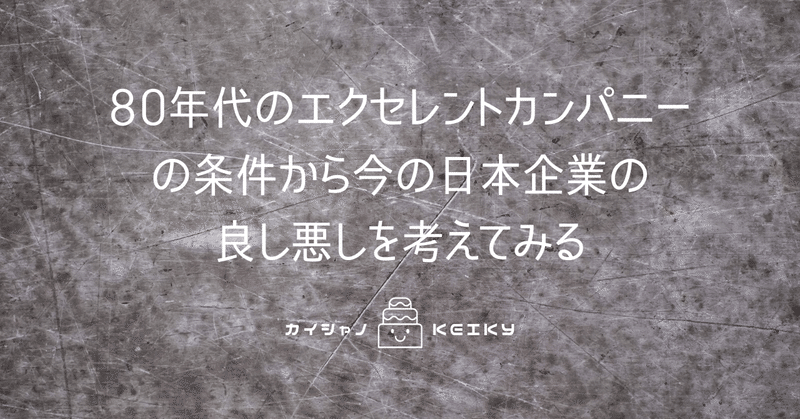
80年代のエクセレントカンパニーの条件から今の日本企業の良し悪しを考えてみる
先日ちょっと夜に時間ができたので「エクセレントカンパニー(トム・ピーターズ、ロバートウォーターマン著)」を読み返していた(1980年代の本。2003年に復刻)。とても古い本だが久しぶりに読み返していたら、翻訳したのはあの大前研一さんではないか。読んだ当時は気づかなかった。
この本は「いったいどういう企業が超優良企業といえるのか?」ということを分析した本で当時アメリカで大ベストセラーになった本だ。最近ではビジョナリーカンパニーシリーズの方が有名かもしれないが、なかなか今よんでも面白いものがある。
実は多くの日本企業がもっていた特徴で最近それらが失われているような気がしたので少し内容を抜粋してシェアしようと思って書くことにした。
■エクセレントカンパニーの要点
この本が生まれた背景には日本の存在がある。当時アメリカは不況で特に自動車などで日本に負けていた時期でジャパンバッシングがおこっていたのもこの時期である。
今では中国がアメリカとドンパチやっているが、当時は日本がアメリカの脅威とされていた。そんな中でもアメリカのどんな企業が優良なのか、その秘訣は何なのかについて共通点を分析した本だ。
例えばヒューレット・パッカード、プロクター&ギャンブル、ジョンソン&ジョンソン、キャタピラー、スリーエム、マリオット、マクドナルド、ダウ・ケミカルなど、当時の60以上の卓越した企業への綿密な面談調査をおこなった結果が書かれている。
特に本を解説することが目的ではないので、この本としては8つの特性があるという結論を出している。
(1)行動を重視する企業であること
(2)顧客に密着している企業であること
(3)自主性と企業家精神をもっていること
(4)人を通じての生産性向上を目指していること
(5)価値観に基づく実践をしていること
(6)基軸から離れないこと
(7)単純な組織・小さな本社をもっていること
(8)厳しさと緩やかさの両面を同時に持つ
例えば、(1)の行動の重視であればトライアルアンドエラーを繰り返すP&G、日本ではサントリーなどが具体例。(2)の顧客に密着して学ぶという例としてはIBMなどが例となっている。どれでも今でも古びた特性とは言えず、(3)の自主性と社員の自主性を重んじることは大切な要素だし、(6)の基軸から離れないという意味ではコア事業を大切にすることなども不変のポイントといえる。
■この本が教えてくれているのは分析と改善の大切さ
これらのポイントについてアメリカで80年代に語られていたこと自体がぼくはとてもすごいことだと思っている。
日本企業という強敵が出てきて、高い品質をローコストで生産しているプレイヤーはアメリカの脅威だった。そんな敵を分析し、自国の強いプレイヤーの特徴を分析してアメリカ企業の底上げの可能性について示唆している。
今でも株式市場は企業に対して合理的になるように強い要求をしているし、あまり当時と状況は変わらないと思うが、この本は行き過ぎた合理主義はよくないということをこれらの8つの特質で示しているといえる。
また、会社の利益だけではなく、個人の尊重も重要であると説いているのだ。あの合理主義の塊のようなイメージがあるアメリカでだ。
今でこそESGやSDGsなど様々な指標が出てきているし、様々なベンチャーが登場したり、利益至上主義ってどうなのか?という点が大きな研究テーマとなっている。
そういったトレンドについて80年代に既に分析をしている内容を見ると、いまでも僕らが参考にすべき点が多いと読み返していて感じた。
■実はこれらの特性はかつての日本企業がもっていた特性
この本に書かれている特性を読み返していると今の日本企業に足りないポイントで、昔はきっと日本企業がもっていたのではないかと思うようなポイントが多く含まれているように読み返してみて感じた。
(1)行動を重視する企業であること
→昔はアメリカやドイツに追いつけ追い越せで勢いがあったはず。今ではトライアルアンドエラーを繰り返す韓国や中国に押されてしまって日本は完全に取り残されて筒ある。
「失敗=ミス=悪」という考えが根強すぎてトライすることを忘れていたり、慎重になりすぎていたり、世の中に製品を出すまでの時間が長くかかってしまっているのではないか。
(2)顧客に密着している企業であること
→顧客に密着することはできているかもしれないが、今問題になっている日本郵政のかんぽの売り方を考えると詐欺に近いし、「お客様第一主義」に本当になれているのか考え直すような事例も多い。
自動車や自動車部品の不正もそうだし、多くの品質保証の不正なども見つかっている。安心・安全の神話が崩れつつあるのではないか。本当にお客様のために行動できているのだろうか。
(3)自主性と企業家精神をもっていること
→日本企業の特性として自主性をもって起業家製品をもっている人は今でもいるにはいる。様々なITベンチャーの社長やソフトバンクの孫さん、楽天三木谷さん他、様々人が生まれてはいる。
渋沢栄一にはじまり稲盛和夫さんクラスまでの一連の成長期を支えてきた時代と比較したら、ぼくらの世代は熱量では負けていないだろうか。生活は先人たちのおかげでとても豊かになり不自由ない暮らしを得られているので枯渇した欲望のようなものはぼくらは全体で言えばないかもしれない。
(4)人を通じての生産性向上を目指していること
→人を通じて生産性を上げる努力よりも人はどちらかというとお荷物扱いをしている節が風潮としては強い。
団塊の世代が団子状態で上層部にいる以上風通しが悪い会社も多いし、人をリストラすることで生産性向上をするような家電業界の動きや銀行業界の動きも強い。
人と企業の関係はドライになりつつあり、それを良しとするか悪しとするかはここでは取り上げないが、今でもぼくらは人を通じた生産性向上というものを愚直にできているだろうか。人をコストと捉えるむきが強くなっていないだろうか。
(5)価値観に基づく実践をしていること
→これは比較的に今も昔からの経営理念を尊重している企業が多いし、新たなベンチャーなど社会貢献を軸に起業されたりしているので、ぼくらも今も大切にしている部分と言える。
(6)基軸から離れないこと
→例えば既存事業が悪化したり、軸がない経営になっている会社も多い。新たな会社をどんどん買収してこの会社のコアはいったい何なのか?というような場合もあるし、新事業を全く既存事業と関係ないところで作ろうとして基軸から離れようとする動きも強い気がする。
基軸をちょっとずらして領域を拡大するという発想はあるにせよ、まったく門外漢の分野に出て行って成功できるほど甘くはないが、成長を考えるそういったことにもトライしない限り成長が実現できなかったりするプレッシャーを受けていろいろ手を出しているケースも多い。
(7)単純な組織・小さな本社をもっていること
→大企業になりすぎて管理思考が強まったり、組織が肥大化していないか。これは常に点検をしなければならない。ポストのための組織を作っていないか。
社内の子会社なのに会長や副社長、役員までいろいろ作ってポストがたくさんある状態になっていないか。降格されることができないのでドンドン高コスト体質になっていないだろうか。
自分で意思決定をしたり責任をとるのが煩わしく新たなポジションをつくったりして指示だけするような体制を作っていないか常に点検したいものだ。
(8)厳しさと緩やかさの両面を同時に持つ
→厳しさばかりが強まって緩やかさ、温かさを失っていないか。自分が身を切らずに立場の弱いものばかりにしわ寄せさせたり、課題の先送りをして「今もてばよい」というようになっていないか。本来日本企業が得意な中長期視点での企業経営を忘れていないか。
■最後に
こうして考えてみると、昔の追い付け追い越せ型でひたすら努力を積み重ねていた日本にはあったような特性が多くこのエクセレントカンパニーという本はよく企業を分析できていると思う。
だからといって日本企業の方がいいというわけではなくて、日本企業は世界の時価総額トップ群にはほとんど入っていないし、収益力だってアメリカの企業の足元には及ばない。部品や材料は一流だけど勝てている最終製品もない。
企業の内輪の理論ばかり強まってしまって粉飾決算や品質改ざんなども横行する。日本のリーディング企業は昔から変わっていない大企業だし、相変わらず年功序列と先送り思考が蔓延している傾向が日本企業は強い。
エクセレントカンパニーご発行された頃と今は時代背景が全く異なるし、当時は生活も豊かではなかったので、やればやっただけ良い生活が手に入ったし、がむしゃらに働くことが当たり前だったので、今とはずいぶんと環境が違っていただろう。
さらに今ではモノづくりからサービス、ITに収益の源泉がシフトしていることからかつて日本が成長してきたようなやりかたをしても成長が望めるわけではない。
こういった時代背景やテクノロジーの進化の程度こそ違うものの、当時示唆された8つの特性というのは、自社を点検する上では今での有用だと感じた。
日本がいい、欧米がいいというような比較の話ではなく自社の良さを活かしながら、成長している相手の良さをどんどん取り込む貪欲さ。冷静な戦況の見極めと分析力、反省と改善する柔軟さ。「うちが一番」と誇らしく語る前に学び続ける姿勢がいまの日本企業にはもっと必要なのではないかと久しぶりに読み返しながら思った。
時々振り返ってみてぼくの会社はどうか、点検してみようと久しぶりに昔読んだ本を引っ張り出して思ったのだった。
keiky.
いただいたサポートは、今後のnoteの記事作成に活かさせていただきます。ますます良い記事を書いて、いただいた暖かいお気持ちにお返ししていきたいと思います☆
