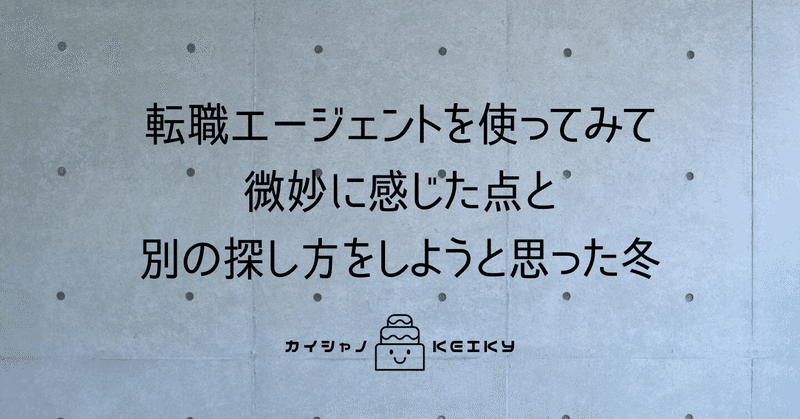
転職エージェントを使ってみて微妙に感じた点と自分は別の探し方をしようと思った冬
慎重なぼくが転職活動をはじめて具体的に昨年やってみたわけだが、僕にとってかなり大ごとだった。会社への裏切りのような気分と、30後半にして今まで経験したことがない道の領域に踏み込むこわさがあったのでなかなか行動できなかった。
部署はそれなりに恵まれている。数名しかいない経営企画で経営には非常に近いし、どの部署の上層部とも関係を深くもてている。事業のラインで10年ほどきつい思いをしてきたこともあって、法務・人事・財務などのスタッフ部門上がりで事業部門から”現場をわかっていない”と言われるようなこともない。
それでも自分の魂を込めた提案や経営や会社が求めている改革案、地道なM&A作業をやっていても、実はそこまで経営に真剣味がなかったり、それでも会社は変わらずむしろ悪い方へ向かったり、良い会社にしていこうという士気が経営層含めて上がらないことなどがっかりすることが多かった。
色々と「もうこれではだめだ」「やり切った感がある」「これ以上経験を踏めない」「もっと仕事がしたいのにやるほど浮いてしまう」といことを感じたので転職活動に踏み切ったのだった。
—— 〻 ——
そんなぼくは昨年、悩みに悩んで2社実際にエージェント経由で受けてみた。結果1社は面接でいろいろ話したときに今より悪くなる気がしたので辞退し、1社は良い会社だったけどスペックが足らず落ちたという結果に終わりまだ転職はしていない。それでも良い経験ができたし、後悔はしておらず縁がなかっただけと思えている。
とりあえず今の会社が1年以内に大きく変わりそうな気配もあるので心ある人達と付き合いながら期待をして働きつつ、一方で長い目で見て転職先を自分で検索するなど主体的にエージェントを使わずに探していこうと思っている。
結局3社ほどエージェントに会った。
■エージェントに会ってみるまで
エージェントに会うまでに徹底して自分を振り返ったり内省したり、企業分析を徹底して掘り下げてしまうためとにかく研究しまくった。転職本は何十冊読み、棚卸をしっかりとやり、いろいろな転職経験者にヒアリングをした。そして職務経歴書を作成し履歴書も作りようやくエージェントと会う決断をした。
気軽にこういったことができる能力はぼくにはなく、一つひとつ深く考えながら進める傾向があるので、エージェントに会うのも背信行為だと感じドキドキだったが会社を色々と紹介してもらった時点で視野が広がったというか気持ちが楽になった気がした。
■ エージェントを使わないことにした理由
エージェントに会うこと自体、はじめての活動だったのでどういったフローで先行が進むか、今の転職市場はどうか、自分のキャリアからしてどういった役割が求められるのかなどそういった情報を教えてくれた上でいくつか求人を出してくれた。
時期的には1年の中でもっとも求人が出る時期ではなかったということもあり、厳選された会社をいくつか紹介してもらった。良い会社と思える会社も数多くあったので一度持ち帰り、企業分析をしてから受ける受けないということを決めることにしたのを覚えている。
仕事柄企業分析が趣味のようなところがあるので1社ずつ深堀りして調査した。こういったことをしていると、今の自分の会社を棚上げして悪い部分ばかり見えてしまう傾向があるので、何を求めて転職するかを忘れがちになるので注意が必要だと感じる。
—— 〻 ——
それでも自分の人生が掛かっているわけで、今の会社で得ているメリットを失ってもなお、転職をした方が良いという状態にならないといけないので慎重になって当然かもしれない。結果なかなか自分の気持ちも踏ん切りがつかず厳選した2社を受けたという結果だった。
本来はもっとポンポン受けてとりあえず会ってみるという方が良いというのはエージェントからも言われていたし、すでに退職した先輩方もそういったことをいっていたがぼくにはなんとなくそれができなかった。
そんな中、エージェントも商売なので、対話ややりとりをしていてちょっと微妙に感じたことがあったのでいくつか箇条書きで書いてみたい。少なくともぼくにはこの仕組みは合わなかった。ちなみに使ってみたのは大手トップ3社。
■ 求人を出している企業側を守る発言が多い
彼らもビジネスなので、求人をそのエージェントに出してくれている企業はクライアントになる。
求めている人材と合わない人材を紹介したらマズイという思いが強く出すぎて求職者のためを思っていろいろと注意事項などを教えてくれるが、どうも発言の仕方から企業寄りの発言が多い人がいると感じた。
求人を出している会社、求職者の両方がクライアントであるはずだが企業寄りすぎる発言が見て取れるとあまり気持ちのいいものではないと感じた(ビジネスなので仕方がないことであるが)
■ 求職者がなかなか決めないとイライラしはじめる
色々なタイプの求職者がいてもいいと思うが、やはり回転率、いかに多くの人に多くの会社を受けてもらって確率を上げていくかということが主眼にあること、ノルマがおそらく厳しいことから求職者がじっくり考えるというと急にやる気なくすタイプの人がいるのも事実。
ポンポン受けてくれる人にどんどん求人を受けてもらう方がビジネスになるので当然そういう人を相手にするほうが良いということになるので理解できる。なのでサービスとしては優秀なのはわかるがぼくにはあまり合わないサービスだった。
■サービスが切れるといってせかしてくる
これもビジネス的にいえば理解できる。いつまでも転職を決めない人に対してサービスをしている方が効率が悪い。
彼らは成約させて入ってくるフィーは数百万とかなのでとにかく物量で勝負しないといけない。なので2,3か月たつとこのサービスがなくなるから早く決めてほしいというようなプレッシャーを与えてくるし、あと1週間で紹介する案件数が減るというような案内を受ける。
ここであせってもしょうがないので僕はそのままそれを受け入れて自然とエージェントサービスを受けない状態になった。
■ 今ある案件を売りやすさでさばく
これも当然と言えば当然。すでにある求人しか彼らは紹介できないので、たまたま転職活動をした1-3か月の間に求人を出している会社で、かつそのエージェントに求人を出している会社しか紹介してくれない。
そうなるとエージェントとしてはいまある案件をさばくことが最優先になり、それに求職者が興味を示さなければサヨナラということになる。なのでタイミングがあっているのも運次第としたらエージェントとしては曖昧な将来を考えるよりも今ある案件をさばくために求職者にお勧めするようになる。
求職者が違う思考をもっていたとしても、その会社のいいことを言って受けてもらう方が良いという発想にどうしてもビジネスモデル上なってしまうのは仕方がないことなのかもしれない。
■こちらの発言や希望を理解しようとしない場合も多い
転職活動をする理由は人それぞれ。なのでそれぞれの動機に合った対応をしてほしいものだが、こちらの話を最初は聞いてくれている雰囲気があるが実際は全然聞く気がないようなそぶりが垣間見える瞬間というのはある。
だいたい自分よりは若い子が多いのでこちらからじっくり話ながら反応を見ているとよくその人の心理的な状況や気持ちの移り変わりが見てとれる。聞いているようで聞いていない、「そんなことはいいからいろいろ受けてくれ」というようなプレッシャーを感じてくる。
どういった会社に行きたいか、どういった理由で活動をはじめたかということ、どういった項目に優先度があるかという話をしてもそれはエージェントの関心のソトの話。とにかくいろいろ受けてもらうことでしかビジネスとして成立しないのでいろいろ求人を紹介してみるということが主眼にあるのでサービスと求職者の意向はあまりマッチしない。
とりあえずあなたの話は聞いてますよというスタンスをとろうとしているのは感じるが実態は異なっているので変な期待はしないほうがいい。一人一人に合わせていたら効率が悪いし彼らのビジネスモデルではない。
■まとめ
結局はそういったサービスをうまく使うことが大切であるというのは言うまでもないが、ぼくはうまく使えなかった。
決してエージェントサービスが悪いというのはなく、割り切って使えればかなり強力なサービスなのでぼくとの相性が悪かっただけだと思っている。
もっと割り切ってビジネスライクに付き合ってどんどん受けられる人には大きな力になってくれるのは間違いない。
とりあえず自分で求人サイトや企業ホームページを不定期に検索をかけて、気になる企業や業種を絞り込んで自分で探すほうが僕には合っていると思ったのでとりあえずエージェントサービスは使わずに今年は一年間、仕事にも真摯に取り組みながら探していこうと思っている。
上記のような物量に任せない転職エージェントというのはいるものだろうか。それはヘッドハンターに近いかもしれないがLinkedInなどに登録していると怪しそうなハンターたちがうごめいている雰囲気を感じるし、会社にも時々英語で電話が掛かってくるからちょっと怖いイメージしかないので使う気にはなれない。
もしいい企業やエージェントと出会いがあればもう一度その時はトライしてみよう。それまではポータブルスキルをもっと磨いて声がかかる人材になっていこう。
今の仕事もたとえ徒労感が強くても自分なりにトライしよう。
仕事で充足されない満足度は私生活で満足させるようにしよう
この3つが今の気持ち。
keiky.
いただいたサポートは、今後のnoteの記事作成に活かさせていただきます。ますます良い記事を書いて、いただいた暖かいお気持ちにお返ししていきたいと思います☆
