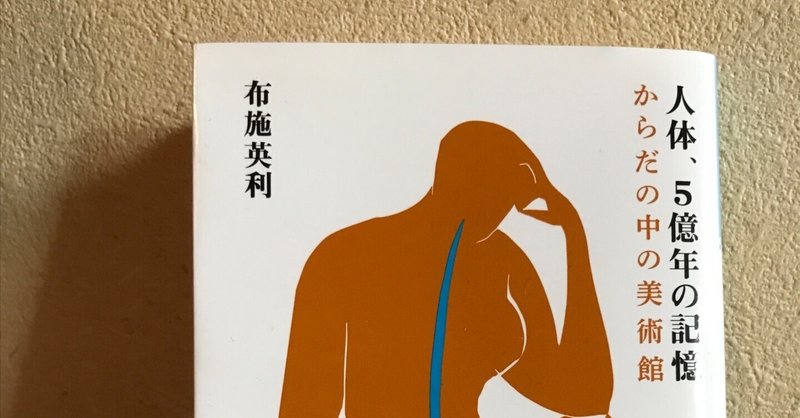
人体、5億年の記憶 からだの中の美術館 - 布施英利 を読んで vol.1
2024.5.14
はじめに、この記録を書いている私は人体の基礎知識も初めて知る素人である。
読みはじめ
これは三木成夫という解剖学者の考えたことを第一章では解剖学的に、第二章ではこの本の著者、布施英利 氏が美術と結びつける本(まだ第二章は読んでいないのでたぶんそういう内容かと。。)を最近読んでる。
内蔵は感覚器官である。「腑に落ちる」「息をのむ」とか、へえと思う。
臓器は単なる機能としての器官ではなく心や宇宙のリズムに対応している。というのも最初の生物、(海の中の時代)は消化器官が最初であったという。出口入口が一つの状態、そこから進化したという。この何億年もの間の海の記憶、自然のリズム、宇宙のリズムを内蔵は記憶している。/内蔵の不快が脳に信号として伝わるまでに他の雑念が混同して不快な気分がでる。/快感は緊張からの緩み->放尿に喩えられる。なるほど。快感は不快の次にあるものか。
/循環器の章で心臓や肺からの体中を巡る血液のことを読んで想像してたらいつもの血がすーっと下がる血圧がさがるような感じがした。体の中をこのような管が張り巡らされて自分の預かり知らぬところで機能しているというのはとても奇妙である。その感覚、驚きから血圧が下がるのだろうか。血を見た時とか。なにか人体の根本に触れるとそういう動揺が起こる。自分とは脳で考えた自我だけではない。むしろ自分ではない臓器や微生物たちがわさわさと体にひしめいて生きている。すごいよな。心臓は血液の循環、肺のガス効果の2つの役割がある。心臓の周りにある神経がその血管の収縮などを感じとり脳へと緊張や緩和として処理する。
何事も脳が先と思っていたけど、どうも先に血液や血管の収縮、骨格筋の収縮動きがあり、それを神経が察知して脳へ信号を送る。やっと脳が快感不快を決めるのか。ほう。壮大だな。
この記録を書いている私は人体の基礎知識も初めてる素人である。人体の神秘を感じる読書始めであった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
