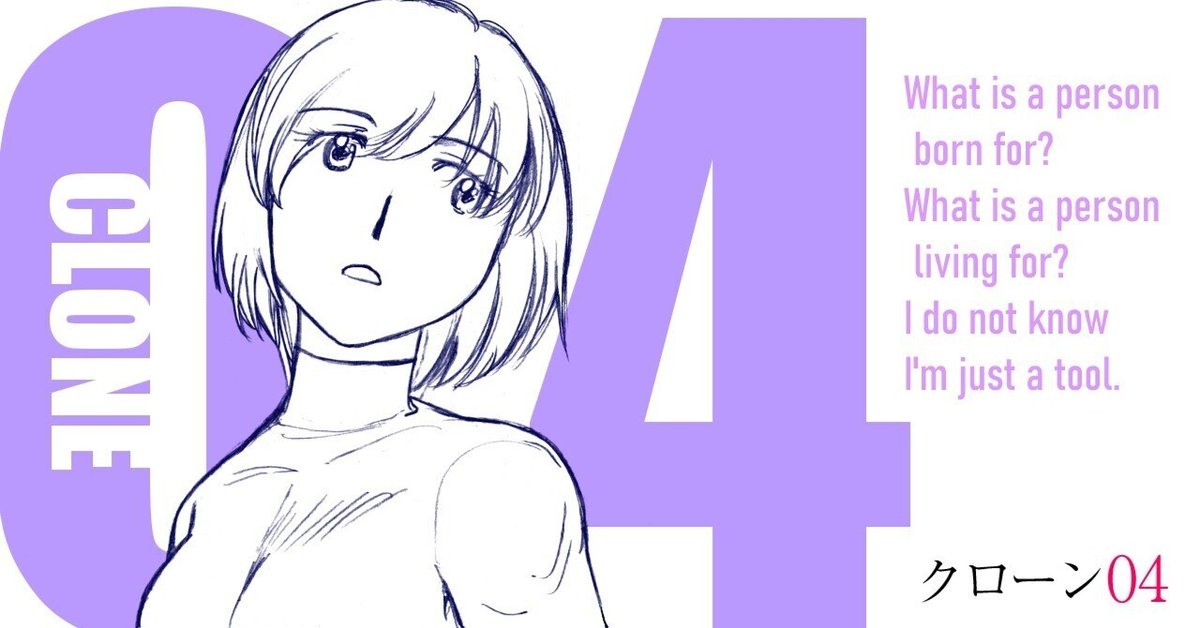
クローン04 第14,15最終話
十四 彼もまた
長引く戦いに、リンスゥの身体が悲鳴を上げ続けている。
クロックアップし、身体の動きをプログラムに委ねている分、痛みに対して敏感になった。意識を身体を動かすことに向ける必要がなく、これだけ激しく動いている中でも冷静に状況を感じることができるからだ。
激しい息づかい、ふみこむ足音、ナイフが風を切り、時折はじきあう。そんな目まぐるしい戦いの中でも、リンスゥの意識はそれと少し距離を置いている。周囲の音は聞こえているのに、同時に静まり返っていて、リンスゥには身体中の筋繊維がぷつぷつと切れていく音が聞こえるようだった。
無理な体重移動にきしむ脚。するどくしならせ伸びきる腕。身をひねり、反らし、かがむ、その時腰にかかる大きな荷重。
そのたびに、ぷつり、ぷつりと音がする。
何十何度目かの自動回避が発動し、大きく飛んで下がった時、とうとう足首にするどい痛みが走った。
「くっ」
顔をしかめるリンスゥ。
これはもう、ぷつり、ぷつりのレベルではない。痛みは脳に異常を知らせる信号だ。これ以上の無理は危険だと、体が脳にうったえている。本能的に、負傷個所をかばおうとする。
だが、今はそんな余裕はない。体の一部がこわれようが、命を失うよりはましだ。その本能をリンスゥは意識的におさえこみ、体にさらなる無理を強いる。
そこに生まれた一瞬の逡巡。
九十六号はその隙を見逃さない。
彼女にとっても、自分と同レベルの相手とこれだけ長い戦いになるのは、初めての体験だった。
遺伝子強化された筋肉に乳酸がたまり、そこへ強い神経信号を送り駆動を強いるたびに筋繊維から悲鳴が上がる。このパフォーマンスをこれ以上維持するのは困難と判断された。
そこへもたらされた、眼前の敵の大きな隙。
それはずっと、探り続けていたものだった。
見逃すわけがない。プログラムが新しい分岐に入る。
ここで決めるために大技をくり出す。
リンスゥが顔をしかめ、一瞬集中がそれた瞬間、九十六号は目の前から消えた。
目標を失いリンスゥの動きが止まる。
リンスゥの耳に、天井に何かがぶつかる音が届いた。
その時、この一瞬をねらってシロウがリンスゥに授けた、最後の武器が動き出した。
九十六号は一気に跳躍して、天井を使った三角跳びをしかけていた。
飛び上がり身をかがめ、くるりと前方宙返りを半回転。ちょうど天井に着地する形になる。そこで天井を蹴り、加速をつけ、相手の背後に着地する。意表を突き、視界から消える奇襲攻撃だ。
だが奇襲は、相手が想定していない場合のみ成立する。
この動きは一度、夜襲の時に見せていた。そしてシロウは建物内のセンサーに残った記録を解析し、この動きの軌道とタイミングを完璧に読んでいたのである。
音を聞き自動回避パターンが発動する。リンスゥは両腕を胸元に引き付け、回転モーメントを最小にして、最速で百八十度反転。両腕を計算された角度で差し出した。
九十六号が背後を取るには、着地するまでにまた半回転し、かつ、振り向くために半ひねりを加えなくてはならない。前半の上昇途中での半回転の間は相手を見すえたまま回れるが、後半の半回転はひねりを加えた動作の時に一瞬目線が切れる。
リンスゥのターンはその一瞬に合わせて行われた。
次に九十六号がリンスゥを視界にとらえた時、その身体はリンスゥの差し出したナイフに向かって落下していた。
空中で取れる自動回避パターンは一つだけ。そのナイフをはらおうとして、九十六号の武器を持った右手が、抱えていた足からはなれて持ち上がる。
しかしその動きもすでに先手を取られていた。リンスゥの左手は、まさにその動きを防ぐ位置に置かれていて、上がってきた右腕の手首をしっかり押さえた。
自動回避ではない意識下の動きでは、もう間に合わない。
リンスゥの与えた運動エネルギーに九十六号の落下による運動エネルギーが加えられ、ナイフは深々と九十六号の胸に突きささった。
いつもなら真っ直ぐ着地する九十六号は、回転不足で、つんのめるような前かがみの姿勢で着地した。
くぷっとその口から鮮血がもれた。
右腕をリンスゥに引かれ、ナイフはますます深く胸をえぐり、どさりとあお向けに倒れた。
見下ろす形になったリンスゥと目が合う。
その目には光が、いつもはない感情のゆらぎがあった。
「あ……」
弱々しくリンスゥに向かって左手が差し出される。
その時、一瞬うれしそうな、一瞬悲しそうな、無垢な赤ん坊のような表情が、その顔に浮かんだ。
その手が、その顔が、リンスゥをゆさぶった。
差し出された手は何かをつかもうとするかのように宙をさまよい、力を失い、地に落ちた。
その瞳には、もうどんな光も宿ることはなかった。
リンスゥはかたわらに膝をつき、まぶたを閉じさせると、自分の手をそっと彼女の手にそえた。
私たちはおたがい道具として生まれた。
戦うことが宿命で、そこに二人の意思はなかった。
さらには、クロックアップという意思と体を切りはなす機構を使って戦い、自分の意思で自身の体を道具そのものにしたのだ。
九十六号の手はもう力なく、でもまだ温かかった。
リンスゥは一粒、涙を流した。
「よう、兄弟」
その戦いを見つめていたクロサキの背後から声がかかった。
「……お前だったのか」
それはよく知った声だった。
「なるほど……道理でな」
ターゲットをサポートする「正体不明の」人物。優秀なはずだ。その能力はクロサキ自身がいやというほど、よくわかっている。
ゆっくりと振り返ると、そこにはシロウが立っていた。
「店に送り込んだ連中はどうした?」
大体の予想はついたが、一応たずねる。
「来るのはわかってたからね。しっかり準備して、丁重にお出迎えしたよ。まあ、少々手荒だったかもしれないが、怪我はちょっと治療すれば済む。廃棄するほどじゃない」
シロウはたいしたことではないかのようにさらりと答えた。当然の結果だとクロサキも思った。人数の不利はあるが、先ほどのヒートトラップのようにしかけをほどこせば、それをひっくり返せるだけの腕がある相手だ。
なぜなら、彼もまた……。
クロサキはバイザーを取った。
ならんだ二人は、髪形はちがえど、顔立ちはそっくりだった。
引きしまった輪郭。はっきりした眉。一重の目。通った鼻筋。薄い唇。
ただ同じ顔、同じ背格好ながら、厳しい表情をくずさず、真っ直ぐ見つめるクロサキ。
少し猫背で、だらしなく、からかう様なほほえみを浮かべているシロウ。
「お見通しだったというわけか……」
シロウは肩をすくめる。
「俺と『暁里(シャオリ)生物科技』は休戦中だ。手を引いてくれるとうれしいんだけどね。それに期待の新型をこうあっさり打ち破られちゃ、そっちも困るだろ。なかったことにしようぜ」
そう持ちかけられたクロサキ四十九号は、クロサキ四十六号をじっと見つめた。
「……事後処理班をそっちに回すぞ」
「おう」
クロサキは振り返り、九十六号のもとへと歩み寄る。
「失礼」
リンスゥに一言断ると片膝をつき、九十六号の脇の下と膝裏に腕を差し込んで、そっと抱き上げた。銃撃を受けた時に負傷した右腕にするどい痛みが走る。
その痛みは、ただ脳に届いた信号というだけではなかった。それは彼の心のうちにもひびいていく。表に見せない傷をかきむしる。
それは生まれた時から、ついていた傷。
それは己が己である限り、ふさがらない傷。
それをかみしめるかのように、歯を食いしばり、立ち上がる。
腕の中の九十六号を見下ろす。
いつも引きしまって閉じられていたのに、今は薄く開いた唇。
眠っているような表情。
何も伝えることのなかった顔に、今は安らぎが浮かんでいるように見える。
彼女はこの傷から逃れることができたのだろうか。
一息つくと、クロサキは九十六号を抱いてフロアを立ち去った。
いつくしむようなその後ろ姿を、リンスゥはじっと見つめていた。
「大丈夫かい?」
気がつくと、シロウがそばに立っていた。
「シロさん……あの人、シロさんとそっくり……」
シロウの顔を見上げる。
「もしかして、シロさんも……クローン?」
シロウはうなずいた。
「KRSシリーズは高い運動能力と情報処理能力をかねそなえた、現場指揮官タイプなのさ。数はそう多く生産されてないけどね。俺は不良品だったんだ。刷り込み不適応で廃棄処分。何とか生き延びて、外部の情報屋として、『暁里生物科技』と付かずはなれずの関係……まあそんなところだ」
シロウはそう言って、口をつぐんだ。そのままクロサキの立ち去った階段の方を、だまって見つめていた。
刷り込み不適応……。私と同じ……。だから?
リンスゥは、シロウの横顔から視線をそらせなかった。
いつもとちがう、愁いを帯びた顔。
いつものからかう様なあの顔の下に、どれだけの苦しみと悲しみがかくされていたのだろう。
本当は何を思って、私を助けたのだろう。
しばらくすると、照れかくしなのかひときわ明るい声で、シロウはリンスゥに声をかけた。
「さて、立てる? さっき足を痛めてたみたいだけど?」
「あ、平気……」
リンスゥはそう答えて足首をさすったが、すでにはれ始めていて、さわるだけで痛みが走る。苦痛に顔をしかめた。
その様子を見ていたシロウが、ぽんと言った。
「何ならリンスゥもお姫様抱っこしてあげようか?」
「え、ええっ! い……いや、いい。いい、です……」
「なんだよう、遠慮すんなよう。不良品同士、なかよくしようぜー」
抑制が外れ、この街に来てからわかるようになった、恥ずかしいという気持ち。シロウは頬を染めてたじろぐリンスゥを見て笑っている。
いつものように、またからかっている。
「もうー……」
すっかりと赤くゆで上がったリンスゥは、すねたような顔にへの字口。シロウを上目づかいに見つめる。
リンスゥが知らなければいけない感情は、まだまだたくさんある。
そんな表情を引き出して満足したのか、シロウはすっと手を差し出した。
「さ、帰ろうぜ。家へ」
「うん」
リンスゥはその手を取った。
シロウの手は温かく、力強かった。
十五 道具じゃないとしたら
シロウは店に来た襲撃チームを撃退したあとで、リンスゥの元へとかけつけていた。乗ってきたのは例の愛用スクーター。足首を痛めたリンスゥを後ろに乗せて、スクーターは軽快に夜の街を走る。
ハンドルをにぎるシロウの背中に、リンスゥはその身を預ける。
大きいな、と思った。
このスクーターでの二人乗りは、ちょくちょく体験していた。相手はいつもマリアだった。シロウといっしょに乗るのは初めてだ。
いつもよりずっと大きくがっちりとした背中が、リンスゥの視界をさえぎっている。
だが前が見えないことに不安は覚えない。
作戦行動中に周囲の情報を確保しておくのは、リンスゥに染み付いた習慣だ。これから通過する前方の情報が得られないということは、本来であれば不安要素のはずだ。なのになぜだろうと、リンスゥは自分でも不思議に思った。
それどころか、今自分は心地よい安心感に包まれている。これも、リンスゥが正体を知らない心の動きだった。
正体がわからないことさえ、心地よい。リンスゥはシロウの背中にそっと頬を寄せた。
「リンスゥ」
「ふぁいっ」
すっかり油断していたところに呼びかけられて、思わず変な声が出た。
だが、シロウはそんなリンスゥの様子にかまわず言葉を続けた。
「さあ、ここからがラスボスだ。手ごわいからな。覚悟しときなよ」
「えっ?」
先ほどの戦いで、事態は収束できたのだと思っていた。シロウと相手の間の雰囲気もそれをにおわすものだった。だが、まだ終わっていないのか。先ほどの様子は、相手を油断させるブラフだったのか。
このあともう一戦となると、負傷したリンスゥにはきつい。しかしシロウがああ言ったということは、それでもさけて通れない相手なのだろう。やるしかないのだ。
「はい」
リンスゥは安らぐ気持ちを振りはらい、もう一度自分を戦闘態勢に置いた。
果たしてそのラスボスは、店の前に仁王立ちして二人の帰りを待ち構えていた。
真っ赤な顔と、泣きはらした目をして。
「何で朝にちゃんと言ってくれなかったのっ! それに昨日の夜に出て行こうとしたんだって? 何で!」
リンスゥがスクーターを降りるのも待たず、マリアがずかずかとつめ寄ってきた。
リンスゥはその迫力に思わずたじろぎ、後ずさる。
ああ、なるほど、ラスボスって……。
「あ……あの、マリア……その……みんなに迷惑かけるかな、と思って……」
リンスゥの戦闘態勢は、この状況にはまったく無力。すっかり腰くだけで言い訳を口にするしかない。しかしラスボスはそれを許さず、たたみかける。
「迷惑って何! そんなこと、夜になっていきなり聞いて! 敵はおそってくるし! お店はめちゃくちゃになるし! なかなか帰ってこないからやられちゃったのかと思ってすごく心配したし!」
ぽか。
マリアがリンスゥの頭を小突いた。
「あいた」
「迷惑って何よ! だれが迷惑だなんて言ったのよ!」
ぽかぽか。
まだ涙の残る目でリンスゥをにらみながら、さらに小突く。
そして首にぎゅっとすがりついた。
「迷惑かければいいじゃないよ。もうー……」
消え入りそうな声で、そうしぼり出した。
「ごめん」
リンスゥもその耳元で小さく答えた。
それでもマリアはリンスゥにしがみついたまま、ぐすぐすと泣く。
確かに、これは手ごわい。
そしてまったく、勝てそうにない。
こっそりと足音を立てないようにして、シロウがそのわきを通り過ぎる。
あ、ずるい。
リンスゥは目でうったえた。
シロウは唇の前に一本指を立て、笑っていた。
店の中は散らかっていて、乱闘のあったことをしのばせていた。隅の方、床の上に襲撃班の面々がテープでしばり上げられ転がされている。みんな、意識を失っているようだ。
だが、自分と同型のクローンたちには目立った傷はない。床には他に見慣れない何かの部品が転がっている。色々と罠を用意したようだ。サポート班の方が実力行使のあとが見えるが、それはいわゆる青タンというやつで、思い切りなぐられた様子。それ以上の負傷の気配はない。
そこに引っかからないようさけながら、ヤーフェイがホットミルクを持ってきてくれた。その手に湿布をはっている。ヤーフェイも活躍したのだろうか。
「これ飲んでもう寝な。疲れたろ。片付けは明日にしよ」
「おばちゃんも……ごめんね」
ヤーフェイもマリアと同様、夜になって唐突に事情を聞いたはずなのに、なんてことないよというふうに手を振った。
マリアはリンスゥにしがみついて放してくれない。着がえる時もぴったりくっついていた。
マリアの寝室で、さあベッドに入ろうとした時、マリアがリンスゥの顔をのぞきこんで言った。
「ねえ、リンスゥ。前から言おうと思ってたんだけど」
真剣な顔。
それにつられて、リンスゥはベッドの上で居住まいを正す。
「え……な、何?」
「リンスゥは前に、自分は役に立たない道具なのに、なんでみんな優しくしてくれるんだろうって言ったじゃない?」
「う…うん」
そう、確かに言った気がする。言わなかったとしても、それは常に自分の心に巣食っている疑問だった。
戦うことしか知らない単機能の道具。言ってしまえば、まったくの世間知らずの役立たず。店の仕事では足を引っ張ってばかり。捨てられても仕方ないぐらいだと思うのに、なぜ……。
「まだ自分の事を道具だなんて思ってるなら、怒るからね!」
リンスゥの想いをさえぎるように、そう強い口調でマリアは告げた。
「リンスゥは自分を道具だと思ってるから、どこか自分が死んじゃっても仕方ないって受け入れちゃってるよね? 今回だって、一人で出ていっちゃおうとしたのは、それで自分が危なくなるのを気にしてないからだよね?」
涙を浮かべた瞳で、リンスゥを見つめる。
「私だってリンスゥと同じクローンだよ。私だって道具だった。最初にリンスゥを助けたのは、昔の私と同じ立場の捨てられた道具なんだろうなと思ったからだよ。でももう私もリンスゥも、道具なんかじゃないんだよ。私は自分の意思で動いてる。リンスゥだって、自分の意思で逃げてきたんでしょう? ここから去ろうとしたことだって、戦うことにしたのだって、自分で決めたことでしょう? 自分で自分の運命を決めた人は、もう道具じゃないんだよ」
リンスゥの瞳の奥まで、真っ直ぐ見つめている。
「それに、道具には、そう使う人がいるんだから。こんなにみんながリンスゥのことを心配していて、道具だなんてはず、ないでしょう?」
ぎゅーっと抱きつかれ、ベッドに二人、ばたりと倒れ込んだ。
「大好きだからに決まってるじゃんか、バカ……」
マリアが小さくつぶやく。
いつにも増してマリアはべったりとすがりつき、リンスゥの頭をその胸にしっかりかき抱いていた。
もう放してくれそうにないので、リンスゥは大人しく抱かれていた。
マリアの胸はやわらかく、あたたかくて、いいにおいがした。
心地よく、そしてちょっと恥ずかしかった。
この日はさすがにマリアの子守歌はなかった。
その代わりに、しっかりとくっついた胸から、マリアの心臓の音が、とくん、とくんと小さく聞こえていた。
それは何かの記憶、自分にはないはずの遠い記憶を呼び覚ますような気がした。
道具じゃないとしたら、私は何のために生まれてきたんだろう?
あいかわらずその答えは出なかったけれど、やわらかくまとわりつく温かさに包まれて、リンスゥは安らかな眠りへと落ちていった。
〈了〉
ここから先は

銃と宇宙 GUNS&UNIVERSE
2016年から活動しているセルパブSF雑誌『銃と宇宙 GUNS&UNIVERSE』のnote版です。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
