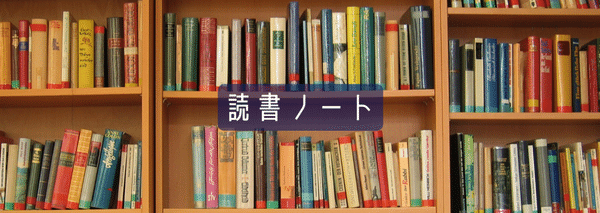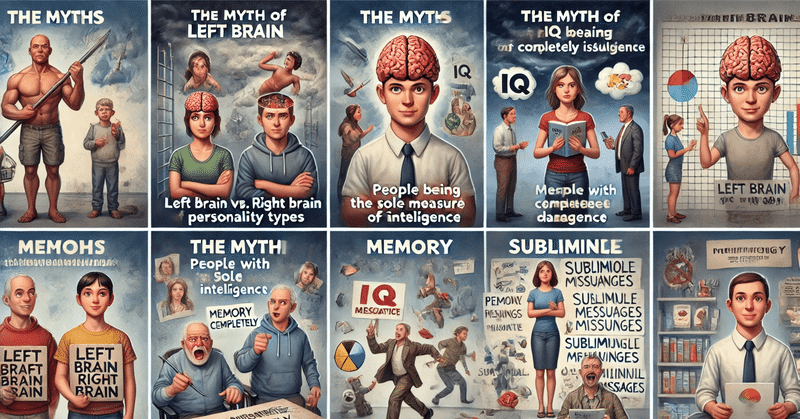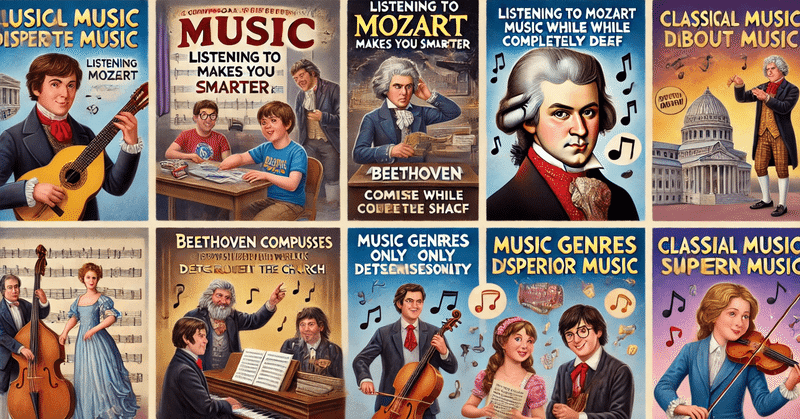最近の記事
- 固定された記事

「フクロウは頭を360度回せる」と信じられているけど、実際には約270度しか回せないんだ。それでもすごい能力だけどね!【アシモフの雑学トリビア・豆知識】
フクロウの首の構造と可動範囲 フクロウはその独特な首の可動範囲で知られており、頭を約270度まで回転させることができます。この驚異的な能力は、フクロウの首の骨の構造と特別な血管システムによるものです。 1. 首の骨の構造 フクロウの首には14個の頸椎があります。これは、人間の7個の頸椎に比べてほぼ倍の数です。この多くの頸椎が、フクロウの首を非常に柔軟にするための基盤となっています。各頸椎は互いに独立して動くことができ、これが広い回転範囲を可能にしています。 2. 血管

おまえ自身を知ろうとするなら、他人の心の動きを見るがよい。他人を知ろうとするなら、おまえ自身の心の動きを見るがよい。【きまぐれエッセイ】
ヨーハン・クリストフ・フリードリヒ・フォン・シラー (Johann Christoph Friedrich von Schiller) なんとも長い名前だが、このドイツの詩人・哲学者の言葉には、深い洞察がある。シラーは18世紀後半から19世紀初頭にかけて活躍し、その作品は今もなお多くの人々に影響を与えている。この引用は、その中でも特に心に残るものだ。 「他人を理解するためには、自分の心の動きを観察せよ、 そして自分を理解するためには、他人の心の動きを観察せよ」 というのが