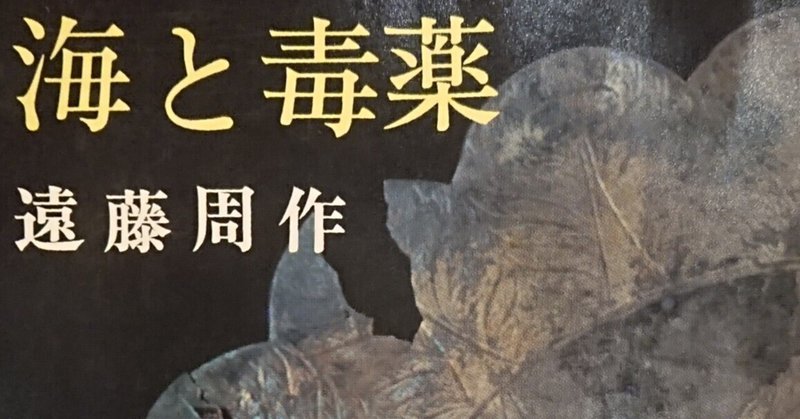
読書記録「海と毒薬」
川口市出身の自称読書家 川口竜也です!
今回読んだのは、遠藤周作さんの「海と毒薬」新潮社 (1958)です!

・あらすじ
1945年5月 太平洋戦争末期 九州のとある大学医学部にて、米軍捕虜8人の解剖実験が行われた。
麻酔で眠らせている間に肺を摘出し、死亡するまでの気管支の断端の限界を調査するという、被験者が死ぬことを前提とした実験であった。
勝呂(すぐろ)は医学部の研究生、九州のF市にある病院で結核患者や爆撃で怪我をした患者の手当などを行っていた。彼の最近の悩みは、大部屋で療養中のおばはんの体調が改善するかどうかであった。
正直治る手立てはない。結核であと半年持つか、手術しても9割方治らない見込みであった。だが、勝呂にとってはじめての患者であったおばはんに気をもんでいた。
いつものようにおやじ(橋本教授)の手術に助手として立ち会っていた勝呂だが、手術中に患者の様子が急変し、そのまま手の施しようもなく亡くなってしまう。
だがおやじは、手術で亡くなったと言わず、手術後に山を超えられなかった、ということにした。
もとより勝呂にとって、空襲で死ぬか病院で死ぬか、2つに一つだと悟っていたようで、感慨深さなど、なかった。
それからしばらくして、例の人体実験に参加できないかと頼まれる。断ろうと思えば断ることはできたのだが、どうしてか勝呂は承諾した…。
「生きた人間を生きたまま殺す」という狂気のような事件だが、果たして実験に参加する者たちは皆狂気に駆られていたのだろうか。
彼らが人体実験に参加することを選択した、その根源は何だったのだろうか。
半年くらい前に、同じく遠藤周作さんの「沈黙」新潮社 (1966)を読んだ。あの話同様に救いようのない物語ではあるものの、どこか一筋の光を感じる作品であった。
当時、彼らがどうして実験に参加したのか、その心を少しでも理解するためには、戦時下という極限状況を考慮しなければならない。
あくまでも私の想像であるが、B29に乗って罪のない日本国民を爆撃していった米軍捕虜に裁きを与えるために実験に参加した。同意こそできないが想像はできる。
だが、本当にそうだろうか。そんな歪んだ愛国心のために、人体実験に参加したのだろうか。
「みんな死んでいく時代やぜ」相手は葡萄糖を新聞紙に包んで机の中に入れた。「病院で死なん奴は、毎晩、空襲で死ぬんや。
実験に参加した者たちの中に欠如してたのは、罪の意識ではなかろうか。
この作品の中で見事なのは、実験に参加する前に手術中に患者を亡くしてしまうところにある。
「手術中に人を亡くしてしまう」という結果に違いはない。どちらも考えようによっては、医学を進歩させる尊い犠牲だったと捉えることもできる。
先の手術で人を殺めてしまったからこそ、今回の実験がその延長線上にあるかと錯覚してしまう。
そして、こんな世の中なのだからという群集意識が、実験に参加した者たちに蔓延っていたのではあるまいか。
またこの作品は「沈黙」しかり、信ずるものを持たない日本人の弱さや欠点を描いている。
物語の途中、勝呂は同期の戸田に対してこう問いかける。
人間は自分を押しながすものから――運命というんやろうが、どうしても脱れられんのやろ。そういうものから自由にしてくれるものを神と呼ぶならばや
たとえ信仰するものが無いにしても、心のなかに自分の念仏を唱えられる者は、強く生きていける。
勝呂にもそれがあったはずなのだが、彼にはその言葉を呟くことができなかった。できなかった…。
内省したいときなどに、読んでみてはいかがだろうか。それではまた次回!
今日もお読みいただきありがとうございました。いただいたサポートは、東京読書倶楽部の運営費に使わせていただきます。
