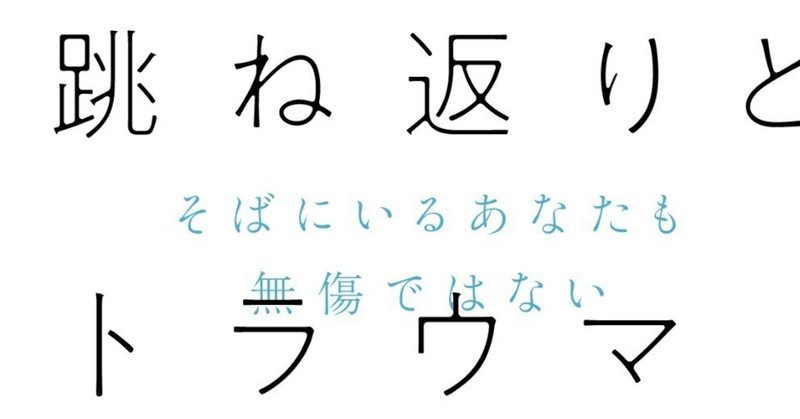
被害者だった人、被害者である人、これから被害者になるかもしれない人へ|跳ね返りとトラウマ|吉田良子
シャルリ・エブド襲撃事件の生き残りとなった風刺画家。その妻であるジャーナリストが、夫のとなりを歩んだ5年間の記録――。

カミーユ・エマニュエル 著『跳ね返りとトラウマーーそばにいるあなたも無傷ではない』(吉田良子 訳)が2022年12月22日に配本されます。本稿では特別に、同書の日本語版より「訳者あとがき」を公開します。
訳者あとがき
二〇一五年一月七日、フランスのパリにある風刺週刊紙『シャルリ・エブド』の編集部に、覆面をして武装した二人組の男(クアシ兄弟)が侵入し、十二名を殺害、十一名に重軽傷を負わせた。犯人たちは逃走するも、二日後に警察との銃撃戦で射殺された。また、八日にはパリ近郊で女性警察官が銃殺され、犯人(アメディ・クリバリ)は翌九日にユダヤ系スーパーマーケット(イペール・カシェル)に籠城するが、こちらも突入した警察部隊に射殺された。一月七日から九日に起きた事件は、犯人たちに交流があったため、あわせて「シャルリ・エブド襲撃事件」と呼ばれることが多い。
直接的な背景としては、同紙がムハンマドの風刺画をたびたび掲載し(とくに議論を呼んだのは二〇〇六年)、イスラム社会やイスラム主義者らの反発を招いてきたことがある。日本でも「表現の自由」をめぐって複雑な議論を巻き起こしたのは記憶に新しい。
フランス政府は、一月十一日に全国各地で犠牲者追悼のデモ「共和国の行進」をおこなった。参加者は全国で数百万人に及んだとされる。パリでのデモ行進には、フランスのオランド大統領をはじめ、イギリスのキャメロン首相、ドイツのメルケル首相などの各国首脳が参加した(いずれも肩書は当時)。
本書の著者カミーユ・エマニュエルの夫リュズは『シャルリ・エブド』の風刺画家だったが、編集会議に遅刻し、わずか数分の差で襲撃を免れた。しかし、凄惨な犯行現場を見たことで、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症し、「直接被害者」として認定された。不眠と悪夢に悩まされ、かすかな物音にも怯えてはパニック状態に陥る夫を支える生活が、こうして始まった。襲撃されるのではないかとの不安、警護による束縛、パリを離れての生活と異国の地での出産、加えて国の理不尽な対応や周囲の無理解……。夫ばかりか著者の生活も大きく損なわれた。だが、夫を気づかう人は多いが、著者に「大丈夫?」と聞いてくれる人はほとんどいなかった。夫は警護されても、一緒に暮らしている著者は警護されなかった。夫のためにパリを離れ、仕事の多くを失い、交友関係を断たれても、妻として当然とみなされた。むしろ、感謝しろとさえ言われたこともある。「きみの夫は生きているじゃないか。幸せだと思うべきだよ」(七七頁)と。
こうした日々を耐えがたく感じた著者の心をとらえたのが、事件当日の夜、心理士に言われた言葉だった。「あなたは被害者の近親者ですから、跳ね返りによる被害者なのですよ」(一六頁)――そのときは意味がわからなかった。自分が「被害者」だとは思いもしなかったから。だが、いまではこんな疑問を抱くようになった。どうして自分には「無償の愛」や「自己犠牲」ばかりが要求されるのか? 直接被害者である夫の影響を受けざるをえない自分のような存在を、どう考えればいいのか?
「いまの私には、何が起きたのかを理解すること、そして寄り添う人たち、つまり、心に傷を負った被害者と強い愛情で結ばれているがゆえに生活をくつがえされてしまった人たちが、何を経験したのかを理解することが必要だった。この役目を、この状況を、冷静に見つめることが必要だった。法的に、精神的に、内面的に、何が変わるのか? 集団の物語のなかに埋もれてしまわない、一人ひとりの物語を書くことが必要だった」(二二頁)――こうして著者は、実体験をもとに関係者や専門家へのインタビューをおこない、さまざまな調査を重ね、「跳ね返りによる被害者」とは何なのか、自分に起きたことにどんな意味があるのかを明らかにすることを決意した。
ところで、この場合の「跳ね返り(ricochet)」は「被害者と身近な関係にある者が被る影響や被害」を意味する(一般的には「石の水切り」や「跳弾」を意味する言葉だ)。日本では馴染みのない表現だと思う。しかし、被害者に寄り添う近親者が、実際に出来事を体験していなくても、被害者と同じ症状を呈する可能性があることは、精神医学や心理学で公式に認められているそうだ。本書に登場する「テロ及び一般犯罪被害の被害者補償基金(FGTI)」も、跳ね返りによる被害者の損害を認め、補償金を支払っている。
ただし現実には、跳ね返りによる被害者の存在はほとんど顧みられていない。理由の一つは、跳ね返りによる被害者本人が、自分をそうだとみなさないことにある。かれらの多くは苦しみながらも、「自分に被害者を名乗る権利はない」と思いこんでいる。「自分はその場にいなかったから。自分は被害者を支える立場のはずだから」と。また世間の風潮として、「自分以外の人間に起きた不幸で金をもらおうとするのか?」という批判的な見方があることも大きい。そもそも、精神医療と心理学の分野で、間接被害者にトラウマの症状が起こると公式に認められたのはごく最近、二〇一三年だという。FGTIの損害認定においても、跳ね返りによる被害者の申請が認められるのはかなり少ないのが現状だ(詳しくは「定義の試み」「再定義」の章を参照)。
そのなかで著者は、「跳ね返り」と呼ばれる人々がその立場を自覚すること、損害を公的に認めてもらうために行動することを強く望んでいる。その目的が補償金の受け取りでないことはもちろんだ。お金をもらっても、以前の生活が取り戻せないことは誰もが知っている。それでは何のためか? 本書にはポーリー弁護士の言葉が引用されている。「支払われる補償金の目的は、苦しみ自体を補うことでは決してなく」「被害者の苦しみは考慮すべきものであると、法が認めたと示すことにある」(一五四頁)と。公的に認められたという「証」を得ることで、被害者は自らの苦しみに意味を与え、その後の人生を(ときに「被害者」であることから自由になった人生を)新たに歩みはじめることができる。その歩みを体験したからこそ、著者は「跳ね返り」の定義を広めたいと考える。「あなたの本を読むことが、きっとかれらの助けになるでしょう」(一六一頁)とポーリー弁護士も述べている。
著者のカミーユ・エマニュエルは、セクシュアリティ、ジェンダー、フェミニズムを専門分野とするジャーナリスト。夫が「テロ事件の生存者」になったことから、突然「被害者の近親者」としての生活を送ることになる。当たり前と思っていたものすべてがくつがえされる日々。そこには失ったもの、得たもの、変わらなかったものがあった。本書では、傷ついた夫に寄り添って生きた五年間の思いが、偽りなく率直に語られている。自らも認めているように、著者はジャーナリストとしての中立な立場にとどまることができなかった(客観よりも主観に重きをおく「ゴンゾー・ジャーナリスト」を自称したのもそのためではないか)。被害者となった人間が、加害者や政治的立場を異にする同業者に抱く割り切れない感情も、非常にリアルに描かれている点は興味深い(だからこそその点は、慎重に読まれる必要もあるだろう)。
テロに限らず、人々の生活を一瞬で破壊する悲劇はいつ、どこで、誰に起こるかわからない。被害者だった人、被害者である人、あるいはこれから被害者になるかもしれない人のすべてにお勧めしたい一冊と言えよう。
最後に、本書を翻訳する機会を与えてくださった柏書房の天野潤平氏と、校正に協力くださった精神科医の阿部又一郎先生に深く御礼申し上げたい。
吉田良子
著者:カミーユ・エマニュエル(Camille EMMANUELLE)
1980年生まれ。作家、主観的な記述を特徴とするゴンゾー・ジャーナリスト。著作は『セックスパワーメント』などエッセイ三作とヤング向けの小説一作。『アンロック』誌などの媒体に記事を書き、テレビやラジオの番組制作に関わる仕事もしている。専門分野はセクシュアリティ、ジェンダー、フェミニズム。
訳者:吉田良子(よしだ・よしこ)
仏文翻訳家。1959年生まれ。早稲田大学第一文学部卒。訳書に『世界一深い100のQ――いかなる状況でも本質をつかむ思考力養成講座』(ダイヤモンド社)、『色の力――消費行動から性的欲求まで、人を動かす色の使い方』(CCCメディアハウス)、『ボルジア家風雲録(上・下)』(イースト・プレス)、『葬儀!』(柏書房)など。
ご予約はこちらから!
