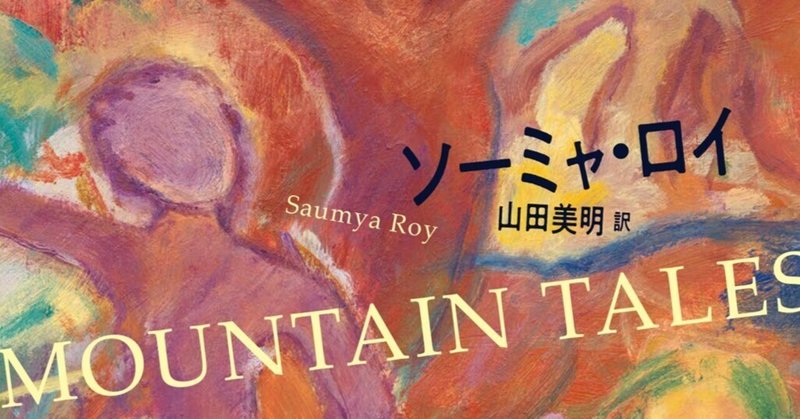
インドに関する本を一冊読むなら、この本を読んでほしい|デオナール アジア最大最古のごみ山|ソーミャ・ロイ【冒頭試し読み】
インドに関する本を一冊読むなら、この本を読んでほしい。
――ギーター・アーナンド(ピューリッツァー賞作家)
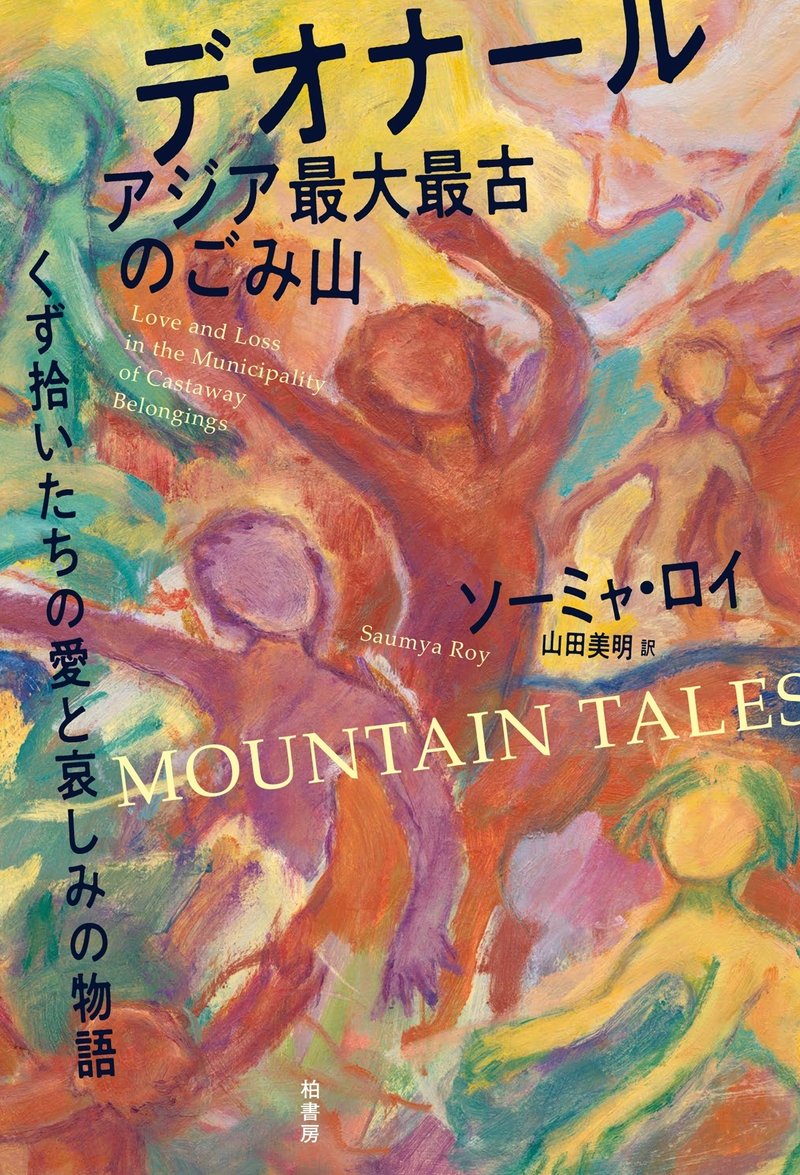
装丁=コバヤシタケシ
2023年8月24日、ソーミャ・ロイ 著/山田美明 訳『デオナール アジア最大最古のごみ山――くず拾いたちの愛と哀しみの物語』が配本となります。
2013年夏、ムンバイでマイクロファイナンスを扱うNPOを運営する著者が出会ったのは、市街地の端にあるデオナールごみ集積場でお金になるごみを集め、それを売ることでその日暮らしをする、くず拾いたちのコミュニティでした。
腐った食べ物、古い端切れ、割れたガラス、ねじ曲がった金属、赤子の死体、花嫁の遺骸、医療廃棄物、等々……。絶えず欲望を追いかけて、モノで心を満たそうとする現代生活の産物でもあるそのごみ山は、20階建てのビルほどの高さになるといいます。誰の目にも見えるところにありながら、誰の目にも見えていない広大なごみの町――。本書は、著者と住民たちとの8年以上にわたる長いつきあいの記録です。
とりわけ著者が注目したのが、10代の少女ファルザーナー・アリ・シェイク。彼女はごみ山で生まれ、そこで愛を知り、子をもうけるに至ります。悲劇的な事故にまきこまれながらも……。
彼女らの目を通して、最も荒涼とし腐臭に満ちた場所であっても、美や希望、愛が花開くことを私たちは知ることになるでしょう。同時に、グローバル資本主義が、最も脆弱な立場にいる人々にどのような影響を与えるのかも知ることになるでしょう。
著者は記します。この地で生まれる物語がまるで非現実的な気がしたとしても、その大半は現実である。そしてそれはごみ山で暮らす人々の物語であると同時に、どこにでもある物語なのだと。
本稿では、その物語のはじまりにあたる「序」と「1 ファルザーナー」の途中までを公開します。ご一読いただけたら幸いです。
【凡例】
・本書は以下の日本語訳である。Saumya Roy , MOUNTAIN TALES: Love and Loss in the Municipality of Castaway Belongings (Profile Books Ltd, 2021)
・原注は通し番号を章ごとに入れて巻末にまとめた。原書の脚注は左ページの欄外に示した。
・各章タイトルと本文中の写真は、著者の了承を得た上で独自に付したものである。
・ヒンディー語とマラーティー語のカナ表記は、現地の発音に忠実になるよう極力注意を払った。ただし「ムンバイ」のように「ムンバイー」と発音すべき単語でも、日本語として一般に定着している名称については、慣習的な表記を優先した。また「デオナール」は現地では「デーヴナール」と発音されるが、本書では英語表記のDeonarに従った。アドバイスをいただいた小磯千尋氏に、この場を借りて感謝申し上げる。
・原書は、本文中の会話を現地の言語で表記したのち、英語でその意味を併記している。その「翻訳」の際に、言語間でニュアンスの違いが生じている部分が何カ所かあった。なるべく原語の意味を尊重したが、日本語としての自然さも優先したため、必ずしも完全に意味が一致していないことはご了承いただきたい。
序
デオナールごみ集積場でごみを拾い集める人々に初めて会ったのは、二〇一三年の夏のことである。私はそのころ、ムンバイ* でマイクロファイナンス〔貧困層や低所得者層への融資サービス〕を扱うNPO財団を運営しており、そのオフィスに少額の低金利融資を求めて彼らがやって来るようになったのだ。話によると彼らは、ムンバイの市街地の端にあるごみ山でお金になるごみを集め、それを売って暮らしているという。私は彼らのあとについて、そこへ行ってみた。融資を受けて何をするのか知りたかったというのもあるが、何よりもその奇妙な場所をこの目で見たかった。以前から話には聞いていたが、ほとんどのムンバイ市民同様、実際に見たことはなかったからだ。やがて私はそこに、誰の目にも見えるところにありながら誰の目にも見えていない広大なごみの町ができていることを知った。ごみ山の高さはすでに三六メートルを超え、一方をアラビア海へと続く入り江に、もう一方をごみ山に沿って延びる居住地に囲まれていた。
こうして、デオナールごみ集積場とそこに暮らす住民との八年以上にわたる長いつきあいが始まった。私は、このごみ山の影のなかで展開される四家族の生活や仕事を追い続けた。そのなかでもとりわけ注目したのが、一〇代の少女ファルザーナー・アリ・シェイクだ。彼女は、ムンバイ市で明滅する欲望とともに成長を遂げたごみ山にも劣らないほど、信じられないような人生を歩んでいた。本書は、そのファルザーナーの物語であり、彼女の家族やその近隣の人々の物語である。その執筆を許可してくれた彼らに感謝したい。
私はやがてこのごみ山を、くず拾いの人たちと同じ目で見るようになった。都会で使い捨てられた幸運を授け、そこで色あせた富をもたらしてくれる存在である。だから、市のごみの管理を目的とする公判があるたびに、今度こそはこの山も移動させられるのではないかと心配しながら、何百時間と審理を傍聴した。また、人づてに聞いた噂を確かめようと、記録や資料を収集した。ごみ山を歩くようになって間もないころ、あるくず拾いから「以前ごみはここへ列車で運ばれてきたんだ(Kachra train ni yaycha)」という話を聞いた。それは、このごみ山にまつわる多くの伝説や暮らしと同じように、まるで非現実的な気がした。ごみのためだけに列車が運行する? ところがそれは本当だった。数年後にオックスフォード大学の歴史に名高いボドリアン図書館で、実際にボンベイのごみが列車でデオナールに運ばれてきたという植民地時代の記録を見つけたのだ。
デオナールのごみ山地区は、他に類を見ない独自の世界を生み出していた。だが、世界中どこへ行っても、やはり刹那的だが揺るぎない欲望の力により、デオナールに似たごみの山がつくりあげられている。記者をしているある友人は、モスクワ郊外にある「ごみのエベレスト」に関する記事を書いていた。デリーにあるごみ山は、タージ・マハルに匹敵する高さだと言われている。この山は雪崩を起こし、何人もの人がその犠牲になった。ちょうど私が、そこよりは安定しているデオナールのごみ山を調査していたころのことである。同じように雪崩を起こしたごみ山は、コロンボやアディスアベバ、深圳にもある。ニューヨークの有名な都市伝説の一つに、市内のごみを積んだ荷船が、どの州にもごみ処理を受け入れてもらえず海岸沖にいつまでも浮かんでいるというものがあるが、実際に私は以前、休日を返上してこの荷船を市に帰港させ、そのごみで新たなごみ山をつくったという元市職員に会ったことがある。
数年間ごみ山を歩いてわかったのは、デオナールのごみ山地区から生まれる物語がまるで非現実的な気がしたとしても、その大半は現実だということだ。似たような物語は、どの都市でも何らかの形で起きている。ごみの塊はもはや海にまで浮かび、島をつくってさえいる。私はいまでは、これらのごみ山を、絶えず欲望を追いかけてモノで心を満たそうとする現代生活の産物だと考えるようになった。その欲望の追求により、この山は長く大きくなるばかりだ。そこで生活手段を手に入れているくず拾いたちがいるというのに、私たちはいまだ満足することなくさらに多くを求め、自分のごみがつくりあげている世界を見ようとしない。
以下に記すのは、デオナールのごみ山地区や、その長い影のなかで暮らす人々に関する物語であると同時に、どこにでもある物語である。
* 本文内ではこの市の名称を、ボンベイと呼ばれていた時代の記述についてはボンベイ、一九九五年に名称がムンバイに変更されたあとの記述についてはムンバイと記すことにする。
1 ファルザーナー
四月のある暑い日の午後、ファルザーナー・アリ・シェイクはごみ山の平地でめぼしいものを探していた。頭上の太陽がじりじりと照りつけ、視界に入るけばけばしい色を揺るがす。腐ったエビのにおいが、ごみの山から立ち上る。ファルザーナーはごみ収集用の長いフォークを突き立て、半透明の魚のうろこや、パリパリと音を立てるエビの殻、動物の内臓や糞をかき分け、いましがたこの平地にばらまかれたばかりの割れたガラスびんをすくい上げた。
煙や熱気を巻き上げながら、ブルドーザーがガラスごみを押しのけていく。周囲に広がるごみの風景が一瞬ぼやけ、腐りかけた肉の悪臭に焦げくさいにおいが混じり合う。ごみをあさる鳥たちがそばに舞い降り、動物のはらわたを探す。ファルザーナーはガラスに目を光らせ、それを回収しようと、ごみの山にフォークを突き刺す。彼女はいつも「ジンガー(jhinga)」で働いているわけではない。ジンガーとはごみ山のこの一画の通称で、「エビ塚」を意味する。そこには、ムンバイの食肉処理場や広大な港湾地区から出るごみが廃棄される。その日の午後、ファルザーナーは妹のファルハーとともに、足場の悪い坂道をくねくねと登ってくるごみ収集車を追って、そこまで来たのだ。
ファルザーナーは大きな袋を引きずりながら素早く手を動かし、そのトラックからばらまかれたガラスびんやそのかけら、生理食塩水バッグを袋に入れていった。トラックは病院から来たらしい。病院のごみは高く売れる。やがて彼女のまわりのあちこちに人が集まり、やはりガラスを探し始める。だが一七歳のファルザーナーは、背が高く、運動神経がよく、怖れを知らない。その目は、ペットボトルや電線、ガラス、洋銀(器具や機械によく使われる合金)、端切を見つけるのに慣れている。ほかの人が手を伸ばすよりも先に、目的のものを拾い上げていく。
ふと目を上げて、ファルハーが近くでごみを拾っているのを確認する。もうそろそろ、父親が弁当を持ってやって来る時間だ。そう思いながら、またごみの山にフォークを突っ込む。すると、重みのある青いビニール袋が出てきた。きっとなかに、小さなガラスびんがいっぱい入っているに違いない。そういうものはたいてい高く売れる。ハエがたかる生温かい斜面にしゃがみ、袋のひもをほどき、そっと袋をひっくり返す。だが、繊細なガラスびんが太陽の光をきらめかせ、カチカチと音をたてながらこぼれ出てくるものと思っていたのに、実際には一個の大きなガラスびんがごとりと落ちてきただけだった。身をかがめ、何が入っているのかを確かめてみると、腕や脚、つま先、はげた小さな頭が水のなかでからまり合っているように見える。眉根を寄せてもう一度よく見て、思わず悲鳴をあげた。まわりにいた友人が集まってきて、手足が詰め込まれたびんをじろじろ眺める。
ファルザーナーはふたを開け、中身を取り出してみた。彼女の骨ばった大きな手のひらより少し大きいだけの、女の赤ん坊だ。市街地からはほかの消耗品と一緒に、死んだ赤ん坊(たいていは女児)が定期的にこのごみ山に送られてくる。女児を産んだことを家族に告げられず、生まれたばかりの子どもをごみ箱に捨ててしまう母親がいるのだ。くず拾いをしていると、そんな子どもを掘り当てることがときどきある。だが今回は違った。ファルザーナーが女児を引っ張り出すと、二人の男の赤ん坊も一緒に出てきた。腹の部分が、女の赤ん坊とつながっている。きっとこの三人は、そのままでも別々に切り離されても生きていけず、一緒に死んだのだろう。ファルハーもこんなことを口にした。月食があると子宮内の胎児が分裂したり奇形になったりするという話を聞いたことがある。この赤ん坊も三つ子として生まれるはずだったんだよ、と。
ファルザーナーは両腕を伸ばし、死んだ赤ん坊をあやすような仕草をした。そしてそっと抱きかかえると、崩れやすい斜面を慎重な足取りで下りていった。その背後には、揺れ動く廃船のような山がそびえている。ムンバイから出る廃棄物でつくられ、泥をかけて固められた山だ。
友人たちもそのあとを追ってきたので、ファルザーナーは一緒に隣のごみの頂に向かった。その頂から眺めると、ごみの山は少しカーブしながら、めまいがするほど遠くまで延びている。この山は全体として見ると、三日月のように長い弧を描いている。その弧の内側をえぐるように、ごみでつくった家が並び、三日月の外縁に沿って、入り江がきらきらと輝いている。この入り江はアラビア海につながり、いくつもの島から成るムンバイ市の一画を縁取っている。ファルザーナーのようなくず拾いは、このごみ山を「カーディー(khaadi)」と呼ぶ。ヒンディー語で「入り江」という意味だ。なぜそう呼ばれるようになったのかは誰にもわからないが、高みからこの山を見下ろすと、悪臭を放ちながらうねるこのごみの流れの上に自分が浮いているような気になる。その流れはまるで、はるか遠くにかすかに輝く、無限に広がる青い海へとつながっているかのようだ。ファルザーナーは、盛り上がっては沈み込むごみ山をさらに歩いていった。
やがて入り江のそばまで来ると、ごみ山の斜面が水路になだれ込む手前にある柔らかい砂地に、友人たちがごみ収集用のフォークで穴を掘り始めた。すると周囲の家から、くず拾いが数人出てきた。その家は、支柱の上に建てられている。干潮時にはごみの上で暮らせるように、満潮時には波をかぶらないようにするためだ。彼らはそばまで来て赤ん坊を目にすると、ファルザーナーの友人たちが穴を掘るのを手伝った。潮は満ちつつあり、優しい波が少しずつ近づいている。破れた布やビニール袋が水のなかを漂ったり、マングローブ林の枝にぶら下がったりしている。入り江のほうからそよ風が吹き抜け、古木の枝に茂った葉やそこにからまったビニールがカサカサと音を立て、ファルザーナーの服がはためいた。
穴ができあがると、この浅い墓に赤ん坊を寝かせた。友人たちがその亡骸を砂で覆い、祈りの言葉をささやく。ファルザーナーはよく友人と連れ立って午後遅くにここへ来て、満ち潮のなかを歩いたり泳いだりした。悪臭のするこの山の向こうに夕日が沈むまで、ここにいるのが好きだった。その時間には、周囲がくすんだピンク色に輝き、波がメタリックな光沢を帯びる。この山がいちばんきれいに見える瞬間だ。
その後、ごみの頂をいくつも超えて急いで元の場所に戻ると、父親が腹をすかせて待っていた。人気のない斜面に立っていたひょろりと背の高いハイダル・アリ・シェイクは、娘たちの姿を見つけると、たばこのやにで黄ばんだ歯を見せて顔をほころばせた。娘二人と父親は一緒に座って食事をした。娘は二人とも、サルワール・カミーズ〔南アジアの民族衣装〕の上に綿の上着を羽織り、泥やごみで衣服が汚れないようにしていた。緩く束ねた長い髪はスカーフで覆っていたが、収まりきらない髪の房がいくつかはみ出している。ファルザーナーは思春期らしく神経質で無口だったが、一五歳のファルハーは、まだ幼さの抜けない顔に絶えず笑みを浮かべ、父親が家から持ってきた弁当を食べながら、さきほどの冒険について話をした。すると父親は、珍しく素っ気ない態度で、二度とその墓場のそばへは行かないよう二人に注意した。「ああいうのはつきまとって離れなくなるからな(Ye sab cheez chhodta nahi hai)」
つづく
目次
序
1 ファルザーナー
2 最初の住民
3 子どもたち
4 管理不能
5 壁
6 ギャング
7 不運
8 火災
9 裁判
10 立入禁止
11 傷
12 シャイターン
13 十八歳
14 闇ビジネス
15 理想
16 惨事
17 ナディーム
18 約束
19 カネ
20 選挙
21 オーカー判事
22 結婚
23 変化
24 延命
25 大丈夫
あとがき
謝辞
原注
著者略歴
ソーミャ・ロイ〈Saumya Roy〉
ムンバイを拠点とするジャーナリストで活動家。2010年、ムンバイの最も貧しい零細企業家の生活を支援するヴァンダナ財団を共同設立し、デオナールに依存するコミュニティに出会う。『フォーブス・インディア』『ウォール・ストリート・ジャーナル』『ブルームバーグ』などに寄稿。アジア最大のスラム街に関するエッセイ集Dharavi: The Cities Within (HarperCollins, 2013)にも原稿を寄せている。
訳者略歴
山田美明〈やまだ・よしあき〉
英語・フランス語翻訳家。訳書にエマニュエル・サエズ+ガブリエル・ズックマン『つくられた格差――不公平税制が生んだ所得の不平等』(光文社)、ジョセフ・E・スティグリッツ『スティグリッツ PROGRESSIVE CAPITALISM』(東洋経済新報社)、トム・バージェス『喰い尽くされるアフリカ――欧米の資源略奪システムを中国が乗っ取る日』(集英社)、『ホロコースト最年少生存者たち――100人の物語からたどるその後の生活』(柏書房)、他多数。
