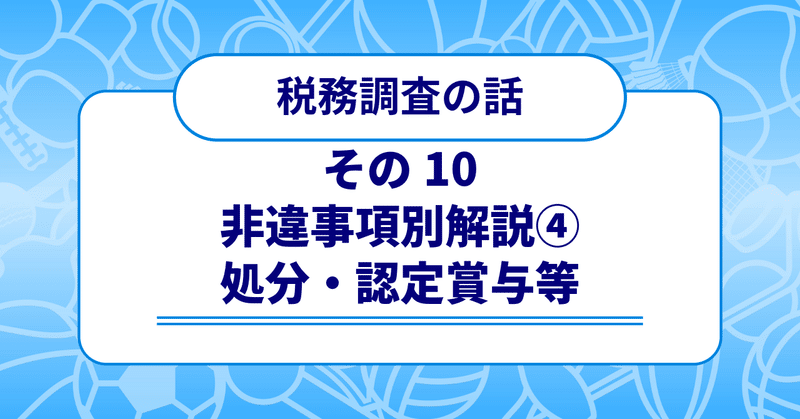
税務調査の話 その10 〜非違事項別解説④ 処分・認定賞与等〜
元国税職員による税務調査のあれこれ。前回に引き続き非違事項(誤りや不正による要是正項目)別の解説をしていきます。今回は、少し毛色の異なる処分について取り上げます。
これまでの記事(税務調査の話その○)
処分とは
会計では、複式簿記を前提にしていますので、期末の売上の計上漏れを修正すると、その相手勘定である売掛金の修正も必要となります。仕訳で書くと次のとおりです。
(借)売掛金 xx (貸)売上 xx
税務上は、複式簿記を明示的に取り扱いませんが、同じような考え方をとります。
売上計上漏れの処分は何ですか?
といったら、
売掛金として社内留保している
という言い方をします。
※本連載では、詳細な税務処理や申告書別表の書き方を取り扱いませんので、厳密な記載はしておりません。
では、売掛金を回収したものの、そのお金が会社の外に出て行ってしまったら、どうなるでしょうか。税務上の仕訳で書くと次のとおりです。
(借)社外流出 xx (貸)売上 xx
会社内に留保されていないので、処分は社外流出となります。
このように、一般的に、処分は、(社内)留保か(社外)流出のどちらかとなります。
社外流出
社外流出は、さらに認定賞与とその他の社外流出に分かれます。
(1) 認定賞与
例えば、売上除外により捻出したお金を、会社の役員が遊興費等の個人的なものに使い込んでいた場合、会社が役員に賞与を支給したと考えます。これを認定賞与といいます。仕訳で書くと次のとおりです。
(借)認定賞与 xx (貸)売上 xx
法人税法上、役員賞与は損金に算入されませんので、修正申告等により、除外した分の売上だけ課税所得が増えます。
なぜ認定賞与なんて考え方をするかというと、賞与を支給された役員の給与所得となるからです。すなわち、会社に源泉所得税を課税することになります。
こうして、法人税と源泉所得税をダブルで課税できるため、税務調査では、処分が認定賞与になるかどうかをかなり重視します。会社側から見ると、俗にダブルパンチや往復ビンタと言われます。
(2) その他の社外流出
売上を除外したが、そのお金は役員が個人的に使っていない…けれども、会社にはもうないといった場合に、その他の社外流出とされます。仕訳で書くと次のとおりです。
(借)その他の社外流出 xx (貸)売上 xx
どこに行ったか分からないなんてことがあるのかという疑問があるかと思います。税務署が認定賞与を立証できない場合にこのような処理となることが多いです。いわゆる使途不明金として扱われます。
法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭でその費途が明らかでないものは、損金の額に算入しない。
ここで注意が必要なのは、使途不明金は、使途秘匿金ではないということです。
使途秘匿金は、さらにその支出額の40%の法人税が別途課税されます。
使途秘匿金課税は、認定賞与よりも重い課税となることが多く、ゼネコンに裏金として上納しているなどの事実を税務署が掴んでいる場合でないと認定されません。税務署が事実を確認できない場合は、やはり使途不明金としてその他の社外流出となります。
おわりに
今回は調査方法の解説ではなかったので、少しとっつきにくかったかもしれません。ただ、税務調査では必須の知識なので記事にしました。次回もお楽しみに!
お仕事のご依頼はこちらまで
最後までお読みいただきありがとうございます😊少しでもお役に立ったらスキ(❤️)していただけると嬉しいです。note会員でなくても押せます。
