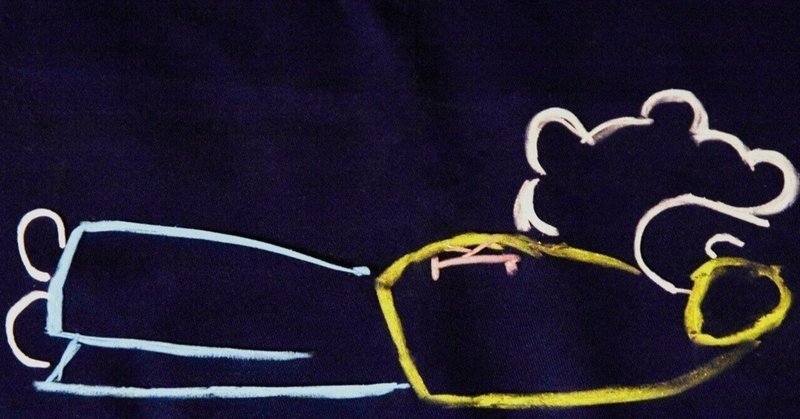
斎藤幸平とセドラチェクの対談から思ったこと
NHK「欲望の資本主義2022」をご覧になられたでしょうか。
正月早々NHKでこのような興味深いドキュメンタリーが観れるのは本当に良いことだ。特に今回印象に残ったのは今絶賛人気上昇中の斎藤氏とセドラチェク氏の対談である。日本の番組ではまれに見る、熾烈な対談であったが、自分の感想を端的に言えば、この二人、結局目指す方向は同じなのだが、両者のバイアスによって、その議論は対立的なものになっていたという感じだ。
まず、自分の家族と国家が社会主義政権を経験したセドラチェク氏は、斎藤氏が執拗に「コミュニズム」にこだわることに対して違和感を示していた。確かに、社会主義というワードの歴史的文脈を考えた時、社会主義政権による抑圧的歴史を経験したことのない(もちろんその歴史については斎藤氏も知っているであろう)斎藤氏が社会主義に対してアレルギーがないことは言うまでもない。その代わりに、斎藤氏は「ネオリベラリズム」というワードに対して日本的文脈に基づくバイアスがあるように思われる。斎藤氏の対談を聞く限り、ネオリベラリズム資本主義とマルクス的な「悲観的資本主義の現実」を合体させたような資本主義像を思い描く。それは、セドラチェク氏が考える資本主義とは異なる、ある種の「悪な存在」としての資本主義であった。そのような意味において、両者は議論の前提的認識に対して共通する認識を持てていなかったように思える。
それ以外にも、セドラチェク氏からはやはり一種の西欧中心主義的な思想を感じさせる。特に、資本主義を生み出した西欧が今行っている資本主義に対する改革がもたらす新たな資本主義像に対する期待が窺える。それは根本的には、前期マルクスが抱いていた進歩史観的西欧中心主義に似ている。もちろん、西欧の資本主義が現状のシステム的問題に対してなんらかの新しい解決策を提示できるような新たな資本主義を提示しているのはその通りである。例えば、スカンジナビア諸国の社会民主主義がそれである。しかし、それが東アジア、アメリカやその他の民主主義社会、日民主主義社会の資本主義に対応できるかはまた別の話である。
最後に、これらのバイアスと前提認識の共有ミスを除いて、セドラチェク氏と斎藤氏の一番大きな違いはやはりどの程度「ラディカル」に変化をもたらすかにあると個人的には思う。両者はともに脱成長を通して資本主義を見直そうとする。セドラチェク氏は「脱成長的」資本主義という形で、資本主義の内部から問題を解決しようという現実的な視点を用いる。他方、斎藤氏はその資本主義システム自体を破壊し、「脱成長コミュニズム」という新たなシステムを立ち上げることを提唱する。
両者が目指すものは同じだ。その最大の違いは理想主義か現実主義かの違いである。その中間ぐらいが丁度いいのではと自分は思った。
読んでくださいましてありがとうございます! もし「面白かった!」や「為になったよ!」と感じたら、少しでもサポートして頂けると幸いです。 他のクリエーターのサポートや今後の活動費に使わせて頂きます。何卒よろしくお願いします。
