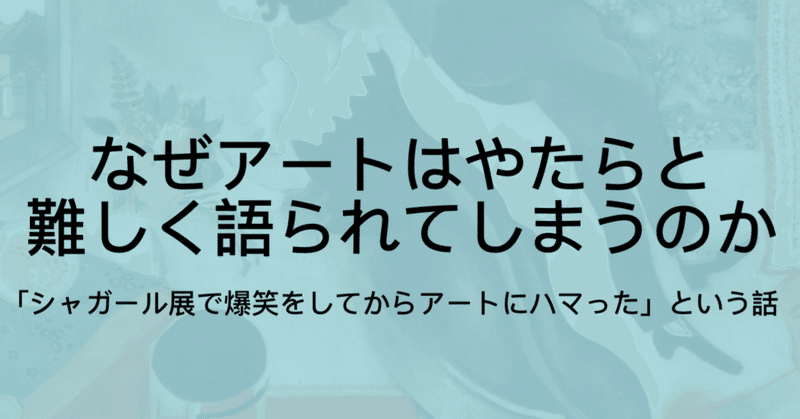
「アートはもっと爆笑しながら学ぶものだ」という持論
「アートは学問の1つであり高尚なものだ」
そんなイメージは世界共通のものだろう。基本的に美術館は重々しい静寂に包まれており、皆マジマジと作品を見ている。アートはけっこう重いテーマなんですよね。
西洋美術史のなかでも長らく王家や教会だけが楽しむハイカルチャーだった。また「学問」として成り立ち、さらに作品の単価はマンガやアニメの数百倍だ。
そのこともあって、日本でもいまだ「アートは高尚な趣味」みたいなイメージが固まっているんだろう。それも素晴らしいと思う。アートがやたらめったら消費されないためにも重要なことだろう。
しかし、ほとんどのアート系コンテンツは、めっちゃむずい。難しすぎる。記事も、YouTube動画も、ラジオも、なぜかわざわざ難解に説明している。それは暗黙の了解的に「アートは高尚に語らねばならない」というイメージがあるからだ。
このハードルの高さが、どこかアートファンの門戸を閉ざしているのも確かだ。「アート知りたいけど、なんか専門用語ばっかでむずいわ。どっからディグればいいのかわからん」と思う人も少なからずいる。
だからこそ私は普段から、できるだけおもしろおかしく書くことを考えている。「深さ」はもちろん大事なので、長文にはなってしまうが、アートって実はもっと気軽でいいと思うのだ。
つまり、マンガやアニメくらい、笑いながら簡単で気楽に学べるものでいいと思うのだ。もはや「学び」というより「遊び」くらいに考えていい。
そこで今回は私がおすすめする「アート入門のやり方」と、コンテンツのポリシーについて紹介させていただきたい。
「どうやってアートを学べばいいかわからない」「これからもっとアートを楽しみたい」という方はぜひ読んでみてください
私がアートに興味を持った日
人生ではじめてアートに興味を持ったときのことは、めっちゃ覚えている。福岡アジア美術館のシャガール展を観たのがきっかけだった。当時は14歳。小説を書いたり、バンド活動をしたりと、なんとなくアーティストに興味があった時期ですが、なんか尖ってました。
ちなみに当時通っていた博多区の中学校はガラが悪いことで有名。御多分に洩れず私もマンガ「WORST」に憧れていたので、ダボダボのTシャツに巨大な金のネックレス、パンツ見せるレベルの腰パン(死語)で美術館に行った。
シャガール展の冒頭には、美術館と主催者からの挨拶があり、親がその言葉を熱心に読んでいるのを観て「この説明のなにがおもしろいっちゃろ?」と思いながら先に進んだ。
最初のスペースにはシャガールの初期デッサン類が並び、シャガールが影響を受けた作品群が並ぶ。隣には専門用語満載の説明があり「ユダヤ人てなんや。どこ中や」と、正直くそつまらなかった。
しかしさらに進んで代表作の「誕生日」を観たときに声出して笑ってしまい、両親に怒られたのを覚えている。当時はこの絵を見て「え? なんこれスピード感やばい」と思ったのだ。

マルク・シャガール「誕生日」
「え、何やこのおっさんの跳躍力。衝撃のバックステップでキスしてるやん。首が速すぎて身体置いていってるやん。女性も不意つかれすぎて引いとるがな……で、『誕生日』てどういうこと? 『おめでとう』とは言えんやろこの状況。顔面蒼白やしこれ」
……とまぁ死ぬほどウケたわけだ。当時好きだったボーボボのギャグにしか見えなかった。ツッコミどころしかないわけである。
それで「シャガールはおもろい」と認識して、彼の人生を図書館で調べる。すると「ピカソと喧嘩した」みたいなエピソードが分かった。
「ピカソってあのピカソやんな」と思って、画集を見てみると「アヴィニョンの娘たち」があった。

パブロ・ピカソ「アヴィニョンの娘たちにむ
「おい〜こいつもふざけとるやんか〜。横2人が顔面ライオンキングやないか〜」と図書館で吹き出ししまったのは、もう言うまでもない。
で、ピカソも調べると、この作品はキュビスムによって作られたことがわかった。キュビスムを調べていくと、ジョルジュ・ブラックという後輩が引き継いだことを知る……といった具合にシャガール展で爆笑してから、美術のおもしろさに気づいていくわけである。
またシャガールやピカソ以外の風景画家などは、作品自体ではツッコミどころが少ない。そこで「なんで書こうと思ったんや?」と考えて調べてみるとおもしろかった。
印象派は「世間で評価されんかったから、もう俺らで勝手に展示会開こうや」と思っていたことがわかる。「いやこいつらパンクすぎるやろ」と考えると、なんかすんごい楽しかった。
でも「黒は使っちゃダメな」とかルールガチガチだったことを知って「いやお前らも規制だらけなんかいおい。どないやねん」とさらに笑えた。
アートにツッコんでいくという楽しみ方
もし「アートをもっと知りたいけど、何から始めればいいかわからない」という方は「アートは高尚なものである」というフィルターを外してみてほしい。そしてアニメやマンガくらいのレベルまでハードルを下げてみてください。
すると、美術はけっこう笑えるものだ。私は今でも美術館でけっこうクスクスやっている。
先述した通り、印象派はパンクバンドやし、ダリはメンヘラナルシストだし、ゴッホは弟のヒモだ。そんな感じで、おもしろおかしく捉えたほうがアートっておもしろいはずである。
そこから興味が湧いて、調べてみるとアーティストが作品に込めた想いなどが見えてくるだろう。そんな想いを知って「他の作品も見てみよう」と掘っていくうちに、いつのまにかアートの知識は増えているに違いない。すると美術館での見方もより深くなるのです。
「アートをおもしろく解説するYouTubeチャンネル」をはじめます
ただし、この見方はあくまで私自身の持論です。ハイカルチャー勢からは批判もあると思う。もちろん前提としてアーティストたちにリスペクトがあるからこそ、美術館に足を運んでいるわけだ。もちろん馬鹿にしているなんて滅相もない。
あくまで私はアートをおもしろおかしく受け入れてツッコむことから興味を持って、遂には大学でカルチャーを学び、美術検定を取るまで好きになった。
ですのでnoteの美術マガジンでは、他のメディアよりも数段おもしろおかしく書いているつもりだ。ただし学びがないとつまらないので「深く書く」という点は必ず意識している。
そして、これは後追いになると嫌なので先に書くが、今年の秋ごろからYouTubeもはじめます。もちろんnoteの毎日更新は続けますのでよろしくお願いします。
YouTubeのテーマは「アートはウケる」ということ。同じく美術館に行って2人で笑い転げている友だちと一緒に作者、作品、流派などを観ながら、ツッコんでいくのがコンセプトです。もちろんYouTubeでも「深く解説する」という点は変わりません。
もしチャンネルを開設した際には、ぜひ寝る前にでも観ていただきたい。そしてアドバイスをください(切実)。一緒に「笑いながらアートを学べるYouTubeチャンネル」に育ててもらえたら、大喜びします。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
