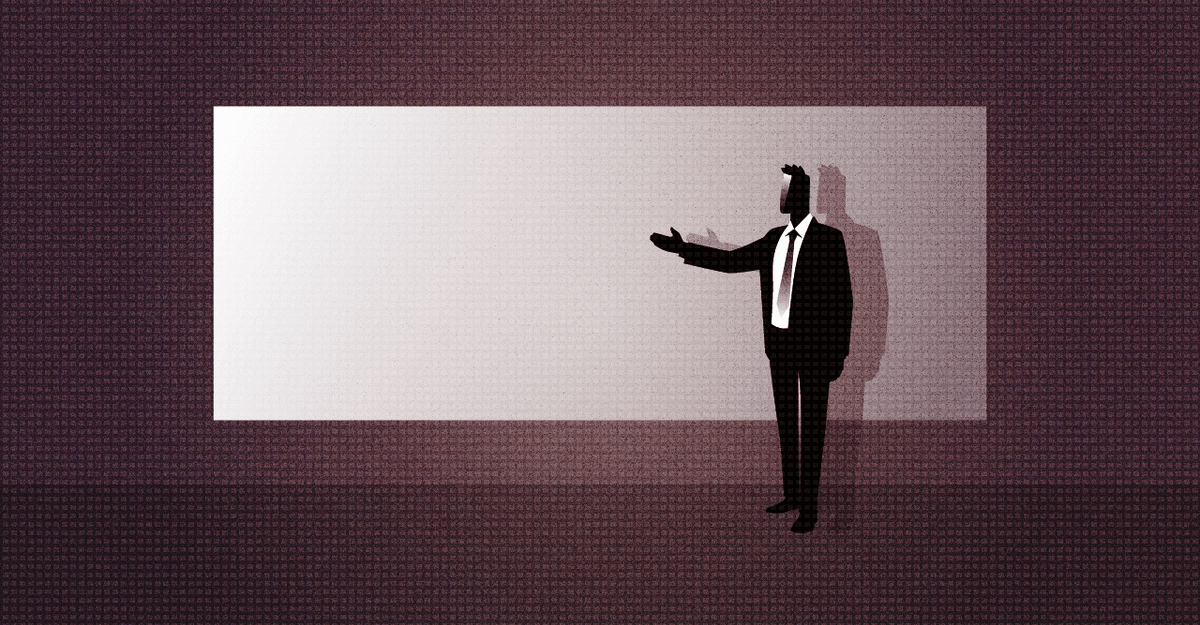
問いをうまく伝える方法~問いのデザインを読んで③~
こんにちは。じゃこです。
今日は、問いのデザインを読んで学んだことを書いていこうと思います。
②はこちら↓
教師などの仕事で大事なのは、興味を持たせるような、子どもの思考を広げるような、すなわち、問いをもたせるように問いを発することです。
問いを発する人にとって大事なスキルの一つとして、説明力が挙げられます。相手にとって必要な情報を分かりやすく伝達する力のことです。
教師は授業全体をデザインし、その中で子どもたちに考えさせるよう(この授業のねらいに迫るよう)に問いを発します。
問いを発しても、子どもたちが理解できないような難易度や、本質に迫っていないもの、すぐ答えられるものは子どもたちの成長につながらないので意味を成しません。きちんと伝えるためには問いの意図というのをうまく伝える必要が有ります。
では、この「問いの意図」をうまく伝えるためにはどうすればいいでしょうか。
問いをうまく伝えるためのポイント
ポイントとしては、3つあります。
一つ目は、問いの焦点を明確に伝えることが必要です。
たとえば、「あなたがこれまで経験した居心地が良かった場はどんな場ですか?具体的な事例を挙げながら、共通する要素について話し合ってください」と投げかければ、参加者にとって問いの探索の対称と制約は明確になり、思考や対話が焦点化されるでしょう。
ところが、「居心地良かった場の経験は?」と曖昧な表現で投げかけてしまえば、問いの意図は伝わらないかもしれません。
二つ目は、問いに記述されていない背景の意図を伝えることです。
この問いを設定した自分の意図や、課題とのつながりを一言添えるだけで、問いに文脈が生まれ、参加者(学校だったら、学級集団の子どもたち)にとって問いが考えやすくなったり、試行錯誤がしやすくなったりすることがあります。
三つ目は、その前の問いとのつながりについて補足することです。
特に「足場の問い」(課題解決のために必要な準備の問い)を活用した場合には、つながりを説明しないと、前の問いで考えたことが、次の問いに活かされない場合も少なくありません。
教師が授業中に問いを発するときは、問いは問いと考え、あまり流れを意識しないかもしれません。いや、流れを意識しないというよりは授業の流れの一部として問いが組み込まれている感じです。
教師は授業の流れは分かって、「ここはこの問い」、「次はこれだな」と意識して問いを発していますが、子どもたちにとっては唐突に出されたものでしかありません。問いの内容が理解できていない場合があれば、前の問いや、そこまでの流れを伝えてもいいかもしれませんね。
【問いをうまく伝えるためのポイント】
1.問いの焦点を明確に伝える
2.問いに記述されていない背景の意図を伝える
3.その前の問いとのつながりについて補足する
問いに惹きつけるポイント
一つ目は、好奇心に基づく「注意」を引くことです。参加者にとって「面白そうだ」「考えてみたい」と思えるような、興味や関心を刺激することで、注意を引くことが出来ます。
二つ目は、参加者自身との関連性を意識させることです。人間は、どんなによく練られた問いであっても、自分とは関係ないと思えば、前向きには慣れません。自分自身の実体験を振り返れば考えられるかもしれない、自分の日常生活に役立つかもしれないと思える補足をすることで、動機づけることが可能です。
【問いに惹きつけるポイント】
1.好奇心に基づく注意を引く
2.参加者自身との関連性を意識させる
パワポなどのスライド資料を投影しながら進行する場合には、スライドのデザインも説明力に含まれます。
考え続けてほしい問いをスライドに明確に表示し、また同時に意識してほしい問いの背景や、注意点なども簡潔に示しておくと、相手方(参加者)は迷子にならずに済むでしょう。
以上、学んだことでした~
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
