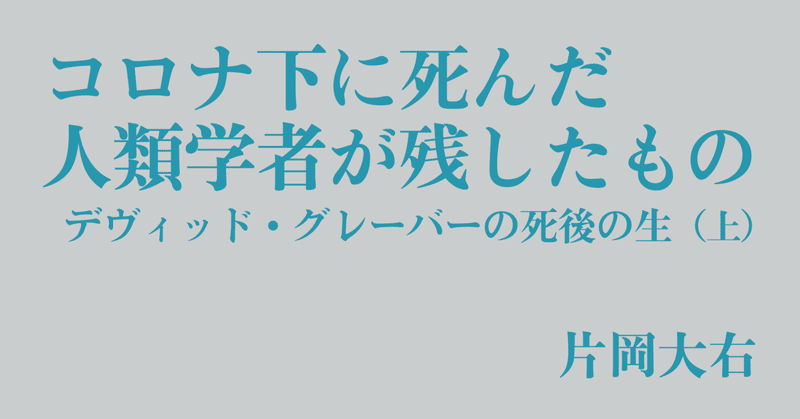
コロナ下に死んだ人類学者が残したもの デヴィッド・グレーバーの死後の生(上)|片岡大右
新型コロナ感染症が世界で大流行し、わたしたちの暮らしを支えるエッセンシャル・ワーカーの仕事に注目が集まった2020年の夏、人類学者デヴィッド・グレーバーの『ブルシット・ジョブ』が日本で刊行され、多くの読者に読まれることとなりました。ですが、その日本語版刊行から1か月あまり後、59歳のグレーバーは突然の病によりこの世界から旅立ってしまいます。「アナキスト人類学」と題した本もあるグレーバーのアナキストとしてのあり方について、「長い呪いのあとで小山田圭吾と出会いなおす」が話題を呼んだ批評家の片岡大右さんにご寄稿いただきました。(編集部)
1 『ブルシット・ジョブ』への称賛と批判
1-1『ブルシット・ジョブ』の反響
デヴィッド・グレーバーの思いがけない死(2020年9月2日)から、早くも2年が過ぎた。日本ではとりわけ、秋口の急逝に先立つ2020年春から夏にかけ、この英国在住の米国人人類学者に対する関心が比較的小規模なサークルの外に広がりつつあっただけに、急逝の知らせはいっそうの衝撃をもって迎えられたと言えるだろう。
この年の4月、コンパクトながら創意に満ちた初期の民主主義論『民主主義の非西洋起源について――「あいだ」の空間の民主主義』の日本語版(片岡大右訳、以文社)が刊行されるとともにパンデミック下の最新の発言が紹介されるなど(これやこれ)、彼の仕事にこれまで以上の注目が集まるなか、同年7月末に国際的ベストセラー『ブルシット・ジョブ』の待望の翻訳が刊行された(酒井隆史ほか訳、岩波書店)。
2013年夏に発表されたちまち世界中にセンセーションを引き起こした小論「ブルシット・ジョブ現象について」のアイディアを膨らませたこの著作については、2018年5月の原著刊行まもなく、いくつかの記事により日本でもその主張の一端が先行紹介された[1]。日本語訳刊行に先立ち、こうした紹介の試みがすでに幅広い層にインパクトを与えていた事実は、2020年秋のテレビアニメ化と2021年冬の劇場版公開を経ていまや『鬼滅の刃』以後最も注目を集めるマンガ作品のひとつとなった芥見下々『呪術廻戦』が、『週刊少年ジャンプ』2018年10月22日号(No.45)掲載の第30話において早くも、登場人物のひとりに明らかにグレーバーの議論を踏まえた発言をさせていることからも察せられるだろう。「ナナミン」こと七海建人は、呪術高専を出たのち金融業界に職を得たものの、「正直私がいなくても誰も困りません」と感じるほかない業務内容の空虚さに失望し、街のパン屋のように人びとの生活を直接支えられたらと願って、自らの命を危険に晒しながらも社会の安全に寄与できる呪術師の仕事に戻ったのだった[2]。
「クソどうでもいい仕事」(ブルシット・ジョブ)、すなわち収入面の安定にもかかわらず社会的な意義を認めがたく「やりがい」が感じられない仕事の存在に光を当てるグレーバーの理論は、21世紀の労働をめぐる議論に重要な一次元を付け加えた。「ワーキング・プア」や「ブラック企業」だけが問題なのではない。生活上の苦境にあるわけではない人びとの少なからずもまた、彼らなりの不幸を抱え、解放の契機を夢想しているかもしれないのだ。
相対的に見て恵まれた層を蝕む魂の空虚に注目し、彼らのために(も)論述をなすという『ブルシット・ジョブ』の企ては、彼自身が2011年に深く関与した〈オキュパイ・ウォールストリート〉に際して、活動家たちがこの金融街の勤務者たちと交わした対話から発想を得ている。トレーダーたちはそこで、「自分は世界になにも積極的な貢献なんてしてないし、システムは腐ってる」と認め、ニューヨークで年収10万ドル以下で暮らせる手段を教えてもらえるならすぐにも今の仕事を辞めてやるなどと打ち明けたのだという(第6章)。
そうであるなら、問題は、相対的に安定していながらも無意味と感じられる仕事に従事する人びとと、それなしでは社会が回らないにもかかわらず多くは(医師のような例外を除き)相対的に低処遇の各種の仕事――とりわけキツい肉体労働をグレーバーは「クソ仕事」(シット・ジョブ)と呼ぶ――をひとつの社会の内部に共存させているメカニズム、そうして社会の大多数を多少とも不幸に追いやっているこの構造それ自体を克服することだ。
1-2 「実証的批判」が思い出させてくれること
内外で大きな反響を得たために忘れられがちなことかもしれないけれど、グレーバーのこうした着想は相当程度に常識破りのものだった。最近、その事実を思い出させてくれたのは、英国の3人の研究者が労働社会学の専門誌に掲載した論文だ。「疎外はブルシットではない――グレーバーのブルシット・ジョブ理論の実証的批判」と題されたこの論文は、英誌『エコノミスト』(2021年6月5日号)で紹介されるなど大学外でも話題になった。
そこで著者たちは、グレーバーのエッセイ「ブルシット・ジョブ現象について」の大反響を受けてなされた英企業の世論調査(あなたの仕事は「世の中に意味のある貢献をしていますか」という質問に、英国の労働者の37%が「していない」と答えた)は項目設定に予断が含まれており信用ならないこと、書籍版『ブルシット・ジョブ』で質的分析のために用いられたデータは、最初のエッセイの直観を支持する人びとの証言である以上、「自己選択バイアス」に侵されていることを指摘する。そして既存の大規模な調査(欧州労働条件調査:EWCS)と照らし合わせることで、グレーバーの主張の多くを退けてしまう。
既存の調査から著者たちが引き出してくる結論は――当然ながら――いたって常識的なものだ。金融業界を含む高学歴の頭脳労働に従事する者は、多くの肉体労働従事者よりも、自分の仕事を無意味だと感じる度合いが低い――要するに、グレーバーの説はまったく転倒しているのだという。自分の仕事が無意味だと感じられる時の苦しみに注目するという彼の着眼点は正しくても、そのような苦しみは多くの場合、高処遇でありながら「クソどうでもいい(ブルシット)」とされる仕事ではなく、裁量の余地に乏しい単純労働に従事する人びとをこそ襲っている。問題は働く人びとに裁量の余地を与え自律性を高めることであって、そのためにはグレーバーの転倒した理論装置ではなくマルクスの「疎外」概念に基づくアプローチのほうがはるかに有効なはずだと著者たちは説く。この論文が「疎外はブルシットではない」(つまりどうでもよい問題ではない)と題されている所以だ。
あえてマルクス主義的概念に立ち返るという選択への好みはさておき、著者たちの主張は全体として、誰も驚かすことのない常識的なものであることがわかる。人びとが一般に、よい学歴を得て実入りのよい職種に就き、そこでの業務が多くの裁量をもって自分の能力を活かせるものであることを――「疎外」ができるだけ少ないことを――願うというのは自明のことであって、大規模な量的調査を踏まえた穏当な提言を待つまでもない。そしてもしも業務が退屈極まりないものであったとしても、ホワイトカラーからブルーカラーに転職するようなケースは例外的だろう。グレーバー自身、「意味のない中間管理職の立場を棄てて溝の掘削仕事に就く人間は、たとえ溝が本当に必要とされているとわかっていたとしても少数である」と認めている(『ブルシット・ジョブ』第1章)。
けれども、労働をめぐるこの常識的感覚には、何かスッキリしないものが残る。ほんとうにそれでいいのだろうかという思いが、少なからずの人びとにつきまとう。グレーバーの著書の成功は、労働をめぐるこの常識的感覚と共存しながらそれと緊張関係を構成する別の感覚に光を当てたこと、誰もの心に折りに触れ浮かびながらも真正面から検討されることのなかった何かを、公共の議論の場に鮮やかに浮上させたことに起因すると言うべきだろう。
2021年10月、季刊誌『tattva』第3号(ブートレグ)は「はたらきがい」を特集し、グレーバーとブライアン・イーノの2014年の公開対談の翻訳を掲載した(「クソどうでもよくない仕事を求めて」片岡大右訳)。そこでグレーバーが打ち明けているブルシット・ジョブ理論の着想の経緯は、この観点からすると興味深い。彼は「年がら年中パーティーをしているような人びと」――高処遇のビジネスパーソンや法律家といった人びとだろう――に会うたび、歓談のなかで仕事の内容を尋ねてきた。最初は言い渋る相手が、「何度も尋ねてちょっとお酒が入ると」、例えばこんな風に答えることがよくあったのだという。「えーと私はこういう仕事についているけど、実際には何もしていないんだよ」、「上司には言わないでくれよ、でもこんな仕事は簡単に自動化できるだろうね」……。
こうした人びとが、欧州労働条件調査の面接のような場で同じ率直さを発揮したとは想像し難い。同じように、低処遇で裁量の余地にも乏しいが誰かがやらなければ世の中が回らない仕事に就いている人びとは、内心自分の仕事の必要不可欠な有用性に思いを致すことがあったしても、それをつねに表立って口にできる心境にあるとは限らないだろう。その意味で、グレーバーの論点に既存の量的調査の結果と噛み合わないところがあるのは、当たり前のことという印象を受ける。彼はまさしく、従来の調査では口にされてこなかったような内心の声に耳を澄まし、誰もが表立って語れるようにしようと試みたのだから。
1-3 内なる「ナナミン」
グレーバーの直観のたしかさは、2013年のエッセイと2018年の書籍の大きな反響によって証明されてきた。けれども、惑星規模のパンデミックを想定することなく書かれた彼の議論は、ポストコロナの世界における「エッセンシャル・ワーク」の重要性の再発見によって、いっそうその先見性を明らかにしたと言えるだろう。
ブレイディみかこは2020年初夏に発表されたエッセイで英国の最初のロックダウン下の状況を語りながら、「社会において尊敬されるべきなのは「ブルシット・ジョブ」ではなく、報われない本物のクソ仕事をしてきた「ケア階級」だという価値観の転換」を報告している(「ロックダウンのポリティクス」、『ブロークン・ブリテンに聞け』講談社、2020年所収)。そこには慎重に、「一時的なもので終わる可能性もあるが」との留保が添えられていたが、実際、2021年のエッセイでブレイディは、最初のロックダウン時に英国中の通りを賑わせた拍手運動――毎週木曜日の夜8時、人びとは医療関係者ほかキー・ワーカーに拍手を送り、感謝と激励の思いを伝えた――が、およそ1年後の3回目のロックダウン時にはまったく盛り上がりを見せなかったことを報告している(「一年ひと昔」、『ヨーロッパ・コーリング・リターンズ』岩波現代文庫、2021年所収)。
しかしそれでも、ロックダウンや自粛生活の日々が遠く過ぎ去ったのちにも、そこで鮮やかに意識されたものが完全に消えてしまうことなく、少しずつ人びとの生活を変えていく力となることはありうる。ブレイディみかこは2020年初夏の別のエッセイで、拍手運動がいつまでも続くものではないだろうと見定めつつも子どもたちの記憶に期待を託して、「価値観のシフトは今すぐ起こらないにしても、その種は確実に未来の世代の中に撒かれている」と記した(「続けた拍手、未来のため」同書所収)。
さらに言うなら、グレーバーの著作のコロナ以前からの成功が示しているように、こうした価値観はパンデミックによって突如もたらされたものではなく、人びとのうちにつねに潜在してきたものであるはずだ。この観点からすると、先ほど言及した『呪術廻戦』における七海建人の人物造形とそれが多くの読者と視聴者の心を捉えたという事実は、改めて注目に値するだろう。七海は金融業界を去ったのちもスーツを着込んで呪術師の活動を行うのであり、企業人の価値観と習慣のすべてを捨て去ったのではない。極限的な危機に直面して、「やり甲斐なんて曖昧な理由」で命がけの仕事に戻った自らの決断を訝しみもする(第120話)。そんな彼はそれでも、勤め人時代に、人びとの命と生活を直接支える仕事に惹かれることができた。
大衆的フィクションが2018年にこのようなエピソードを描いていたことを思えば、コロナ下における日本語版刊行を受け、ビジネスの現場に身を置く人びとの少なからずが『ブルシット・ジョブ』の問題提起に関心を示したのも驚くには当たらない。「わたしたちは99%だ」というあの〈オキュパイ・ウォールストリート〉の有名なスローガンは、「階級」の問いの回帰と社会の大部分の融和可能性を同時に示唆していた。この観点からすると、「紀伊國屋じんぶん大賞2021」第1位と第33回「トップポイント大賞」――2020年下半期のビジネス書第1位――をともに獲得したという事実は、グレーバーの著作の融和的でコンセンサス志向の側面を照らし出していると言えるかもしれない。誰の心のなかにもナナミンはいるのだ、たぶん。
2 フルタイムのアナキストは存在しない
2-1 「アナキスト人類学」など存在しない
集合的コンセンサスを志向するこうした側面と関わっているのかもしれないけれど、ある時期からのグレーバーは、「アナキズム」という言葉とそれが指し示す思想と運動のあいだに一定の距離を保とうと努めてきた。たしかに、彼は1990年代におけるアナキズムの再活性化に立ち会い、人類学研究の傍ら運動に身を投じて、そのためシカゴ大学時代の指導教官マーシャル・サーリンズの求めに応じ、「アナキスト人類学」なる分野をめぐる小さな本を書くことになった。本稿の筆者が別の機会に指摘したように、グレーバーが21世紀の大学の一角における「アナキズム的転回」を準備した最重要人物であるのは間違いない[3]。
しかしやがて、彼はこの2004年の著作の表題が自らにつきまとうのを厄介に感じるようになったらしい。グレーバーはこの点をたえず強調していたものの、日本語世界ではほとんど意識されていないように思われる。本稿の筆者はこの点を幾度か指摘してきたけれど、この機会に改めて強調しておこう[4]。
2018年前半に――『ブルシット・ジョブ』刊行に合せて[5]――立ち上げられた公式ウェブサイトのために書かれたグレーバー自筆の「略歴」(現在は、没後に新たにつくられたサイト内で読むことができる)には、以下のように記されている。
恩師マーシャル・サーリンズが小冊子の叢書を始め、わたしに一冊協力するよう求めてきたので、『アナーキスト人類学のための断章』〔以文社、2006年〕と題する小さな本を書いたのですが、そのせいで以後ずっと、「アナキスト人類学者」と呼ばれるのがわたしの宿命になってしまいました(実際にはこの本はおおむね、アナキスト人類学など存在していないし、たぶん現実に存在することはありえないと説いているというのに。お願いだからこんな風に呼ばないでください。誰かを「社民主義人類学者」などとは呼ばないものでしょう?)
そもそもそれ以前から、より多くのひと目に触れるツイッター・アカウントにおいて、グレーバーは長らくこの点を明記してきた。ウェイバック・マシンに残る記録によると、ツイッターでの発信を始めた2011年後半――つまり〈オキュパイ・ウォールストリート〉のさなか――のプロフィールにはこう記されていた。
わたしは人類学者です。それからアナキストです。(しかしアナキスト人類学者ではありません! 人類学者にそんな種類はないので。)
2012年の記録を見ると、この禁止要請は一旦プロフィールから消えているものの、それと同時に「アナキスト」という自己規定も掲げられなくなって、彼の関わる運動には、「反権威主義的」というより一般的な形容が与えられている。
わたしは人類学者で、OWS〔オキュパイ・ウォールストリート〕やその他いろいろな反権威主義的プロジェクトに関わっています。
そして、2013年2月14日の記録には再び、明示的な禁止要請が現れる。
わたしは人類学者で、時々いろいろなものを占拠します。アナキズムというのはやることであってアイデンティティになるようなものではないと思うので、わたしをアナキスト人類学者と呼ぶのはやめてください。
以後、グレーバーはこの文言をずっとツイッターのプロフィールに掲げ続けた。没後の現在も、アカウントを訪れる誰もがそれを目にすることになる。もちろん、2011年のプロフィールで明言されていたように、「アナキスト人類学者」ではないという主張は、「アナキスト」としての自己規定と両立可能なものだ。
2-2 誰もが時々はアナキストであり、誰もフルタイムのアナキストではない
けれども、彼は2018年8月15日のツイートでこのように訴えている。
わたしのツイッター・プロフィールには「わたしをアナキスト人類学者と呼ぶのはやめてください」とあるのだし、それにわたしは人びとに、わたしをいつどこででもアナキストとして紹介するのはやめてほしいと頼んでいるのですが、それでも一日に1ダースはそうしたことが起こるのです。
彼は「アナキスト」という自己規定についても、必ずしも強調する意図はなかったらしいことがわかる。実際、「アナキズムというのはやることであってアイデンティティになるようなものではない」というプロフィールに記された立場からも察せられるように、彼は「アナキズム」、あるいは「イズム」を排した「アナーキー」を、彼自身を含めた特定の人びとに排他的に帰属するような何かとはみなさないよう配慮していたように思われる。それは「やること」、つまり振る舞いのなかに表れるものであって、その時ひとが「アナキズム」の名のもとにそれを行っているかどうか、「アナキスト」を自認しているかどうかは、本質的にはどうでもよいことなのだ。
そのことは、早すぎた晩年になされ、没後に刊行された「アナーキー」を主題とする対話の記録を読んでも察せられる。フランスとチュニジアに出自を持つ哲学者・作家・俳優メディ・ベラジ・カセム――グレーバーによれば、1973年生まれのこの独学者は一度はアラン・バディウに近づいたものの、今なお毛沢東主義の遺産に忠実であり続ける老哲学者が〈アラブの春〉や〈オキュパイ・ウォールストリート〉を真の〈出来事〉と認めようとしないのをひとつの理由に決別し、アナキストに転じたのだという――が企画したこの対話集のタイトル、『Anarchy—in a Manner of Speaking』はなかなか翻訳しがたい。けれども、in a manner of speakingとは文字通りには「ひとつのものの言い方では」くらいの意味であり、「いわば」、「ある意味では」、「まあ大体のところは」のような含意を持つ表現であるので、ここには容易に、「アナーキー」という言葉が読者に与える強い印象を和らげようという趣旨を認めることができるだろう。「アナーキー、のようなもの」、「アナーキー、と言えば言える」、「アナーキー、みたいな」等々……。対話の冒頭で、グレーバーはこのように断っている。
わたしが避けたいと思っているのは、アナーキーに関する権威のような存在としてインタビューを受けることです。それには明白な理由もありますが、わたしはまた実際、アナキズムの政治理論の歴史をそんなに知らないのです。たしかに、クロポトキンとバクーニンのことはだいたいわかる。プルードンをいくらか読んでもいます。けれどもわたしはいかなる意味でも、アナキズム学者ではない。アナキズムの原理に賛同し、折りに触れそれに基づいて行動するけれども、ふつうはかなり限定的なやり方でそうしているにすぎない、そのような学者です。
こうしたところにも、狭義のアナキズムの伝統にこだわりたくないという姿勢が感じられる。「アナキスト」の自己規定を終生保ち続けたとは言え、彼はそれをあまり固定的なアイデンティティのように受け取られるのを好まなかった。以前別の機会に取り上げたように、急逝の数か月前のある日、彼はツイッターで「わたしはアナキストのようなものなのでね(I'm kind of an anarchist)」と打ち明け、この曖昧な自己規定の真意を問いただされて、次のように応じている。
わたしは声高にではなく、穏やかさとユーモアをもって、アナキストなんです。何か問題が?
結局のところ、アナーキーが実質的な意味を持つのは、たくさんの人びとが日々の営みのなかで――多くの場合、それをアナキズムの実践として意識することなしに――実現していくことを通してなのであって[6]、そう考えるなら、誰かがアナキストであり他の誰かはそうではない、などという規定にはそれほど意味がなくなってくるはずだ。2013年10月14日のツイートを引こう。
わたしは基本的に、誰もが時々はアナキストである一方、つねにアナキストであるようなひとは誰もいないと思っています。少なくとも、この社会においては。
2-3 マルクス主義との対抗関係
「少なくとも、この社会においては」という留保は、フルタイムのアナキストが存在可能になるような未来を示唆しているものと解釈することもできる。そして実際、グレーバーは来るべき「革命」を示唆することを決してやめなかった。しかし――本稿(下)の「3」で見るように――人間本性を「ありのままに」、つまり善良さとともに邪悪さ、賢明さとともに愚かさを含んだものとして受け止め、あくまでもそうしたものでしかありえない人間本性を基盤に新たな社会を展望するという彼の基本的スタンスからして、この留保が不要になる全面的なアナーキーの可能性を真剣に考えてはいなかったのではないだろうか。誰もがパートタイムのアナキストであり、誰もフルタイムのアナキストではありえないというのは、その程度は別として、人類が人類である限り、あらゆる社会に共通の条件であるように思われる。
ともあれ、ここまで見てきたように、『アナーキスト人類学のための断章』執筆後のグレーバーは、自らの人類学がアナキストの立場に引き寄せて理解されるのを断固として拒絶する一方、誰もが多少ともアナキストなのだとしてこの立場を一般化しようと努めていた。2つの姿勢は矛盾しているようにも見える。けれども、アナキズムを掲げることが他の人びととのつながりの妨げとなるような場合にはそれを差し控え、その原理を説くことでより多くの人びととのつながりを生み出していけるのであればアナキズムを語る、と考えるなら、それなりの一貫性を認めることができるようにも思う。
実際、結局のところ、グレーバーが最も躊躇なくアナキズムの立場を打ち出してきたのは、マルクス主義との対抗関係においてのことだ。この点については以前論じたことがあるが[7]、ここではツイッターでのやり取りを見ておくことにしよう。ある哲学系ユーチューバーは「アナキストたちのマルクス主義批判はまったく意味がないと思う」と主張し、その理由を理論の欠如に求めながら、「わたしはグレーバーがアナキスト人類学を探究してきたことを知っているけれど」と留保を付け加えた。グレーバーは2019年11月22日のツイートで、「アナキスト人類学」など存在しないという立場を改めて確認しつつ、マルクス主義批判の自説を繰り返している。
わたしは別にアナキスト人類学を探究してきたわけではないのですが。アナキズムは、世界のなかで行動できるためには何らかの全体化する理論が必要だ、という考え方を拒絶します。全体化する理論へのアプローチは、知的な満足感を与えてくれるのかもしれませんが、それが現実世界にもたらす影響はほとんど必然的に惨憺たるものとなります。
要するに、グレーバーにとってアナキズムが重要なのは、かつてマルクス主義が体現したような単一の全体的な世界観の提示を退けるためなのだ。アナキズムは、そうした世界観においては意味を持たないような行為にも意味を与え、人びとの活動の余地を広げていくことに役立つ。
2-4 アナキストもまた反民主主義的でありうる
そうであるなら、逆にそれを掲げることが人びとに偏見を与えるような場面で、グレーバーがこの言葉にこだわる意味を見いださなかったのも当然と言えるかもしれない。
実際、2005年に雑誌掲載された初期著作『民主主義の非西洋起源について』の序論に「アナキズムと民主主義はおおむね同じものである」という信念を書き付けたグレーバーではあるけれど、現実のアナキスト活動家の振る舞いには時に辟易していたようで、とりわけ英国の有力なアナキスト系ウェブサイト「リブコム」(「リバタリアン・コミュニスト」の略)とは、米国からの「亡命」後のわずかな親交ののち、深刻な敵対関係に入ることになった。
何が問題だったのか。特定の世界観への帰依を求めないはずのアナキストたちもまた、マルクス主義を範例とする左派に固有の悪弊と無縁ではないということのようだ。ここではまず、それをグレーバーの対話相手を務めたブライアン・イーノの意見を通して見ておくことにしよう。今日では欧州の代表的知識人の相貌を示すようになったこの著名な音楽家は、本稿「1」に既出の『tattva』第3号掲載の対談で、グレーバーの指摘を受けつつ彼なりの観点から、左派の抱える困難を論じている。イーノによると、現状維持のためにさしあたりの団結が可能な右派と対照的に、左派はどのような未来が望ましいのかをめぐり複数のビジョンを競わせることに向かいがちであって、そのため絶えざる内輪もめが生じるのだという。「複数ある未来のどれかを守るのは、一つしかない現在を守るのよりもずっと難しい」。
こうした困難は、それをコンセンサス形成の粘り強い努力によって乗り越えるなら豊かな果実を実らせることにもなるだろうが、そうでなければ実際、終わりのない不毛な抗争へと道を開くほかない。グレーバーも多少とも、イーノのこうした懸念を共有していたはずだ。彼はさらに加えて、自らのビジョンの意義を確信した少数派が、それ自体としては尊いものでもありうる自負をある種の選民意識へと屈折させてしまうことを問題視していた。急逝の3週間ほど前、2020年8月9日のツイートを引こう。
多くのグループは、単に大衆的基盤を求めていないだけではなく、それだけだったらよいのですが、一部はそもそも多数派の人びとがラディカルになることをまったく望んでいないのです。というのも、そうなると自分たちが特別な存在ではなくなってしまうからでしょう。
こうなると、口先で何を言おうとも、こうした人びとが民主主義を真面目に考えているとは信じられなくなってくる。「トローリング」、つまり意見の違う誰かを議論の相手ではなく殲滅すべき敵とみなして苛烈な人格攻撃を繰り広げるネット上の流儀が、こうして可能になる。グレーバーはと言えば、ラディカルな左派がしばしば採用するこの流儀に必ずしも乗れないものを感じて、2017年4月7日にこのようにつぶやいていた。
わたしの問題は、わたしが民主主義的な本能を持っていることです。わたしはみんなのことを真面目に受け止めたい。トローリングは、エリート主義者として行動するようにデザインされたやり方だと思うのです。
本稿の筆者は、昨年執筆した3つの追悼記事のひとつでこれらの発言を引きながら、以下の所見を記した。「自分たちの側に正しさの専有を想定したうえで、相手の説得を放棄してもっぱら人格的な非難に力を注ぐというのでは、合意形成の基盤となるような共同体をつくるのは難しい。それにまた、ラディカルさの根拠を多くの人びとの無理解に求め続けている限り、世の中の大がかりな変化を促すこともできないだろう[8]」。
言うまでもなくこのことは、単につねに多数派の意向を尊重すべきだということをまったく意味しない。そうではなく、立場を異にする相手を知的な対等者として尊重しながら、可能であれば相手の意見を変え、必要に応じ自分の意見を変えていくことが重要だ、ということだ。
グレーバーは、2009年以来の若い友人(1979年生まれ)、ドキュメンタリー映画作家のアストラ・テイラーとの公開対談(2019年10月18日)で、ある種の民主的意思決定モデルへの違和感を表明している。人びとを固定的な利害集団に分類し、誰も帰属集団に応じた当初の意見を変えることがないという前提のもと、一定の力関係の介在するなかで交渉を行うというのは、彼によると「非常に敵対性重視の発想」であって、実際には、参加的意思決定の経験のなかで、ひとはしばしば意見を変えるのだという。テイラーは追悼記事でこのときの発言を振り返っている。
デヴィッドはとてもしっかりと自分の見解を保っていたけれど、教条的でもセクト的でもなかった。意見の相違は楽しみの一部をなしていた。〔…〕去年の10月にロンドン・レビュー・ブックショップで行った最後の対話のなかで、彼は熟議のプロセスを通して自分の考えを変えていくことの喜びについて語った。「ああ、自分の考えはおかしい、別の考え方をしてみてはどうだろう」といった気づきは「政治的幸福」のひとつのかたちであるのに、正当に評価されてこなかったのだというのだ。彼は、わたし自身よりもずっと型破りでユートピア的な考え方を、信用できるやり方で示してくれる存在として、わたしが当てにしているわずかなひとのひとりだった。わたしたちのデュオでわからず屋を演じられなくなるなんて、とても寂しい。
テイラー自身が追悼記事で強調しているように、彼女は決してアナキストではない。むしろ、コンセンサスに基づく意思決定は稀にしかうまくいかないとみなし、強力な国家の役割に多くを期待する立場だ。そんなテイラーをはじめ、明確な反国家志向を共有しない多くの友人との対話を彼は楽しみ、時に彼らの考えを変え、場合によっては自らの考えを改めたのだろう[9]。その意味で、一見すると逆説的なことに、グレーバーのアナキズムは彼の立場を共有しない人びととのあいだで最も意義深く発揮されたのだと言えるかもしれない。
[1] おそらく最もよく読まれたのは、藤田結子「私たちが「クソどうでもいい仕事」に忙殺されてしまう意外な理由」(現代ビジネス、2018年7月9日)だろう。
[2] なお高島鈴「罠の外を知っているか?――『呪術廻戦』論(1)」(webちくま、2021年5月27日)は、この点も踏まえつつ作中の呪術師たちと労働の関係を論じている。
[3] 『民主主義の非西洋起源について』訳者あとがきおよび「未来を開く――デヴィッド・グレーバーを読むために」(『群像』2020年9月号)参照。なお「アナキズム的転回」は、ニューヨークのニュースクール・フォー・ソーシャルリサーチで2011年5月に開催されたシンポジウムの表題。そこではとりわけ、かつて同校で教えたライナー・シュールマンおよびハンナ・アーレントの思想のアナキズム的次元に光が当てられた。
[4] とりわけ、前掲「未来を開く」を参照。なお、彼の仕事の政治的射程を強調するために時に用いられる「アナキスト人類学者」とは別に、日本では通常のプロフィールで「文化人類学者」の肩書がほとんどつねに採用されてきたけれども――そしてこの学問分野は実在しているけれども――、グレーバーは大抵の場合、単に「人類学者」を名乗ってきた。実際、筆者が最近ティム・インゴルトの事例と併せ論じたように、「彼にとって人類学とは、人類を総合的に研究し一般化を行う力を持つ唯一の学問として貴重なものだったのであり、「アナキスト~」はもちろんのこと、「文化~」であれ「社会~」であれ何らかの下位分類を設定し、その枠組みの内部に自己を限定するようなことに大きな意味を認めていなかったことはたしかだろう」(「デヴィッド・グレーバーの人類学と進化論」『現代思想』2021年10月号)。日本語世界でも、単に「人類学者」として紹介されることが一般化していけばと願っている。
[5] グレーバーの出版エージェントを務めたメリッサ・フラッシュマンの追悼文によると、「『ブルシット・ジョブ』刊行前のある時点で、デヴィッドはようやく個人ウェブサイトの立ち上げに同意してくれた」とのことだ。
[6] 松村圭一郎『くらしのアナキズム』(ミシマ社、2021年)は、おおむねこの方向でグレーバーの仕事を活かしているように思われる。
[7] 前掲「未来を開く」を参照(「資本主義は「全体化するシステム」ではない」)。
[8] 「懐疑的に、けれど「とりあえず信じること」」、『図書新聞』2020年10月17日号。
[9] そもそもグレーバーは最後の数年を、福祉国家再建志向の労働党党首コービンの強力な支持者として過ごした。この点については前掲「懐疑的に……」および以下を参照。「「神秘的な、楽しい未来」に向けて」、『群像』2020年11月号。
片岡大右(かたおか・だいすけ)
批評家、社会思想史・フランス文学。東京大学、早稲田大学ほか非常勤講師。最近の雑誌寄稿に「アジアの複数性をめぐる問い――加藤周一、ホー・ツーニェン、ユク・ホイの仕事をめぐって」(『群像』2022年7月号)、「『鬼滅の刃』とエンパシーの帝国」(『群像』2021年11月号)、「デヴィッド・グレーバーの人類学と進化論」(『現代思想』2021年10月号)、「「惑星的ミサ」のあとで――『ゲーム・オブ・スローンズ』覚え書き」(『文學界』2020年2月号)、ウェブ上で読める最近の仕事に「多様性と階級をめぐる二重の困難――HBO版『ウォッチメン』とそのコンテクスト」(文化庁メディア芸術カレントコンテンツ)、「「魔神は瓶に戻せない」――デヴィッド・グレーバー、コロナ禍を語る」(以文社ウェブサイト)、「人生の時間とその後――展覧会「クリスチャン・ボルタンスキー Lifetime」に寄せて」(図書新聞/以文社ウェブサイト)、「「世の中の裂け目」はいつだって開く――小沢健二が帰ってきた」(図書新聞/以文社ウェブサイト)など。本noteにて「長い呪いのあとで小山田圭吾と出会いなおす」を全5回連載、そこから派生した小山田圭吾の炎上事件をめぐる記事を集英社オンラインに掲載した(前編・中編・後編)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
