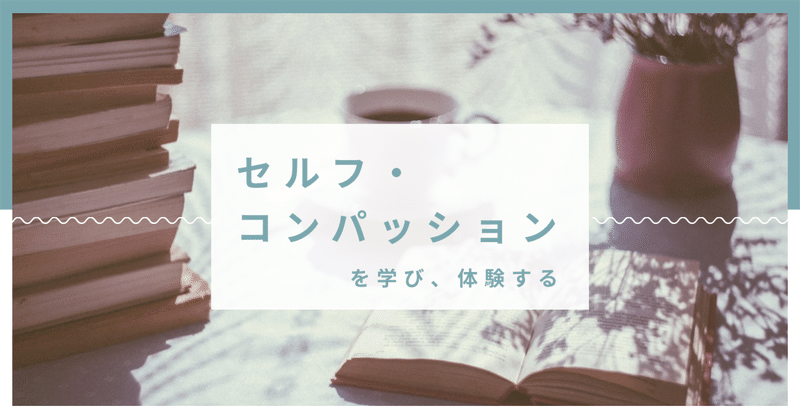
42-4.セルフ・コンパッションを学び、体験する
特集:2024年☆心理職ワールドの行方
中野美奈 (福山大学 准教授)
下山晴彦(跡見学園女子大学教授/臨床心理iNEXT代表)
Clinical Psychology Magazine "iNEXT", No.42-4
オンライン体験研修会
セルフ・コンパッションを学び、体験する
−自分とつながり、人とつながる−
【日時】2024年2月23日(金曜:祝日)午前9時〜12時
【講師】中野美奈(福山大学准教授)先生
【プログラム】
🔸セルフ・コンパッションとは何か
🔸セルフ・コンパッションの理論背景
🔹セルフ・コンパッション体験ワーク
【申込】
◾️[臨床心理iNEXTのiCommunityメンバー(無料メンバー含む)](無料)
https://select-type.com/ev/?ev=UMt9Z4-3IuY
◾️[臨床心理iNEXTのiCommunityメンバー以外](2,000円)
https://select-type.com/ev/?ev=AekbnM3D7z0
◾️[オンデマンド視聴](2,000円)
https://select-type.com/ev/?ev=M-O-iYazUY8

注目新刊本「著者」対話講習会
第7回公認心理師試験の直前対策を伝授
―さあ!3/3国家試験までどう過ごす?ー
【日時】2024年2月10日(土曜)9時〜11時
【講師】宮川純 河合塾KALS 講師
受験生のバイブル「赤本」著者
【講師インタビュー動画】
研修会について宮川講師にインタビューした紹介動画があります。
(前半)https://www.youtube.com/watch?v=GN5FWVW4cSk
(後半)https://www.youtube.com/watch?v=1piea6J00HA
【注目新刊書】
赤本 公認心理師国試対策2024(講談社)https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000380796
【申込み】
[臨床心理iNEXTのiCommunityメンバー(無料メンバー含む)](無料)
☞https://select-type.com/ev/?ev=ZMPzT_7B0ho
[臨床心理iNEXTのiCommunityメンバー以外](1000円)
☞https://select-type.com/ev/?ev=ZYNGTzjf5pE
[宮川講師の講義部分のみのオンデマンド視聴](1000円)
☞https://select-type.com/ev/?ev=sFe0hHXRut4

1.セルフ・コンパッションとは
セルフ・コンパッション(self-compassion)は、「自分に対する思いやり,やさしさ,慈愛,慈悲,慈しみ」などと訳されます。カタカナの訳語であるとわかりにくい印象もあります。しかし、実は仏教に由来する考え方であり、日本人にとっては、むしろ馴染みやすい考え方です。しかも、心理職にとってはとても重要な概念なのです。
私たちは自分が苦しい時に自分を責めてしまいがちです。その一方で、大切な家族や友人が人生の辛い課題に直面していたり、大変な状況に陥ったりしているとき、優しい言葉や態度で接することができます。
セルフ・コンパッションは、大切な人に接するように、自分を否定したりすることなく、他者に対して思いやりを持って接するように、ありのままの自分を受け入れて自己肯定感を高めていきます。つまり、セルフ・コンパッションとは、「自分を大切にし、他者も大切にする」という考え方であり、態度であり、行動の仕方なのです。このようなセルフ・コンパッションは、下記の3つの構成要素から成り立っています。
1.自分へのやさしさ(Self-Kindness)
2.共通の人間性(Common Humanity)
3.マインドフルネス(Mindfulness)

2.心理支援の基盤となるセルフ・コンパッション
人は、自分を大切にできるからこそ、他者の“自分”を大切にできます。これは、心理支援の基本となるあり方です。他者を大切にするだけで、自分を大切にできない自己犠牲的な心理支援は不自然であり、そこには無理が生じます。バーンアウトの原因にもなります。逆に他者の“自分”を大切にせずに心理職自身の方針を押し付ける支援は、自己中心的な心理支援になります。
したがって、「自分を大切にし、他者も大切にする」というセルフ・コンパッションは、心理職の専門性の基盤となるあり方なのです。それは、心理職のセルフケアとも深く関わります。そこで、臨床心理iNEXTでは、冒頭に示したようにマインドフルネスの専門家でもある中野美奈先生 ※1)を講師に迎え、2月23日(金曜 祝日)に「セルフ・コンパッションの考え方を体験的に学ぶ」オンライン研修会を開催します。
※1)https://www.maruzen-publishing.co.jp/item/b295083.html
研修会では、ワークを通してコンパッションを体験的に学んでいただきます。具体的には、日常生活でストレスや辛さを感じたときに、自分自身に思いやりを向けるトリガー(きっかけ、合図)となるスージング・タッチ(Soothing Touch)などのワークなどを実施します。
心理職以外の方も含めて多くの人に体験いただけるように、iCommunityメンバー※2)は無料としました。また、その他の方も2000円と参加費を廉価に抑えました。一般の方も含めて多くの方の参加をお待ちしております。
※2)https://cpnext.pro/lp/icommunity/

3.「セルフ・コンパッション」体験プログラムご紹介
セルフ・コンパッションの原点となっているコンパッションの考え方 ※)は、仏教の理論や実践方法を取り入れるとともに、進化心理学や神経科学を踏まえて「怒り・不安・嫌悪」、「動因・興奮・バイタリティ」、「満足・安全・繋がり」の3つの感情制御システムの中でも癒し(soothing)のシステムに注目して構成されたものです。
※)臨床心理マガジンでは、「コンパッション」をテーマとする記事を発行しています。
①https://note.com/inext/n/n7d32b62dee4f
②https://note.com/inext/n/nf9b02164581c
したがって、複雑性PTSDなどの感情制御が困難なケースの心理支援において役立つ考え方と技法を提供するものです。その点でセルフ・コンパッションは、幅広く感情制御の問題に関心のある皆様に役立つものです。そこで、臨床心理iNEXTでは、隔週土曜日の4回シリーズの「セルフ・コンパッション」体験プログラムを企画しました。講師は、2月23日研修会講師の中野美奈先生です。概要は、下記となっています。時間は毎回9時〜10時30分の90分です。心理職だけでなく、一般の方も参加できます。
「セルフ・コンパッション」体験プログラム
① 5/11(土曜) 『マインドフルな気づき』
② 5/25(土曜) 『共通の人間性』
③ 6/ 8(土曜) 『しんどい感情との付き合い方』
④ 6/22(土曜) 『他者へのコンパッション』
プログラムの詳細、申し込み方法や参加費については、2月23日の研修会でご説明するとともに、臨床心理iNEXTサイトでもご案内致します。セルフ・コンパッションの理解と方法をより深めたい方は、ぜひご参加ください。以下に、セルフ・コンパッションの体験研修会と体験プログラムのご案内も兼ねて、講師の中野美奈先生との対談を掲載します。

4.マインドフルネスからコンパッションへ
[下山]中野美奈先生には、2月23日の体験研修会と、5月11日から隔週4回シリーズの体験プログラムにおいて、セルフ・コンパッションについてご指導をいただくのですが、まず先生がセルフ・コンパッションに関心を持った経緯をお話いただけますでしょうか。中野先生は長いことマインドフルネスを学び、その教育や実践をされていました。テーマが、マインドフルネスからコンパッションに広がってきた理由も教えていただけたらと思っています。
[中野]セルフ・コンパッションとマインドフルネスは、鳥の両翼に喩えられます。片方だけでは不十分であり、どちらも大切であると言われています。私は、最初にマインドフルネスをしっかり学びました。その後、現在、臨床でも研究でも主に取り組んでいるのがセルフ・コンパッションです。マインドフルネスを学んでいると、セルフ・コンパッションの理解はさらに進みます。腑に落ちることも多くあります。
改めて思い返してみると、セルフ・コンパッションは、マインドフルネスだけでなく、臨床場面での活動、例えばカウンセリングや心理療法とも深く関わっていることに気づきます。今になって思えば、セルフ・コンパッションは、臨床活動をする際には、それとは意識しませんでしたが、実際には頭の片隅で同じような考え方をしていたなあと思いますね。

5.心理支援の基盤にあるコンパッション
[中野」おそらくコンパッションやセルフ・コンパッションの概念を学ばれた心理職の方は、「そういえば、私、普段こういうことを意識していたかもしれない」と改めて思われる方も多いのではないでしょうか。
[下山] 近年、心理職の間では、セルフ・コンパッションがとても注目されるようになっています。しかし、実は皆さん気づかずに実践してきたことを、改めて意識し、自覚するようになったという面があるのだろうと思います。
そうなると、ここで一度立ち止まり、セルフ・コンパッションとはどのようなものかを正しく学ぶ必要がありますね。なぜならば、我々心理職の活動の基本になっているのがセルフ・コンパッションやコンパッションであると考えられるからです。詳しくは研修会当日にお話いただくことになりますが、簡単で結構ですので、セルフ・コンパッションとは何かということを、ここで説明していただけないでしょうか。
[中野]コンパッションは、慈愛と訳されたりします。日本語で言うと、慈悲とか優しさとか、そのような感じの事柄です。セルフ・コンパッションは、自分に対してそのようなコンパッションを向けるということです。それに加えて、「みんな同じ人間なのだ」という、共通の人間性を意識することも特徴としてあります。また、その構成要素の一つにマインドフルネスも入っているので、改めて「今ここ」での気づきにしっかり意識を向けることも重視されます。自分に対してのコンパッション、共通の人間性、マインドフルネスといったことによって構成されるものが、セルフ・コンパッションとなります。
[下山]そのようなセルフ・コンパッションについて知ると、我々が心理相談をしている時に、実はセルフ・コンパッションを大切にしていたということに気づきますね。

6.セルフ・コンパッションを学ぶ意味
[下山]心理相談の基盤になるのが“共感”であると思います。私の感覚では、セルフ・コンパッションはその共感と密接に関連しているように思います。そう考えると、セルフ・コンパッションを学ぶことで、我々の臨床の活動が、より深まったり、より自覚的になったりする面があると思います。そのことは、心理職の訓練とも関わります。そのようなセルフ・コンパッションを学ぶ意義について、中野先生から何かアドバイスやサジェスチョンがありましたら、お願いします。
[中野]カウンセラーやセラピストとしてクライエントさんに接している心理職であれば、コンパッションは、実は日頃から身についているのだと思います。おそらくコンパッションの概念を学んでみると、いつもクライエントさんに対する時の気持ちはコンパッションと同じなんだと、しっくりくる心理職は多いと思います。
しかし、なかには、クライエントさん等の他者に対してはコンパッションをしっかり感じられるが、自分には優しくなれないという心理職もいるのではないでしょうか。自分へのコンパッションが足りてないと感じられる方も多いのではないかと思っています。共感疲労やバーンアウトは、心理職には本当に身近な問題になっています。
そのような問題への対処として、セルフ・コンパッションは活用できます。また、日常生活で余裕がなくなったり、怒りを感じやすくなったりという場合でも、コンパッションはその対処に使えます。他者に対しても使えるし、自分に対しても使えます。

7.セルフケアに役立つセルフ・コンパッション
[下山]なるほど。コンパッションやセルフ・コンパッションは、心理職にとってはセルフケアのために必要だということですね。そのような意義もあるということですね。
[中野]コンパッションを養うことは、心理職のセルフケアで欠かせないと思います。
[下山]それと関連して、心理職を目指す学生や初心の心理職にとってセルフ・コンパッションを学ぶ意義は何かあるでしょうか。というのは、心理職になるということは、共感を学ぶことでもあるので、コンパションの学習が役立つのではないかと思ったりするのです。
[中野]私は、大学の実習担当教員です。そのため、公認心理師養成カリキュラムの実習の参加院生を対象として、コンパッションを学ぶ意義について研究しました。先日、その研究結果を学会で発表したばかりです。その研究では、セルフ・コンパッションの反応尺度を用いて院生を対象に調査しました。
その結果、セルフ・コンパッションの高い院生は、抑うつや不安、さらに完璧主義、社会機能障害との間で全て負の相関にありました。また、他者の意見を気にしすぎてしまう傾向や能力を他者と比較しすぎてしまう傾向とも負の相関がありました。そのような点で心理職を目指す学生にとっては、セルフ・コンパッションを身につけ、高める意義はあると思います。

8.「あるがままの自分」を育てるセルフ・コンパッション
[下山]セルフ・コンパッションが、一般的に健康的な人間関係を持つ上で大切な意味を持つことがわかります。それに加えて心理職になるためには、特に意義があるということですね。
つまり、心理職であることや心理職を目指すことは、様々な苦しみとか否定的な考え方にも触れることになります。だからこそ、心理支援をする場合には、セルフ・コンパッションのあり方を身につけておくことが、心理職にとって健康でいられるために特に意義があるということですね。
[中野]日本人は、ついつい他人の目を気にしてしまう、人と比べてしまうという傾向があります。そして、自分を責めたり、劣等感に苦しんだりします。そのような日本人には、セルフ・コンパッションは、本当に必要だと思います。
とにかく人と比べずに、他者にも優しい眼差しを向けつつ自分にも優しい眼差しを向け、他者の評価を気にしないでいられるようになることが大切です。セルフ・コンパッションは、そのように他者の評価を気にしなくてもいいというあり方も育てていくものです。
[下山]なるほど。セルフ・コンパッションは、他者評価を気にする日本人が「あるがままの自分」でいられるために必要なものですね。

9.マインドフルネスとセルフ・コンパッション
[下山]そのことと関連して、セルフ・コンパッションとマインドフルネスの違いを教えていただけますでしょうか。
[中野]両者は違っているというのではなく、セルフ・コンパッションの中にマインドフルネスが含まれているということになります。マインドフルネスだけですと、今ここにしっかり意識を向けて気づきを高めるということだけになります。そこには、必ず倫理観や道徳心が存在しているとは言い切れません。
しかし、マインドフルネスの原点である仏教的な面に立ち返るならば、そこには倫理観や思いやりなどが必要となります。その点でマインドフルネスだけでなく、コンパッションやセルフ・コンパッションも学ぶということが大切になります。
[下山]確かに最近では、マインドフルネスを仏教から切り離して、それだけを取り出してビジネスのマインドを研ぎ澄ますために利用する動きが広がっていますね。それは、ビジネスにおいて人に勝つためにマインドフルネスを利用することにも繋がります。マインドフルネスだけであると、原点である仏教から離れて、どんどん慈悲や思いやりの精神を切り捨てていくことになるわけですね。
[中野]そう思います。

10. セルフ・コンパッションの理論的背景
[下山]次にセルフ・コンパッションの理論的背景についてお聞きします。コンパッションは、脅威に対しての反応の一つのあり方という考え方があると思います。コンパッションは、ただ単に他者や自分に優しく、思いやりを持って接することが道徳的に正しいから重要というのではないと思います。
コンパッションの考え方には、実は人間はいつ脅威を受けるかもしれない環境の中で生きており、そこでの反応の仕方によってはさらに脅威が増してしまう危険性があるということが前提となっていると思います。そして、その脅威に対してコンパッションを用いて反応することで、環境が穏やかな、危険の少ないものになる。その点でコンパッションが重要となるという見方があると思います。
そのような理解でよろしいでしょうか。それは、現在、PTSDの治療などでも注目されているポリヴェーガル理論にも通じる考え方だと思いますが、いかがでしょうか。
[中野]人間が脅威を感じると戦うか、逃げるか、あるいは固まるといった反応となりやすいわけです。そのような中で、安心や安全を感じるとか、人とのつながりを感じるということが、とても大切になってきます。脅威システムに対して、人とつながって安心・安全を確保するシステムを強くするという点でセルフ・コンパッションがとても大切になります。それは、ポリヴェーガル理論とも通じるところだと思います。
[下山]ポイントは、“つながり”ということですね。

11.医学モデルに替わるコンパッション・モデル
[下山]それと関連して私が関心を持っているのは、コンパッションの考え方を、医学モデルに替わる問題理解のモデルとして活用できないかということです。医学モデルは、問題が起きた場合、「それはあなたの病気ですので、その病気を治療しましょう。」となります。そこでは、問題を、その人の器質障害や機能障害に由来するものとして、「個人化」してしまいます。つまり、個人の問題として、その人を治療することが目標となります。ですので、医学モデルは、問題を個人化してしまうシステムです。
それに対してコンパッションの考え方は、環境、特に脅威をもたらす環境に対して、その人がどのような反応をするかという観点から問題を理解します。その点で、環境とその人との間の相互作用として問題を理解します。しかも、脅威があっても、その人が安心や安全を感じるためにどのように対応するかが介入の方針となります。そこでは、コンパッションを用いて環境との関係変化を促すことを目指すのだと思います。その点でコンパッション・モデルは関係化を促すシステムであり、医学モデルに替わるモデルではないかと思いますが、どうでしょうか。
[中野]それについては、私も同感です。コンパッションを用いた心理支援は、一人で薬を飲む、あるいは一人で考え方を変えるといった治療アプローチとは異なります。また、問題への直面化をさせるといったアプローチとも異なります。
[下山]そうですね。個人化は、医学モデルだけではないですね。コンパッションを基盤としない認知行動療法も個人化をしてしまいますね。
[中野]コンパッションに基づく心理支援では、問題理解として、まず環境との関係を考えます。また、心理支援では、人と人とのつながりによって癒されることだけでなく、自分自身としっかりつながることを大切にします。セルフ・コンパッションは、精神的な問題を持っている人だけでなく、健康な人にとっても人生全体の底上げをすることにつながる利点があります。より良い人生を生きるということと関係してきます。

12. セルフ・コンパッションのワークについて
[下山]コンパッションやセルフ・コンパッションには、いろいろな可能性がありますね。最後に、研修会で実施するワークについて、簡単に説明していただけますか。
[中野]ワークは、安心や安全を感じられるような場所を想像してイメージしてもらったり、安心や安全を感じられる色をイメージしてもらったりします。それは、人それぞれで違います。しかし、多くの人は、日々忙しいために、自分にとって安心や安全を感じられるイメージはどのようなものかを時間をとって考えることはありません。
研修会では、「スージングタッチ」といって、自分の体に触ってみるワークもしようと考えています。簡単なワークではありますが、きちんと時間をとってやっていただく余裕を持つことが大切と思っています。
[下山]じっくり自分を思いやるためには、時間の余裕があることが大切ですね。そこで、当初は2時間の研修会を予定したのですが、1時間延長して3時間にすることにしました。しっかりと時間をとって参加者の皆さんにセルフ・コンパッションの体験をしていただくことにしました。最後に参加を考えている方にメッセージをお願いします。
[中野]今は、学生さんも働いている方も、本当に忙しいですね。日本人は、特に効率化が上手ですね。若い人は、動画教材は2倍速で見る人も多いと聞きました。映画でさえも2倍速で観る人もいるとのことです。現代社会では、そのような効率化を求め、多くのことを成し遂げていくことも必要であると思います。でも、それだけだと疲れて、気持ちの余裕がなくなってきます。
そうなると、自分に優しく人に優しくといったセルフ・コンパッションの気持ちを持てなくなります。だからこそ、ゆっくりと自分自身と向き合い、自分や他者を癒すことの意味を再認識することの意義があるのです。研修会では、そのようなセルフ・コンパッションの考え方に触れ、体験的に学んでいただければと思っています。

■記事校正 by 田嶋志保(臨床心理iNEXT 研究員)
■デザイン by 原田優(公認心理師&臨床心理士)
目次へ戻る
〈iNEXTは,臨床心理支援にたずさわるすべての人を応援しています〉
Copyright(C)臨床心理iNEXT (https://cpnext.pro/)
電子マガジン「臨床心理iNEXT」は,臨床心理職のための新しいサービス臨床心理iNEXTの広報誌です。
ご購読いただける方は,ぜひ会員になっていただけると嬉しいです。
会員の方にはメールマガジンをお送りします。
臨床心理マガジン iNEXT 第42号
Clinical Psychology Magazine "iNEXT", No.42-4
◇編集長・発行人:下山晴彦
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
