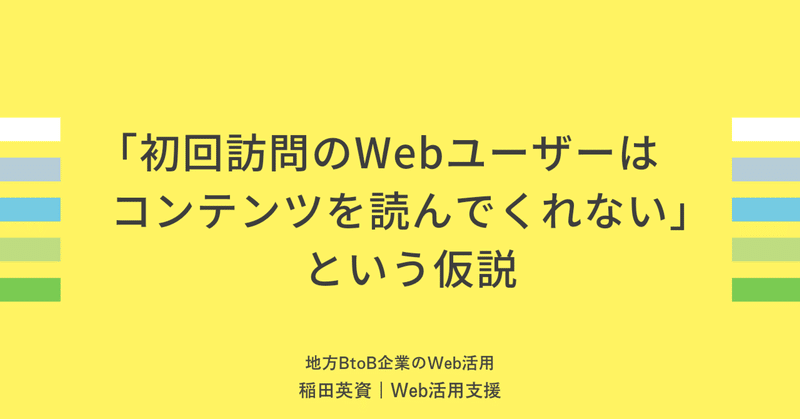
「初回訪問のWebユーザーはコンテンツを読んでくれない」という仮説。
「初回訪問のWebユーザーはコンテンツを読んでくれない」という仮説を信じています。
ここから逆算するに、Webページでまずやるべきことは論理的な説得じゃないんですよね。今にもページを離脱しようとしているユーザーに「ん?」と思ってもらうことです。特に製造系BtoBのWebでは。
ページの上から下まで数秒で移動するユーザーの目に「これは読んだ方がいいかも」と思ってもらうその一瞬が「ん?」です。ユーザーが近寄ってくれる瞬間。それに寄与するのはロジカルな長文ではありません。その内容を指し示す小見出しでありラベリングです。
小見出しによるラベリング例
例えば製造系BtoBのWebで「◯◯製作所の3つの特徴」といった表現はよくあります。ここでありがちなのが「ポイント1」「ポイント2」「ポイント3」と小見出しをつけて、その次に20〜30字ほどの見出しで特徴を語る手法です。
悪くないですが情報の提示としてはもったいないです。ユーザーはそのエリアを1秒で通り過ぎるかもしれないので。小見出しで内容をまず伝える方が「ん?」と思ってもらう機会は増えます。
ポイント1、ポイント2、ポイント3
↓
1. 量産能力、2. 高精度、3. 対応素材
どこがフックになるかユーザー毎に違うので分かりやすくラベルを貼ってあげるイメージです。通り過ぎようとしたユーザーは「自分の興味のあることが書いてありそうだ」と思って初めて本文を読んでくれます。そう考えると小見出しの役割は重要です。数字を伝える以上の役割を持たせられます。ユーザーの意識をページにつなぐ案内版です。
コンテンツの完成はスタートライン
論理的に組み立てられた文脈を頭から理解して納得してくれるユーザーの方が少数派です。コンテンツを成立させるためにロジックは不可欠ですが、ロジカルだから読んでくれるだろうは横柄だし浅はかです。そこはスタートラインに過ぎません。論理的に組み立てたコンテンツを作ったら、その次は「読んでもらえるための/伝わるための作業」が必要になります。
その作業を進めるときに「初回訪問のWebユーザーはコンテンツを読んでくれない」という思考が役に立つんですよね。Webディレクターはいつも頭の片隅に置いておくと助かると思います。
ユーザーとの関係構築が大切な理由
「初回訪問のWebユーザーはコンテンツを読んでくれない」という仮説を覆せる方法がひとつあります。BtoBの場合、メールマーケティングがそのひとつだと思っています。
顧客の課題解決に役立つコンテンツをメールで継続的に届けることでユーザー側に「◯◯社のコンテンツは役に立つから読もう」と思ってもらえるようになります。いつでも離脱しようという気分で読んでいるユーザーとは雲泥の差です。なにより、せっかく書いたコンテンツを一発勝負で終わらせなくて済む。顧客にとって有益なコンテンツだったら1年で複数回案内しても大丈夫です。
刹那的な興味関心だけでなく、「参考になるから読んでおくか」という気分になってもらえるなんてすごくハッピーな関係です。顧客が必要になったタイミングで「そういえば前に読んだな」と思い出してもらったり、同僚にリンクを送ったりするというネクストアクションも生まれます。この関係性が保てるとコンテンツのアセット的な価値が向上します。
ナーチャリング(顧客育成)という言葉は嫌いですが、継続的な接触を通して自社に親しんでもらうこと(関係構築)は「何を言うかではなく、誰がいうか」につながると思っています。コンテンツ活用の視点で考えても「顧客育成」なんて横柄な視点はいらないんですよね。大切なのは「関係構築」です。
関連note
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
