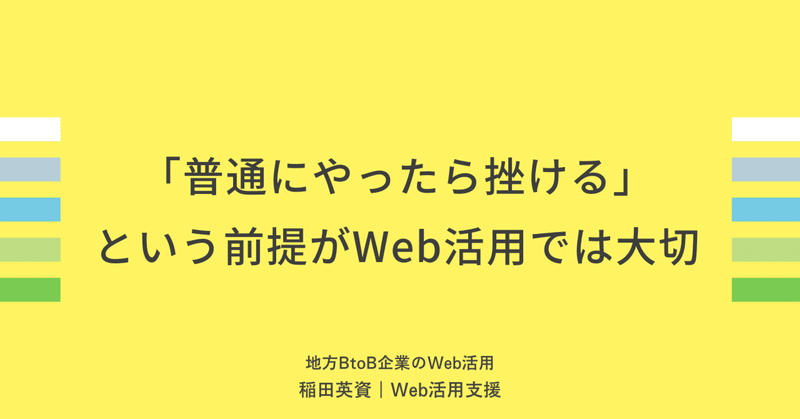
「普通にやったら挫ける」という前提がWeb活用では大切。
「Web活用について何で稲田さんはそんなに詳しく大量にコンテンツにしてくれるんですか?同業のぼくはありがたいけれど」と沖縄の若い同業者の方が質問してくれました。
一番は「自分の思考の整理のため」で、めっちゃ役に立っています。日々の発見や学びを言語化し、ストックされた思考を足がかりにWeb活用の考え方を更に深める。フレーム化していく。ぼくには欠かせない手法です。向き不向きはあると思うけど。
Web活用の挫折について意外と誰もコンテンツにしていない
もう一つ、やってみて分かったのが「Web活用の挫折について意外と誰もコンテンツにしていない」でした。
教科書的な内容は沢山あるんです。勉強になります。でも、「なんで多くのBtoB企業はWeb活用を失敗するのか?始められないのか?挫折するのか?」について書かれたコンテンツはあまり見ない。というか無い。自分で書くようになって初めて気づきました。
「挫折の乗り越え方」がWeb活用ではめっちゃ重要
それって自転車に例えると、「自転車とは?」とか「自転車の乗り方」とかのハウツーコンテンツは沢山あるけれど、「練習で挫折する原因トップ5」とか「転んでも立ち上がるための言葉」「部下の練習のやる気をなくさせる典型的な上司像」とかは誰も書いていないんですよね。自転車と同じで、れんしゆ中の挫折をどう乗り越えるか。Web活用の現場ではそれがめっちゃ大事なのに。
Web活用は「普通にやったら挫ける」を前提に、それでもやり続けるには、社内で定着させるには、という試行錯誤が重要です。特に地方のBtoBでは。
誰もコンテンツが書けない問題
そして、多くの企業が最初に躓く問題は「誰もコンテンツが書けない問題/書いても続かない問題」です。
でも、それについて誰も書いてない。コンテンツの重要性についてはどの会社も書いているけれど、挫折を前提にどう乗り越えるかは誰も書いていない。
MAを提供するSaaSも「コンテンツが重要」とほとんどが書きますが、「挫けてからの立ち直り方」はどこも書いていない。自分たちでも通った道のはずなのに。
これは書く価値があると思いました。Web活用では必ずぶつかる普遍的な問題だからです。コンテンツのきっかけは向こうから来る。しかもネタは日々の業務に溢れている。
テーマとターゲットの発見
「普通にやったら挫けるを前提に、それでもWeb活用をやり続けるには」がぼくのコンテンツテーマになりました。ターゲットは「いま挫けている/挫けそう/過去に挫けた/始めたいけど心配」という地方BtoBの皆さんです。
コンテンツが彼らに届いてぼくにどんなメリットがあるかは知りません。まずは届ける。
ぼくとしたら、コンテンツは「自分の思考整理&ストックすることでの複利効果」でめっちゃ有益なので、作成した時点で充分役に立っています。テーマとターゲットがはっきりしていれば書きやすいし。
コンテンツが届いた先のことは分かりません。でも、届ける。Webのコンテンツ活用はそれでいいと思っています。インバウンドマーケティングとはそういうものだと教科書にも書いてあったし。どこかの誰かの役に立ったら嬉しいです。
インバウンドマーケティングとは
インバウンドマーケティングとは、価値あるコンテンツと顧客それぞれに合わせた体験を創出し、相手を惹きつけるビジネス手法です。望まれないコンテンツでオーディエンスの邪魔をしかねないアウトバウンドマーケティングとは異なり、インバウンドマーケティングでは、オーディエンスにとって望ましい形で信頼関係を構築しながら、オーディエンスが現在抱えている問題を解決できます。
関連note
「まずはお客さんの課題解決に貢献しよう」のマインドで動ける企業の方がWeb活用には向いている。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
