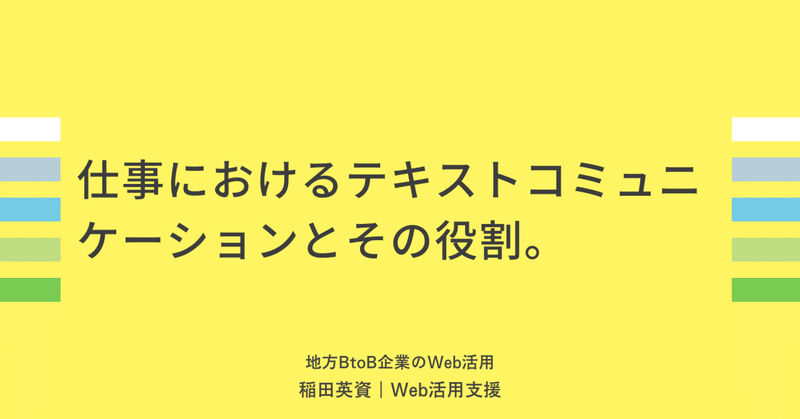
仕事におけるテキストコミュニケーションとその役割。
仕事において、ぼくはけっこうテキストでのコミュニケーションを信じている。必要があれば1000字を超えるメールを平気で書く。先日も「ちょっと困っちゃって…」と社内で相談された案件があったので、現状の整理と課題と解決策をメールで書いて顧客に送ったら1300字になった。
パッと見はけっこうなボリュームだけど、好意的に受け止めていただき建設的なメールが返ってきた。
同じ内容を電話やオンラインMTGでも説明できるけれど内容が複雑なので理解いただくのに労力が必要だし、何より「説得する/された」の雰囲気がつきまとう。込み入った内容であるほどテキストの方がぼくは信頼できる。
- - - - - - - - -
テキストのメリットは「自分の速度で理解できる/理解するまで何度も試せる」の2点。つまり、理解するための速度やプロセスを他人に支配されないということです。テキストの特性としてあまり注目されないけれど、ぼくはかなり重要だと思っています。誰だって支配されたくないですよね。ぼくは嫌です。
オンラインMTGが一般的になってすごく便利になったけれど、時と場合によると思っています。少なくとも「①込み入った状況を整理して ②相手側の理解を深めていただく必要があるとき」にはあまり向いていない。ちょっと大変でもテキストを送ってから電話やオンラインをした方がお互いに有益ですよね。
- - - - - - - - -
もしあなたが「言いたいことは分かるけど書くのが苦手で…」と思ったら、たぶん文章について勘違いしています。文章の役割を「他者を説得するため/コントロールするため」だと思っていませんか?ビジネスの文章にそんな力はありません。必要もないし。名文を書く必要すらありません。むしろ邪魔です。
ビジネスでの文章の役割は「次の話し合いの場を用意するため」です。文章で合意形成は生まれません。それは面談などのコミュニケーションが担います。文章はそのための下拵えであり舞台づくりです。
現状の整理
課題の抽出
解決策の提案(または次の議題)
文章でやるべきことはこの3点です。
整理 → 課題 → 提案
これって文章の話じゃないですよね。皆さんが日々の仕事で毎日やっていることです。社内でも社外でも。「書くのが苦手…」という人は文章を書かなきゃと思い込み過ぎです。文章を書くんじゃないんです。ぼくたちの日々の仕事を文字に置き換えるだけです。次の話し合いの準備として。やってみましょう。
関連note
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
