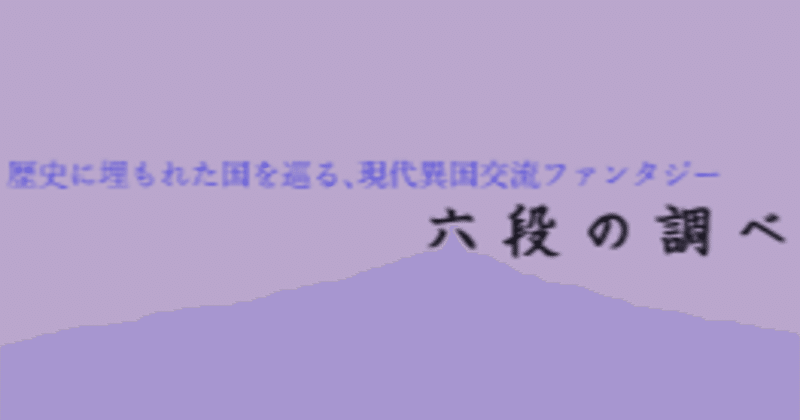
六段の調べ 急 五段 一、長き夜を越えて
前の話へ
序・初段一話へ
寒さが厳しくなると朝から予報されていた日に、その男はやって来た。兄と違って既に受験を終えている彼は、小さな紙袋を炬燵に置いて美央の隣に座る。
「遅れて申し訳ない。これ、誕生日プレゼントです!」
誕生日は十二月だというのに、二月の今プレゼントをあげるとはどういう了見なのか。美央は小さく息をつく。受験で忙しかったから仕方ないのか。
信が渡した紙袋の中には、リボンで縛られた白い箱があった。それを取り出して中を見ると、両掌に収まる大きさをした、木製のこれまた小さな箱が出てきた。
片側が蝶番で留められた蓋を開けるなり、耳に心地の良い澄んだ音色が流れる。オルゴールが好きな自分に合わせたプレゼントの選択だった。その旋律を何度か聞いているうちに、美央は気付く。
「これと同じ曲のオルゴール、持ってます」
厳密には調が違うので、旋律を構成する音は自分が所持しているものと異なっている。それでも信はショックを受けたのか、炬燵の上に額を載せてぶつぶつと言い訳がましいことを呟いていた。
「美央さんに合ってると思ったんだけど……そうか、よく聞いてたからそのイメージがあったんだ……」
思えば自分は信の前で、何度かオルゴールを回す姿を見せてきた。それがこのプレゼントに反映されているのだろう。音が鳴り続ける木箱から目を離し、美央は信の横顔を見やった。彼に会って話すのも久しぶりだ。昨秋ごろになぜか瑞香にいた時以来か。学校ではちらりと見掛けるだけで、会話らしい会話はなかった。ほんの数ヵ月でしかない別れだったのに、こうして再会するとなぜか胸が締まる。これは体に毒だと、美央は彼から顔を背けた。
「大学はどこに行くか、決まっているんですか?」
まだだと即答する信は、もし全部落ちていた場合の恐れを零しながら、顔をさらに炬燵へ押し付ける。すっかり不安でいっぱいのようだ。自分も来年、あのようになってしまうのかと思いかけて、不意に問いが口から出てきた。
「生田さんが卒業したら、もう会えなくなるんでしょうか?」
信が頭を持ち上げ、美央を一瞥した。
「ああ……清隆と同じところに通えるかもわかんないからねぇ」
瑞香での出来事を通じて、信と兄が接点を持てるかも不透明だ。シャシャテンは結婚後、故国に留まるという。瑞香の事件を追う兄に信がついて行くことも、もうなくなるだろう。
「じゃあ美央さんとはより……今までみたいにちょくちょく会うなんて難しいだろうなぁ。勉強の邪魔もできないし」
「そもそも生田さんは、大学進んだ後のこととか考えているんですか?」
「なんにも。美央さんは将来の夢とかあるの?」
突然の質問に、美央は少し口ごもる。こうした質問には、今まではぐらかしてきた。反対される分には気にしないが、実際になれるかと言われたら別問題だ。そんな自信の欠如から黙っていた思いを、なぜかこの男には打ち明けたくなった。彼の方は見ず、言葉を押し出す。
「作曲家か編曲家か……。とにかく、音楽に関わることがしたくて」
昔から温めていた夢だった。長く音楽や楽器に携わってきたからかもしれない。美央がそれを明かすと、信はすぐにも消えかねない寂しげな声を出した。
「そんな夢を持ってまっすぐ生きてるなんて、うらやましいなぁ。おれとは全然違うや」
そこで会話が途切れる。オルゴールの音色がするだけで、何も聞こえない。自分たち二人がいる居間で誰も話さないでいるうちに、美央はだんだん肩が重くなるのを感じる。今までこうした沈黙があっても、気にしてこなかったのに。
オルゴールの動きが止まり、美央はねじを回した。再び流れだした旋律へ耳を傾けようとしたが、それよりも隣にいる男へ目が行ってしまう。昔は音楽のみに集中できていた自分は、いつの間に「人」へ興味を持つようになったのだろうか――そう思いかけて、美央は首を振る。自分が視線を投げている先は、不死鳥の血を引いた「人でなし」だ。
だが彼は、以前に自身を「人」と言い張っていた。そこから鑑みるに、「人」という存在は考え方次第で何にでもなるのか。
「生田さん、『人』ってなんでしょうか?」
美央は尋ねたが、返事がない。信はただ、オルゴールの中を見つめている。ガラスで透けた板の向こうに、ぜんまいが忙しく回っていた。
信が帰った後、美央はもう一度オルゴールを鳴らし始めた。誰もいない間なら、音楽に集中できるはずだ。それを期待したものの、脳内にはまだ彼の姿がちらついている。浮かぶのは先ほどの落ち込んだ様だけでなく、会う度に向けてくる笑顔や、男にしては高い、聞けばすぐ分かるような声だった。
なぜここまで、彼を考えてしまうのか。人についてあれこれ思うなど、昔の自分とは明らかに違っていた。そんな変化を思った途端、ずきりとした頭に美央は手をやった。余計なことを考え、弱くなった身が嫌になる。何にも揺らがずにいられた元の自分に戻るには、どうすれば良いだろう。
ふと、もう誰もいない隣を見る。自分を変えた一因として真っ先に浮かぶ彼を消せば。だがそう思うなり、激しく心臓がざわついた。確か伊勢が彼とシャシャテンを狙った時も、同じ感覚を抱いた気がする。
「おお、それは確か……『おるごーる』じゃったか。如何したのじゃ?」
今まで和室にいたのか、存在をすっかり忘れていた居候が入ってきた。不器用にねじを回し、シャシャテンは何の曲が流れているのか尋ねた。説明しようとして、美央は言葉に詰まる。興味があったのは音楽のみで、それが劇で使用されている一曲としか知らなかった。随分昔に、吹奏楽のメドレーとしてその曲が入っていたのを、たまたま動画で聞いただけだ。
オルゴールの底に貼られていたシールから曲名――『長き夜を越えて』を見つけ、スマートフォンで検索する。『サンゼール』なる舞台の主人公が、ヒロインのために歌う曲らしい。
「その音楽劇か? 如何なる筋書きなのじゃ? そもそも音楽劇とは何じゃ?」
シャシャテンにはまず舞台芸術について簡単に教えてから、美央は検索で出てきた音楽劇の内容を説明した。倉橋輪の父である菅宗三が、作曲を手掛けたようだ。悲劇で終わるそのあらすじを美央が話していると、シャシャテンの目に涙が溜まり始めた。公演自体をしっかりと見ていないのに感情移入する彼女へ、美央は渋い顔を向ける。それも気にしない様子で、シャシャテンは実際の作品を見せるよう頼んできた。調べたところ、近場での上演予定はないがDVDはあるという。
「シャシャテン、なんでその劇が気になるの?」
あらすじを改めて見返し、美央は問い掛ける。人を食うと周りから恐れられる男がヒロインと恋に落ちるも、最終的に死別する。感動する者もいるかもしれないが、まだ文章でしか概要を知らない美央にはすぐ理解し難かった。それに対し、シャシャテンは何度か目元を袖で拭って答える。
「この男がな、人でありながら周りにはなかなか人として受け入れてもらえぬのが哀れでのぅ……」
「その、『人』っていうのは何?」
上演中の写真が映る画面を指していたシャシャテンが、何も言わなくなった。以前彼女は「人を思うことなく人を利用する」ことを「人でなし」と定義していたが、それならヒロインの生まれた村を破壊していくこの主人公も同じではないか。美央が指摘すると、シャシャテンはスマートフォンをじっと眺めてから返した。
「それは懸想人への恩愛によるものじゃろう。村の者に忌まれる娘を救うためにな。人を思っておることには変わらぬ」
主人公の行動には、確かに褒められないものもある。しかし人を思うことが、人にしか出来ない優れたところだ。そう自慢げに言い、シャシャテンは空中へ視線を移した。
「しかし城秀は何をしておるかのぅ……。伯母上は本当にあやつを宮へ帰すつもりがないのか?」
いまだ妙音院邸にいる山住を案じるシャシャテンを無視し、美央はオルゴールを手に取った。物語や歌詞を知ってから聞いた音色は、ゆったりとした旋律の間に主人公の悲哀が滲んでいるようだった。音楽が繰り返されるうちに、またもあの男が浮かんでくる。それを打ち払おうと、美央は自らの視界を閉じた。
次の話へ
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
