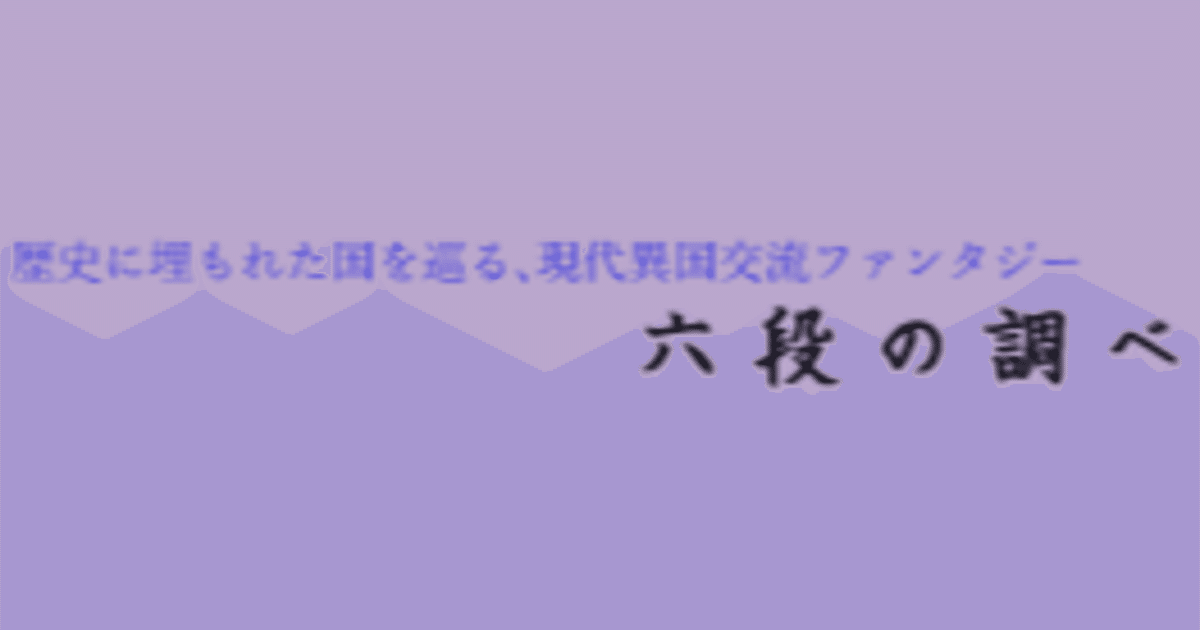
六段の調べ 急 六段 七、瑞香よ永遠なれ
前の話へ
六段一話へ
序・初段一話へ
昨日まで居候がいた部屋は、もぬけの殻となっていた。瑞香より持ち込まれた調度は向こうへほとんど運び込まれ、元からあった仏壇の他は一張の箏しかなかった。いつもシャシャテンが使っていた「玉水」だと気付き、清隆はそのそばに腰を下ろす。まだはっきりしている記憶を辿り、結婚式で弾いたソロを奏でる。本番では難なくこなせたが、シャシャテンに教わっていればもっと質の良い演奏になっただろうか。彼女が妹に指導していたと思い出し、今になって悔やむ。
一通り弾き終えて立ち上がろうとした時、箏の下に紙が挟まっているのが見えた。それを引っ張り出すと、シャシャテンの手紙だと分かる。きっちりした楷書と口語体で、形見としてこの箏を置いていったと記されている。そしてもし手紙を送りたければ、御所の部屋と結界が繋がるよう、操作しておくともあった。文を読み進めながら、清隆は知らないうちに箏の表面を指で撫でていた。
階段を下りる音が聞こえる。清隆は紙片を畳み、襖から顔を出した妹を見返った。
「ああ、ここにいたの。シャシャテンに手紙出したいんだけど、どうすればいいかわからなくて」
美央は片手に封筒を持っている。別れの折に言い切れなかったことを書いているらしい。清隆もシャシャテンにもっと何か伝えるべきだったか考え、しかし手紙を簡単に送れないだろうと肩を落とした。今まで何度やっても、結界手繰りには失敗した。身近で唯一出来る信が羨ましい。このまま瑞香と何の繋がりも持てずに終わるのが心苦しかった。
畳の方へ、清隆はゆっくりと手を伸ばす。空気を押すような感触を捉え、一気に下へ振り払った。途端に火の燃え立つ音がし、小さな輪が広がっていく。畳にぽっかりと開いた空間には、雪を被った草原があった。昔にシャシャテンから見せてもらった光景だ。手を入れると、冬の冷たい風が当たる。結界が閉じても、清隆はしばらく現実味を持てずにいた。
美央も自身の封筒を見、何気ないように清隆の動きを真似した。そして同じような景色が現れると、呆然とそれを眺めていた。もしかしたら自分や妹以外にも、結界を操れるようになった人がいるのではないか。
清隆はまず、八重崎へ電話を掛けた。清隆の言った動きをしてみるよう伝えると、彼女も火の輪が出来たと驚いていた。
『これってさ、わたしたちもシャシャテンへ会いに行けるってことじゃない?』
八重崎の言葉を聞いて、清隆は思い至る。さすがに御所へ直接入るのは難しいだろう。だが門の前までであれば。自宅から直接瑞香へ行けるかもしれないと話す八重崎と待ち合わせをし、清隆は北にも連絡をした。やはり彼も、瑞香への移動が可能になっていた。
『でも、すぐにシャシャテンさんと会うつもりはないね。あの人も忙しくなるだろうからさ。きみたちだけで楽しんでおいでよ』
通話を切り、清隆はしばらくスマートフォンの画面を見つめる。瑞香を知らなければ深く関わらなかっただろう人との縁に、奇妙ながら喜ばしいものがあった。そして信に事情を電話で伝え、宮城の門前で待ち合わせようと約束した。快い返事を受けてから、清隆は妹に声を掛ける。
「瑞香へ行くぞ。シャシャテンにその手紙を直接渡せるかもしれない」
すぐに支度をし、玄関を出る。暖かくなってきた風の中で、清隆は目指す門を思い浮かべて手を動かす。現れた輪の向こうに先客が見え、無事に操れたと安堵して異界へ入った。
「おめでとう、清隆! でもなんで急にできるようになったんだろう?」
信の疑問は、清隆にも答えられそうになかった。彼の隣にいた八重崎と目を合わせてから、衛士の並ぶ門へ視線を移す。既にこちらに気付いていた衛士たちは、互いに何かを話し合っていた。美央が手紙を握り直して歩きだし、三人もそれに続いた。姿勢を正した衛士へ、清隆は六段姫へ会えないか問う。
「あなたがたは確か、女王陛下が日本でお世話になった方でございますね? ……申し訳ながら、陛下はしばらく皆さまとお会いするつもりはないと」
衛士の表情にも、無念が垣間見えた。自分たちに会ったら心を動かされて政に集中できなくなりそうだと、女王は気にしているそうだ。四辻姫の急逝により忙しくしながら、六段姫は早速新たな動きを始めている。八橋もとい生田家への監視を止め、女王が直接罪人を捕らえられる牢「花籠」の取り壊しを決めた。また再開された拷問の廃止や、刑罰の緩和も検討しているそうだ。
しばらくは為政者の邪魔をするわけにはいかない。清隆は大通りへ行こうと信たちに促した。それぞれが歩いていく中、清隆はふと振り返って足を止める。まだ妹だけが留まって、手紙を衛士へ渡していた。
「これ、六段姫様へお願いします」
笑顔で受け取った衛士に頭を下げ、美央は先に行っていた清隆たちに走って追い付いた。
門から伸びる通りでは、あちらこちらで人々の声が聞こえた。六段姫の結婚や即位にまつわる話題が盛んで、彼らが新しい女王に期待していると伝わってくる。
シャシャテンのことは、頭の片隅に追いやるべきなのだ。彼女がいなくても、もう自分で瑞香を調べられる。それに寂しさを覚え、清隆の歩みは遅くなった。周りの三人からも置いていかれそうになる。
その時、結婚式に参列していたらしき町人に呼び止められた。女王夫婦の御前で演奏していた人か聞かれ、信以外が肯定する。町人は昨日の奏楽が素晴らしかったと褒め、また調べを聴かせてくれる時はあるか尋ねてきた。
本当にその機会が来るかは分からない。しかし、そう答えて目の前の人をがっかりさせたくはなかった。興奮を隠し切れていない町人へ、清隆はただの願望を口にした。
「はい。またいつか、瑞香の人々に音楽を楽しんでもらいたいと思っています」
町人が嬉しそうに去ってすぐ、後悔が湧き上がった。もし現実にならなかったら、あの人を失望させてしまう。それこそ裏切りに等しい。聞こえないように呟いたつもりだったが、直後に隣から励ますような囁きが聞こえた。その声は今までより、いくらか大人びている。
「興味あるなら、自分でやってみたら? なんだったら、わたしも手伝うからさ」
それから八重崎は何事もなかったかのように、美央へ話し掛ける。こそばゆさの残る耳を掻いていると、信から不思議そうな顔をされた。彼に事情を伝えるのは、まだ気恥ずかしい。
あてどもなく進んでいると、後方で人のざわつきがした。先ほどまで何もなかった道の脇に、立て看板が刺さっている。それを見ようとする町人たちに紛れて、清隆たちも何が書かれているか覗き込んだ。平仮名が多い文面の内容は、ざっくりと読み取れる。かつて瑞香と親しかった国・日本との交流を数年かけて再び活発化させようとする旨が、そこにはあった。日本の者が来ても、快く受け入れてほしいなど記されている。今騒いでいる瑞香の人々は言うまでもなく、いずれ日本でも戸惑いが広がるだろう。
朝重へ告げた言葉を、清隆は自分へ言い聞かせる。知らない国を不安に思う人のために、瑞香を調べていきたいのだ。これからも多くを学ばなければならない。
後ろに集う人へ看板を譲り、清隆たちは近くにあった道へ入り込んだ。一気に人が少なくなったそこの有様は、時代が時代であれば王になっていた者が住む屋敷辺りを思い起こさせる。
「そうだ、妙音院さんは元気かなぁ。昨日話せなかったし、せっかくだから会いに行く?」
自分を救おうとした恩人に挨拶がしたいと言う信の提案に、清隆は頷いた。妙音院は、自分の知らなかった瑞香を教えてくれた一人だ。そしてこの国には、まだまだ隠されたことがあるに違いない。それを思うと、自然に心が躍った。
「嗚呼、行こうか」
記憶を頼りに、碁盤状の町を行く。不安混じりに進む中、やがて琵琶の音が風に乗って届いてきた。変わった趣味を持つという屋敷の主が、相変わらず屋根の上で調べを奏でているのだろう。
まだ邸宅は先だと分かっていたが、清隆は妙音院が遠くに見えないか顔を上げた。そこに十三羽並んで飛ぶ不死鳥が視界に移り、それを追って首を巡らす。眩い輝きを放つ絢爛な鳥の群れは、風を切りながら澄み渡る青い空を翔けていった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
